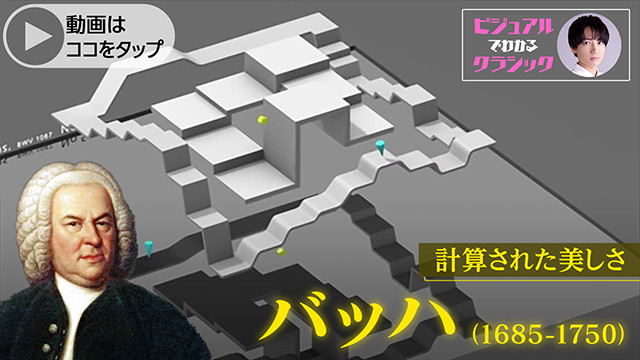【読み応えアリ!】「青オケ」声優・千葉翔也と学ぶ クラシック名曲ざっくり解説[まなびノート]
2023年7月29日(土)
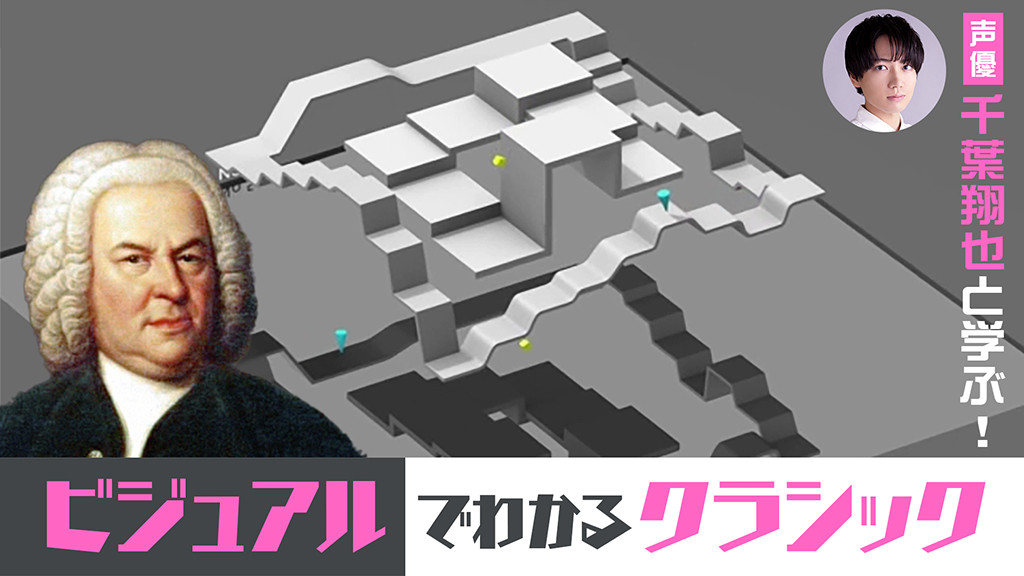
「ビジュアルでわかるクラシック」と題した今回のプレイリスト。気鋭の映像クリエイターがクラシックの名曲を映像化した番組「名曲アルバム+」の中から、「クラシックの歴史を語る上で欠かせない作曲家の作品」を5つセレクトしました。一緒に観賞してくれるのは、アニメ「青のオーケストラ」(通称:青オケ)で主人公・青野一(あおの はじめ)役を演じる声優の千葉翔也さんと、ピアニストで作曲家の加藤昌則さん。難しい知識はいりません!映像を通して音楽を自由に感じながら、クラシックの奥深い世界をのぞいてみましょう!
|
|
 《加藤昌則》 《加藤昌則》作曲家・ピアニスト。東京藝術大学作曲科首席卒業、同大学大学院修了。 作曲のジャンルはオペラ、管弦楽、声楽など幅広く、作品に新しい息吹を吹き込む創意あふれる編曲にも定評がある。多くのソリストに楽曲を提供しており、共演ピアニストとしても評価が高い。独自の視点・切り口で企画する公演やクラシック講座も注目を集めている。NHK-FM「鍵盤のつばさ」番組MC。 |
目次
――千葉さんは「青オケ」にご出演されるまで、クラシック音楽にはあまり触れてこなかったと伺いました。これまで演じてきて、ご自身のクラシックのイメージに変化はありましたか?
千葉:それこそ学校の音楽の授業くらいでしか触れたことがなかったので、クラシック音楽についても「1曲が長いな」といった程度のイメージしかもっていなかったのですが、「青オケ」にご縁をいただいてからは、演奏を聴く機会が増えました。作品のモデルにもなった千葉県にある幕張総合高校のオーケストラ部の演奏をプライベートで鑑賞させてもらったのですが、3時間もの間ずっと演奏を聴き入っていた自分にびっくりして。「クラシックって知識がなくても楽しめるんだ!」ということは感じていますね。今回は楽しみです。よろしくお願いします!
――よろしくお願いします。今回のプレイリストでは、クラシックの歴史上重要な作曲家の作品を5つ選んだんですが、その前に一曲、こちらをご覧ください。
――「パッヘルベルのカノン」という作品です。この曲は「青オケ」の1話&2話で、千葉さん演じる主人公の青野が再びバイオリンと向き合うきっかけとなった重要な曲ですが、改めて映像で見るとどう感じますか?
千葉:同じことを違うタイミングで、違う人が繰り返しているという曲の構造を、めちゃくちゃわかりやすく表現できている動画だと思いました。実は、アニメの中で青野が演奏するこの曲は、「一人で演奏しているんだけど、二人で弾いているように聞こえる」編曲になっているんです(動画はこちら)。
なので、元々何人かで追いかけっこのように演奏する曲だということは知ってはいたんですけど、音だけでは実感できていなかったのが、この映像だと目で見てよくわかりました。

アニメ「青のオーケストラ」
毎週日曜 Eテレ 午後5:00~5:25 (再放送) 毎週木曜 Eテレ 午後7:20~7:45
※放送予定は変更になる場合があります。
【番組HP】
――作曲家の加藤さんから見るとどうでしょう?
加藤:カノンというのは、“同じことをずらしてやる”という、いわば「かえるのうた」と同じ技法なんですよね。この曲を作ったパッヘルベル(1653~1703)もそうなんですが、バッハの活躍したバロック時代には、ベースとメロディーラインだけのシンプルな音楽の作り方というのがありました。この曲もベースの音はずっと同じことを繰り返していて、その上のメロディーがどんどん変わっていっているんですけど、先に演奏している人と後の人とで、偶然的に絡まって生まれてくる面白さがありますよね。
千葉:わかります。音が細かいところと、ゆったりしたところが同時に重なって聞こえたり――
加藤:この時代に音楽を楽しむ人というのは、貴族や聖職者のような、ある程度教養があったり、お金に余裕があったりする立場の人だったわけですけど、この曲はそういう人たちが聴いて「あ、いまこれ絡まっていて面白いな」とわかるような、そういう“高級な遊び”みたいな面があったと思います。メロディーで追いかけっこをしていって、その中で偶然起こる音の現象をみんなで楽しむという、音楽的にはすごくシンプルな作品ですね。
千葉:そんなに複雑なことをしているわけではないけれど、だから分かりやすいというか。
加藤:そういうことです。そんな「カノン」という音楽の形式をより極めた作品を書いたのが、次に紹介するバッハという作曲家です。彼の作曲した「カノン」の動画を見てみましょう。
1.計算された美しさ バッハ 「14のカノン」
――バッハの「14のカノン」という作品です。本来は14の短い曲を集めた作品ですが、この動画ではそのうち7つを抜粋して紹介しています。
千葉:パッヘルベルの動画と比べると、ちょっとつかみにくい感じがしました。パッヘルベルのカノンは、1人目の音を追おうと思えばずっと追えたし、それがだんだん豪華になっていって楽しい、というイメージだったんですけど、この曲はどう聴いたらいいのかわからないというか――
加藤:おっしゃるとおりで、この曲は理屈がわからないと何が何だかわからない曲だと思います。
千葉:なんかすごいな、とは思ったんですが……聴いていて「何を楽しめばいいんだろう」と思いましたね。
加藤:パッヘルベルのカノンは、追いかける人が最初の人と同じメロディーを演奏しますよね。「かえるのうた」もそうです。でも、バッハのこのカノンは、追いかける人の音の「高さ」を変えたり、音の入る「タイミング」を微妙にずらしたりしています。そうすると普通は、和音として美しくない音が同時に鳴って、きれいな“ハモり”にならなかったりするんですけど、バッハという人はそれをものすごく緻密に計算して、本来ぶつかるはずのものがぶつからないようにしているんです。――もっとわかりやすく言うと、「回文」ってありますよね。
千葉:「たい焼き焼いた」、みたいなやつですか?
加藤:そうです。あれって長い文章になればなるほど、「逆から読んでも同じになっている」というところに発見がありますよね。パッヘルベルの場合は同じ形のものを追いかけっこしていて、これを「順行」というんですけど。バッハはメロディーを逆から、いわば「回文」と同じ形にして、前からと後ろから、同時に演奏しても音楽としてハモるようにしているんです。
千葉:なるほど、そういうことか!すごい!
加藤:さらにすごいのは、単純な回文にするだけではなくて、音の場合「高さ」があるので、例えば「上がって上がって下がって」というメロディーを、「下がって下がって上がって」とすることもできますよね。これを音楽では「反行」というんですけど、それも使ってさらに複雑な文にして……という要はちょっとした“マジック”なんですけど、そういうことをすごくこだわってやったのがバッハという人なんです。
千葉:確かに、この曲全体が最初からそれを目指して作っていることが、動画を見るとよくわかります。
加藤:そうですね。一番最初に演奏される曲(14曲のうちの第1曲)は、音の並びとしてはいびつで、聴いていてもそんなに美しい感じはしないんですけど、それはなぜかというと、後からひっくり返したりして複雑にした時に全部上手くいくように仕組んであるという――
千葉:いろいろ発展できるように、最初の骨組みを見つけたんですね。すごいなあ。
加藤:バッハという人は、“職人”だったんです。職人って目には見えないところにもすごくこだわって、色々なことをやるじゃないですか。バッハは教会に勤めて宗教音楽みたいなものをたくさん書いていた時代があったんですけど、宗教音楽というのはあくまで神に対して献身するというか、神を敬う気持ちを音楽に書いているので、人々を楽しませるような世俗的なところはないですよね。ヨーロッパの作曲家たちは「神の世界をどうやって表現するか」ということをずっとやってきて、その一番複雑化した、いわば頂点にバッハという人がいるんです。それまでのいろんな音楽を統合して、職人として徹底的にこだわった作品を残したのがバッハという作曲家なんですね。
2.常識を覆す作曲家 ベートーベン 「運命交響曲」
――続いての動画は、ベートーベン(1770-1827)作曲の「運命交響曲」です。
千葉:この曲は有名ですよね。僕も子供のときにふざけて口ずさんだりしていました。さっきのバッハはどこに注目したらいいか分からなかったんですけど、この曲は冒頭の「ジャジャジャジャーン」みたいな、口ずさめるわかりやすい音と、それをダイナミックに表現した映像が印象的でした。
加藤:そうなんです。まさにこの曲のすごい部分もそこにあって、実はこの曲はすべて、冒頭の「ジャジャジャジャーン」という4つの音だけでできているんです。
千葉:そうなんですか!最初は4音ずつだとわかったんですが、途中からは全然違うことをやっているんだと思いました。
加藤:ところどころメロディーのように変形しているところもありますが、最初から最後まで、キーになっているのは「タ、タ、タ、タン」という4つのリズムです。僕がこの曲でよく例えるのは、実際に何かの広告で見たんですけど、壁にすごく大きな木の絵が書いてあると思って近づいてみたら、実はそれがたくさんの家族写真が集まってできていたという――
千葉:モザイクアートみたいなものですね。
加藤:そうです。この曲も同じで、楽しい雰囲気も悲しい雰囲気も、同じ「ジャジャジャジャーン」だけで語っているんです。それって、やっぱりちょっとすごいじゃないですか。多くの言葉で多くのことを語るというのはある意味簡単なことなんですけど、たった4つの音だけを組み合わせて一つの世界をつくるというのは、当時の音楽の常識を覆すすごいことだったんです。
千葉:ベートーベンって、この曲を作ったときには耳が聞こえなかったんですよね。
加藤:そうです。それはとてもいいご意見で、僕はきっとベートーベンは耳が聞こえなかったからこそ、この発想になったんじゃないかと思います。じゃなかったら、自分でいいメロディーを追い求めると思うんです、作曲家として。でもそれがだんだん音の聞こえない世界になっていったときに、きっとこういう発想になって。
千葉:アイデアだけで音楽を作る、っていうことですね。こういう技法は音楽的にはなんて言うんですか?
加藤:こういうメロディーに満たない細胞みたいなものを、音楽用語で「モチーフ」といいます。このモチーフだけで音楽を展開していくということを最初にやったのがベートーベンで、それ以降の作曲家はみんな、いいメロディーというよりは、モチーフをどう使って新しい世界を作っていくか、ということを考えて作曲をするようになりました。それくらい、この「運命」の交響曲は後の時代の作曲家たちにインパクトを与えた作品だったんです。
3.魅せるピアニスト リスト 「ラ・カンパネラ」
――続いての動画は、リストの「ラ・カンパネラ」です。
加藤:僕、声優さんのお仕事ってあまり詳しくないんですけど、声優さん同士だから分かる「これはすごい!」みたいなテクニックってあったりするんですか?
千葉:あります。たとえば叫ぶ演技をするときに、実際に叫んでいるわけじゃないんですけど“叫んでいる風”に聞こえて、しかもそれがしっかりマイクに乗っている、とか。本当に叫んでしまうと、マイクの音が割れてしまったり、逆に迫力がなくなったりしてしまうんです。収録の現場で、声は大きくないけどめちゃくちゃ響いているような人を見ると、すごいなって思いますね。
加藤:なるほど。僕もホールの舞台上でしゃべることがあるので、響く声と響かない声があるというのは実感としてわかります。いまお話ししてくれたような“伝えるテクニック”みたいなものが声優の世界でもあると思うんですけど、クラシックの世界で「演奏者の技術」というものが注目され始めるのが、実はこのリスト(1811~1886)の時代なんです。この映像ではピアニストの手に注目していて、激しく手が動いていますけど、これ、ピアノを弾いたことがない人から見るとすごく“弾いている”ように見えると思うんですよね。
千葉:はい、そう思いました。動画に出てくるピアニストの右手も左手も常に大変そうで、こんなに細かく動いているんだって。
加藤:でも実はピアノって、鍵盤を押し込んだときの深さがだいたい10ミリなんですけど、この10ミリをどうやって押さえるかでいろんな音を出しているんです。だから、映像のように派手に手を動かさなくても、この10ミリの中でいろんな音の変化が出せる方が、ピアニストとしては「弾ける人だな」と感じるんですね。逆に、この映像のような手の動きはいわば“まやかし”みたいですが、リスト以前の時代は王様や貴族、ごく限られた人しか音楽を楽しむことができなかったので、そういう派手さは必要なかったのかもしれないんですけど、この時代になると、ブルジョワと呼ばれる裕福な市民も音楽を楽しむようになったんです。その中には音楽の教養がない人もいるので、こういう派手なパフォーマンスをすると、今でいう“アイドル”のように「キャー!」ってなる人が増えて、自分のファンになってくれるんですね。そこに自身も魅せられて、目をつけたのがリストなんです。
千葉:なるほど。声優の世界でも、結局派手な方が上手いと思われがちだったりするので、なんとなくわかる気がします。
加藤:実際、リストの曲って手の「跳躍」が多いんです。この曲も高い音から低い音まで、広い音域に音をちりばめている。そうすると鍵盤の上で手があっちこっちに飛ぶので、視覚的に映えるじゃないですか。
千葉:たしかに、さっきのバッハの曲とかは音楽としてはすごいけど、弾いているところを見て「この演奏スゲー!」とはならなそうですね。
加藤:「キャー!」とはならないですよね(笑)。私個人としては、「派手さだけじゃねえぞ!」という気持ちもあるんですが、でも人間ってどの分野においても視覚が全てを優先する気がするんです。音楽も本当は耳で聞くものだって言いながら、視覚的なものというのはすごく大きいと思うんですよね。そういう意味で、音楽を“視覚的に魅せる”ということをピアノで最初に切り開いたのは、このリストという人。この曲には、ある意味、リストのパフォーマーとしての顕示みたいなものが込められていると思いますね。
4.バレエ音楽の巨匠 チャイコフスキー 「花のワルツ」
――続いての動画は、チャイコフスキー(1840-1893)が作曲したバレエ音楽「くるみ割り人形」から「花のワルツ」です。
千葉:これも有名な曲ですよね。ゲーム風の映像でクラシックを表現するなんて、初めて見るアプローチだなって思いました。
――「花のワルツ」は「くるみ割り人形」という2時間ほどあるバレエ作品のうちの一場面で流れる音楽ですが、この動画ではバレエ全体のストーリーをこの曲に乗せてアニメーションに仕立てています。千葉さんはバレエは見たことありますか?
千葉:知り合いが出ている発表会を見に行ったことがあって、色んな演目を見たんですけど、セリフがないこともあってなかなか理解できなくて……難しいなと思った記憶があります。
加藤:実は僕もそうで、バレエの良さが30歳くらいまであまり分からなかったんですが、クラシック音楽の人気の曲には、実は元がバレエの曲だったものが結構あるんです。たとえば、ラヴェルの「ボレロ」という有名な曲がありますが(動画はこちら)
、ひたすら同じメロディーを繰り返しながら終わりに向けてだんだん盛り上がっていくという、クラシックをよく知らない人が聴いても絶対興奮する曲があるんですけど、それももとはバレエの曲なんですよ。
千葉:どうしてバレエの音楽に人気の曲が多いんですか?
加藤:一つは、バレエのストーリーが複雑でなくて、わかりやすいからだと思います。しかも、バレエには必ず“型”があって、ストーリーとは関係なくダンサーたちが踊る場面がある。そこに来たら話の内容は一旦置いて、純粋に踊りを観て楽しむことができます。もちろんストーリーがわかるとより楽しめますが、理解できるところだけをキャッチしても楽しめるのがバレエなんです。そうなると、音楽も「場面ごとにいい楽曲を並べる」ということが大事になるわけで、難しい理屈は必要ない。そういう気軽に聴ける点が、バレエ音楽の人気の理由なんじゃないかなと思います。
千葉:なるほど。じゃあゲームのサウンドトラックを聴いているような――
加藤:そんな感じです。一方で、さっきのベートーベンの「運命交響曲」みたいに、純粋な音楽を聴かせる作品だと、作曲家はその仕組みをすごく大事にするわけですよね。
千葉:たしかに、バレエ音楽はベートーベンのようにモチーフでガチガチにして曲を作る必要がなさそうです。
加藤:そうです。聴き手の側としても、もちろんいろんな楽しみ方があっていいんですが、僕はバレエ音楽を聴くときは理屈を考えずに聴いていいと思います。純粋に音楽として聴いて、「美しい!」「楽しい!」って感じればいい。だからこそ、この曲も音楽から自由に想像力を働かせてこういう映像にすることができるんだと思いますし、クラシックにもそういう曲があるんだよ、ということはぜひ知ってほしいですね。
5.新しい美を求めて ドビュッシー 「月の光」
――最後の動画は、ドビュッシーの「月の光」です。
千葉:この映像は、僕が感じた曲のイメージよりも明るいと思いました。もうちょっと暗い部屋で聴くイメージだったので。バーとかで流れていそうな。
加藤:僕もこの動画は自分のイメージとは少し違いました。僕は普通に、月とお団子とすすきなんかが出てくるような、わりと静止画に近いイメージだったんですけど……この映像は常に何かが動いて、変化しているっていう感じですよね。作者はこの曲に流動的なものを感じたのかな?
千葉:たしかに、カーテンがずっと揺らいでいるみたいな感じはありますね。この曲は5分間、ずっと同じことをしているっていう印象でした。あとは全然違いますけど、“生命の誕生”みたいなものも感じますね。
加藤:逆に言うと、いろんな捉え方ができる曲ってことですよね。例えばベートーベンの「運命」を聴いて、「楽しい曲ですね」とは絶対思わないじゃないですか。たぶん音楽の印象って、みんなある程度同じようなことを感じるんですけど、ドビュッシー(1862-1918)くらいの時代になってくると人によって捉え方が全然違ったりする。
千葉:ドビュッシーってどんな作曲家なんですか?
加藤:語弊を恐れずに端的に言うと、それまでの音楽って喜怒哀楽のような感情をわりとはっきり表現していたんですが、ドビュッシーという人は「そういう枠組みに入らない感情」みたいなものを表現した人なんです。時代的にも、美術の世界では印象派の画家が活躍した時期で、モネの絵みたいに “ぼかす”ことによって、そういった微妙な感情を音楽で表現しようとしました。「バーで流れていそう」という、まわりに溶け込むような感じはそういうところから来ていると思います。
千葉:なるほど。
加藤:音楽的な理屈でいうと、和音って基本は「ド、ミ、ソ」みたいな3つの音の積み重ねでできるんですよ。その真ん中の音を半音変えるだけで明るくなったり悲しくなったりする、メジャー(長調)/マイナー(短調)という和音の構造ですよね。そこに、さらに音を加えて4つの音でできた和音にすると、共鳴の仕方が少し変わってぼやけるんです。ドビュッシー以前の作曲家というのは、基本的には3つの音で形成される和音を使って、ときどき4つの音を使う、ということで音楽を作っていたんですけど、ドビュッシーは最初から「4つの和音」を多用して、明確なキャラクターをぼかすという手法で音楽が作れないか、ということをやり始めました。その結果、単純な「明るい」とか「悲しい」とかじゃなくて、“もわん”とした印象になる。ドビュッシーは、そんな“新しい表現”を追求した作曲家なんです。
千葉:そうなんですね。ぼんやりと、クラシック音楽ってもう完成して止まっているものだという印象が勝手にあったんですけど、ドビュッシーに至ってはつい最近の20世紀まで生きていて、バッハから連綿と続くいろんな作曲家の流れの中で新しい表現を模索していたと思うと、ちょっとイメージが変わりますね。
――ここまで5つの作品を映像とともに見てきました。いかがでしたか?
千葉:新しいことをたくさん知れて楽しかったです!特に、僕は理系的な仕組みの説明とかを面白いと思うタイプなので、バッハのカノンの説明は面白さがよくわかりました。音楽って触れない人にとっては全く興味のないものだったりすると思うんですけど、こういう角度でならちょっとはわかってもらえるかなって思います。
加藤:今回の5つの動画だけを見ても、いろんな時代にいろんな音楽があって、いろんな見せ方、聴き方があることがわかりますよね。固定観念を取っ払って、「クラシックって別に遠いものじゃなくて、結構楽しめるものなんだ」ということがわかっていただけたなら嬉しいです。今日はありがとうございました!
千葉:ありがとうございました!
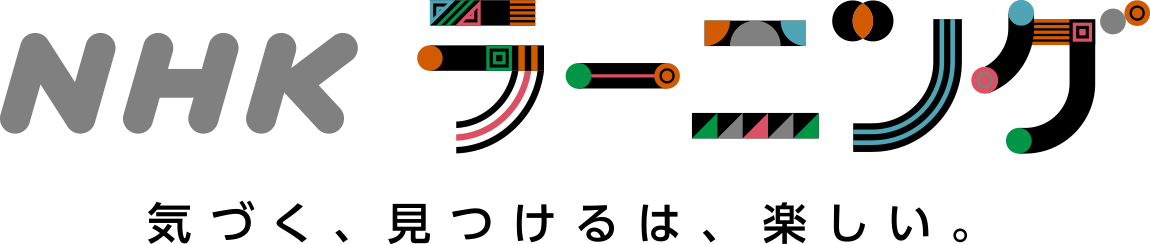
 《千葉翔也》
《千葉翔也》