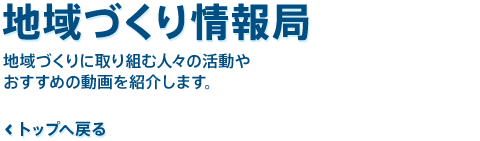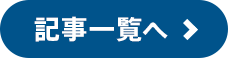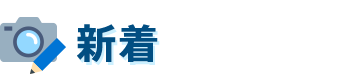- ホーム
- 地域づくり情報局
- 地域の誇り・ふるさとの宝
- 小学校で生きる力をはぐくむ!地域に伝わる「食と農」の教育。(島根県雲南市木次町日登地区)
2016年11月26日 (土)
小学校で生きる力をはぐくむ!地域に伝わる「食と農」の教育。(島根県雲南市木次町日登地区)

島根県雲南市日登地区は人口約1600、山あいにある農村です。この地区にある雲南市立寺領小学校(児童数63名)では、地域の人たちの協力でたくさんの「食と農の学習」をしています。米、大豆、トウモロコシ、サツマイモ、ソバ、夏野菜、ブドウなど、毎年たくさんの種類の農作物を育て、さらに収穫した作物を使って加工・販売も体験します。
春、新学年が始まるとすぐ、米づくりをする5年生は、稲の種まきをします。5月初旬には田植え。どろんこになりながら手植えします。2年生は夏野菜を育てます。小玉スイカ、キュウリ、ナス、ミニトマト、ピーマン...など、収穫の夏には毎日のようにとれたて野菜を食べることができます。
6月の学習は盛りだくさん!サツマイモづくりが始まり、1~4年生が畝立てした畑に、全校児童で苗を植えます。米づくりでは田車を押し、草取りをします。さらに、3・4年生はブドウのお世話で、余分な芽をとりのぞく「芽こぎ」や「袋かけ」をし、1・2年生は大豆の種まき、6年生は菜種の刈り取りと菜種落としの作業をします。
2学期になると、地区内の葡萄園で収穫体験(3・4年生)や蕎麦畑の見学・収穫体験(6年生)があります。そして10月には全校で芋ほりし、焼芋パーティーをします。米づくりでは10月中旬に5・6年生が稲刈りします。まずはハデを作り、昔ながらの手刈りをし、自分たちでなったより縄で稲を結束し、ハデにかけて干します。5年生の家族も手伝いに参加し、大変な作業ですが、みんなで汗をかくのはいいものです。そして脱穀作業をし、収穫した米はごはんとして食べるだけでなく、ポン菓子にして地区の祭りで販売し、糀にして1・2年生が育てた大豆で味噌を作ります。そして、1・2年生は豆腐づくりをします。
日登地区でのこうした教育のはじまりは、昭和22年の日登村立日登中学校創立までさかのぼります。初代校長の加藤歓一郎先生は、戦後の復興途上にあった当時「生活に根付いた教育こそが、真の学力をつける」と考え、経済基盤の確立と民主的な村づくりを展開しました。その中で学校教育に農業生産活動を取り入れた「産業教育」や、生徒たちが心情を赤裸々につづった生活綴り方の実践は、全国的な注目を浴びました。現在、日登中学校は統合されてありませんが、加藤先生の教えは現在の寺領小学校に脈々と受け継がれ、地域の多くの方々の協力で「食と農の学習」を続けています。
【投稿者:ひろ さん】