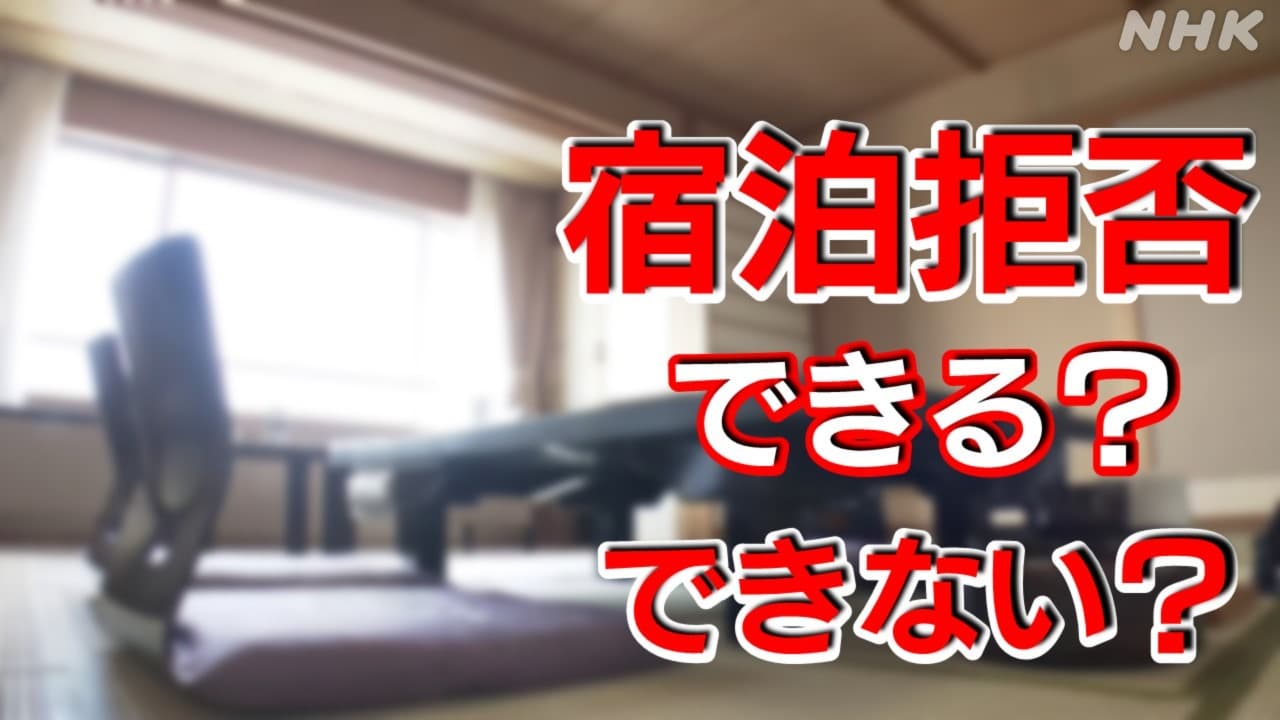首都圏情報ネタドリ!
- 2024年5月10日
カスハラの原因に“ある共通点”タクシー会社の調査で判明 ポイントとなるドライバーの対応は
- キーワード:

カスタマーハラスメント(カスハラ)と呼ばれる、客からの著しい迷惑行為に対して、自治体や企業が次々と対策を打ち出しています。
沖縄県にあるタクシー会社では、客のクレームがエスカレートしたケースを分析したところ、約半数に“ある共通の原因”があったといいます。
ポイントとなるドライバーの対応とは?
消費者が企業の対応にイライラしてしまったときの対処法についてもお伝えします。
(全2回の後編/前編を読む)
(首都圏情報ネタドリ!取材班)
カスハラの原因は 未然に防ぐには
カスハラと正当なクレームの違いとは何か。カスハラ行為に対して、毅然(きぜん)と対応するにはどうすればいいのか。
こうした悩みに直面する現場の事情を前編の記事でお伝えしました。
サービス業に携わる人たちにカスハラ行為のきっかけとなった理由を聞いた調査では、いちばん多いのが、「顧客の不満のはけ口・嫌がらせ」でしたが、およそ2割の人が「接客やサービス提供側のミス」、つまり店側にも落ち度があったと答えていました。
店の対応がカスハラにつながるケースをどうしたら減らせるのか、模索を始める業界も出てきています。
5月、全国のタクシー会社の従業員がウェブ上に集まり、セミナーが開かれました。
聴く力をテーマに、専門家を招き、カスハラを未然に防ぐための接客のポイントを学びました。

講師 岡えりさん
「相手がどんな表情で何を求めているのか、観察も含めて傾聴力が重要になります。傾聴力が無いと、お客さまが言っていることを理解できず、トラブルになることが多いです」
講座を企画したのは沖縄県にある従業員1000人以上のタクシー会社です。

カスハラの分析に力を入れてきたこの会社。
原因を追究すると、従業員にも課題があることが分かってきました。
腹を立てて「降りましょうか」といった客に、ドライバーが「降りてください」と言い返したことで口論になったなど、客のクレームがエスカレートしたケースのおよそ半数で、ドライバーの対応に何らかの原因があったのです。

沖東交通グループ代表 東江優成さん
「ドライバーがどのような対応をするかで、お客様の反応が全然変わってくると思います。お客様とのコミュニケーションが取れていれば、カスハラが防げた事例もあるのではと考えています」
今この会社では、客への対応のしかたに特化した研修を実施しています。

講師のベテランドライバー
「行き先に関しては、よくクレームがきます。『いつもはいくらで行けたのに、何できょうは高いの?』とか、『自分が指示した道、走ってないじゃない』といったものです」
どのような行為がカスハラにつながるリスクがあるのか、これまでの蓄積をふまえて具体的に伝えます。
その後、従業員たちがドライバー役と客役に分かれて、実際のやりとりを想定した研修を行いました。

本日、どちらまで?

そうですね。ちょっと遠いですけど、美ら海

美ら海水族館。
えっと…ちょっとナビで調べてみてもよろしいですか?

最初に、どのコースを通りましょうか?とお客さまに1回、聞いてくださいね。
客との限られたやりとりからでも、関係を築くスキルを磨くことで、カスハラを減らすことができるのではと考えています。
東江さん
「適切な対応をすることによって、少しでも減らせるというのは可能性としてあるのかなと。クレームもカスハラも、1人で起きている問題ではなく、人と人なので。コミュニケーションなど、我々ができる対策で減らしていけるものだと思っています」
カスハラ防ぐ 企業・消費者の対応とは
企業のカスハラ対策のアドバイザーを務める島田恭子さんによれば、カスハラが起こるとき、お客の原因や企業側の瑕疵(かし)だけでなく、イライラを助長させるような要因があることが多いといいます。
ちょっとした工夫で消費者の不満を減らす手だてがあることから、カスハラの未然防止策として、企業側が対応を工夫するケースが増えているそうです。

日本カスタマーハラスメント対応協会代表 島田恭子さん
「たとえば、お客をなるべくイライラさせない、カスハラさせない環境づくりに取り組む現場がでてきました。
長時間待たされる待合室。お笑いやほっこりする動画を流したり、リラックス効果のあるアロマを置いたり。また、エレベーターのまわりを鏡に変えることで、客が身だしなみに気を取られて長い待ち時間が気にならなくなるといった、ナッジという言われる工夫です。
また、一企業ではなく業界でまとまり、対応を決めるといったことも有効です。
例えば、お菓子業界は、各社のお客様担当者による協会を作り、統一ルールを決めることで過剰サービスをやめる仕組みを作りました。
カスハラしやすい客は、悪質クレームを言いやすい企業を回ってカスハラをしていく、という傾向がありましたが、業界が一丸となれば、それを防ぐことにつながります」
消費者としてサービスに納得がいかず、不満や要望を伝えなくてはいけない局面では、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

島田さん
「大前提として、要求内容が妥当である必要があります。
冷静さがあればその要求を『落ち着いて』伝えればいいだけなのですが、あまりにも怒りや不満を抑えきれず、声を荒げたくなるようなときもあるでしょう。その場合はまず、『冷静になること』。
冷静さを取り戻すにはいくつかの方法がありますが、1つおススメなのは、怒りを感じたときに思い出すキーワードを決めておくことです。たとえば『怒ってもいいことないよ』とか。それらをパッと思い浮かべることで、少し冷静になれるはずです。
私はカスハラに限らずイライラしたときは、いつも『私は何に困っている?』と自分に尋ねることにしています。実は怒りやイライラは”二次感情”と言われていて、その裏には必ず『困った』があるからです。
自分がイライラしたとき、いつもその”困った”をみつけるクセをつけるのも、よい方法です」
冷静になったところで、要求を伝えるときのポイントは2つあるといいます。
(1)(”私”が主語の)I(アイ)メッセージ
(2)主張はするけど威圧はしない
島田さん
「”私”が主語であれば、相手は自分のことを言われているわけではないので、傷ついたり、腹が立ったりはしづらいもの。相手の人格を攻撃するのではなく、『自分が今、何に困っているのか』そして『何をしてほしいのか』をきちんと伝える。
その際、自分の主張はきちんとするけど、威圧はしない、というのが大切です。
これらはカスハラに限らず、あらゆる対人関係で大切なポイントですので覚えておいてくださいね。これらのポイントで、多くの“無自覚カスハラ”は防げると思います」