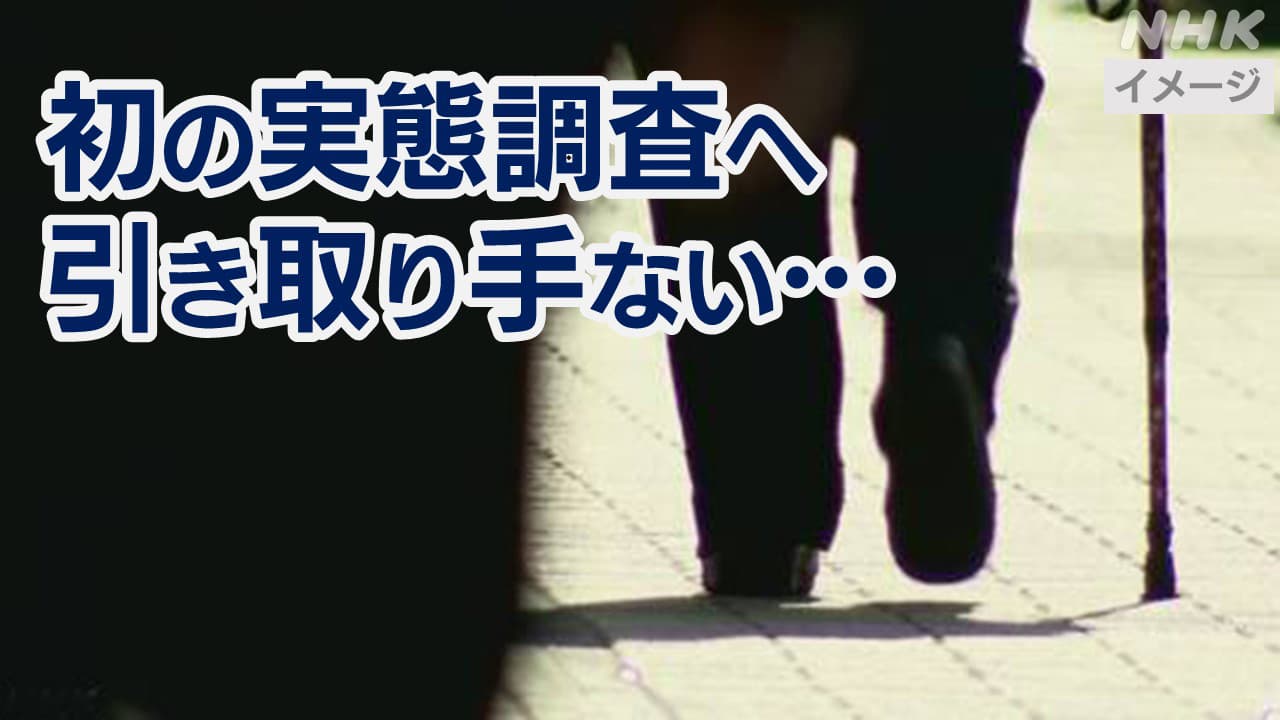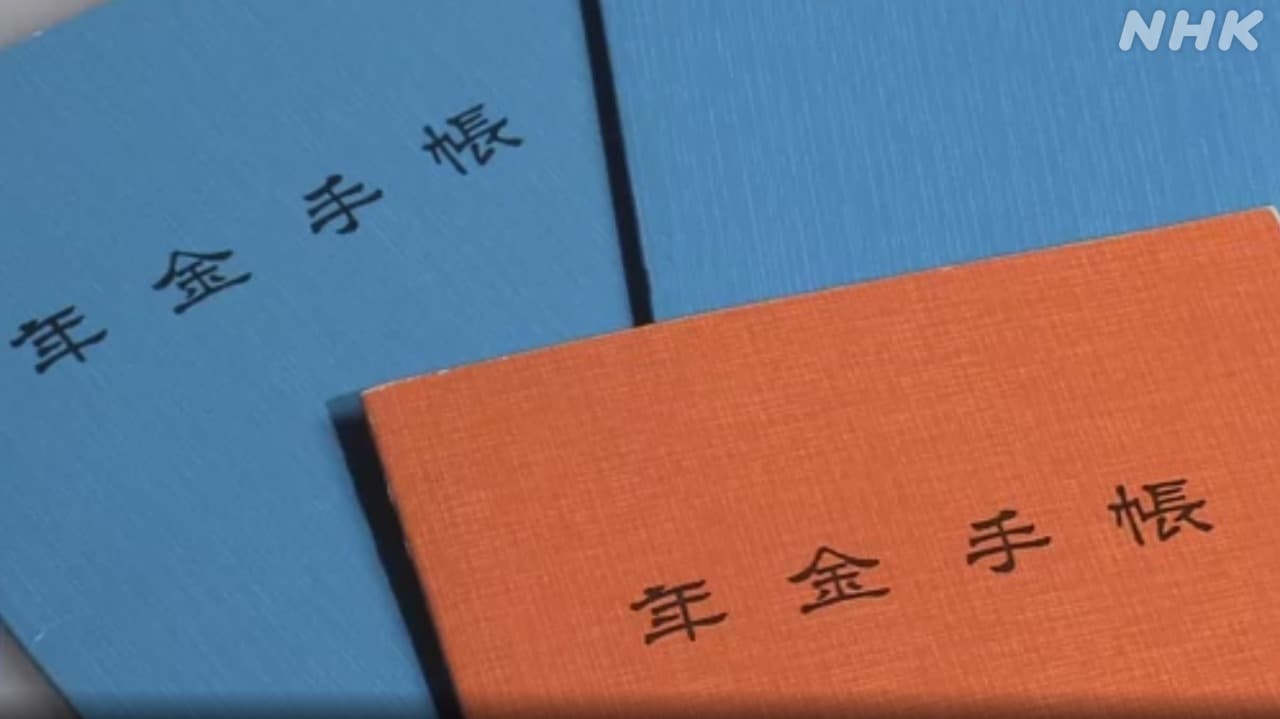首都圏ネットワーク
- 2024年5月8日
2040年 高齢者の約15%が認知症 全国で584万2000人と推計 “地域でどう支えるかが課題”
- キーワード:

団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年。
認知症の高齢者が584万人あまりにのぼるという推計を厚生労働省の研究班がまとめました。
これは高齢者のおよそ15%、6.7人に1人にあたります。
介護の問題に詳しい東洋大学の高野龍昭教授は、「今後、1人暮らしの認知症の人が増えるとみられ、家族の支援が限られる中、地域でどう支えるかが課題だ」としています。
2040年 高齢者6.7人に1人が認知症に

厚生労働省の研究班は、全国から4つの自治体を抽出して医師などが65歳以上の高齢者について認知症の診断を行い、それぞれの自治体の有病率から将来の全国の認知症の人の数を推計しました。
それによりますと、認知症の高齢者は▼来年、2025年には471万6000人となり、▼団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年には、584万2000人にのぼると推計しています。
2040年には高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症と推計されます。
前回9年前の調査では、2040年に認知症の人が802万人にのぼると推計していましたが、今回の推計値がそれよりも低くなったことについては、▼生活習慣病の改善や▼健康意識の変化などによって認知機能の低下が抑制された可能性があるとしています。
また、今回の調査では物忘れなどの症状はあるものの、生活に支障がなく、認知症と診断されるまでには至らない「軽度認知障害」の人の将来の推計を初めて公表し、2040年には612万8000人にのぼるとしています。
「軽度認知障害」の人は、認知症に移行することが多い一方で、運動や栄養状態の改善によって症状の進行スピードを抑制できる可能性もあるということです。
国 “認知症サポーターの養成進めてきた”

認知症の人の増加に対応するため、国は認知症の人やその家族を地域で手助けする「認知症サポーター」を養成する取り組みを進めてきました。
「認知症サポーター」は、自治体などの講習を受けて認知症に関する知識を身につければ、誰でもなることができます。
国は2005年から養成を始め、現在、全国に1534万人あまりと人口の1割以上いるということです。
サポーターは、できる範囲で周りの認知症の人やその家族を手助けすることが期待されていますが、現在、その多くは認知症の当事者たちが集まる会の支援など活動の場が限られているのが現状だということです。
中にはもっと認知症の人の力になりたいという人もいるということですが、どのように活動してよいか分からず、行動に移せていないという人もいるとみられ、サポーターを活用しきれていないという指摘もあります。
また、国はサポーターがチームを組み認知症の人やその家族の生活面の支援を早期の段階から行う「チームオレンジ」と呼ばれる施策を進めていて、来年、2025年までにすべての市町村でチームが活動を始めることを目標にしています。
しかし、実際にチームを立ち上げて活動している自治体は全国で339自治体と(339/1718自治体)全体の2割にも満たないのが現状です。
“市民の力を借りられるような仕組みを”

介護の問題に詳しい東洋大学の高野龍昭教授は、認知症をめぐる現状について、次のように指摘しました。
東洋大学 高野龍昭 教授
「老後に1人暮らしをする認知症の人は今後間違いなく増えますが、家族は離れて暮らすなどしているため支援を期待するわけにはいきません。一方、増えていく認知症の人を制度や施策、専門職の力だけで支えていくのも当然不可能で、今後は専門職ではない一般の人たちの力を借りざるを得ない状況です」
そして、認知症の人たちは社会とつながることによって一定程度、症状の進行スピードが抑制されるとしたうえで、次のように話していました。
高野 教授
「専門的な関わりだけが必要なわけではなく、地域の顔なじみの人たちが声をかけたり、一緒になんらかの活動をしたりするということが重要です。日常的な関わりや、何らかの見守りといったことについては、一般の方が十分に活躍できます。行政や専門的な団体が市民の力を借りられるような仕組みをまずは公的な力で作り、そこに市民の方、『認知症サポーター』の方などに参加してもらい、行政や専門職がその力を借りていくというスタイルでやっていくことが必要になってくる」