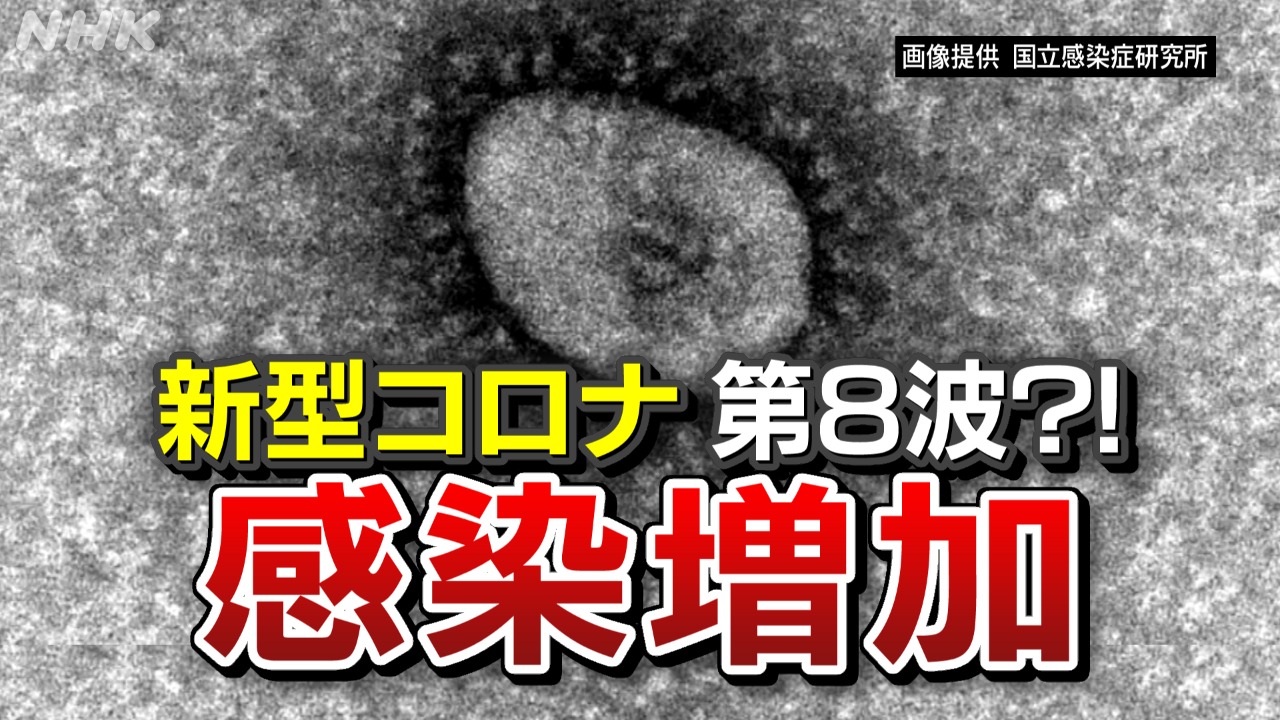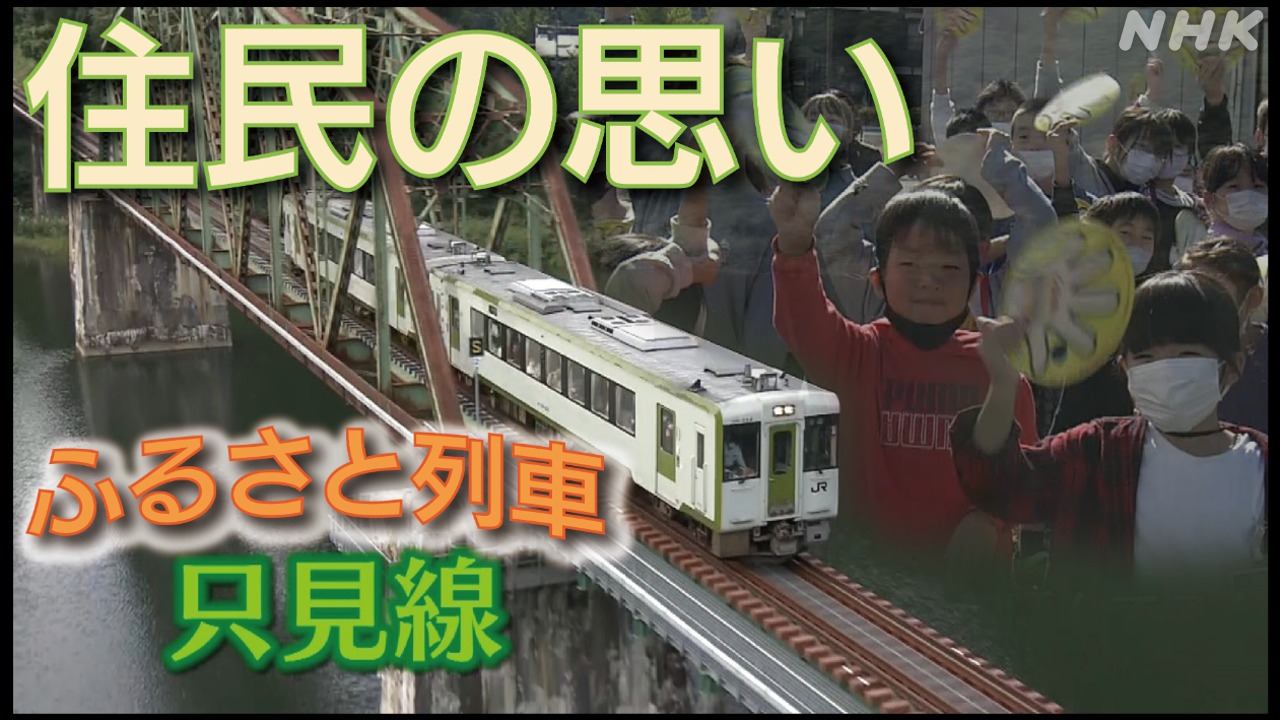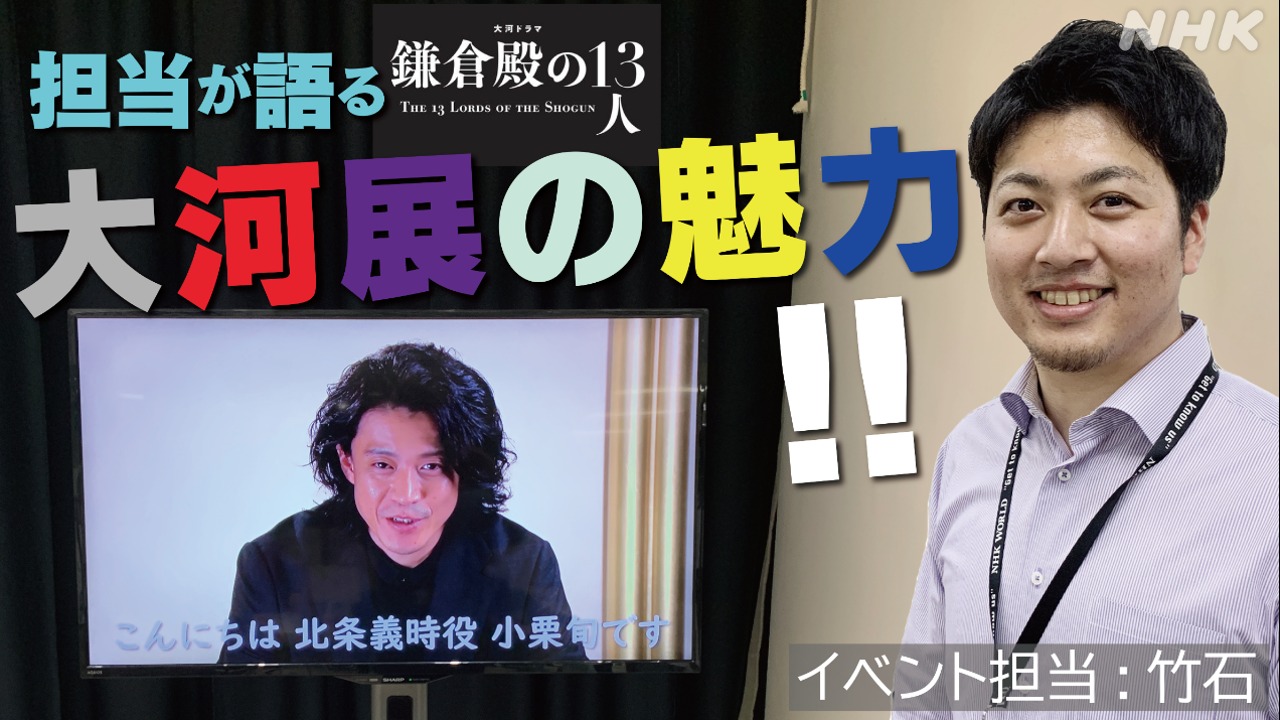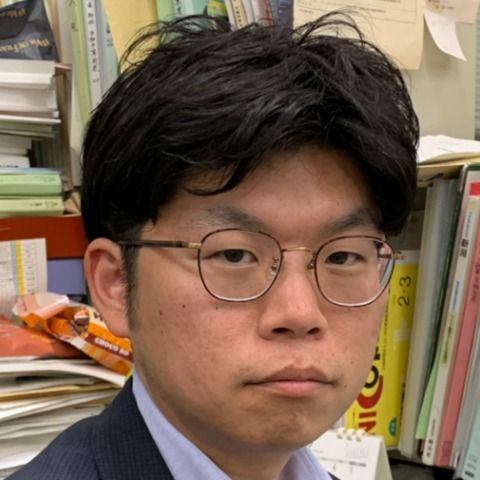不妊治療保険適用拡大 患者数や妊娠数増も 薬不足で現場ピンチ
- 2022年12月07日

「困ったことが起きているんです、薬がなかなか手に入りません」。
晩婚化や働く女性が増える中、少子化対策の一環で国は2022年4月、不妊治療の公的保険の適用範囲を拡大した。
私自身、不妊治療を経験していたこともあって、春から継続取材していたところ、新潟市のクリニックの医師から悲痛な声を聞いた。
適用拡大から半年、当初混乱も予想されたが実際政策の効果は出ているのだろうか。そして薬不足の状況とは。医療の現場や国、メーカーの状況を取材した。
(新潟放送局 野口恭平 記者)
動画はこちら
高まる関心 不妊治療勉強会に熱
11月中旬、新潟市にある産婦人科の「ARTクリニック白山」で行われた不妊治療の勉強会を取材した。

このクリニックでは新型コロナウイルスの感染拡大を受けてこうした勉強会を休止していたが、保険適用の拡大や感染の落ち着きを踏まえ、今春から再開していた。
会場に集まったのは20代から40代の女性とそのパートナーなど約20人でほぼ満席。
これから治療を始める人やより高度な治療を望む人たちに対して治療方法や保険適用の内容、費用などについて理事長の荒川修医師が説明する。

会場を訪れた40代の夫婦に話を聞いた。

妻
このクリニックには2年ほど前から通っていますが、先生に勉強会を紹介してもらい参加しました。タイミング法や人工授精を行っていましたがうまくいかず、保険適用の拡大で負担が減ることもあり治療のステップアップを検討しています。
夫
4月から拡大された保険適用がどのように利用できてどのように負担が軽減されるのかを知ることができてよかったです。どちらかと言えば「妊活をサポートする立場」にいたんですが、これからは「2人一緒に歩んでいく形」で治療に臨みたいと思います。

午後1時半から5時頃まで3時間以上続く長丁場の勉強会だが、皆さん熱心に話を聞いていて関心の高さを感じた。
自己負担 原則3割 高額療養費制度でさらに月額負担を低下
ここで改めて保険適用拡大について整理したい。

不妊治療には患者の状況によっていくつか治療法がある。
保険適用となった主な治療は
▼精子を注入器で直接子宮に注入する「人工授精」、
▼精子と卵子を採取した上でシャーレの上などで受精を促す「体外受精」、
▼卵子に注射針などで精子を注入する「顕微授精」。
国の調査では人工授精にかかる費用は平均で約3万円、より高度な治療となる体外受精の場合は平均で約50万円かかっていたが、保険が適用されて患者の自己負担は原則3割になっている。
さらに大きいのが医療費が一定の上限を超えた際に返還される国の「高額療養費制度」も活用できるようになったことだ。
この制度では年収によって月にどれくらいの負担になるか区分が設けられている。

例えば「ウ」の年収約370万円~770万円の場合、月の医療費の自己負担額は8万円ほどに抑えることができる。
若い世代の患者増 妊娠数も増加
勉強会を行っていた新潟市のクリニックでは保険適用拡大の効果が出ている。
11月下旬、クリニックを訪れた。

「いいですか?5週になったばかりだけど袋(たいのう)も大きいし、ホルモンもいっぱい出ている。順調にいけば心臓が動くのも分かってきます。よかったですね」

荒川医師が伝えると30代前半の女性はうれしそうにエコーの画像をのぞき込んでいた。

こちらの女性、1人目の子どもを人工授精で授かり、保険適用拡大などを受けて2人目の子どもを望んで2022年4月から人工授精を開始。この秋、体外受精に移行し、妊娠が確認された。
荒川医師によると、このクリニックでは今若い患者が増えている。

2022年4月~10月上旬の期間、体外受精や顕微授精のために採卵したのは317件で前年同期比10%の増加、このうち30代前半は60件で33%の増加。
また、クリニック全体で凍結胚移植(体外受精の受精卵を適切なタイミングで移植する。不妊治療の主な治療法)による妊娠率は50.5%と前年同期の34.5%を上回っている。
保険適用の拡大で若い世代の負担が減り、治療を受けやすくなったことが背景にあるという。

荒川医師
私たちのクリニックはもともと新規の患者をある程度抑えているので、絶対数はそこまで変わりませんが、年齢構成では20代、30代が増えています。不妊治療の敷居が低くなっている。一般的には若い方が治療の効果は出やすいので、それが若年齢化と妊娠率の上昇という結果に表れている。非常に短期間に制度が設計される中、混乱も予想されたが多くの現場で医師やスタッフの努力もあって成果に結びついている。
こうした傾向は全国的にも同様のようだ。

全国の不妊治療専門クリニックによる団体「日本生殖補助医療標準化機関」が調査したデータでは、保険適用拡大で体外受精などの患者数が増加したと回答したのは26施設中19施設で73%。35歳未満の若年患者が増加したという施設も58%に上っている。

団体の蔵本武志理事長は「調査では人工授精などの一般不妊治療から体外受精など高度な治療にステップアップした患者も増加していることが分かっていてプラス効果はあった。保険適用で社会的に不妊治療が認知されたことも大きい」と指摘していた。
薬がなかなか手に入らない!
一方で課題も出ているという。それが冒頭お伝えした不妊治療薬の問題。
クリニックの倉庫を見せてもらった。

「薬品を冷蔵庫に入れておくんですけどすっからかん、空っぽなんです」
体外受精などの不妊治療では薬を多く使う。治療前に卵子を育成させてできるだけたくさん採卵できるようにしたり、受精した胚を着床させ発育を支援するためだ。


11月下旬のこの日、クリニックでは主要な治療薬のうち2つの在庫がゼロ。冷蔵庫にはほとんど薬が入っていない状態だった。

荒川医師
40年ほど不妊治療に携わってきたがこんなことは初めてです。
できるだけ患者さんには迷惑をかけないようにやりたいんですが、こればっかりは本当に『ない袖は振れない』ということになります。
厚生労働省やメーカーの見解は
これはこのクリニックに限った話しではなく、不妊治療専門のクリニックによる団体の理事長も薬が入手しづらい状況だと指摘していた。
こうした状況を厚生労働省はどう認識しているのか。
医薬産業振興・医療情報企画課の担当者は「治療ができなくなるほど深刻な状況ではない」としつつ、薬が調達しづらくなっているとの認識を示した。要因は不妊治療で国内の需要が高まっていることに加えて、一部の製薬メーカーの個別の事情で供給が減ったことで他メーカーへの注文が増加する形で連鎖的に需給バランスが崩れているという。
卵子を育成するためなどに使う「黄体ホルモン剤」というタイプの薬は11月時点で保険適用の薬を提供する14社のうち12社で需要が供給を上回るなどして「限定出荷」の状況になっていたそうだ。このため厚生労働省ではメーカーに増産などの対応をとるよう呼びかけている。
製薬メーカーにも話を聞いた。
あるメーカーは在庫を活用して出荷量を2倍に増やし、また「増産に向け対応を検討中」と回答したメーカーもあった。
一方、「すぐには生産ラインを増やせないし、薬の材料を調達する必要もある。可能な限り努力をしたいが具体的なことは申し上げづらい…」と増産のハードルが高いことを示唆する会社もあった。
「治療に影響も出かねない」
このように、メーカーがどのように対応するか不透明な部分も多く、需給バランスがいつ改善するか見通しがつかない。

新潟市のクリニックでは、通常よりも値段が高い薬でも手に入るようであれば入手して、患者の理解を得た上で使うなど何とか対応を続けている。ただ、こうした状況が続けば治療に影響も出かねないとして改善を訴えている。

荒川医師
患者さんに「ごめんなさい」といってあるものでやっているのが現状。これ以上製品が入ってこないと体外受精を予約制にしたり、1~2か月体外受精をストップしないといけないところまで来ています。春になれば状況がよくなる見込みもなく不安に思いながら何とか1日1日過ごしてるという感じです。
今回はお伝えしきれなかったが、保険適用拡大では高齢で治療が必要な患者でも治療の回数が少なかったり保険の対象とならなかったりなどといった課題もある。新たな制度は運用がまだ始まったばかりで、今後も現場の課題や患者の声を伝えていきたい。