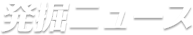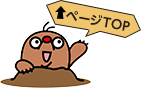No.260
2020.03.20
スポーツ
1964東京パラリンピックのカラー記録映像発掘!

今回の「発掘ニュース」は56年前に開催された東京パラリンピックの貴重なカラー記録映像発掘です!今月3日『おはよう日本』と『ニュースウォッチ9』でいち早くお伝えしました。


さらに翌日4日には午前10時5分から総合テレビで放送の『くらし☆解説』でもご紹介。
内容は番組のホームページで詳しくご覧いただけます。
★どんな映像が?

今回発掘された映像には冒頭にご覧のような画面があり、当時の厚生省(現在の厚生労働省)と、1964年パラリンピック東京大会に多くの参加者を出した当時の国立箱根療養所が企画・製作したものであることが分かります。さっそく映像の一部をご紹介しましょう!

「パラリンピック東京大会は、1964年11月8日から12日までの5日間、20か国約370名の選手たちを集め、東京・代々木のオリンピック選手村を中心に盛大に行われました。」

女性のナレーションとともに始まった27分あまりの映像、エンジ色のそろいのユニフォームで入場する日本選手団の様子も鮮やかなカラーで!
開会式の紹介後には、こんなコメントが…

「私たちは、このようにたくさんの外国選手が集まった大会を機会に、各国の選手の損傷の状態や生活状態などについて実態を調査しました。」
単にパラリンピックの様子を紹介するだけでなく、各国からの参加者がどのような環境の中で障害者スポーツを行っているのか?調査結果を報告するための映像でもあるようです。
★どんな競技が?
1964年の東京パラリンピックでは17種目の競技が行われましたが、そのうち15種目が記録されています。映像からは色々な発見が…

現在のパラスポーツの中でも代表格・車いすバスケットボールです。会場は屋外のバスケットボールコートで国立代々木競技場が向こうに見えています。現在との違いはなんといっても“車いす”。まだ競技用の車いすではなく、一般の車いすを使用しています。

車いすフェンシングの映像では、車いすが動かないように支えるボランティアの姿!選手と同じように防具のマスクをしてのサポートです。

陸上のフィールド競技でもボーイスカウトのボランティアが車いすを支えています。
また、現在は行われていない競技の映像もしっかりと残されていました…

こちらは『やり正確投げ』という競技です。ナレーションを聞いてみると…

「やり正確投げは、投てき線から男子では10メートル、女子は7メートルのところに中心をもつ直径3メートルの標的を置き、それに向かってやりを正確に投げ、採点する競技です。」
このほかにも、アーチェリーとダーツを組み合わせた『ダーチャリー』という競技や、車いすで狭い旗の間を通ったり段差を越えたりする『スラローム』という種目などが記録されていました。
★誰が映像を?
『おはよう日本』や『ニュースウォッチ9』では映像を提供してくださった細谷晃宏さんを取材しました。

神奈川県厚木市にお住まいの細谷さん、父親の公夫さんが保管していたフィルムの中に映像が残されているのを見つけました。
「父は映像に関わった仕事をしていましたので、おそらく映っている中身の価値についてはすごく意識があったと思います。」

父親の公夫さんは多くの選手が出場した国立箱根療養所で写真技師として働いていました。公夫さんが大切に保管していた16ミリの鮮明なネガフィルムは状態が良く、当時の色彩が鮮やかによみがえりました。
★調査結果は?
27分余りの映像の最後には、1964年東京パラリンピックの際に行われた調査の結果がコメントされています。

「脊髄損傷138名の外国人選手について、傷を受けたあと病院にいた期間を見ると次のようになっています。6か月以内22名、1年以内41名、2年以内32名、3年以内12名、4年7名、5年8名で、半数は1年以内で病院生活から離れているのです。そして193名の全調査数のうち、フィリピン選手の全員とイタリア選手の大半をのぞく121名は自動車を持っており、また49.2%に当たる95名が職業を持っています。」

「競技を通じて、あるいは日常生活を通じて、外国選手と日本選手がよく比較されました。外国選手は全般に朗らかでスポーツも楽しみながらやっているのに対し、日本選手はその逆であるということです。この比較の陰には、日本選手の大多数は病院や療養所の入院患者であり、外国選手は社会人であるという環境の差があるのです。」
この記録映像は、パラリンピックを通して当時の日本の障がい者が置かれている環境について問題提起しているのかもしれません。あれから56年、何がどう変わったでしょうか?進化した2020東京パラリンピックに注目です!