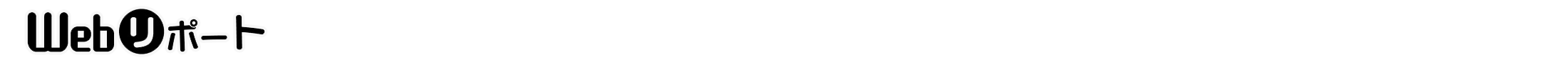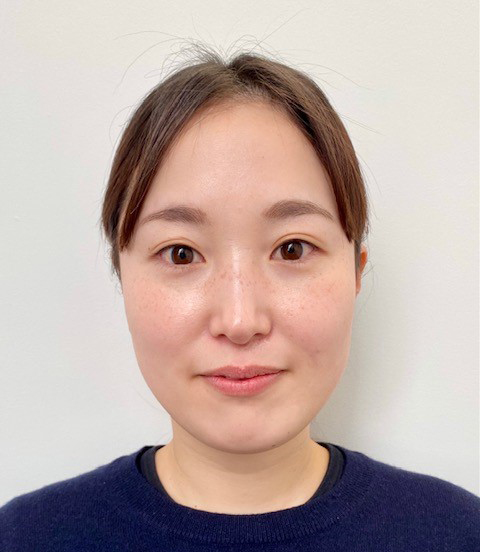芥川賞候補作「ハンチバック」作家・市川沙央さん 重度障害の当事者として描く
- 2023年6月26日

「本を読むたび背骨は曲がり肺を潰し喉に孔を穿ち歩いては頭をぶつけ、私の身体は生きるために壊れてきた。」
歴史ある文学賞のひとつ、第128回文學界新人賞を受賞し、第169回の芥川賞も受賞した話題作「ハンチバック」。重度障害者の主人公が、グループホームの一室からあらゆる言葉を送り出す様を、ユーモアを交えながらも鋭い言葉で描く作品です。
作者は、みずからも重度障害者の市川沙央さん(43)。文学界では非常に“珍しい”重度障害当事者の作家として、今回、みずから初の純文学に挑みました。強く響く言葉の数々…、市川さんはこの作品にどんな思いをこめたのでしょうか。(首都圏局/ディレクター 田中かな)
※市川沙央さんの作品「ハンチバック」が、第169回芥川賞を受賞したため、後日記事に追記いたしました。
20年挑戦し続けてきた“小説” 初の純文学で鮮烈デビュー

タブレット型端末を使って執筆する市川さん
市川沙央さんは、SFやファンタジーなどエンターテインメント系の作品を中心に20年以上執筆活動を続け、毎年公募に挑戦してきました。今回、芥川賞にも選ばれた作品は、市川さんにとって初めての純文学。鮮烈なデビューを果たした市川さんは、これまでの公募生活を振り返り、とにかくほっとしたといいます。
作家 市川沙央さん
「全然予想していなかったのでびっくりすると同時に、私はずっと20年も小説を送り続けていたので、やっとそれが届いたようでほっとしました。
公募挑戦者にとって選考期間における原稿のゆくえは“シュレディンガーの猫”なんです。
私は20年間、箱の中の猫の安否に精神をすり減らしてきましたので、やっと生きて箱から出てきた猫を見て安心しましたし、もう二度と心配する必要がないんだと思って脱力しました」

中学生の頃の市川さん
市川さんは、幼少期に難病のひとつ、筋疾患先天性ミオパチーと診断されました。中学2年生の5月ごろには疲れやすくなって毎夜のように金縛りにあい、大事をとって入院した翌日、昼食後に病室でテレビを見ていたら眠るように意識がなくなりました。それ以来、横になる時は人工呼吸器をつけて暮らしています。
思うように外出ができなくなった市川さん。特別、小説家になりたいと思ったことはないといいますが、20歳を過ぎた頃「自分には小説家くらいしかやれることがない」と自覚し、作品を書き続けてきました。
話題作「ハンチバック」 重度障害者を主人公に“人間”を描く

市川さんが初めて挑んだ純文学の作品「ハンチバック」。
その主人公、井沢釈華(しゃか)は、親が残したグループホームで暮らす重度障害者です。通信制大学で論文を書きながら、Webライターとしてもコタツ記事(独自に取材をせずインターネット上の情報などのみで書く記事)を書き、日々を過ごします。
記事を書いて稼いだお金は、全額寄付へ充てるなど、金銭的には裕福な釈華。一方で、理想とする“人間”の姿に葛藤し、SNSの裏アカウントでは「生まれ変わったら高級娼婦になりたい」「普通の人間の女のように子どもを宿して中絶するのが私の夢」などと書きつづります。
釈華は、どこかふかんした視点で、ままならぬ体で生きる心情を吐露していきます。
市川さんが重度障害者を描くことにしたきっかけは、何だったのでしょうか。
「去年まで通学していた通信課程大学の卒業論文を書くために、障害者の歴史や差別の歴史をずっとリサーチしていました。今までよりもそのことに関心が深まったと同時に、ちょっとした怒りみたいなものも生まれてきました。
なかでも、日本の読書バリアフリー環境の前進のなさに対するいらだちは執筆のいちばんの動機でした。小説も学術書も、障害者の読書が想定されていない(=電子化されていない)ものが多く存在すること自体に大きな問題があると思っています。重度障害者が本を読んだり学者になったりするとは思わないのかもしれません。
その可能性に目を向けていただくために、論文を書く釈華というキャラクターに自分自身を投影して『当事者表象』を行うことが必要でした」

障害者は読者ではないのか?―作品に込めた「怒り」
執筆の大きな動機となった「読書バリアフリー環境」に関するフレーズは、作品の随所に見られます。
―私は紙の本を憎んでいた。目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、
読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること、――5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモを憎んでいた。
「健常者の特権性」を指摘する鋭い描写に対し、SNS上では「考えたこともなかった」「胸に突き刺さった」などと反響が集まり、大きな話題を呼ぶひとつの要因になっています。
一方で、市川さんはこうした世間の反応には驚きがあったといいます。
「こういうものは珍しいだろうと思って書いたのは事実ですが、いやでもそこまで言われるほど重度障害者の実態って珍しかったですか…そ、そんなに…???と首をひねるばかりです。
(「健常者の特権性」を指摘した部分については)結構大きな反応をいただいてしまって、私としてはそこまで刺さるのかという気持ちで…。
そこまで刺したいとは思っていなかったのですが、でも通じたことはとてもうれしく思っています」
“障害者が怪物化されるのでは…”という懸念 当事者の声を伝えたい

当事者である自分が障害者を描くことには、不安もあったといいます。ただ一方で、当事者が書くことで、実存する“多様性のうちのひとつ”を伝えられるかもしれないという思いもあったと市川さんは話します。
「当事者だといっても私が重度障害者や筋疾患患者を代表できるわけではないし、するべきでもないし、そう見られることに危惧がないわけではありませんが(私が困るのではなくて、他の障害女性に迷惑がかかるのではと…)。
近年、介護者や、きょうだい児や、ヤングケアラーといった、障害者を支える側に光が当てられる傾向が拡大していて、もちろんそれはとても良いことで大切なことなのですが、その一方で相対的に支援を受ける側の障害者がやっかいなものとして大衆の意識の中で悪魔化、怪物化されていくのではないか、という懸念があります。人間はどうしても自分に似たもののほうにシンパシーを寄せるものだからです。なので、障害者も同じ人間であるということが大衆にも感覚的にわかるように、客体ではなく主体的に、障害者自身が声を出していくことが必要だと思っています」
障害者の生活も心情も克明に記す

「ハンチバック」の主人公・釈華は、市川さんと同じ病気です。作品には、重度障害者の生活や心情のひとつひとつも、丁寧に、克明に描写されています。
今回特別な取材は行わなかったということですが、医療行為の描写は、市川さんの実体験がもとになっています。
―奥から湧いてきた痰をふたたび吸引して取りきると脳に酸素が行き渡って気持ちが、いい。
―悲鳴のための空気は声帯に届く前に、気管切開口にカニューレを嵌めた気道からすうすうと漏れるだけだ。
「これはしかし、あまりほかの作家さんと変わらないと思います。通学経験にもとづいて青春ものを書くのも、会社員が会社員の話を書くのも、障害者が障害者の話を書くのも、創作過程やイマジネーションの濃度に違いがあるとは思いません。
一つ、(作中にある)「転ばないでね」というのは実際に母からよく言われております。転んだら最後だと思って常に次の一歩でつまずいて転ぶさまを脳内シミュレーションしながら家の中を歩いています。VRのように脳内で転ぶたびに心臓がヒヤッとするのでこれもう実質的に転んでるのと変わりないんじゃないかなと思っています」
作品の中では、支援を受ける側から見た異性入浴介助の問題についても触れています。
―私の身体を丁寧に洗われてしまうのか?洗わなければ仕事にならない。仕事をしてもらう。それだけの話だ。
―障害者は性的な存在ではない。社会が作ったその定義に私は同意した。自分に都合よく嘘を吐いて同意した。
「先日『異性入浴介助』に関する話題が、SNS上で大炎上していました。
当事者女性の悲痛な訴えが、世間からあれほどの総攻撃を受けることに私は大変驚きました。
振り返って『ハンチバック』の異性介助への言及部分を読み返してみて、自分がかなり世間に気を遣った書き方をしていることに二度驚きました。炎上しないように周到な書き方をしていますね。
どうしてこういった書き方がされているのかを含めて、読まれた方には考えていただければいいのかなと思いますが…。
諸々の現実的事情から行われている異性入浴介助は、信頼関係が前提であるべきものです。
件のツイートへの総攻撃の中に、婦人科など医療機関での検査を例に相対化しようとする意見が多くみられましたが、医療機関での行為は自己決定にもとづいた信頼関係が前提となっています。
多少無理をすれば受診先を変えることも健常者にはできます。
長く行われてきた障害者施設や病棟での異性入浴介助は、身体の動かない障害者にとって他に逃げ場のない状態、命に関わる衣食住の自由と権利をすべて相手に握られた状態で強制されてきたもので、閉鎖空間での虐待であり人権侵害です。健常者の経験とは性質がまったく異なります。
自立生活においても、国のガイドラインどおり、同性介助が基本であるべきと思います。
『異性入浴介助』…こんなにも人間の心情的にごく普通の訴えすら共有されず、共感してもらえないらしい現状に、私は本当にただただ驚いています」
「メインストリーム」に… 重度障害者が主体の作品をこれからも
20年近い間、“書くこと”を続けてきた市川さん。小説の執筆だけでなく、ライターとして、また読者としても、多種多様な文章に触れてきました。しかし、「重度障害者が主体となる文学作品」にはなかなか出会えませんでした。今回の作品に多くの反響も集まる中、障害者が主体となる作品を今後もみずから手がけたいと考えています。
「エンタメ小説、アニメ、漫画、映画、ドラマなどでは、パッと思いつく、(重度障害者が主人公の)“超有名作品”がなくはないんですよ。SFが多いですけど。『鋼の錬金術師』だって片手片足がない主人公です。前回のアガサ・クリスティー賞は脊損で寝たきりの医師が遠隔手術を行ったりVRゲームに没入したりするSFでした。
しかし、いずれも当事者作家の作品ではない。仁木悦子さんくらいまでさかのぼらないと、障害者で有名作家という人は見当たりません。国会議員に重度障害者が三人もいて作家がいないというのもおかしいだろうと思ったのでした。この現代に。
加えて私は「メインストリーム」というものにこだわりがあって…。福祉関係のものって、もともとそれに関心のある福祉関係者の目にしか触れないんです。そんなことでは一向に障害者を分離している状態が解けないと思うので、よりポピュラーなかたちで多くの人のもとに届くようなお話を書きたいです。
今回この小説が反響をいただいていること自体、重度障害者の生活があまり知られていないのかなと思いました。今この社会は健常者と障害者の社会が分かれてしまっているところがありますけれども、本当に隣近所に障害者がいて、ふたつの世界が混ざり合っているような状態になればいいなと思っています。それが教育の段階から必要だと思っています」

市川さんが、より多くの人に読んでもらいたいという思いで、「文学」にこだわり執筆した「ハンチバック」。読者には、純粋に作品を楽しんで読んでもらいたいと話します。
「作家としては、まず作品で伝えきることが誠実であろうとは思います。『ハンチバック』は難解な比喩も暗喩もなく、そこそこ分かりやすい小説だと思いますので、短いですし、まずは手に取って読んでいただければ、そこに平べったい『多様性』という題目ではなく『実存としての多様性』をのぞき見することができるのではないかと思います」