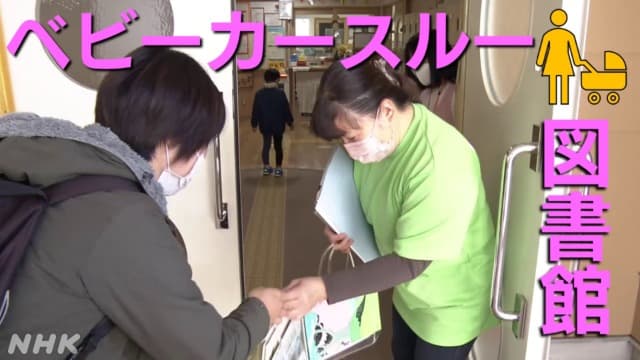WEBリポート
- 2021年12月30日
川崎市がけ崩れ実験15人死亡 事故から50年 なぜ実験は惨事に
- キーワード:

「人工の雨でがけ崩れを起こす実験をしていたところ、予想を上回る大量の土砂が崩れ落ち、15人が死亡…」
50年前のNHKニュースで、アナウンサーが緊迫した様子でこう伝えた。東京の多摩地区や川崎、横浜の丘陵地帯で相次いでいた土砂災害のメカニズムを解き明かそうと行われた実験が、一転して大惨事になったのだ。
「川崎ローム斜面崩壊実験事故」はなぜ起きたのか、50年後の今に何を問いかけるのか。
(首都圏局/ディレクター 三島康生)
3.2秒の悲劇
実験は昭和46年11月11日、当時の科学技術庁や建設省などによって、川崎市の生田緑地で行われた。土砂災害を再現して防災対策に生かそうと、実際の斜面に散水ポンプで大量の雨を降らせたのだ。しかし、実験中に予想を超える斜面崩壊が起こり、現場に立ち会っていた15人が犠牲となった。

幅15m 長さ19mにわたり斜面が崩れ落ちた
この実験はマスメディア各社も取材。NHKのカメラもその様子を記録していた。映像では、斜面が突然盛り上がって崩れ落ちる様子が映っている。
動画は速度を10倍に遅くしたスローモーション
ニュースは連日、報じられた。2日後のNHKニュースでは、映像から分析した結果を次のように報じている。

(1971年11月13日NHKニュースより)
15人の犠牲者を出した川崎市のがけ崩れの実験事故は、斜面が異常に盛り上がり始めてから下にいた人々が土砂に巻き込まれるまで、わずか3.2秒しかなかったことが、NHKのカメラマンが撮影したフィルムからあきらかになりました。
続いて画面には、崩れた土砂を懸命に掘り起こす様子や、泥だらけになって運ばれる人が映し出される。撮影していたNHKのカメラマンも犠牲になったこともあり、アナウンサーは終始、沈痛な様子でこのニュースを伝えている。

都市化で頻発したがけ崩れ被害
それにしてもこの実験は、なぜ行われたのか。

政府の事故調査委員会が3年後の昭和49年にまとめた「ローム斜面崩壊実験事故調査報告書」がNHKにも保管されていた。
それによると、昭和30年代から40年代にかけて急速に宅地化が進んだ東京の多摩地区や横浜・川崎など京浜地区で、がけ崩れの被害が相次ぎ、年平均で200か所に達することもあったとされている。
事故の5年前に放送されたNHKの番組「新日本紀行」では、当時の状況が次のように説明されている。

(1966年1月放送 新日本紀行~多摩丘陵~より)
山の斜面をただ切り取っただけという危険な宅地が、許可もなしにあっという間に出来上がっています。高い家賃や地価に追われるように、安い土地を求めて押し寄せる人の波は、これまでそのままでは人の住めなかった山の斜面にまで今伸びているのです。こうしたがけ崩れの危険のある場所は川崎市だけでも82か所(当時)に達しています。
被害を受けた場所の多くに、ローム層という、火山灰に由来する地層が分布していた。実験の目的は、このローム層が露出した崖に人工的に雨を降らせてがけ崩れを起こすことで、メカニズムを解明し、防災対策のための基礎データを得ることだったのだ。

(1966年1月放送 新日本紀行~多摩丘陵~より)
“土砂は柵の所まで来ない”
実験の概要はこうだ。
生田緑地内に設定された試験地は、高さ20メートル幅15メートルほど、角度30度の斜面。ポンプでくみ上げた水を放水して人工的にがけ崩れを起こし、斜面のおよそ150か所に設置した観測機器で、土砂や水の動きを記録するというものだ。

防護柵の下に見学者や報道陣がいた
計測班や報道陣は、試験地の側面ではなく、斜面最下部から約50メートル離れた正面で計測・記録を行うことになっていた。手前には高さ1メートルの竹で作られた柵も設置され、実験関係者は「土砂は柵のところまでは来ない」と説明していた。

記録用のカメラ
放水は11月9日から始まり、現場では「11日の昼ごろには土砂崩れが起きるだろう」とされていた。ただ、自然を相手にした実験は必ずしも思いどおりには進んでいなかったようだ 。

散水の様子
予定では正午から午後1時にかけて“土砂崩れ”が起こる予定であったが、予定時刻を過ぎても崩れないので、さらに放水を続けた。
(生田事故20回忌と事故のあらまし/地質ニュース438号 村瀬正・鈴木尉元 1991年)
実験は当初、非公開で行うと計画されていた。しかし、話をききつけた報道関係者からの問い合わせもあり、急遽、前日になって実験の実施を報道発表。
当日は報道関係者や見学者30名ほどが集まった。 報告書には、関係者の間に、ある“危惧”があったと記されている。
「実験担当者の間では、崩れないであろうとか、崩れてもその規模は小さいであろうなどの予測が話題になっていたようで、むしろ、崩壊が起こらなかった場合に、見学者達を失望させることを心配しあっていた」(報告書より)
川崎市職員の証言
この時、現場に居合わせたのが長沢進さん(73)。川崎市公害局で地盤沈下対策の仕事をしていた。
当時23歳の新人職員だった長沢さんは、事故発生の2時間ほど前、午後1時半ごろ、同僚とともに現場の生田緑地を訪れた。

当時の映像を見る長沢さん
長沢さん
「たまたま実験があることを知り、自分の仕事に直接関係はないけれど、教養というか、見学するのもひとつの勉強かなと思って出かけました。同僚と2人で、見学コースという看板にしたがって崖の下に行って『あそこが崩れるのかな』などと言いながら見ていました」
すでに、がけ崩れ実験の瞬間をとらえようと、報道各社の記者やカメラマンも集まっていた。 当時の映像では、実験関係者と思われる数人のほかは、ヘルメットをした人が見当たらない。

朝9時台には時間当たり最大19ミリだった雨量を徐々に増やし、午後0時台には時間55ミリ、午後1時台、2時台には60ミリを超え「非常に激しい雨」に相当する雨量に達した。

散水用のポンプ
当時の資料を分析した防災科学技術研究所 井口 隆 客員研究員
「そろそろやめて明日にしてはと進言した方もおられたようです。しかし、せっかく報道陣が来ているのだから、なんとか崩壊させていいシーンをとらせたいというようなサービス精神もあったのではないかと推察されます」
午後3時29分 崩壊
午後2時には放水機器を2台から3台に増やし、午後3時台には時間100ミリ相当の「猛烈な雨」が降り注いだ。
午後3時23分、崩壊が切迫していることを知らせる笛が鳴らされた。
「あと15分から20分で崩壊」
ハンドマイクでアナウンスが行われた。
報告書には「やや待ちくたびれていた報道陣や見学者に緊張が走り始めた」と記されている。
そして午後3時29分、再び笛。崩壊を知らせる合図が響いた。
長沢さん
「カメラを持っていたので、ファインダーをのぞき始めたんです。崖の上のほうに照準を合わせて、一番上のところが一瞬、土が盛り上がったというのは分かりました。シャッターを切ったのとほぼ同時に、隣で見ていた人が『逃げろ』と言ったんです」
土砂は目の前の柵をなぎ倒して襲ってきた。
長沢さんは土砂に飲み込まれ、数メートル後ろの池の近くまで流された。幸い顔の半分は埋まらず手も使えたので、土砂を取り除き、呼吸をして助けを呼ぶことができた。腰の骨や鎖骨などを折る重傷を負ったが、一命をとりとめることができた。

「最初の衝撃で飲み込まれて、『ああもう死ぬかな』と思いながら流されたという感覚です 。私の右隣に、新聞社の方か何かわかりませんが、大きなフィルムのカメラで座って撮られていた方がいて、逃げる余地はあったのだろうかと。あれだけの方が亡くなって重軽傷者が出て、一生懸命仕事していてそうなったのだなと思うと…」

泥にまみれて見つかったカメラ
見過ごされた捨て土と封印されたデータ
この事故で、15人が土砂に飲み込まれて亡くなった。
実験関係者のほか、川崎市の公園事務所の職員、報道関係者、中には実験関係者に書類を届けに来て、そのまま見学していたという会社員2人もいた。
最後まで行方が分からなかったNHKのカメラマン1名は、夜を徹した捜索の結果、翌日未明にみつかり、死亡が確認された。享年35歳。妻と幼い子ども2人が遺された。
のちの調査で、土砂は最大で毎秒17メートル、時速60キロ以上で流れ落ちたことがわかった。当初の想定、毎秒6メートル(時速22キロ)の、実に3倍近いスピードだった。
当初の計画では、数万年以上前に堆積した深い地層の下で、比較的ゆっくり崩壊することが想定されていたとみられている。しかし、実際に崩れた土砂の多くは、実験のわずか4年前、公園内の遊歩道を整備する際に削られた残土「捨て土」だったことがわかった。しかも「捨て土」の存在は、実験地が生田に決まったあとにわかったというのだ。

(1971年11月13日NHKニュースより)
この事故では、当時の平泉科学技術庁長官が辞任。実験関係者ら2人が業務上過失致死傷の罪に問われて起訴された。事故から16年後の1987年、横浜地裁は「当時の学問水準では事故の危険性を予測することは不可能だった」などとして、2人の被告にいずれも無罪を言い渡した。検察は控訴を断念。1審で無罪が確定した。
実験データは長きにわたり押収され、本来の防災にいかされることはなかった。そして事故のあと、自然斜面での崩壊実験は長らく“タブー”とされた。
令和の今 実験事故を振り返る
事故から50年後の2021年12月、防災科学技術研究所が主催する土砂災害予測に関する研究集会がオンラインで行われ、テーマのひとつに、「川崎ローム斜面崩壊実験事故から50年」が据えられた。関係者が減る中で改めて事故を振り返り、教訓を次世代につなげたいと企画された。

研究所に残された当時の記録などを調査した防災科学技術研究所の井口隆客員研究員は、実験の経緯について次のように報告した。

井口隆 客員研究員
「人工降雨による斜面崩壊実験は当初の研究計画にはなかった。しかし、『予算が通りやすい』ということで、いわば『目玉』として、あとから追加された」
研究者からは、目標設定が不十分なまま、実験ありきで行われたのではないか、といった厳しい見方が出された。
一方で、陽の目を見なかった50年前の実験データを、今後、活用できないかという議論も交わされた。

(画像提供:防災科学技術研究所)
日本地すべり学会元会長 日本森林技術協会 落合博貴さん
「なかなか目にするチャンスがないデータだったが、改めて見ると、かなり解析する余地があるデータだと思う」
井口隆 客員研究員
「事故調査報告書の付属資料として300ページ以上のデータが残っている。計測機器の精度は今の水準からみると劣るかもしれないが、公開されていれば、いろいろな研究に役立ったのではないか」
研究者らは今後、当時のデータや映像を、現在の技術で解析するなどして役立てることができないか、模索していきたいとしている。
取材後記
木々が色づく川崎市多摩区の生田緑地にはいま、慰霊碑が、崩れた斜面を背にしてひっそりと建っている。

事故から50年たった11月のある日、現場を訪れると、亡くなった方の関係者だろうか。花が手向けられていた。
筆者はかつて大学で土木工学を学んだ。実験室では、土を装置に入れてデータを取る実験が盛んに行われた。実際のフィールドでどんな現象が起き、どんなデータが得られるのかを確かめたいという当時の研究者たちの思いには共感も覚えた。 しかし、15人という多くの人命を奪い、その周囲の人たちを悲しみに陥れた事実は、あまりにも重い。
生田の森で研究者たちが求めた現象解明、そして失われた15の命。今なお、想定を超える雨が降り災害が絶えない中で、川崎の惨事から学ぶことは、少なくないと思う。