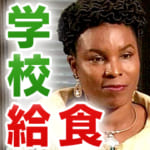東日本大震災 被災後の生活で肥満増加 “魚介類でリスク低減”

東日本大震災で被災した人の食生活について岩手医科大学などの研究グループが大規模調査を行ったところ魚介類を食べる頻度が高い男性ほど肥満になるリスクが低かったことがわかりました。
研究グループは被災後の食事に脂肪を燃やす働きがある栄養素が豊富な魚介類を取り入れる重要性を指摘しています。
岩手医科大学と医薬基盤・健康・栄養研究所などでつくる研究グループは東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県の陸前高田市や大槌町など4つの自治体で被災した1万人について追跡調査を行いこのうち4410人の健康と生活習慣の関わりについて結果を分析しました。

その結果、震災から2年間で新たに296人が肥満になっていましたが、魚介類の摂取量との関連を統計学的に分析したところ魚介類を3食食べていた人はまったく食べていなかった人と比べて肥満になるリスクが低くなっていたことがわかりました。
魚をとる食事の回数が多いほどリスクは低かったということです。
この傾向は男性にのみ見られ、特に仮設住宅に暮らす人のほうが影響が大きくなっていました。
大規模災害が発生し避難生活が長引くと、おにぎりなどの炭水化物中心の食生活になるうえ、環境の変化で運動不足になることなどが影響していると見られるということです。

魚介類には脂肪を燃やす働きがある「タウリン」やDHA、EPAが豊富に含まれているためだと考えられるということです。
専門家「バランスを考慮した備蓄を」

医薬基盤・健康・栄養研究所 国際災害栄養研究室の笠岡宜代室長は「男性に傾向が強く見られたのは平時から女性より肥満の割合が高いためで、女性には魚介類の摂取の効果がないということではないと思う」としたうえで「大規模災害への対策として、ふだんの食生活に近くバランスの取れた食事がとれるよう備えておくことが大事なので家庭や職場、自治体でも何を備蓄しておくかや被災したあとの食生活についても考えてもらいたい」と話していました。