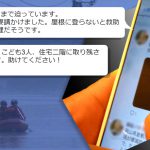豪雨被災の町内会 複数が
再開できず 倉敷 真備町

3年前の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町で、複数の町内会が被災したあとに、かつての活動を再開できていないことがわかりました。
西日本豪雨で甚大な被害を受けた倉敷市真備町では、豪雨からおよそ3年で、人口が全体の1割に当たる2000人余り減少し、地域の町内会をどのように運営するかが課題となっています。
町内会は住民どうしの任意団体で、届け出る必要がないため、自治体は現状の正確な数を把握しておらず、NHKは倉敷市の広報紙を受け取っている町内会などの代表者の数で全体状況を推定しました。
その結果、真備地区では被災前の平成30年7月時点で、384人が代表者として倉敷市に登録されていましたが、今月は271人と、およそ3割減っていることが分かりました。
また、代表者が登録されなくなった複数の地域の人に理由を尋ねたところ、町内会が機能せず活動がほぼ行えなくなったとか、解散を決めたなどの回答相次ぎ、複数の町内会が、被災後にかつての活動を再開できていませんでした。
東日本大震災の被災地で地域活動の支援を続けてきた岩手大学の広田純一名誉教授は「災害時には地域の住民どうしで助け合う必要があり、町内会の役割は重要だ。コミュニティーは自然には再生できないので、行政が積極的に支援する必要がある」と指摘しています。