自民党は必要ない!?
“官邸主導”の行方

「官邸主導」、「政高党低」ーーーこれらは、第2次安倍政権発足以降の政治状況を表す言葉として、たびたび使われてきました。政府・与党内での意思決定を首相官邸がリードする状況が5年余り続き、自民党内からは、「このままでは自民党は必要ない」という声まであがっています。政府と与党の理想的な関係は?また、ことし秋の自民党総裁選挙に向けて、状況が変化する可能性はあるのか探ります。
(政治部記者 根本幸太郎 川田浩気)
進次郎氏、ほえる

「このままでは自民党は必要ないですよ。おかしい」
衆議院選挙での自民党圧勝の余韻が残る去年11月、小泉進次郎筆頭副幹事長から、その発言は突然、飛び出しました。
小泉氏は、安倍総理大臣が、衆議院選挙の公約で掲げた幼児教育の無償化に充てる財源の一部を経済界に負担するよう要請したことに対し、党内で議論がないまま政府が方針を決めたと、強い不快感を示したのです。
党内では、衆議院の解散にあたって、「消費税の使いみちを見直し、幼児教育の無償化に充てる」という方針を、安倍総理大臣が党との議論抜きに打ち出したことにも不満が出ていました。それだけに、ある閣僚経験者も「小泉進次郎議員が怒るのもよくわかる」と同調するなど、小泉氏の発言に賛同する意見も聞かれました。
変わる政治「天気図」

自民党内から不満が出る背景には、政策を決定するまでの政府と与党の関係が変化してきたことがあります。
自民党政権では、政府が、国会に予算案や法案などを提出したり、重要な政策方針を決定したりする前に、党の政務調査会などで審査し、了承を取り付ける「事前審査」という制度をとっています。決定までに、政府・与党・関係者の調整を整え、その後の国会審議などを円滑に進めるという狙いがあります。
かつては、この仕組みを通じて、各政策分野に精通している、いわゆる「族議員」が、政策作りそのものにも関与し、関係団体などとの調整も行うなど、存在感を示しました。党が政策決定を主導し、政府に実施を迫るという「党高政低」と言われる時代が続いてきました。

(経済財政諮問会議)
しかし、平成13年に発足した小泉政権以降、総理大臣のもとに設けた「経済財政諮問会議」などを活用し、首相官邸が主導して、政策を決定する流れが強まります。変化の激しい国際情勢や世界経済などにスピード感をもって対応するために、総理大臣のリーダーシップが、より求められるようになったのです。また、改革を進めるために「族議員」の影響を排除する狙いもありました。
徐々に政府と与党の力関係が変化し、「党高政低」から、政府=首相官邸が主導する「政高党低」になったと言われるようになりました。
官邸主導に聖域なし
こうした官邸主導型の政治は、「安倍1強」と呼ばれる政治情勢が続く中、一層強まっていると指摘されています。
象徴的な出来事として印象に残っているのは、3年前、消費税率の軽減税率導入をめぐる税制改正の議論です。

安倍総理大臣が、導入に慎重な姿勢を示してきた党税制調査会の野田毅会長を宮沢洋一氏に交代させ、導入に向けて調整を急ぐよう指示したのです。その後も、軽減税率の対象品目などが首相官邸の意向を受けて決定されました。
自民党税制調査会は党の政務調査会の一機関ですが、税制が各業界の利害が複雑に絡み合うことから、一部の議員が専門的な知識を背景に絶大な権限をふるい、増税や減税などを一手に決め、時の総理大臣も口出しできない「聖域」とされてきました。「聖域なき構造改革」を掲げた小泉総理大臣でさえ、税制改革を進める際には「税調のドン」と呼ばれた当時の山中貞則最高顧問のもとを訪れて協力を求めたほどです。
このため、軽減税率をめぐる一連の動きは、「聖域なき官邸主導」として、党内に大きな衝撃を与えました。
不満くすぶるも静かな党内
去年暮れの税制改正論議でも、所得税の控除の見直しで増税の対象となる範囲をめぐり、自民党側でいったん固めた方針が、公明党に配慮する首相官邸の強い意向を受け変更される事態となりました。
ベテラン議員からは、「首相官邸に好き放題やられ、挙げ句の果てに税調まで踏み込まれてはどうしようもない」と、ぼやく声が聞かれました。党側の意見が、政策決定に十分に反映されないなどと、党内では不満がくすぶっています。
しかし、表だって「官邸主導」に異を唱える動きは、ほとんど見られません。党の意思決定機関である総務会で、批判もいとわず発言している村上元行政改革担当大臣は、選挙制度が、官邸主導を加速させていると指摘します。そして、党内の議論がなくなってきていることに危機感を募らせています。

「小選挙区になってから、選挙の公認や人事権を、全部、党執行部が握ったために、選挙やポストのことを考えて、正論や本音が言えなくなりつつある。昔と比べると非常に議論が少なくなった。本来ならば議論が白熱し、何回も止まるべきところがほとんどノーマークで通ってしまう。官邸主導で打ち出された政策のチェックや方向転換ができなくなっている」
また、ある自民党の重鎮議員は、政権交代で野党への転落を経験したことを踏まえ、「党内で意見が対立したり、揉めたりすることは有権者にマイナスの印象を与える」と話します。党内で、侃侃諤諤、議論をするより、党内がまとまり政策をすみやかに実現していくほうが、国民の理解を得られるというのです。
「事前審査」から「提案型」に
「官邸主導」は、今後も、続いて行くのでしょうか?
日本の政治制度に詳しい学習院大学の野中尚人教授は、グローバル化の進展や技術革新のスピードが速くなっている現代においては「官邸主導」は今後も続くと見ています。

「世の中の動きが急になり、機敏に対応する必要が出てきた時にリーダーシップのない状態ではどうにも立ちゆかない。官邸主導はやらざるをえないし、やっていくしかない。今の官邸主導のやり方がベストだとは思わないほうがいいが、リーダーシップをきちんと明確にし、説明責任を果たしながら、やることは実行できる形にしないといけない」
そして野中教授は、自民党も、これまでの「事前審査」を中心とした政策決定への関与から、積極的に政策提案するなど、役割を抜本的に見直す時期に来ていると指摘します。
「自民党の中のルールや仕組みを作り直す時期に来ている。『官邸に対して意見を言っても何も認めてくれない』というのではなく、今までのやり方になかった本来の政務調査をやり、提案を持って行くということがなければ、政党として本当の意味でバージョンアップはできない。残念ながら、そこのアイデアが自民党には今は十分にない」
「ポスト安倍」は何を思う?
自民党の政策決定の責任者でもあり、「ポスト安倍」の1人とも目されている岸田政務調査会長は、決断をする政府、国民の声を受け止める党と、それぞれの役割を果たすことが重要だと指摘します。

「『党はいらないんじゃないか』という声が出ているのは、政府が、すべて党の議論をすっ飛ばして、物事を決めているのではないかといった不満の声だと思う。政府と与党・自民党は、車の両輪であり、どちらが上とか下という問題ではない。ある時は、党として、しっかり政府と対じしなければならない場面もあるだろうし、大事なのは、それぞれの役割を果たすことだ」
そして岸田氏は、目先の政策課題だけでなく、中長期的な課題について、党が先取りする形で政府に提言していきたいと意欲を示します。
「目の前の法案の事前審査など、単に政府の取り組みについて議論するだけではなく、2050年のあるべき社会像や財政問題など、中長期的な課題について議論し、与党が先取りする形で、しっかりとした提言を行う場面がたくさんあってよいのではないか」

また、自民党総裁選挙への立候補に意欲を示している石破元幹事長は、ことしのひと言として「自由」を挙げています。石破氏は、「自由にものが言える。議論ができる。まず必要なのは自由だと思っていて、そういう政党が自民党だ」と、その言葉を選んだ理由を解説します。 党内で十分な議論を尽くし、決まれば、その方針に従う。そうした政権運営を目指すべきだとしています。
9月に行われる自民党総裁選挙では、政府と与党・自民党の関係についても、議論が行われるものと見られます。総裁選挙を経て、両者の関係に変化が生まれるのかどうかという点にも注目して、取材していきたいと思います。
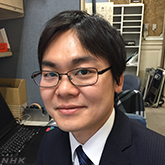
- 政治部記者
- 根本 幸太郎
- 平成20年入局。水戸局から政治部。趣味は、ロックミュージック。

- 政治部記者
- 川田 浩気
- 平成18年入局 。沖縄局、国際部を経て政治部へ 。現在、自民党政務調査会などを担当。


