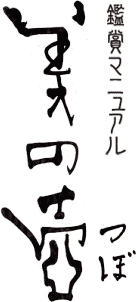file210 「鳥居」

|
はるか昔から、日本人は自然そのものを神としてあがめてきました。滝や大きな岩など特に神々しさを感じさせる場所には、縄を張って大切に祭りました。 |
 |
縄はやがて、二本の柱の間に張られるようになります。一説によるとそれが鳥居に変化していったとされています。誰もが知っている鳥居。今回は意外な鳥居のルーツとその役割を紹介しながら、鳥居の美を鑑賞します。 |
壱のツボ 笠木で読み解く神々のルーツ
 |
神社を研究する外山晴彦さん。鳥居を見るときは、「笠木(かさぎ)」と呼ばれる、一番上の横木が、直線なのか、反っているかがポイントと説明してくれました。 |
 |
笠木は、神社に建つ社殿の形の影響を受けています。直線的な社殿の造りは「神明造り」と呼ばれ、日本古来の建物の特徴です。 |

|
京都にある木嶋神社は飛鳥時代から続く古い神社です。直線を組み合わせた拝殿は典型的な神明造りです、祭られているのは、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)。宇宙の中心をなすとされる神です。 |
 |
位が高く由緒ある神を祭る神社に、神明造りの建物、そしてまっすぐの鳥居が多く見られます。 |
 |
次に笠木が反った鳥居のルーツを見てみましょう。6世紀、大陸から仏教が伝来しました。寺院建築では、軒先が反っているのが特徴で、神社建築もその影響を受けて、曲線が取り入れられるようになったのです。 |
 |
京都の城南宮。鳥居のなだらかな曲線美でしられています。この神社は平安遷都の際に、京都の南を守るために建てられて神社です。こうした仏教の広まった後の時代に作られた神社には、曲がった笠木の鳥居が多いのです。 |
 |
山王権現(さんのうごんげん)の総本宮、日吉大社の社殿は反りの多い、お寺によく似た建築です。平安時代ごろ、日本古来の神と外国から伝わった仏教が、融合するようになります。山王権現は延暦寺の守護神として平安時代から信仰が始まった神様なのです。 |
 |
日吉大社の鳥居の上には帽子のような装飾が施されています。一説によると、傘のような部分は延暦寺のたつ比叡山を表していると言います。日本の神と仏教が融合したシンボルなのです。 |
弐のツボ 神々の威厳を感じさせる演出
 |
東京、杉並にある馬橋稲荷神社の参道には三基の鳥居が建っています。そして入り口から8メートル、7.5メートル、7メートルと50センチずつ低くなっていて、参道が長く見えるような工夫が施されています。 |
 |
馬橋稲荷神社の禰宜(ねぎ)、本橋さん。この仕掛けの狙いを教えてくれました。 本橋 「この参道がもっと長く、そして神様のお住まいである神殿が奥深くにあるような、そうした視覚的効果を考えて作ったのです。」 |
 |
徳川家康を祀る日光東照宮には、さらに手の込んだ仕掛けがありました。 |
 |
日光東照宮の禰宜(ねぎ)、高藤さん。あえて大きな鳥居を最初は小さくみせる狙いについて伺いました。 高藤 「(参道をあるいて、階段をのぼり)鳥居の下まで来て見上げると、(小さく見えた鳥居の)大きさを実感できます。この大きな石鳥居を見たときに、東照宮の偉大さといいましょうか、家康公の偉大さを実感させられるでしょうね。」 |
 |
京都の伏見稲荷大社では、小ぶりな山全体のそこかしこに鳥居が建てられています。もっとも密集したところでは、80メートルにわたり、すき間無く鳥居が連なっています。伏見稲荷の鳥居は、笠木の反った形に朱色で統一されているのが特徴です。 |
 |
25代にわたって、 伏見稲荷の鳥居を作り続けてきたという宮大工の工房を訪れました。ここでは、木製の「型」を使って鳥居の形を統一させています。 |
 |
棟りょうの長谷川泰史さんに伺いました。 長谷川 「昔から、稲荷鳥居には決まった形がありまして、その型を職人それぞれが伝えていって、誰がつくっても同じ形の鳥居になるようにします。」 |
 |
この鳥居はほとんどが全国の信者から奉納された鳥居です。伏見稲荷では、商売繁盛の願いが叶ったときに鳥居を奉納する習わしなのです。 |
 |
神道研究家の稲田さんに、鳥居が奉納されるようになった経緯を伺いました。 稲田 「なぜそれが鳥居かといえば、語呂合わせ的に、願いが『通り入る』というような、そういう考え方で奉納されて、それがパターン化して、鳥居を奉納するようになったというふうに考えられています。」 |
 |
同じ形の鳥居が果てしなく連なることで生み出される不思議な空間。鳥居をくぐる人にお稲荷様の威光の絶大さを感じさせる、そんな圧倒的な演出です。 |
参のツボ 鳥居越しに神宿る自然をみよ
 |
奈良の大神神社では、神様をまつる本殿がありません。神道研究家の稲田さんは、もともと神社に社殿はなく、神々が宿る自然そのものを拝むのが太古の祈りの形であったと語ります。 |
 |
ご神域の目印として建てられた鳥居。古代の人々は、鳥居ごしに神そのものとされた美しい山を拝んでいたのです。 |
 |
写真家の久保田光一さんは「聖地」をテーマに、10年前から、全国の神社を撮影してきました。神社の境内ならではの神秘的な空気に感動したと語ります。久保田さんが追求してきたのは、鳥居と自然が溶け合うような神々しい風景です。 |
 |
大阪、四天王寺に建つ石の鳥居。夕暮れ時に大都会の中に美しい風景を生み出しています。その昔、この鳥居の向こうには海が広がっていました。 |
 |
ゆるやかな台地の頂であるこの場所から、鳥居越しの西の海に沈む太陽に向かって手を合わせたといいます。 |
 |
広島県、厳島神社の大鳥居。瀬戸内海を旅する人が、船の上から島を拝むために建てられました。 |
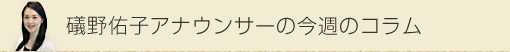
私の実家の隣に神社があります。そこの鳥居は横木が反っているものでした。子供の頃そこで遊んだり、祭事に行ったりと何気なく目にしていたものですが、今回初めてその意味を知り感慨深いです。
それにしても、鳥居の形がこれほど多様だったなんて驚きです!形や配置の場所に細かな決まりはなく、人々の信仰の思いが、それぞれの形になって表れたということなのでしょう。
これからは、街を歩くとキョロキョロと鳥居の形が気になってしまいそうです。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| Train A Banjo And A Chicken Wing, A | Winton Marsalis |
| December | 赤松敏弘 |
| Follow The White Rabbit | Yaron Herman Trio |
| How Did It Happen | Horace Silver Quintet & Trio |
| Down Fuzz | Lem Winchster & Benny Golson |
| Strange Swedish Taste | Ronald Baker Quintet |
| Cantaloupe Island | Hank Jones-The Great Jazz Trio |
| Excursions I, Opus 20 | Gary Burton, Makoto Ozone |
| Little Piece For Justin | Jef Neve Trio |
| Lone | Bugge Wesseltoft |
| Montara | Bobby Hutcherson |
| Blue In Green | Mark Egan |
| Down | Trio Elf |
| As I Am | Michael Brecker |
| School Boy | Winton Marsalis |