 |
 |
 |
NHKアジア・フィルム・フェスティバルに期待する
Expectations
for the NHK Asian Film Festival
高野悦子(岩波ホール総支配人/NHKアジア・フィルム・フェスティバル・アドバイザー) |
 |
第4回NHKアジア・フィルム・フェスティバルが12月16日から始まる。継続は力なりというが、これまでに15の国と地域で制作した17作品のリストを見ると、あらためて感動の想いがわいてくる。
去る11月4日に閉幕した第14回東京国際映画祭のコンペティション部門では、東京グランプリにアルバニア映画『スローガン』、審査員特別賞にイラン映画『月の光の下に』が選ばれ、アジア地域の映画の力を示した。また映画祭期間中に実施された“コリアン・シネマ・ウィーク”も盛況だった。
私がジェネラルプロデューサーを務める国際女性映画祭のセクションでも、イランの『街の陰』、フィリピンの『母と子』、日韓独合作の『On The Way』に沢山の観客が集まった。
こうした日本におけるアジア映画の隆盛ぶりは、映画祭にかぎらず一般の興行館でも見ることができる。私はこの現象に、NHKアジア・フィルム・フェスティバルの存在が大きいと考えている。
今回上映される共同制作作品は、インドネシア、イラン、カザフスタン、台湾の4本である。どの作品も私はまだ見ていないのだが、インドネシアの『囁く砂』は、制作の過程を少し知っているだけに興味がある。
この映画は女性監督ナン・アハナスのデビュー作で、プロデューサーも女性、そして企画と母親役を演じるのが、インドネシアの国民的女優といわれるクリスティン・ハキムである。ハキムさんは1982年、国際交流基金10周年を祝う映画祭に参加し、多くの日本人の心をつかんだ。その後、日本との交流を深め、小栗康平監督の『眠る男』にも主演した。
アメリカ映画に押されて低迷をつづけるインドネシアにおいて、ハキムさんが自らプロデュースし、主役で出演した『枕の上の葉』は世界的な成功を収めた。スハルト政権が崩壊し、経済的混乱をきわめる祖国で、いまハキムさんは若い映画人の育成に力を注いでいる。この『囁く砂』は、やはりインドネシアを代表する俳優であり監督の、スラメット・ラハルジョの共演を得て完成した。きっとハキムさんたちの夢が一杯につまった作品であろう。
4回目のNHKアジア・フィルム・フェスティバルの開催をよろこびながら、私は新作が見られる日を楽しみにしている。 |
 |
 |
 |
 |
アジア映画の協力関係に向かって
Toward Cooperation for Asian Films
佐藤忠男(映画評論家/NHKアジア・フィルム・フェスティバル・アドバイザー) |
 |
世界じゅうどこの映画祭でもアジアの映画を競って特集する時代になった。全般的に作品の水準の向上も目覚ましい。21世紀はアジア映画の時代になる、と言いたい勢いである。しかし他面、アジアの多くの映画界は産業としては、たいへんな危機的状況である。
モンゴルではフィルムではもう製作が困難で、映画人たちはビデオ作品を劇場用に作っている。しかしそれでも作品としては、自由で闊達でのびやかな精神は、失っていない。
台湾では政府の保護政策なしには、映画が成り立つのは容易でない状況である。しかし映画人たちは、旺盛な製作意欲を失ってはいない。心にしみ入るような情感のある映画や先鋭な実験的な映画への意欲は、ますます盛んである。
インドネシアでは近年、製作本数は激減した。しかしこの国の映画人たちは、かつて描くことがタブーだった政治的主題をようやくその手に掴むことができるようになった。
インドや韓国やフィリピンのように、映画が産業として大いに活況を示している国もいくつかあるが、全体としてはアジアの映画は存亡の危機にあり、しかもそのなかで映画人たちの意欲は、大いに燃えている。
ヨーロッパでは多くの国々の映画界が国境を越えて結束し、個々の国の映画というよりはヨーロッパ映画全体をアメリカ映画の支配から守ろうとする動きが著しいが、もうそろそろアジアでも、同じような行き方が考えられなければならなくなってきていると思う。
もちろん文化的、経済的に共通する要素の大きいヨーロッパと、国ごとにそれぞれの事情や立場のあまりにも違うアジアとでは一緒には出来ない。しかしいつまでもそうは言ってはいられない。もっと接触を密にすれば、互いに協力しあえる面もきっと発見できるし、それを拡大してゆくことも可能だと思う。
NHKアジア・フィルム・フェスティバルは、まだまだ小さい動きだが、そういう方向に向かっての展望を開く先端にある貴重な活動だと言えるのではないか。これまでこの活動にかかわってきて、私はその手応えを確かなものとして感じている。ますます有意義な催しとなってゆくと私は信じている。
|
 |
 |
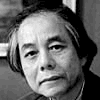 |
もっと映画の力を
What a film can do
山田太一(脚本家/NHK アジア・フィルム・フェスティバル・アドバイザー) |
 |
東アジアの一国に分類される日本でも、アジアは決して明瞭ではない。国々は多彩多様で、その区別は離れれば離れるほど茫漠としてしまう。韓国人が日本人に対してどのような感情を抱いているかは、ある程度分かるが、マレーシアの人がシンガポールに対して抱く感情、タイの人がミャンマーをどう思っているかという程度のことでも見当がつかない。ましてや国々の中での地域差、階級差、宗教、慣習、結婚事情などの錯綜した生活の現実は、アメリカの日常、イギリスの家庭よりも思い浮かべることが難しい。
それは簡単にいえば、その国の映画を見ているかどうかに関わっている。その国の映画があるかどうか、あってもどのくらい見る機会があるかに関わっている。
いま私たちはアフガニスタンの地理、人々の生活にいくらかくわしくなっている。それはかつてベトナムがそうであったように、戦乱のレポートのせいである。
しかし、それでは分からない。映画が見たい。劇映画が見たいと強く思う。アフガニスタンの一家族の物語を描いたすぐれた映画があったら、ニュースの中の人々に、今よりはるかに近寄れるだろう。それは時に世界の人々の判断を変える力を持つかもしれない。
アメリカはつくるだろう。テロに遭った「普通の人々」のすぐれた作品をつくるにちがいない。それに拮抗するアフガニスタンの「普通の人々」の映画がなければいけない。無論、共にプロパガンダとは無縁にである。
もし戦争が映画と映画の闘いであったなら、などといえば寝言のように聞こえるかもしれないが、すぐれた一本の映画は軽く百のミサイルを越える力を持っている。
アジアは、もっと映画に注目すべきなのだ。実情は、あまりにきびしい。
その中で更に不況不穏の折に、「アジア・フィルム・フェスティバル」が4回目の幕をあけるとの意義は深い。実現に努力した人々、作品を完成した人々に、末端から、強い共感と敬意を申し上げたい。
|





