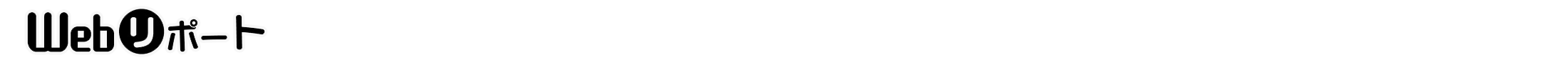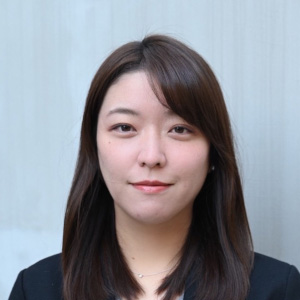ヤングケアラー 望ましい支援の形は?
- 2022年1月11日

去年4月から立ち上げた、このヤングケアラーの特設サイト。取材を通して、多くの当事者、元当事者、支援者、専門家などのみなさんに出会うことができています。
去年11月末、これまで出会った中の何人かに集まっていただき、シンポジウムを開きました。参加した人の声の中には、新たな気付きがたくさんありました。
このシンポジウムの内容の一部について、2回に分けてお伝えしたいと思います。
後編は、学校の現状や、望ましい支援の形についてです。
<シンポジウムの出席者>
森田久美子さん(立正大学社会福祉学部教授)
宮崎成悟さん(元当事者)
持田恭子さん(元当事者・現在はヤングケアラーの中高生を支援)
勝呂ちひろさん(精神保健福祉士)
中野綾香さん(スクールソーシャルワーカー)
藤岡麻里さん(埼玉県地域包括ケア課)
司会:NHKアナウンサー 中野淳
※シンポジウムは、埼玉県、埼玉県教育委員会、NHKさいたま放送局、NHK厚生文化事業団の共催で、11月26日に開催しました。
前編はこちらからご覧いただけます
ヤングケアラーの本音は?元当事者・支援者・専門家のみんなで話してみました(前編)
相談を受ける大人も、さらけ出して

ヤングケアラー支援に関する課題が、さまざま出てきましたが、中でもそれぞれの家庭にどう関わっていくのか、難しさもあると思います。スクールソーシャルワーカーの中野さんは現場でどう感じていますか?

ソーシャル
ワーカー
中野さん
おそらく家庭に入っていくことがとても得意だと、胸を張って言える学校の先生は少ないです。個人情報の関係もあって、民間の福祉機関と学校がつながりにくい実情はあるんじゃないかと思います。
学校と福祉がつながるために、スクールソーシャルワーカーがいて、先生とは違った立場で、ていねいに本人や家族の話を聞くことができます。
すでに家族の介護やケアが入っている場合は、病院やケアマネージャーとも積極的につながっていくことができるので、ぜひ活用してもらいたいと思います。

当事者だった宮崎さんは、学校や福祉の人がどのような関わり方をしたら相談をしやすいと思いますか?

宮崎さん
やはり高校の先生に話したとしても、「この人分かってくれるのかな」「この人に話してどうなるんだろう」と思うと、わざわざ話したくないことを話さないと思います。相談する先の大人が自分の情報をさらけ出していないのに、「なぜ子どもの自分だけがさらさなきゃいけないんだろう」と私自身は感じます。
ですので、先生をはじめ、子どもに関わる福祉の関係者も、ある程度自分の家族の事情などちゃんと示して、聞くだけではなく、お互い歩み寄る姿勢を見せてほしいです。

森田さん
本当にそう思いますね。実際、私のところに来ている高校生は「学校の先生は病気や障害のことを知らない」と言っていました。
例えば、精神疾患ってどういうものなのか知らないので、イメージしてもらえないと言うんですね。高校生たちは、もう少し学校の先生たちに病気や障害のことを勉強してほしいと言っています。
もちろん先生たちにとっては専門外なので難しいところもあるかもしれませんが、やはり子どもの家庭内の実態を想像する力がまだ足りていないなと実感として思います。
“親子まとめて”支援を

勝呂さんは、精神保健福祉士の仕事をしながら、ヤングケアラーの子どもたちの支援にも当たっているということですが、家庭への介入や支援についてどう考えますか?

福祉士
勝呂さん
まず今の“縦割り”の制度のまま進めていては、親子に支援が届ききらないと感じています。
現状では、例えば母親と子どもを支援するには、別々の制度で、窓口も担当者も別々になっています。そのため、支援を受ける家族が大変なのはもちろん、支援者側も情報共有がうまくできず困っているんです。

教育関係者と福祉関係者が情報共有できない、つながれない状況があるということですね。そういった中で勝呂さんはどう支援をしているのでしょうか。

福祉士
勝呂さん
私は「親子でまるっと支援をします」ということをやっています。家族に関わるそれぞれの支援者を1つのチームとして、お互いに名前を知っている、顔が見える、そういった形で支援に当たります。


どのような効果があるのでしょうか?

福祉士
勝呂さん
1つは、チームで支援に当たると、子どもの成長、ライフステージに合わせて、柔軟に対応できます。
例えば、子どもの進路の問題に対応しなければならない時に、支援者どうしはチーム内で知り合いになっているので「すぐに話し合って、支援の量を増やそう」「やり方や時間帯を変えよう」と迅速に対応できます。
もう1つは、「子ども」と「介護・ケアされる家族」の双方を見ているので、双方の持っている能力を見ながら必要な支援を検討しています。

支援を検討している間に、子どもはどんどん成長して学年が上がってしまうということも課題とされていますが、こうして迅速に判断して、その時必要な支援を考えていく支援のあり方は大切ですね。

支援者
持田さん
ヤングケアラーへの支援は、行政内や関係する機関どうしの縦割りをなくして、“横串”を刺すことへの突破口になるんじゃないかと思っています。
これまで教育側、福祉側が集まって話ができる仕組みがなかったんですね。ですのでヤングケアラーを単純に「かわいそうで、大変な子ども」として支援するということではなく、縦割りをなくして「みんなでまるっと支援」「つながっていく支援」、そんなきっかけになるといいと思います。
NHKではこれからも、ヤングケアラーについて皆さまから寄せられた疑問について、一緒に考え、できる限り答えていきたいと思っています。
ヤングケアラーについて少しでも疑問に感じていることや、ご意見がありましたら、自由記述欄に投稿をお願いします。