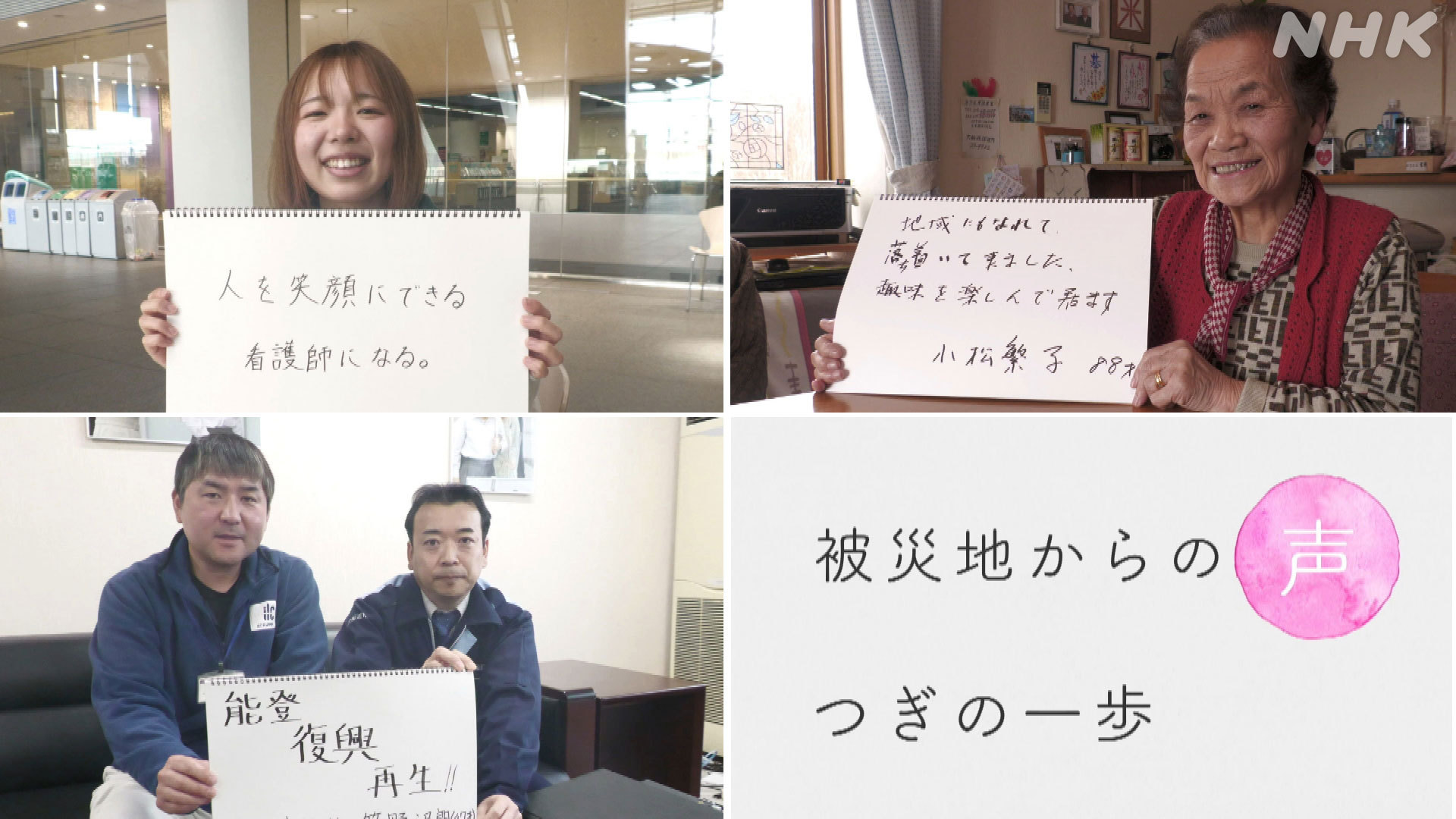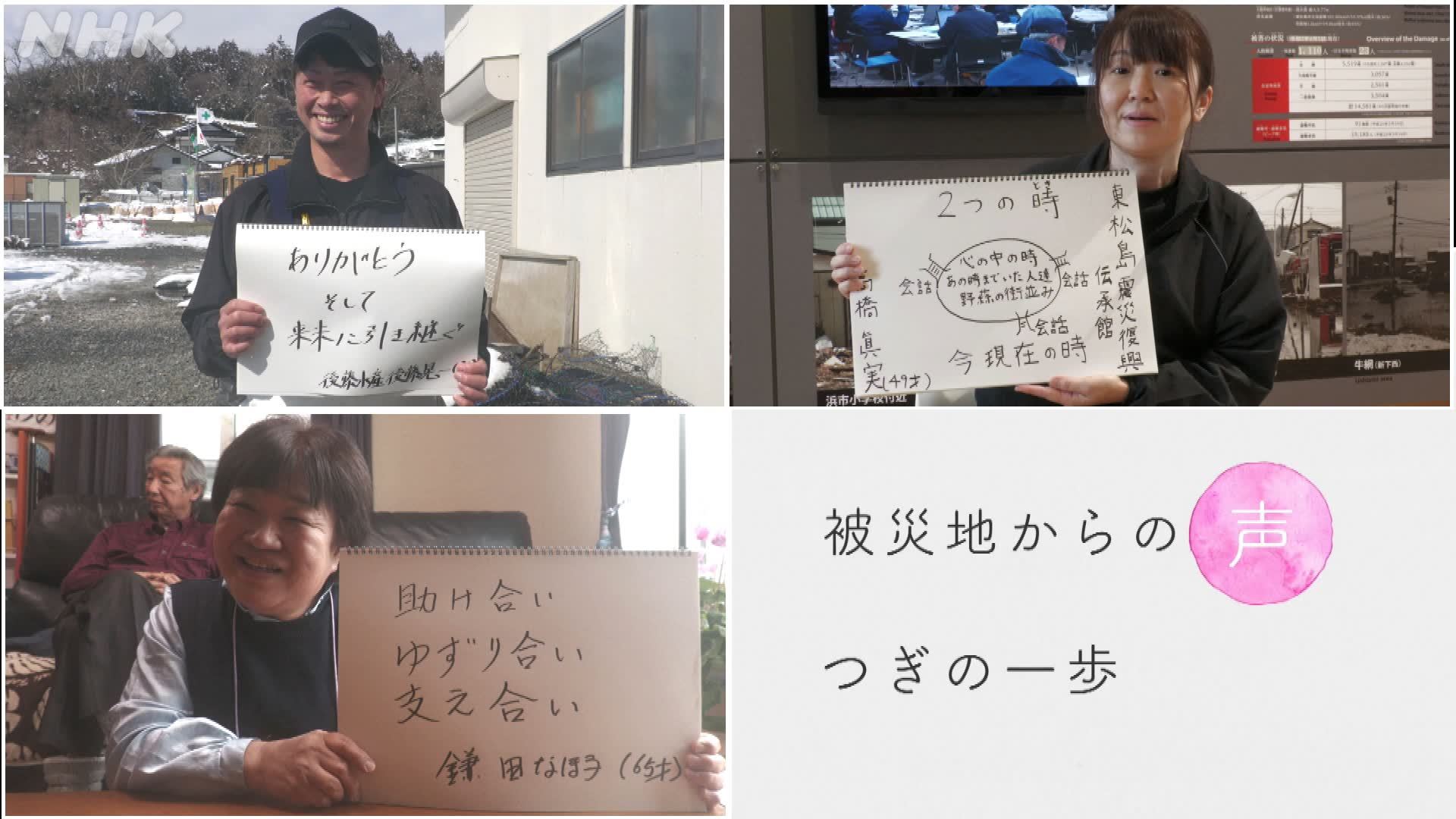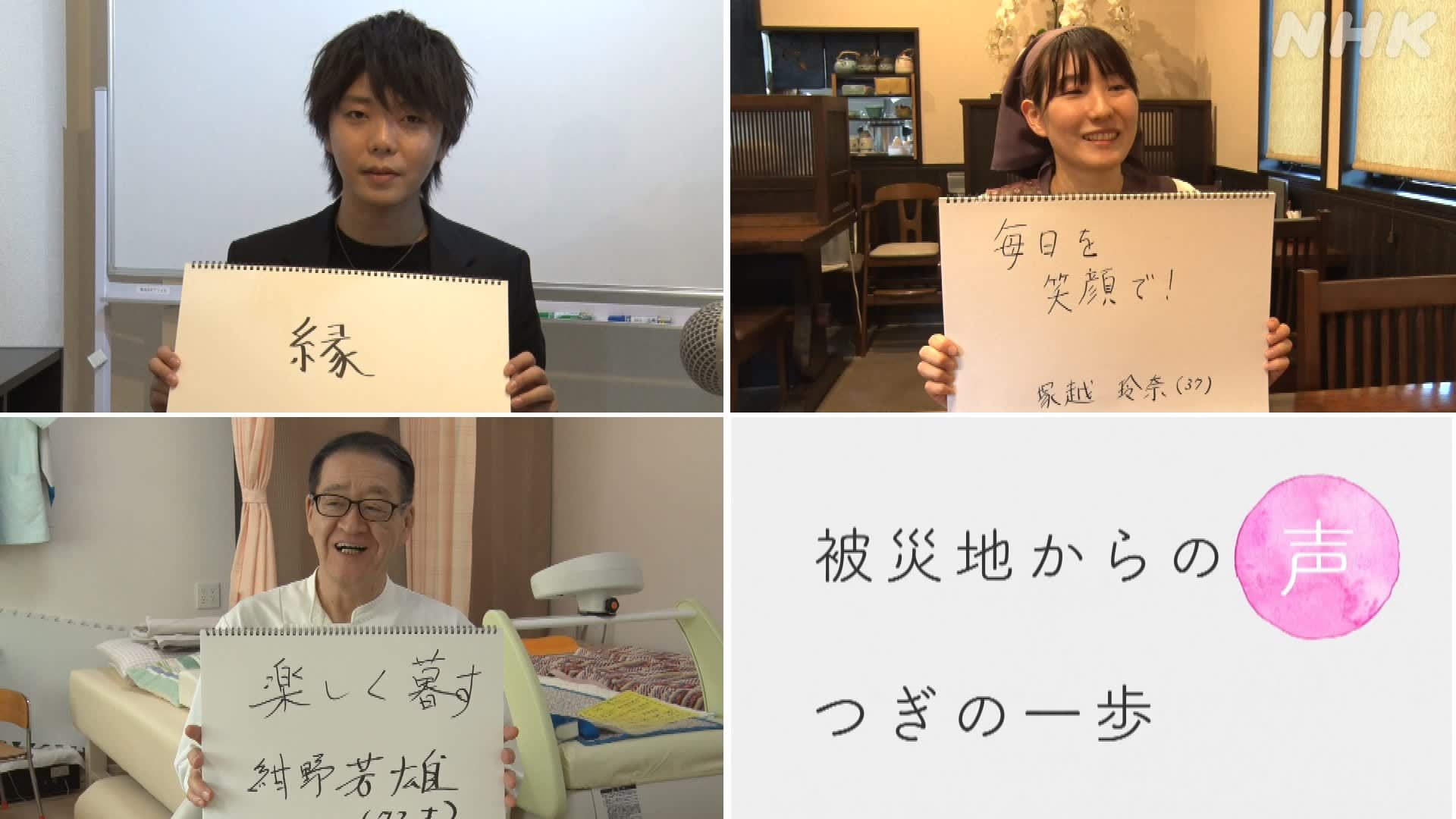6月13日放送「岩手県 大槌町」
いつも番組をご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、岩手県大槌町(おおつちちょう)です。人口は約11000で、中心部に約10mの津波が押し寄せ、1200人以上が犠牲になりました。町にあった家屋の7割近く、4300棟が被害を受けています。去年12月、最後に完成した災害公営住宅で、当初の予定より約5年遅れて入居が始まりました。集団移転事業の宅地造成は、当初の予定より4年遅れて完了しました。どちらも県の沿岸部では最後です。今年3月末には、一時2000世帯以上が暮らしたプレハブ仮設住宅で、入居者がゼロとなりました。文化交流センター“おしゃっち”や三陸鉄道の大槌駅が新たにつくられ、駅前には、居酒屋やピザ店など、9つの地元飲食店が入る施設もオープンしました。
はじめに、中心部の町方(まちかた)地区に行き、4年前に取材した、大正時代から続く自転車店を訪ねました。

店主は40代の男性で、妻と8歳の双子の息子がいます。前回の取材時は、店と自宅を流されて仮設商店街で営業していました。中心部での再建を目指し、家族全員でこう言いました。
「自転車店とカフェを一緒につくりたいと思っています。たくさん人を呼んで、ゆっくりお茶を飲んでもらったり、そういう場所をつくりたいなと思います」
あれから4年…。一家は2年前に町方地区で店を再建し、補助金などを活用して隣にカフェをつくりました。奥さんと先代のお母さんが作る洋菓子や大福、ご主人自慢のカレーなど、メニューも様々です。

地元の主婦など女性が多く訪れますが、人口減少は経営にとって大問題で、町の人口は震災前の7割ほど、特に町方地区はわずか3割ほどです。150億円以上を投じた土地区画整理事業が行われたものの、資材と人手の不足で工事が進まず、最初の土地の引き渡しまで5年近くかかりました。津波の印象が残る場所でもあり、住民は次々と地区を離れました。さらに今は新型コロナの影響で、自転車店とカフェの売り上げは去年より半減し、国の給付金を申請しつつ、手持ちの運転資金も切り崩しています。
「震災で生きるか死ぬかを経験しているから、“このくらいなんだ”みたいな…強がりかもしれないけど。俺たちは震災から一歩踏み出せましたけど、まだ踏み出せない方もいっぱいいるので、“あれ、取り残された”とならないように、ずっとずっとこの店とカフェで待っていようかなと…。本当は頭を抱え込むことばかりなんですけど、子どもの笑顔を見ていれば大丈夫と感じます。子どもが大人になっても今のまま笑っていれば、この町も笑っているのかなって思うので、一番守らなきゃならないのは子どもの笑顔かなと…そのために僕は生きています」
次に、“コラボ・スクール大槌臨学舎”という学習塾に行きました。

震災後、仮設住宅の子どもに学習支援した活動が始まりです。この塾で学んで仙台の大学に進学し、今はオンライン授業で帰省中だという19歳の女性は、高校2年の時に、塾が主催する復興活動にも参加しました。商店街の活性化のため、地元特産品の販売を立案し、マンボウの腸を加工した珍味“コワダ”などを売りました。

「大した計画も立てられず、企画会議に行ったんですよ。でも地域の人たちが私のやりたいことを聞いてくれて、言ってくれた言葉が全部温かい言葉で…。こんなに心の温かい人たちがいる地域だったんだって気がつきましたね。地元の個人商店に興味を持って、経営というものにすごくひかれて、いま経営学科に入っています。塾に出会わなかったら大学に入っていなかったかもしれないし、人生の大きな転換をたくさん与えてもらったのかなと思います。高望みかもしれないけど、将来は大槌の個人商店や中小企業を盛り上げる、経営コンサルタントになりたいです。私がやりたいことを肯定して、手伝ってくれた人たちが大槌を盛り上げようと頑張っているので、そのお手伝いができたらなって思います」
そして、小鎚(こづち)地区にある体育館では、小中学生が通う空手教室におじゃましました。

新型コロナ対策で、一人一人がかなりの距離をとって稽古していました。師範は40代の女性で、国体に6度出場しています。中心部にあった道場は津波で流され、ひと月後に再開したものの、体育館が避難所だったため、はじめは“屋外道場”でした。道場の創設者だった父親は、津波で今も行方不明です。
「父とつながっているものが空手だったんですよね。空手だけは唯一、父と私をつなげてくれた…空手をやめたら、つながるものが無くなってしまうのが嫌だなと、道場を再開しました。最初のころは指導がうまくいかなくて、“私、向いていないのかな”というのは正直ありました。今もたまにあるんですけど、子どもの成長を見て、教えていることは間違っていなかったと思うたび、また頑張ろうという気持ちになります。子ども達には、どんなにつらくても、 前を向いていけば絶対いいことはあるので、まずは諦めるな、前を向け、とにかく前を向けと伝えたいです」
武道家らしいこの言葉は、震災以降、自分に一番言い聞かせてきた言葉でもあり、お父さんも娘にきっと伝えるに違いない言葉だと思います。
その後、内陸にある臼沢(うすざわ)地区に行き、グラウンドゴルフを楽しむ高齢者に話を聞きました。

町内では多くの人が元の場所を離れて自宅を再建しており、ここにも被災した方々が様々な地区から移り住んでいます。震災前に比べ、地区の人口は倍増しました。集会所の管理人を務める70代の男性は、津波で自宅を流され、3年前ここに家を新築しました。定年後は地域活動に励みたいと、グラウンドゴルフやお茶会など、精力的に住民交流を図る機会を増やしてきたそうです。
「はじめは全然、知り合いはいませんよ。みんな違う地区から集まった人だから。集会所の鍵を開けたり閉めたりするだけだったけど、やっぱりそれではだめだなと思って、自分が先頭になって何のイベントでも参加してきました。何かやっていれば、人は集まってくるんじゃないかな。徐々にみなさん、 知り合いができてきたから、これからどんどん交わっていけばいいなと思っています」
さらに、中心部から3kmほどの赤浜(あかはま)地区で、以前ここで商売をしていた70代の女性から話を聞きました。938人いた地区住民のうち、90人が津波の犠牲になっています。

女性は食料雑貨店を営み、店舗兼自宅を流されました。1400万円をかけて、リフォームしたばかりだったそうです。
「前はとても活気があってね…お客さんとふれあったり、楽しかったですよ。仕入れに行って、いっぱい車に載せてきて、それを店の前に広げて…みんなと商売できて幸せだったね。流されたけど…。津波がなければ、今も細々とやっていたと思いますよ。でも、いくら津波になったからって、暗い顔で過ごすのもつまらない…どんなことがあっても、食べねば、生きねばね。コロナでどう変わっていくんだか、台風が来るかもしれないし、気持ちを備えて強くしていなくちゃ。私は負けない、負けないです」
そして、内陸の大ケ口(おおがくち)地区に行き、震災の2年後に沿岸部から移転し、新たに建てられた民宿を訪ねました。主人は60代の男性で、9代続く漁師です。漁のかたわら、父が始めた民宿を経営していましたが、宿と自宅が流されました。かさ上げなどの造成工事が長引く中、宿の再開を優先させるため、元の場所での再建は諦めました。

復興事業の関係者で宿はにぎわいましたが、今では特需が去り、新型コロナが追い打ちをかけています。さらに、ホタテ養殖では貝毒のため出荷規制が出され、二重の苦しみです。それでも男性は、先祖代々受け継いだ土地だけは売るつもりはないと言います。
「お客さんは激減です。前は公共事業のダンプカーとか作業車とか、毎日ひっきりなしに走っていましたから。それがもう1台もいないですから、きついですよ、きつい…。元の土地は、天保12年、初代が家を建てた場所なんです。思い出はありますよ、俺、本音を言えば帰って来たいもん。私は土地を守らなくちゃいけない義務があると思っています」
さらに、男性が守りたいのは、故郷の海だと言います。町の沿岸部は、1955年に“陸中海岸国立公園”に指定されました。

「国立公園内で仕事ができることに感謝し、海の保全に努めるようにしたいと思います。自分のものではないから、次に渡さなくてはならない。漁師はみんな、流木や浮遊物を見つけたら、捨てないで船に積んでくるし、徹底しているんだよ。次の世代の人にいかにいいものを残すか、それが俺の信念」
赤浜地区で商売していた前述の女性やこの男性の言葉には、画面を通して、胸をドスンと突かれるような力強さがありました。SNSなど世にあふれる言葉の軽々しさとは真逆の、魂が入った言葉でした。