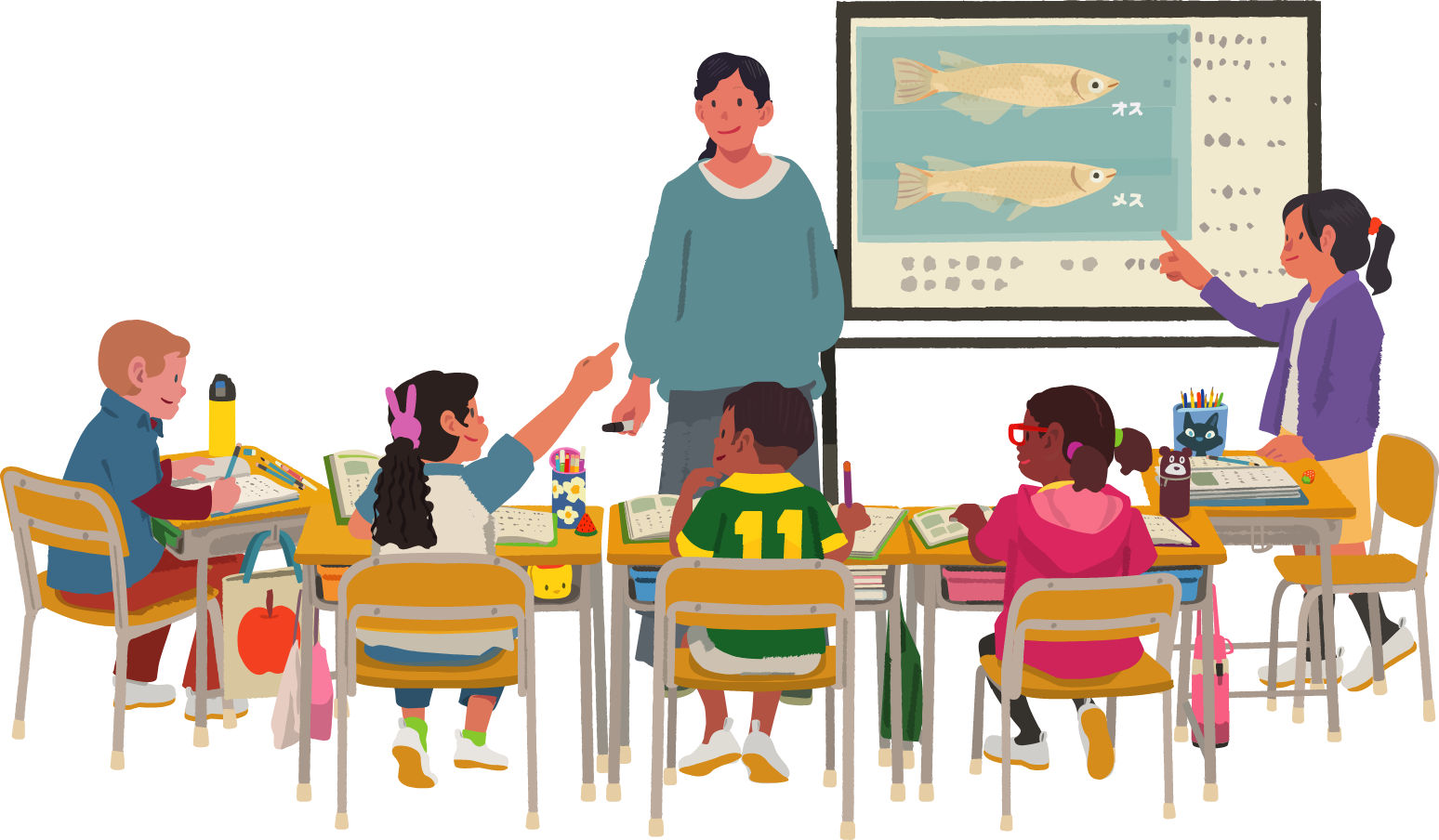
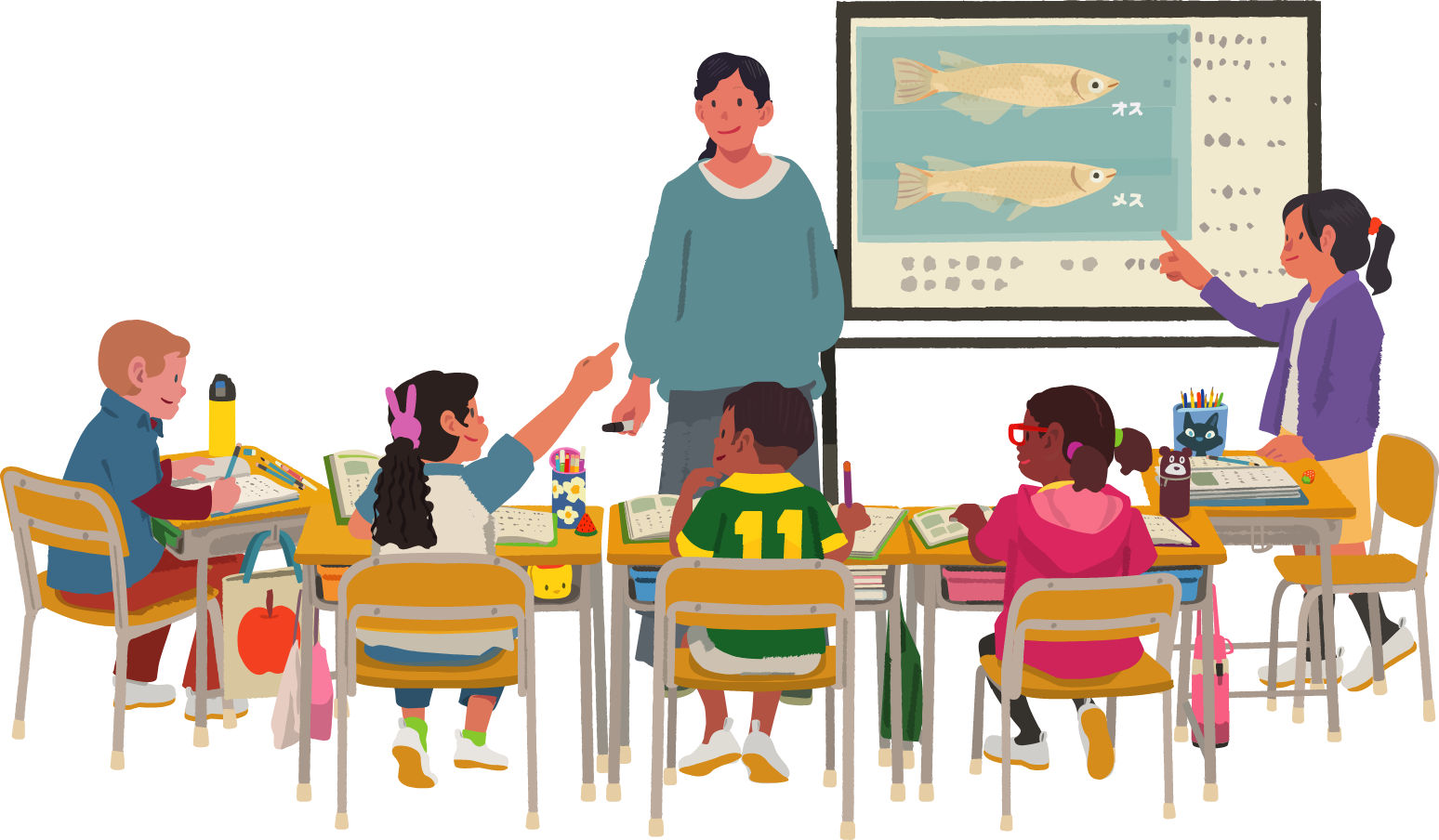
外国につながる子どもたちとともに学ぶために、
NHK for Schoolの動画を活用するアイデアを集めました。
一斉授業、日本語クラス、地域の支援など、
さまざまな現場でお役立てください!
協力
齋藤ひろみ(東京学芸大学大学院教授・子どもの日本語教育研究会事務局長)
田原健之介(大阪市立小学校教頭・大阪市学校教育ICT推進リーダー)
藤川純子(三重県四日市市立中学校教諭・JICA中部開発教育アドバイザー)
いろんな⾔語で NHK for School を⾒てみよう!
おしらせ
コンテンツ活用・実践集
- 校種:
- 形態:
- 校種:
- 形態:
多⽂化共⽣プレイリスト
多文化共生を学ぶヒントになりそうな動画を集めました。
教室で、学校で、地域で…動画を見て、考えたり、話し合ったり、なにかを始めたりしてみませんか?
協力:
- 佐藤真久(東京都市大学教授)
- 鎌田理子(千葉市立中学校教諭)
- 藤川純子(三重県四日市市立中学校教諭)
- 吉田祥子(東京都江戸川区立小学校教諭)
よくある質問
関連リンク
-
「がいこくごのニュースと防災情報(ぼうさいじょうほう)」(NHK WORLD-JAPAN)
NHKのニュースや番組を20の言葉で発信しています。 -
「Learn Japanese」(NHK WORLD-JAPAN)
日本語学習に役立つ番組や動画、日本語の先生向けのサンプル授業案(日本語)を掲載しています。 -
「NEWS WEB EASY」(NHK)
NHKのニュースを「やさしい日本語」で伝えます。 -
かすたねっと(文部科学省)
文部科学省が管理・運営を行う、外国につながりのある児童・生徒の学習を支援する情報検索サイトです。
※NHKサイトを離れます。 -
外国につながる子供向けの教材が知りたい!(文部科学省)
文部科学省の「子供の学び応援サイト」内にある、外国につながる子供の学び応援リンク集です。
※NHKサイトを離れます。 -
日本語学習教材(国際交流基金)
国際交流基金が開発した日本語学習教材が集められています。
※NHKサイトを離れます。 -
多文化共生ツールライブラリー(自治体国際化協会CLAIR/クレア)
各地域で作成された外国人支援や多文化共生ツールを検索、ダウンロードして利用できます。
※NHKサイトを離れます。 -
「JICA地球ひろば」(国際協力機構)
開発教育・国際理解教育の実践や、より一層の充実を目指す教員、児童・生徒のために、様々な情報や教材を提供しています。
※NHKサイトを離れます。
