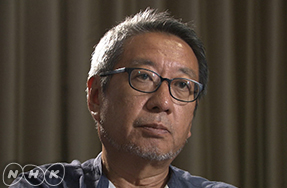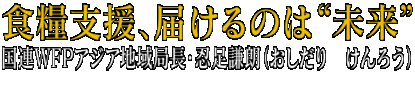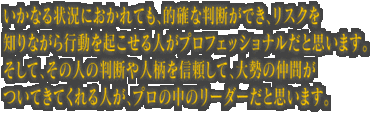80万の難民を出したコソボ紛争。世界最悪の人道危機と評されたスーダン・ダルフール紛争。そして去年11月に発生したフィリピンの巨大台風。忍足は、それら世界の紛争地や被災地にいち早く食糧を届け、多くの命を救ってきた「食糧支援」のエキスパートだ。
駆けつける現場の多くは、家屋やインフラが破壊され、緊急的に食糧難に陥った場所。リーダーである忍足は、状況に応じて配給ルート、食糧の種類や量、部下の動きを決め、即座に指示を出していく。その中で貫くのは「やるべきことのためなら、あらゆる手立てを尽くす」という強い信念。輸送手段なら、トラックや船はもちろん、道がなく交通手段がない場合には動物に担がせてまで運ぶ。さらに一刻の猶予がないときは、飛行機から直接物資を投下するという大胆な技にもでる。そしてときに忍足は、世間のルールすら破ることもいとわない。コソボ紛争のとき、オフィスや食糧倉庫もない中現地に入ったため、住民が避難した倉庫を急きょ接収し、食糧倉庫などに使用。また難民キャンプで火が使えず、支援物資の小麦粉を調理できないと分かるやいなや、地元のパン屋を探し、その小麦粉を手間賃として渡す条件でパンを焼いてもらい、難民の命をつないだ。
「緊急支援の現場では、“物事を正しくやる”ことと、“正しいことをやる”のは違う。どんな状況だろうと確実に届けるためには、ルールを破ってでも、“正しいことをやる”という意気込みが必要」。これが、四半世紀にわたって世界の最も過酷な現場を生き抜いてきた男の哲学だ。
![]()

![]()
 世界の紛争地を生きて25年 食糧支援のプロ
世界の紛争地を生きて25年 食糧支援のプロ
 飛行機から食糧を投下 常識やルールを破ってでも絶対に届ける
飛行機から食糧を投下 常識やルールを破ってでも絶対に届ける
 時には、動物の力を借りて食糧を運ぶことも
時には、動物の力を借りて食糧を運ぶことも
忍足が届ける「食糧」。それは単に人々を飢えから救うためだけのものではない。忍足たちは、食糧の支援を通じて、紛争や自然災害で被害を受けた地域の「復興」を後押しすることを狙っている。たとえば緊急的な食糧難を乗り越えたあとは、集落内の道路作りや家屋の修復、がれきの撤去、菜園作りなど、村の復興に関わる計画を村人自身に考えてもらい、その各プロジェクトに対して食糧を渡す。こうして飢えを防ぐと同時に、集落の復興を後押ししている。
そして、紛争などに巻き込まれた小学校には、給食を支援している。給食でお腹が満たされることで、子どもたちは勉強に集中することができ、それが教育の復興・向上につながると考えているからだ。
食糧を届けることは、その地域の発展や人々の夢といった、“未来”を届けること。それが忍足が信じている食糧支援の仕事だ。
 食糧支援とは、“未来”を届ける仕事
食糧支援とは、“未来”を届ける仕事
食糧で人々の命を救い、“未来”を届けるために奮闘を続けてきた忍足。だが、百戦錬磨の彼をいつも悩ませるのが、支援の打ち切りを決断することだ。
今、世界で飢餓状態にある人々の数は8億4千万人あまり。だが資金不足から、WFPが実際支援できるのは、全体のわずか10%、すなわち8千万人に過ぎない。そのため忍足は常に、どこの誰に、どれだけ支援できるかのシビアな選択を迫られ続けている。
そして支援というものは、ただ漫然と続ければいいのではない。長引かせるほど、人々が自分で生きていく活力をそぐことにもなりかねない。そのため、打ち切りの判断には細心の注意が払われる。リーダーである忍足はみずから視察に向かい、本当に支援を打ち切っても人々が自立できるか、丹念に見極める。時に涙ながらに訴えられ、支援の継続を懇願されることもある。そのたびに忍足は迷い、葛藤しながら判断を下していく。
忍足は言う。「この仕事の原動力は、“かわいそうだな”“なんとかしてあげたいな”という“感情”です。熱い心がないと、命をかけた支援はできない。でも、感情だけではこの仕事はできません。決断を下すときには、冷静な考え方、判断力というものがどうしても必要になってくる。原動力であるはずの“感情”が邪魔をして、そこに悩まされるわけです。この仕事のいちばん苦しいところです。」
 台風に襲われた被災地を回る忍足
台風に襲われた被災地を回る忍足
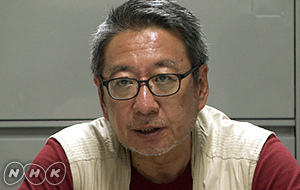 視察を重ね、支援の打ち切りを決断。苦しい選択だ
視察を重ね、支援の打ち切りを決断。苦しい選択だ
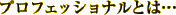 画像をクリックすると動画を見ることができます。
画像をクリックすると動画を見ることができます。
政治的な紛争、宗教的な紛争、思想的な紛争、いろいろあると思うんですけれど、そこに巻き込まれる人っていうのは間違いなく苦しみしかないと思うんですよね。というのは、紛争があって戦闘とかが行われてる限り、絶対にそこの地域の発展というのはあり得ないんですよね。貧しい人たち、もともと貧しい人たちは必ずさらに貧しくなります。持ち物も全部なくす、家もなくす、知らないところに逃げなくちゃならない。そして紛争が治まったところでまた戻ってきてゼロから始めなくちゃいけない。だからいいこと何もないと思うんですよ、正直言って。