脳動脈瘤(りゅう)治療の多くは、破裂前の瘤を処置する予防治療だ。「成功して当たり前」。そのプレッシャーは半端なものではない。坂井が行うコイルを使った血管内治療は、後遺症のリスクなどが低いとはいえ、開頭手術のように目視下で処置できるわけではない。カテーテルの先のわずかなぶれで血管や動脈瘤がやぶれてしまえば、人為的な脳卒中を引き起こすことになり、最悪の場合、患者の命を奪うこともある。
「恐れを越え、最善に挑む」。手術中、坂井は判断を迫られる度にこの言葉を反芻する。瘤にわずかでもコイルを詰めすぎれば、破裂を引き起こす。かといって慎重にいきすぎ、血液が入り込む隙間を残してしまえば、患者の不安をぬぐいさることはできない。治療が進むほどに迫る恐怖。その恐怖と向き合い、勇気を持って99%を100%にするためのひと押しに挑む。治療の成否を分かつのは技術ではない。「最後は逃げない気持ちかな」と坂井は言う。
![]()

![]()
 治療中の坂井
治療中の坂井
 カテーテルとその先から押し出されるコイル、このコイルで瘤を埋める
カテーテルとその先から押し出されるコイル、このコイルで瘤を埋める
年間100件やれば多いと言われる血管内治療の世界で、坂井は年間400件超という群を抜いた施術数を数える。その圧倒的な経験値こそが坂井の手技を支えている。
自宅は、病院から徒歩7分の位置にあり、救急の連絡が入れば、昼夜を問わずすぐに治療に走る。自宅には、医局と同じパソコンやプリンタを備え、CTやMRI画像などがどこにいても見られるようにした。1日の睡眠時間は、平均2、3時間。朝3時には起床し、術前のシミュレーションを行う。
「思いだけで、願いが通じるとは思っていない。そうでないと、本当の意味で患者さんや家族の願いを考えられる医者じゃないと思う」という坂井。20人の部下を従える立場になった今でも、誰よりも多く現場に立ち続けている。
 治療前の坂井、シミュレーションを行い、起こりうる事態を考え尽くす
治療前の坂井、シミュレーションを行い、起こりうる事態を考え尽くす
 脳の血管にできた、わずか数ミリの瘤、破裂すれば、脳卒中を引き起こす
脳の血管にできた、わずか数ミリの瘤、破裂すれば、脳卒中を引き起こす
坂井は30代の頃、血管内治療の後で患者を亡くすという経験をしている。「いける」と判断して加えた1ミリにも満たないひと押し。その治療の後、患者の指先にわずかなしびれが生じ、それがきっかけで患者は自ら命を絶った。これ以上この治療を続けることはできないと、辞表を提出した坂井を止めたのは、「これで辞められなくなったな」という、上司のひと言だった。
「自分は誰よりもひと押しの重みを知っている。だからこそ、誰よりもひと押しにかける厳しさを突き詰めなければならない」。多くの部下を率いる立場になった今でも体裁にこだわらず、時には、年下の部下たちに意見を求めてまで、確実な手技を考え抜く。「倒れるまでやるんや」という坂井の机の中には、今も治療が上手くいかなかった人たちのカルテが入っている。
 深夜2時、手術室に向かう坂井
深夜2時、手術室に向かう坂井
 30代、留学先のUCLAで血管内治療に出会う
30代、留学先のUCLAで血管内治療に出会う
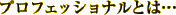 画像をクリックすると動画を見ることができます。
画像をクリックすると動画を見ることができます。
坂井は、カテーテルを使った脳血管内治療のパイオニアと言われる。かつて脳梗塞、脳動脈瘤などの脳卒中は開頭手術以外に治療法が無かった。しかしその安全性などが認められ、現在では3割以上が血管内治療。欧米では6割以上が血管内治療にとって変わった。
坂井は、自身の膨大な治療データをすべて公開、さらに年に2回、世界中の大学病院を衛星で結び、治療を中継する取り組みを続けている。新たな治療機器の開発にも率先して取り組み、「坂井の元では未来の治療が見られる」と、世界中から視察が訪れるほどだ。「勝ちに不思議の勝ちなし」という坂井、常に勝ちを必然にするためのアイディアを考え続けている。
 子供の時から一貫して阪神ファン
子供の時から一貫して阪神ファン
 朝食は朝6時、好物の卵焼きは自分で焼く
朝食は朝6時、好物の卵焼きは自分で焼く


