二郎が使う魚は、最高級の天然物。魚は、とれたての新鮮なものが鮨ネタとしておいしいとは限らない。味を決めるのは、「手当て」と呼ばれる職人技だ。魚の種類や状態に応じていったん寝かせたり、塩や酢でしめることで、魚のうま味を最大限に引き出す。
しかし、「手当て」を施した魚のすべてが客に出されるわけではない。例えば、同じ手当てを施した締め鯖でも、二郎が味を見て、その舌にかなったものだけが、鮨として握られ、残りは賄いに回る。こうした「無駄」が、うまい鮨を握るために欠かせないという。
![]()

![]()

二郎の鮨は、20カンの「おまかせ」というコース仕立てになっている。それは、半世紀以上鮨を握り続けてきた二郎が、試行錯誤の末にたどり着いた究極の20カン。すべてのネタがおいしく食べられるように、握る順番や、ネタの温度に細かな配慮がされている。そのドラマは、あっさりとした白身で幕をあける。鮨の王様・マグロの次には、さっぱりしたコハダを握る。マグロの脂を、酢の酸味でぬぐい去るためだ。常温のハマグリの次には冷えたアジを握る。温度差のあるネタを交互に出すことで、一つ一つのネタが際だつと、二郎は考えている。そしてコースの中盤には、藁(わら)で燻(いぶ)して香りを付けたカツオを配置。最後は、芝エビをたっぷり使った甘い玉子焼きで幕が下りる。

静岡県に生まれた二郎は、家庭の事情から7歳で奉公に出される。奉公先は地元の料亭、掃除、出前、皿洗いと毎晩遅くまで働いた。学校では居眠りばかりして過ごしたという。生来不器用だった二郎は、何をやっても時間がかかり、どなられてばかりいた。そんな二郎を支えていたのは、自分には「帰る場所はない」という思いだった。

去年11月、二郎の店を終生のライバルという一人の料理人が訪れた。「フレンチの帝王」と言われる三つ星シェフ、ジョエル・ロブションだ。ロブションとは、20年前に出会って以来、料理を追求する者同士、互いに尊敬しあってきた。二郎はロブションの舌を「誰よりも敏感」だという。二郎にとって最も握りがいがあり、自分の腕が試される相手だ。そのロブションが1年ぶりに店に来るという。二郎は、ロブションに真剣勝負を挑む。1尺5寸のカウンターを挟んで、フレンチを極めた男と、鮨を極めた男が対峙(たいじ)する。握るのはいつも通りの20カン。黙々と食べていたロブションは、最後に穴子を口にしたとき、大きくうなずき、OKのサインを出した。

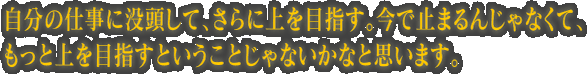
![]()
すしの6割を決めるのはシャリ。そのシャリも人肌の温かさでなければならないと二郎は考える。そのため、シャリの保温には二郎独特の道具が使われている。
炊きあげたシャリを鉢に入れ、さらにそれを手製の毛布で巻いてから、藁(わら)で編んだおひつに入れる。必要最小限のシャリを炊き、冷めないうちに使い切るのが二郎流だ。


