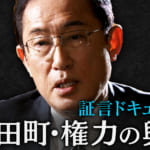コロナ禍の首相交代劇
辻元清美の証言
「野党第1党の傲慢さ」
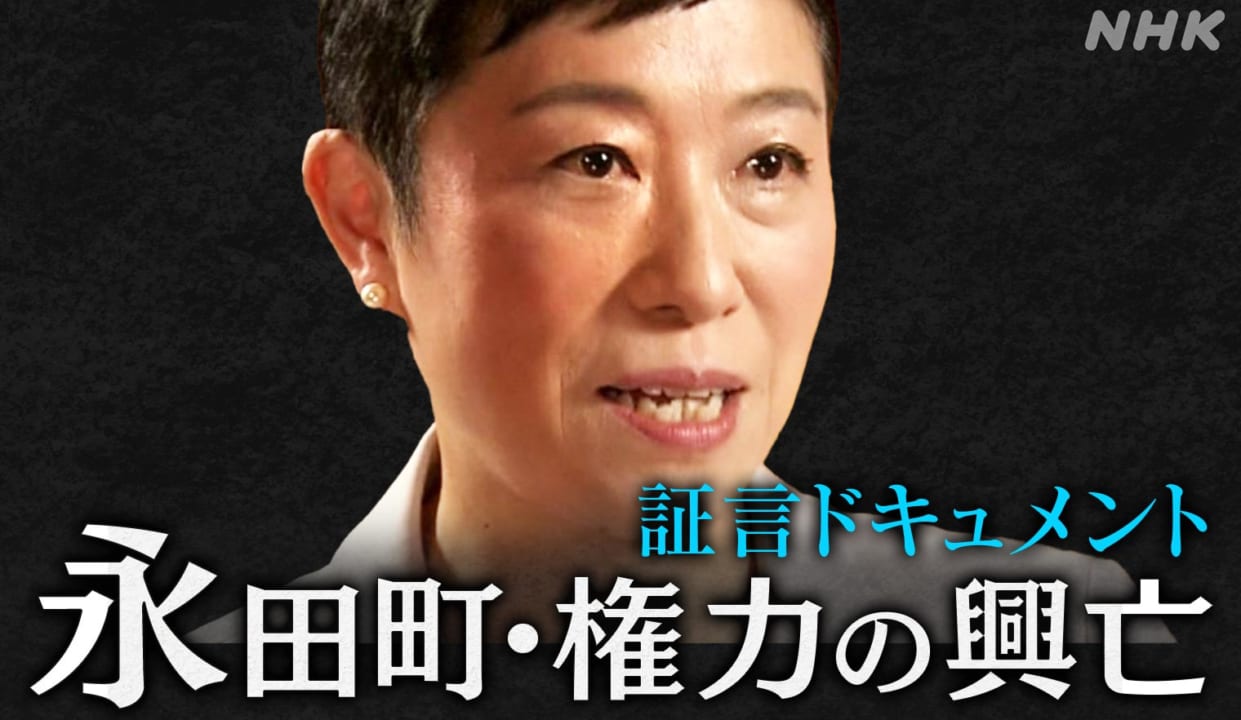
コロナ禍で日本社会が大きな岐路に立った2021年。
総理大臣の座は、菅義偉から岸田文雄へと移行した。ワクチン接種をコロナ対策の切り札として推し進めながらも支持率が落ち込み、志半ばで退任した菅。その舞台裏で何があったのか?
そして前回の自民党総裁選挙で大敗した岸田は、どのように総裁の座を手にすることができたのか?
キーパーソンによる証言からコロナ禍の政権移行の内幕に迫り、日本政治の行方を展望。
NHKスペシャル「永田町・権力の興亡」の取材をもとに、詳細な証言を掲載する。
今回は、立憲民主党の辻元清美に話を聞いた。
この1年の政局について
Q)コロナ禍のオリンピック開催、菅総理退任、自民党総裁選、衆院選と続いた。永田町で起きた自民党の権力を巡る争いをどう見ていたか?
A)コロナ危機ということで、人々の命が懸かっていて、そして多くの人の犠牲を生んだ時代に、相変わらず権力闘争を展開しているなというふうに見ていました。一方、多くの方々が亡くなるという事態の中でも、国会を開かないという状態が長く続きました。国会は開かないがオリンピックは開催する、国会は開かないけれども自民党総裁選は派手におやりになるという事で、誰のための政治をされているのかという思いでいました。
Q)野党は国会を開くことを求めていたが?
A)そうです。何が起こるか分からないコロナ禍で、多くの人たちが自宅待機という名の自宅放置状態で亡くなっていく中、私の友達も亡くなっているんですよ、そんな中、何をすべきか国会で議論しなければならないのに、6月に早々に国会を閉じて開かない。その後(総理大臣の)顔だけ代えて、十分な議論もせずに総選挙をされるというのは、権力を維持するために国民を顧みていないじゃないかという気持ちで、非常に危惧を抱いていました。
横浜市長選挙の影響
Q)衆院選が迫る中でコロナの第5波が拡大し、NHKの世論調査でも菅内閣の支持率は29%と過去最低を更新。横浜市長選では、立憲民主党が推薦した候補が与党候補を破って勝利した。立憲民主党は当時、衆院選に向けてどんな空気だったか?

これは菅総理にとっては大打撃だなと。これは菅下ろしの引き金になってしまうと。ここまでは攻めてきたけど、一挙に向こうが総裁選に打って出たら、反転攻勢されるかもしれないなっていう危機感は大きかったですよ。パッと空気を変えてしまう嫌な予感がありました。
衆議院選挙について
Q)当時、党幹部として、衆院選の獲得議席数の予測について手応えを感じていたか?
A)メディアの予測なんかでも野党が小選挙区で30から40議席増やすんじゃないかと言われていたところから、横浜市長選の頃には(自民党が)70議席を減らすんじゃないかと。で、雪崩を打てば、ひょっとしたら政権が代わるところまでいっちゃうんじゃないかとか、いろんな観測が当時流れたし、私たちの間でもそういう空気もありました。でも私はちょっと違って。その前の東京都議会議員選挙で相当勝つと言われてたんですけど、蓋を開けたら中途半端な議席増だったんですね。ですから、そう甘い事にはならないのではないかなとは思っていて半信半疑でした。民意がどっちに行くのか。その民意の振れ方によっては、雪崩を打って自民党が議席を減らす可能性があるというような、ギリギリのですね、言ってみれば水がどっちに溢れるのかみたいな空気はありました。
Q)民意がどちらに行くという境目はどこにあると感じていたのか?
A)やっぱり自民党総裁選をおやりになるのか、総裁選の前に菅さんで選挙を打ってこられるのか、そのどちらかということだったと思うんですね。まだその頃は総裁選をやっても、やっぱりコロナ禍に対する対応があまりにも後手後手だったり、国会を開かないとか、オリンピックに対してもやっぱり不信感が広がっていましたので、総裁選を打ったとしても(選挙で)一定数やっぱり議席は減るんじゃないかというふうには予測はしてたんですね。菅さんで選挙をされるのか、顔を替えるのか、これがどっちに水がこぼれるかの大きな要因でしたね。
新型コロナ対応への不満
Q)政府のコロナ対応への世論の不信感が追い風になっている実感は?

衆議院解散をめぐる心理戦
Q)全体の状況として、立憲民主党の議席数はどれくらいになると思っていたか?
A)そんなに甘くないと思っていました、私はね。私は2017年の衆議院選挙のあと国対委員長もやりましたので向こうの事情も何となく分かるんですけど、(自民党は)当時、菅総理、二階幹事長、森山国対委員長、それから林幹事長代理、この4人が常に仕切っていたわけですね。で、この4人の利害と野党の利害が一致した瞬間があるんですよ。それは、横浜市長選が終わって菅総理の形勢が悪くなってきた時。菅総理や森山国対委員長は、国会を開いて解散カードもちらつかせて党内を引き締める、また解散を打つというカードも持っておこうとされていたように思うんです。
これは野党と利害が一致するわけですよ。それで(与野党の)両国対委員長が急に国会を開こうと言い出したわけですね。野党のほうから申し入れて国会を開く、そして予算委員会を開こうと。森山国対委員長はいつもならば絶対国会を開かないんですよ。なのに、野党の国対委員長が国会を開こうと言ったら、あうんの呼吸のように「やっぱり国会を開くということも必要かもしれません」とおっしゃったわけですね。私はこの時に、これは解散含みで、解散するための国会開会を自分たち菅政権の執行部でやるという意思表示だなと思いました。
Q)国会が開かれるかもという話が来たとき、ほんとに国会を開いて解散になるという可能性もあると思ったか?
A)思いましたね。ただ、解散の可能性を総理が担保しておきたいと、まず、そこに第一義的な意味があるんだろうなっていうふうに思いました。だって、国会を開かないと総理の解散権っていうのは封じ込められたままですからね。だから勝負に出てきたなと。野党の手を借りて国会を開会しようとするぐらい追い詰められているなっていうふうに感じていました。
菅政権退陣、そして岸田政権のもとでの衆議院選挙
Q)立憲民主党の立場としては、やっぱり菅さんと戦いたい選挙だったか?
A)それはそうですよ。菅さんのまま、やっぱりね。今回の選挙で問われるべきは、安倍政権と菅政権、この長期政権の9年間だったんですよ、まずね。で、その間にコロナもあります。そしてさらに桜を見る会とか、森友とか加計の問題があって、これも片づいてなかったわけですね。赤木さんの妻の話もありました。ですから、やっぱり長期政権、菅さんも安倍政権の官房長官として、この10年近く官邸の主だったわけですよ。ですから、この安倍・菅政権の長期政権の膿も溜まりきっていた。だから本来であれば、菅さんの手で解散をして、これを国民に問うべきだと私は思っていました。ですから菅政権で解散をしてほしいし、するべきだったと。それをコロッと表紙だけ替えて、何か取り繕って、ここはなかったことのように臭い物に蓋をしてと。私、岸田さんに代わった時に言いましたけどね、本会議場の代表質問で。臭い物に蓋をして、新しい家を建てましたといっても、柱が腐ってくるでしょうと。やっぱり国民に信を問うとすれば、安倍新政権の長期政権について問うべきだと思っていたし、だから追い込みたいと思ってました、解散に。
自民党総裁選挙について
Q)菅総理の退陣を表明を聞いた時、率直に衆院選への影響をどう感じたか?

Q)戦略変えないといけないと?
A)結局、総裁選になっていくじゃないですか。そのとき私が思ったのは、ああ自民党のお家芸の総裁選という権力維持装置をギリギリのタイミングで発動したなと思ったんです。ああ、これが”ザ・自民党”やなと。生き延びるための古い伝統的なお家芸なんですよ。
Q)お家芸?
A)はい。やっぱり空気が変わっちゃうわけですね。権力維持装置なんですよ、総裁選というのは。顔を替えるっていう事だけではなくて。総裁選のプロセスをある一つのショーのように仕上げていくのも上手だし。そして総裁選を戦う事で自民党の党員を甦らせるわけですね。それぞれの陣営で総裁選を戦う事によって眠っている自民党の党員たちが、「よしやろう」と。衆議院選挙の前に一回投票するわけですから、選挙運動をやるわけですから活性化されるわけですよ。それは相当侮れない大きなパワーですね。そういう事を今までも見てきましたので。私の場合は初当選から25年なんですけど、そういう局面が今までもあったので。いや今回も、どっちに転ぶか分からないけれども、そういうやり方できたなと思いました。たぶん向こうとしてはギリギリのタイミングだったでしょうね。
Q)菅政権を追い込みすぎたという思いもあったか?
A)それはないですね。やっぱり手加減はしてはいけない。おかしな事はおかしいと、はっきり徹底的にやらないと。そういう手加減っていうのは、有権者に見透かされると思うので。それは野党としてやっぱり行政のチェック、それからコロナの対応で不備があったら、徹底的に議論していくっていう事は大事だったと思うんですね。一方、与野党っていうか、菅政権の幹部と野党の利害が一致したというような政局的な事に、策士、策に溺れるじゃないけど、そういう事に頼って、菅政権で解散に追い込んでいこうと、仮に野党のほうも、それから政権を維持するほうも考えていたとしたら、それは浅はかだったんじゃないかと思いました。やっぱり与野党はガッチリ戦って、野党は与党を追い込んでいくべきだと。
Q)総裁選のおよそ1カ月間、野党の埋没感を指摘する声もあった。当時、危機感はあったか?
A)今回の総裁選挙は見ていて、やられたと思う面と、いやらしいなと思う面と両方あったと思ったんですね。やられたと思ったのは男性2名、女性2名、男女同数の候補者が出たこと。これは先にやられたなって思いましたよ。で、いやらしい面は、結局ですね、A・A・Aという、安倍さん、麻生さん、甘利さん、この3人が後ろでどうも操っているような総裁選の構図が見えましたのでね。ですから、何かいやらしい感じがしました。
河野太郎さんが当時は人気がありましたんでね、河野さんになったら一番嫌だなという気持ちと、河野さんになったら戦いやすいっていう気持ちと両方あって、むしろ岸田さんみたいなあんまり尖ってはいないけれども、可もなく不可もなくと言ったら悪いですけどね、そういう人の方が戦いにくいような気もしていましたね。
Q)河野さんだと人気が上がって大変だというイメージはあったが、岸田さんもやっぱり戦いづらいと?
A)岸田さんもですね。ただ、岸田さんも途中でですね、なんか安倍さんにちょっと釘を刺されたのか何か知らないけれども、森友の再調査を引っ込めたりとか、後ろにいわゆる派閥の親分的な人たちの顔がちらついてましたんで、そういうことを国民の皆さんにしっかり嗅ぎ取って頂いて、表紙を変えただけで、結局、安倍・菅政権とか麻生さんの支配が続くんじゃないかというところを、しっかりと見て頂ければいいなという一抹の期待を寄せておりました。
Q)総裁選の政策論争の影響で、野党が差別化を図っていくのが難しくなってきたと感じたか?
A)それはあまり感じなかったですね。その後、岸田さんに決まってからですね、新しい資本主義とか新自由主義からの脱却とか、分配とか、それから介護士や保育士の待遇改善とか、まるで立憲民主党の政策をコピペしたようなことを言い出すわけですよ。いや、それはちょっとですね、抱きついてきたなっていうか、かなわんなっていう気持ちはありました。
衆議院選挙から得た教訓
Q)立憲民主党は議席を増やせなかったが?

Q)修正が必要だったと?
A)でも修正は難しいよね、あのぎりぎりのタイミングだからね。野党第1党だと必ず政権交代と言わなきゃいけないっていう、そういう何かですね、使命感と、それから脅迫観念にちょっと縛られ過ぎたかなって私は思うんです。そのずれとか、野党第1党っていう傲慢さみたいな事が、票が伸びなかった結果なのかなって、私自身の選挙を見てもそう思っています。
野党勢力の現状は
Q)野党の現状をどうみる?
A)4年前(2017年)に、野党が希望の党騒動があって分裂してね、複雑骨折しちゃったわけですよ。私は国対委員長として6党1会派を何とかまとめようと思って、なんとか複雑骨折の骨をつなぎ合わせたりしてきたんだけど、今回の選挙でまた違う、いわゆる第3極的なところも強くなったので、違う形での野党の厳しい現状があると思うんですね。野党の主導権争いが前より激化したと思うし、それから路線対立みたいなものも、前以上に顕在化してきてるんじゃないかなと危惧しています。そこをですね、あんまりまとめようとしても無理かもしれないっていうか、難しいんですよ。ですから、それぞれの独自性を発揮して、政府や与党をしっかりチェックしていくと。そこからしか道は開けてこないんじゃないかなと。自分のアイデンティティを大事にしながら、歩んで行かないといけないんだと思います。
権力とは
Q)権力闘争がなくなる日は来ると思うか?