なぜ脱退か 鯨と政治家

「日本は商業捕鯨禁止のルールに逆らうことになる」(英BBC)
「反捕鯨国であるオーストラリアやニュージーランド、アメリカは、非常に深刻に受け止めている」(豪ABC)
年の瀬が迫った去年12月26日、日本政府は、IWC=国際捕鯨委員会から脱退し、ことし7月から商業捕鯨を再開すると発表した。
日本が広く知られている国際的な機関から脱退するのは極めて異例だ。海外から批判や反発が相次ぎ、国内からも懸念の声があがった。クジラを食べたことがない若者も増える中、なぜ捕鯨再開にこだわるのか。その背景には、政治家の意向があった。舞台裏に迫る。
(政治部 関口裕也)
きっかけは、ある政治家
IWCからの脱退が発表された日の自民党本部。
「我々からすると…神様みたいなもんですよね」
記者団にそう話したのは、和歌山県太地町の三軒一高町長。直前に面会した二階幹事長のことをそう表現したのだ。

太地町は、衆議院の選挙区でいえば和歌山3区、二階氏の地盤だ。

紀伊半島の南に位置し、太平洋に面している。網やモリを使ってクジラを捕獲する「古式捕鯨」発祥の地とされる。長年、商業捕鯨の再開を切望してきた三軒氏は、脱退は地元選出の二階氏の尽力があってこそと強調する。「幹事長は、懸命の努力を、地方の声を官邸に届けてくれた。その結果だと思っております」
その二階氏。IWC脱退について、次のようにコメントしている。
「政府を全面的に支持する。IWCは組織が変質し、反捕鯨国は鯨に依存する漁業者の暮らしを一顧だにせず、商業捕鯨を再開するためには、IWCから脱退するしかない。今回の決定は、商業捕鯨の再開を待ち望んでいた全国の願いをかなえるものだ」

「どうして他国の食文化に文句を言ったり、高圧的な態度で出てくる国があるのか。日本が他国にそんなことをしたことがあるか。我々は再三再四、脱退も辞さないと前々から警告してきたが、一顧だにせず、『クジラがかわいい』とかそんな話ばっかりだ。我々が脱退するということは、並々ならぬ決意であるということを、ご理解いただきたい」
IWCと日本の捕鯨
ここで、IWCとはどういう組織で、日本の捕鯨との関係がどのようなものか、ひもといておこう。

IWCは1948年に発効した国際捕鯨取締条約によって設立された組織で、もともとはクジラの資源を保護し、捕鯨を続けていくために設立された。日本は1951年に加盟。ホームページによると、加盟国は日本を含め89となっている。
日本ではクジラの肉はタンパク源として重宝され、1960年代には「商業捕鯨」は最盛期を迎えた。
しかし、シロナガスクジラなどの貴重なクジラが減少したとして、次第に国際的な批判が高まり、1982年にIWCで「商業捕鯨」の一時停止が決議された。
日本は異議申し立てをしたものの1985年に取り下げ、1987年からは資源量や生態調査などを行う「調査捕鯨」を行ってきた。この「調査捕鯨」で捕獲された肉が、「調査副産物」として日本国内で流通しているのだ。

また、IWCが管轄しないツチクジラなど小型のクジラに限って捕獲する沿岸の捕鯨が、太地町など一部で小規模に行われている。
今回、日本は脱退を表明したが、実は過去にも例がある。先住民が捕鯨を行うカナダは、1982年の「商業捕鯨」一時停止の段階で脱退。アイスランドも1992年に脱退しているが、その後再び加盟し、2006年に「商業捕鯨」を再開している。そもそも、捕鯨をしていてもIWCに加盟していない国もあるが、加盟国で「商業捕鯨」をしているのは、アイスランドとノルウェーだ。
加盟国の中では、捕鯨を支持する国と反対する国が拮抗(きっこう)する状態が続いている。
なぜ今なのか
脱退は、何がきっかけだったのか。
同じ和歌山県の選出で、二階氏とともに捕鯨問題に携わってきた、自民党の鶴保庸介参議院議員はこう語る。

「IWCからの脱退論は以前からありました。ただそのたびに『時期尚早だ』とか『外交への影響を考えて粘り強く努力すべきだ』などと言われた。私の知る限り10年以上前からくすぶっていたんです」
そこに長く関わってきたのが、二階氏だという。鶴保氏は、こんなエピソードを語った。
「ある総理大臣が、若いころの二階氏を海外に連れて行く時に『二階くん、クジラのことは(相手国には)言うなよ』と言ったそうです。そしたら二階氏は『それなら私を外してください』と、啖呵(たんか)を切ったそうですよ」
商業捕鯨が過去のものとなり、クジラが日本の食卓から消えつつある中、2014年に自民党本部や外務省の食堂に、クジラの肉が入った「クジラカレー」を提供させたのも、二階氏だった。

そうした経緯がある中、今回、一気に「脱退」という決断に至るには、3つの要素があったという。
ひとつは、ある国際的な裁判所による判決。
もうひとつは、「調査捕鯨」を継続するかどうかという問題。
そして何よりも、去年9月のIWC総会が、決定的だったという。
想定外の判決
まず、ひとつめの「判決」だが、これは2014年にオランダ・ハーグにある国際司法裁判所が言い渡したものだ。

訴えたのは、オーストラリア政府。日本が南極海で行っている「調査捕鯨」は、実態は商業的な目的を持った捕鯨であり、国際捕鯨取締条約に違反しているとして、捕鯨の中止を求めた。先に書いたように、「調査副産物」としてクジラの肉が市場で売られていること、それに捕獲される頭数が年間数百頭に及んでいることなどが理由だった。

これに対し日本は、捕獲する頭数は調査のために必要で、クジラの肉の販売も条約で認められているなどと反論。科学的な調査が目的で成果をあげていると主張した。

だが、判決では、日本のそれまでの「調査捕鯨」は条約で認められている科学的な調査には該当しないと判断を示し、このままの形で捕鯨の許可を与えることはできないと言い渡した。

当時、判決の内容を楽観する見方が大勢を占めていたこともあり、関係者に少なからず衝撃を与えた。
鶴保氏も「理解していただけると期待していたにもかかわらず、厳しいものだった。これが日本の捕鯨政策の暗い見通しにつながった」と解説する。
「調査捕鯨」実は負担にも
次に、「調査捕鯨」そのものを継続する意義があるのかどうか、それもポイントだったという。
鶴保氏によれば、南氷洋での調査捕鯨は、事実上、日本が全てを担っているという。日本の科学者が中心となり、拠出金も日本が出していると説明する。さらに、老朽化した調査のための船を更新するには大変な資金がかかり、判断しなければならない時期にさしかかっていたという。

「我々としてはIWCの調査捕鯨を継続していくだけの意義を拠出金と比べてみた時に、判断しかねるな、というのがありました」
決定的だったのは9月
そして、決定的だったのが、去年9月のIWC総会だった。

ブラジルで開かれた総会には、鶴保氏をはじめ自民党の捕鯨議員連盟のメンバーらが参加。
日本は商業捕鯨再開を提案したが認められず、その一方でクジラの保護を求める宣言が採択された。

「これまで手を変え品を変え努力してきたはずだったのに、ほとんど影響力を及ぼすことはできなかった。むしろ悪化の一途という状況だった。それに加えて9月の総会。IWCの質がもう完全に変わってしまったと判断したんです」
慎重な外務省、それに対し…
しかし外交への影響を懸念し、外務省は脱退に慎重だった。
IWC総会の直後に開かれた議員連盟の会合。

議員らが、脱退への具体的検討を進めるよう求めたのに対し、外務省の担当者から前向きな返答はなかったという。
そこで、声をあげたのが二階氏だった。

「何をボヤボヤしているのか。党をなめとるんじゃないか」
「覚悟を決めて対応しろ。いいかげんにしろ。まじめにやれ」
それが号砲になり、この日以降、二階氏を中心に議員連盟のメンバーは、IWC脱退に向けた取り組みを加速させたという。
官邸が同調 その理由は
外務省が頼りにならないと感じた二階氏は、総理大臣官邸への働きかけを強めた。
すると官邸サイドも、二階氏らの動きに一貫して同調したという。
安倍総理大臣のお膝元は、山口県下関市。そう、ここも日本有数の「クジラのまち」だ。

鶴保氏は、官邸の理解を得られたのには、そのことも大きいと分析する。
下関市は、戦前から戦後にかけて近代捕鯨で栄えたが、日本が商業捕鯨を中断したあと、市内でクジラ料理を出す店は大幅に減少したという。
「安倍総理は、下関という一大捕鯨拠点を地元に抱えて、水産関係者の生活や業態も肌感覚として入っていたのではないかと強く思いますね」
一斉に反発、懸念の声も
こうして自民党と官邸が歩調をあわせて、脱退へ進んでいくことになったが、反捕鯨国を中心に強い反発が出た。
「日本はクジラの虐殺をやめろ」
12月31日付けで、米紙ニューヨーク・タイムズに掲載された社説のタイトルだ。

「IWCは減少する海洋資源を管理するという世界共通の責任を体現する場だ」などと、脱退を考え直すよう求める内容だ。
これに対し、外務省の大菅岳史外務報道官が反論する文章を寄稿して今月11日に掲載された。「社説は決定的事実に言及していない」と指摘した上で、「日本はクジラの保護に取り組んでいる。絶滅の危機にある種類のクジラの捕獲は禁じている。捕鯨は日本の領海とEEZに限定し、国際法にも完全に従っている。捕鯨は、ノルウェーやアイスランドなどと同様に、何世紀にもわたり日本の文化の一部であった。日本だけを批判するのは不公平だ」としている。
しかし、批判はほかの国からも相次いでいる。反捕鯨国の中でもとりわけ厳しい立場で知られるオーストラリアは、ペイン外相とプライス環境相が共同で声明を発表。

「極めて失望している。日本の決定は残念であり、オーストラリアとしては、日本に、IWCに戻ることを優先的に検討するよう促す」として、IWCに速やかに復帰するよう呼びかけた。
フランス政府も「日本の決定に遺憾を表明する。脱退するという日本の選択は、環境分野における多国間主義に送られた誤ったシグナルだ」とする声明を発表した。
また、国際的な環境保護団体「グリーンピース」は「日本政府は、世界のメディアから注目を浴びないように、年末にこそこそと発表した。

商業捕鯨を再開するよりも、海洋生態系の保全に速やかに取り組むべきだ。多くの種類の鯨はまだ生息数が回復していない」と主張した。
国内からも懸念する声が上がった。
立憲民主党の枝野代表は「感情的とレッテルを貼られかねない」と話す。

「脱退が国際社会での孤立に向かうきっかけになりかねないのではないか。脱退したら、日本の捕鯨がどうなるのか、ビジョンが示されているわけでもない。ほかの分野でも『日本は、都合の悪いことは、感情的に国際社会の協調から抜け出すような国だ』とレッテルを貼られると、大きく国益を損なうので、今の進め方は適切ではない」
共産党の小池書記局長は「アメリカのトランプ大統領のまねみたい」と揶揄(やゆ)した。

「伝統的な日本の食文化の1つであり、科学的な根拠に基づいて、厳格な管理のもと、引き続き捕鯨は行われるべきだ。ただ、『主張が受け入れられないから脱退する』という対応は、国際的な理解を得られないのではないか。『うまくいかないと国際機関から脱退する』という、アメリカのトランプ大統領のまねみたいなことは、やめたほうがよい」
国内の新聞各紙も、日本外交にマイナスになることを懸念したり、国会などでの十分な議論がなかったと批判したりする社説を掲載した。
クジラ、食べていますか?
国内では、NHKの世論調査で、日本政府がIWCから脱退し、商業捕鯨を再開すると表明したことについて、「大いに評価する」が13%、「ある程度評価する」が40%で半数を超えた。

一方で、「あまり評価しない」が27%、「まったく評価しない」が10%で、歓迎一色とは言えない結果となった。
そもそも、クジラの肉の流通量は減っている。水産庁によれば、1962年度の23万3000トンをピークに減少が続き、商業捕鯨を中断すると3000トンにまで減った。ここ数年は、調査捕鯨による供給や海外からの輸入で、年間3000トンから6000トン程度で推移している。

今回のことについてネットでの反応をみると(NHK「SoLT」調べ)、平成生まれと見られる若い人からも、
「昭和の給食には鯨が出てたってツイートやサイト見たけど、平成生まれの私も小学校の給食で鯨食べてたよ」
「鯨の唐揚げうまいよなぁビールとあうわぁ」
などと、食べたことがあるという反応もあったが、やはり縁が無いという書き込みが見られた。
「さっそく今日上司にクジラの事(IWC脱退)言われたよ 私がクジラを一度も食べたことないって言ったらびっくりしてた」
「僕世代の人たちは鯨なんて食べたことない人が多いから、IWC抜けたことに関してあんまり興味がないと思う。個人的には捕鯨はある地域での文化だし、鯨食を野蛮と欧米諸国に思われようとも文化を理解しようとしない方が野蛮だから、気にしなくていいと思う」
「日本の10代、20代の殆どはクジラを食べたことないと思うのですが、大学生の私はクジラを食べることには抵抗があります。犬や猫を食べるのと同様に。需要も少ないと思うので、伝統という名目で沿岸部で捕鯨をやってくれればいいのですが、わざわざ遠方までいって捕鯨(※注 調査捕鯨のことを指しているとみられる)する必要は無いと思います」
意義はあるのか
鶴保氏は「『クジラは食べなくなっているのだから、捕鯨は必要ない』と言うなら、『食べたいという人や捕鯨に携わる人たちの気持ちはどうなるの』と聞きたい」と話した上で、文化や技術の継承の面でも意義があると強調する。
「例えば、『文楽』の糸は鯨のひげで、マッコウクジラは香料のもとにもなっている。こういう文化を守り、復活させていくことがひとつ。さらに捕獲や解体には特殊な技術が必要で、技術者は高齢化している。技術の伝承という観点からも捕鯨再開は必要なんです」

さらに、水産資源の確保の上でも重要だと語る。
捕鯨の中止でクジラが増え、そのクジラが海中の魚介類をエサとして補食することで、水産資源の減少につながっているというのが、従来からの日本の主張だ。水産庁によれば、クジラによる捕獲量は、世界の海面漁業の漁獲量のおおよそ3倍から5倍に上るとしている。
「5倍は大げさだとしても、相当量の水産資源の圧迫になっているのは事実。平たく言うと、間引いた方がいいということです」

そして国際機関の脱退という決断については、こう語った。
「北方領土や尖閣諸島、沖縄の基地問題にしても、日本の主張は通せていない。そうした時代に、IWCを脱退しないというのは『主張しない』と言っているようなものです。日本が主権国家である以上、あらゆる外交チャンネルを使って主張していくことが必要なんじゃないでしょうか」
IWCを抜けると、どうなるのか
今回の通告で、日本はことし6月30日にIWCから正式に脱退し、7月から「商業捕鯨」を再開することが可能になる。日本の領海とEEZ=排他的経済水域で再開する方針だ。
ただ、日本は、海の利用などを定めた国連海洋法条約を批准していて、この中で捕鯨を行う場合には国際機関を通じて適切に管理することが定められている。このため、日本政府はオブザーバーという形でIWCの総会や科学委員会に関わっていく方針で、新たな国際機関を設立して捕鯨を行うことも検討している。一方、「調査捕鯨」についてはIWCで認められる必要があるため、脱退すれば今のまま続けることはできなくなる。
これについて「クジラが豊富な南氷洋でこそ捕鯨を続ける日本の役割を果たせるのに、みずから放棄することは主張の整合性がとれない」と語るのは、元水産庁のIWC日本代表代理だった、東京財団政策研究所の小松正之上席研究員だ。

小松氏は平成3年から13年余り、中心メンバーとしてIWCでの交渉に臨んできた。
「調査捕鯨で得られたデータの分析や公表が十分ではないうえ、調査捕鯨の捕獲枠を余らせているのに計画を修正しないなど、反捕鯨国に批判される隙を与えている」と述べ、日本側の取り組みにも問題があると指摘している。

そして、「脱退して何をしたいのかが不明確で、裁判など国際社会からの締めつけが強まるだけだ。むしろ、持続的な利用をどう進めるか、日本が世界の先陣を切って粘り強く交渉を進めることが重要だ」と述べた。
問われるもの
IWCのように主要な国際機関から日本が脱退するのは極めて異例だ。
日本外交は戦後、国際協調を重んじて、主張が他国と対立しても話し合いを重視してきたが、今回の政治主導による脱退という決定は、1つの転換点となるかもしれない。
海外からの厳しい声にどう答えていくのか。
マグロなど他の水産資源の管理をめぐって、日本の主張が通りにくくなるという懸念もある。
クジラの肉の国内消費が低迷する中、再開する商業捕鯨が産業として成り立つかという問題もある。
主張は通した。
だが、問われるのは、これからだ。
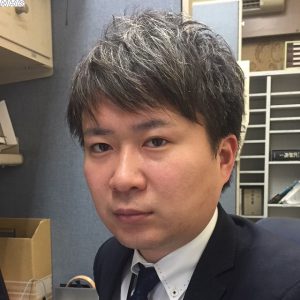
- 政治部記者
- 関口 裕也
- 平成22年入局。福島局、横浜局を経て政治部へ。現在、自民党二階幹事長番。





