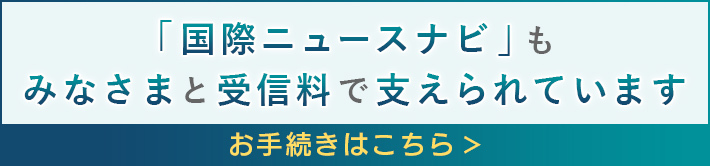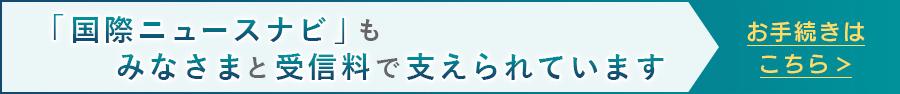G7広島サミットに出席するため、日本を訪れるアメリカのバイデン大統領。
ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシア、影響力を拡大する中国に、G7としてどう対応していくのか。
そして、アメリカは日本に何を期待し、日米韓3か国関係の将来は?
バイデン政権の元高官に、広島訪問にあたってのアメリカの狙いについて聞きました。
(聞き手:ワシントン支局長 高木優)
バイデン大統領のG7でのねらいは?
話を聞いたのは、バイデン大統領のもと、去年までホワイトハウスのNSC=国家安全保障会議で東アジア部長を務めたクリストファー・ジョンストン氏です。

ジョンストン氏は今回のG7サミットについて「バイデン大統領は、G7という枠組みの復活、インド太平洋地域への脚光、そして、広島という特別な場所での開催、この3つの意味で重要だとみている」とした上で、それぞれの意味について次のように述べました。
※以下、ジョンストン氏の話
G7という枠組みの復活
G7は世界の主要な経済大国のあいだで政策を調整する重要な枠組みとして復活しました。つい最近まで、G7は廃れ行き、G20のような枠組みに取って代わられるという見方がありました。

ところがもはやそうした見方はありません。ロシアがウクライナに軍事侵攻したことで、この見方は完全に逆転し、極めて重要な国際問題について政策を調整する、最重要の枠組みとして復活したのです。
インド太平洋地域への脚光
今回は日本が指導力を発揮でき、かつインド太平洋地域に焦点を当てることが可能な7年に1度の機会です。
そしてその最大のテーマが中国です。
バイデン大統領と岸田総理大臣双方にとって、今回は、国益優先で「法に基づく秩序」を変えようという中国に焦点を当て、そうした行動を押し戻し“経済的威圧”と呼ばれる行為などへの対策を調整するうえで大事な機会となります。
広島という特別な場所での開催
初めて原子爆弾が使われた場所である広島でことし、G7サミットを開くということ自体に大きな意義があると思います。

ロシアのプーチン大統領が核兵器使用の可能性をちらつかせ、朝鮮半島情勢が懸念されるさなかにあるからこそ、核の使用がいかに危険で、核のない世界に向けて長期的なビジョンを維持していくことがいかに重要かという、非常に力強いメッセージを発信することになります。
G7とG20の違いとは?
G20の課題はロシアや中国がメンバー国だということです。
ロシアがウクライナに侵攻した今日において、G20が効果的に機能することは非常に難しくなっています。

一方で、私がオバマ政権時にホワイトハウスにいたときは、正直に言って政権内でG7の意味合いが非常に低下していました。
オバマ大統領自身、G7に熱心ではありませんでした。彼はG7はもはや過去の枠組みであり、G20こそが今、そして未来に向けた枠組みだと捉えていました。いま、バイデン政権はそれとまったく逆の考えを持っています。
広島でのG7 バイデン政権のメッセージは?
危険な核の使用に対してG7が強いメッセージを発信することは確実だと思います。
2016年に広島を訪問したオバマ大統領は当時、「核なき世界」の実現を掲げていました。しかし不幸なことに、世界はそこから遠ざかってしまいました。

その後、北朝鮮は核兵器開発を続け、中国は核兵器の近代化をはかり、ロシアはヨーロッパで核使用の可能性をちらつかせています。
しかし、私たちが「核なき世界」の実現というビジョンを持ち続け、あきらめないことは重要です。だからこそ、広島で開かれる今回のG7サミットは、重い意味を持ちます。
「グローバル・サウス」への対応は?
G7や先進国のあいだでは、ウクライナでの戦争やロシアへの対応で非常に強い結束がありますが、グローバル・サウス(アジア、アフリカ、中南米などの新興国や途上国)のあいだではそこまでの合意がありません。
グローバル・サウスの中には西側諸国のやろうとしていることは偽善だと見る国もあります。
彼らは、(アメリカなどの軍事侵攻によって始まった)イラク戦争のことを覚えており、ウクライナへの軍事侵攻をめぐって、アメリカなどがどうやったら「法に基づく秩序」などと言えるのか、といぶかしんでいます。

中国やロシアはこの力学を利用して自分たちの利益を拡大しようと動いています。それは東南アジアだけでなく、アフリカやラテンアメリカなどいたるところで起きているのです。
ですから、今回のG7では「法に基づく秩序」が途上国の経済にどんな利益をもたらすのか、という前向きなビジョンを発展させるため、各国が協力すべきです。
それは投資、気候変動対策での協力、グローバルなレベルでの健康といった領域を通じてやるべきです。
グローバル・サウスの繁栄にG7がどのように貢献できるのかを示すことがとても重要になります。岸田総理大臣はこのことにおいて力強い発信力を持っていると思います。
G7のメンバー国であるフランスのマクロン大統領が4月、台湾情勢をめぐってヨーロッパはアメリカと中国の対立から一定の距離を保つべきだという発言をして波紋を呼びました。
マクロン発言 バイデン政権の受け止めは?
マクロン大統領の発言は、実際にはほかのヨーロッパの指導者の考えからは、ずれたものだと思います。

イギリスやドイツの指導者の中国をめぐる公の場での発言はまったく異なっています。現実には、中国の振る舞いに対する懸念という点において、インド太平洋地域とアメリカ、ヨーロッパのあいだの認識はますます一体化しています。
中国の習近平国家主席が「無制限のパートナーシップ」と称してロシアのプーチン大統領に同調する決断をしたことや、ことし前半にプーチン大統領に会うためにモスクワを訪ねたことは、非常にマイナスのメッセージを送り、アメリカ、ヨーロッパ、インド太平洋地域が結束することを助けました。

中国に対する見方は当然、国によって多少の違いはあります。しかし、サミットの首脳宣言では、台湾海峡をめぐる問題に加え、南シナ海、東シナ海の問題についても、とても力強いことばが並ぶはずです。
中国による“経済的威圧”に対しても、強いメッセージが出されると思います。
バイデン政権は台湾海峡情勢をどう見ている?
切迫したものだと見ています。ただ、良いニュースはアメリカも中国も、台湾をめぐる衝突を望んでいないということです。
中国が台湾統一に向けた、確固たる工程表を持っているとは思いません。中国が軍事的な準備を進めていることは間違いありませんが、中国がいかなる軍事的衝突であってもリスクが伴うことをよく認識していることも確かです。

だからこそ、抑止力が衝突を回避するうえで、非常に有効な方法となります。
アメリカがインド太平洋における安全保障上の態勢を強化し、日本が防衛費を増額して反撃能力などの新しい能力の獲得に動き、オーストラリアやフィリピンといった友好国や近隣国が行動を起こしているのは、そのためです。
これらすべてのことが抑止力を高め、中国が軍事力を行使した場合に支払うことになる代償を高めることにつながるわけです。
最終的にはわれわれは安定を保ち最悪の結果を回避できると、私は楽観的に見ています。
中国への対抗 日本に望むことは?
第一にわれわれ日米両国は、同盟関係を継続して深化させ一段と統合された関係へと発展させていくべきです。

私はまさにその方向に両国は動いていると思います。日本が防衛費を増額し反撃能力やサイバーへの対処能力などを備えることにしたことは、同盟関係をより深化させる上での扉を開きました。
地域のほかのパートナー国家との関係を強化することも必要です。
日本はオーストラリアと速やかに安全保障面での関係を強化しました。これは大変、歓迎されています。日米豪3か国は多くの共同作業や演習に一致して取り組むことができるでしょう。

そして、日米韓3か国は非常に重要な関係の枠組みです。
日本と韓国がミサイルの脅威に関するデータの共有に踏み出したことは非常に心強く、こうした動きを加速させるべきです。
日本は地域での経済援助戦略を実行に移しました。そしていま、防衛装備品を東南アジアなどの友好国に移転するという新しい手段も持つようになりました。
日本は、共通の価値観を持つ国々のあいだのネットワークを構築する上でも大事な役割を果たせます。そのことが集団的な抑止力の強化につながるのです。
日本との関係改善に踏み出した韓国 どう評価?
韓国のユン大統領は、正しいことをするために相当な政治的なリスクを負いました。そのことは称賛に値します。

日本の植民地時代の「徴用」の問題を解決しようという行動が、3月の日本訪問を実現させました。そして岸田総理大臣の韓国訪問もとても前向きなものでした。
ユン大統領の決断と、それに対する岸田総理大臣の対応によって、今まさに関係改善のモメンタム(機運)が醸成されました。私が期待するのは、このモメンタムを加速させることです。
日米韓という3か国は、地域で最も重要なグループです。
この3か国のあいだにはたくさんの共通利益があります。それは北朝鮮問題だけでなく、インド太平洋地域における経済安全保障分野での協力しかりです。私たちは多くのことに一緒に取り組めます。
日米韓3か国の関係は格上げされる?
経済安全保障など多くの分野で、日米韓3か国の協力は深まっていくと思います。
3か国の対話がより制度化されていくと見ています。防衛分野で言えば、拡大軍事演習やミサイルの脅威に対する情報共有です。そしてインド太平洋地域をめぐる対話、そして戦略の調整といったこともあるでしょう。

もし、こうした分野での3か国の関係を制度化できれば、この力強い協力の枠組みを後戻りのできない永続的なものにすることができます。
アメリカの核戦力を含む抑止力で同盟国を守る「拡大抑止」をめぐっては、日本と韓国のあいだで考え方に温度差があります。
「拡大抑止」でも日米韓3か国の関係はうまく機能する?
私は「拡大抑止」において3か国が対話を深めていく余地があると強く感じています。
確かに日本と韓国のあいだでは議論に性質の違いがあります。
韓国では核兵器をめぐって非常に深刻な議論があります。ユン大統領のワシントン訪問の際には、アメリカが戦略原子力潜水艦を韓国に派遣することや情報共有の枠組みを新たに設置することで合意があり、多少なりとも韓国での議論が前進しました。
これに対して日本での議論は性質が異なります。しかし、日本もアジア地域における核の脅威に懸念を抱いているという点では同じです。

「拡大抑止」やアメリカによる「核の傘」の信頼性への考え方において、日本と韓国のあいだには一定の共通点もあります。ですので、私は「拡大抑止」についても将来、日米韓3か国の防衛当局者が意見を交わす機会が訪れるものと確信しています。
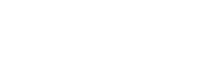















 国際ニュース
国際ニュース