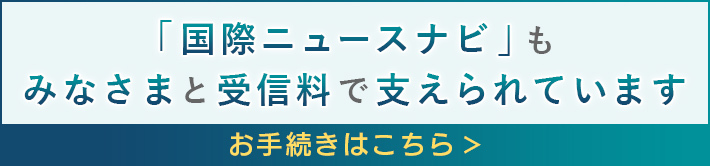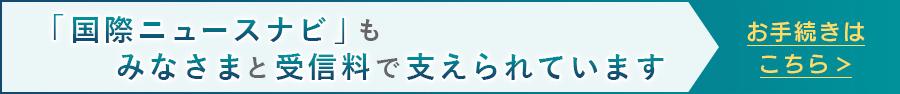ある日突然、国が侵略されて武器を持って戦場へ行けと言われたら、あなたならどうしますか?
ウクライナ人の男性には、幼い2人の娘がいて、いつまでも妻と成長を見守っていくつもりでした。しかし、ロシアの軍事侵攻により、妻と娘は国外へ避難。
国を守るために兵士として戦うべきなのか。残された男性が選んだ道は、大学への進学という“徴兵逃れ”でした。
(ウクライナ取材班 松尾恵輔)
「目的の50%は教育のため、残りは…」
話を聞かせてくれたのは、ウクライナ南部出身の30代の男性です。匿名を条件に取材に応じました。
(※インタビューは2023年12月に行いました)

「みんなが戦争に行ったら、誰が働くのでしょうか? 専門性を身につけて働くことも国益につながります。私の大学進学の目的の50%は教育を受けることです」
男性は去年、大学に入学することを決めました。
すでに大学を卒業していたため、大学生になるのは2度目です。目的の「半分」は教育を受けるためと言うものの、残りの「半分」は、当初は語ろうとしませんでした。
それは、表だって口にしづらい「徴兵逃れ」でした。
大学生は徴兵対象外 30代の入学者数は侵攻前の20倍
ウクライナは総動員令が出ていますが、学生は徴兵の対象外になります。このため軍隊に行きたくない人たちが、大学に入学していると指摘されています。
現地のジャーナリストなどでつくる団体「NGL.media」によると、30歳から39歳で新たに学生になった男性の数は、ロシアによる軍事侵攻前の2021年には2186人だったのが、2022年には3万277人と13倍に増加。
さらに、2023年は4万3722人と侵攻前の20倍になりました。

全世代で合わせると、2023年だけで11万人もの男性が大学に入学し、徴兵を逃れた可能性があるといいます。大学側も学費を得ることが出来るため、こうした学生の受け入れを拒んでいないとみられています。
取材を受けた男性は「合法的なやり方だ」と話しています。男性の周囲にも大学への入学を選択する人は少なくないといいます。
当初は軍に志願 気持ちが変わった理由とは
2年前、ロシアによる侵攻があった直後、男性は、軍に自ら志願していました。
実は、男性のふるさとは、ロシア軍に占領されていました。仕事を失い自宅を追われ、妻と2人の娘は安全を考えて、ウクライナの国外に避難させました。
「私はすべてを失いました。でも、ロシア軍には決して屈しません」
ウクライナ国内では志願する若い男性が相次いでいました。
男性もまた事務所に向かいましたが、担当者から「もっと若くて健康な人や、軍事経験がある人を採用したい」と言われ、その時は入隊には至らなかったといいます。

なぜ、一転して徴兵を逃れたいと思うようになったのか。
男性がまず指摘したのが、ウクライナで相次いで報じられる汚職です。ウクライナでは、ロシアによる侵攻が続く中でも、汚職の問題が明らかになっていて、国防省による装備の調達の汚職疑惑なども報じられています。
市民が命をかけて戦場に行くのに、スキャンダル続きの政権や軍を信頼して良いのか、疑念を深めていました。
祖国も大事だが、家族も
さらに、男性が見せてくれたのが外国に避難している妻と2人の幼い娘の写真でした。

ウクライナでは、18歳から60歳の男性の出国が原則禁止されていて、男性自身も国外に行くことは出来ません。
1年以上もひとりぼっちで過ごし、スマートフォンで妻に娘の写真や動画を送ってもらっては眺めていますが、抱きしめることも出来ずにいる日々。
次いつ会えるのか。会える日は来ないのではないか。
そんな中で、もしも自分が戦争に行くことになり、亡くなったり、けがをして後遺症が残ったりしたときに、誰が娘や妻を養うことが出来るのか、考えただけで不安になります。
家族を守らなければならないし、そうする自由を尊重してほしい。侵攻が長引く中、男性は、戦場ではなく、大学に向かっていました。
「ふるさとや家を失った悲しみを怒りに変えて、敵(ロシア軍)を殺しに行く人たちもいます。
でも、私にはその準備が出来ていません。戦闘が怖いんです。私たちは家畜ではなく、人間です。なぜ家畜のように、塹壕に追い立てられなければならないのでしょうか。
強い思いだけで戦場に行こうという人は、もういなくなってしまいました」
軍事専門家「前線兵士のローテーションで新たな兵が必要」
こうした“徴兵逃れ”は、ウクライナ軍の戦いにどう影響しているのか。ウクライナの軍事専門家、オレクサンドル・ムシエンコ氏に話を聞きました。

ムシエンコ氏
「徴兵逃れは、現時点で兵員の確保に影響はない。ただ、ウクライナに対するロシアの侵略は続いており、新たな兵士、新たな予備役は必要になる。
2年近くにわたって戦場の最前線にいる人たちを交代させ、ローテーションさせることも検討されている」
長期的には兵力の確保が課題になるとした上で、軍に入隊することに対する市民の意識を変えるようウクライナ当局側の努力も必要だと指摘しています。

ムシエンコ氏
「300万人、400万人が一度に動員されるわけではないのに、多くの人たちがパニック状態に陥っているように見える。動員を避けようとする人の考えや行動を、無理に変えることが出来ないのは(ウクライナのような)民主主義の社会では当たり前のことだ。
動員は『罰』ではなく、『国のためになること』だと、人々の考えを変えていかなければならない。戦争によって経済が悪化する中でも、兵士により高い給与を払うなど待遇も改善していく必要がある。そのためにも欧米や日本などからの援助が重要だ」
取材後記
レストランで食事を楽しむカップル、ショッピングセンターで買い物をする家族連れ。
私たちが取材を続けていたウクライナの首都キーウでは、ロシア軍による空襲が繰り返される中であっても、大切な人との時間を過ごす人たちの姿を目にします。

そうした雰囲気の中から突然引き離され、戦地に行くという決断は、たとえ祖国を守るためであっても簡単なものではないと感じます。
自分が取材した男性の立場だったらどうするか、取材を終えた今も、心に重いものが残ったままです。
ただ、ロシア軍と前線で戦う士官のひとりは「兵士は疲れている。勝利のためには新たな兵士が必要だ」と人員確保の必要性を話していました。
ロシアの軍事侵攻が長期化する中、どうやって国民の理解を得ながら兵力を確保し、侵攻を食い止めるのか。
ウクライナ社会に突きつけられた大きな課題だと感じます。
(2024年1月7日 ニュース7などで放送)
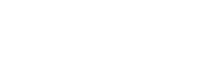













 国際ニュース
国際ニュース