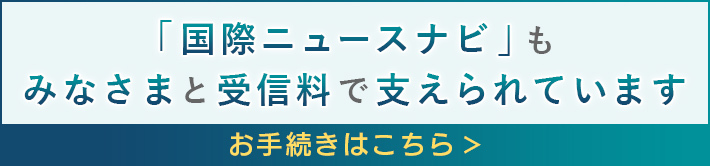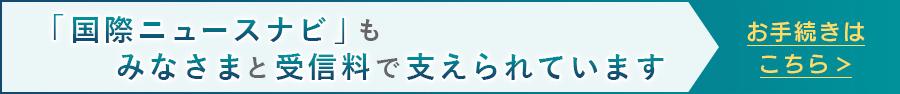「取材に応じるけど、先に荷物を置いてこさせて」
やっと取材に応じてくれる人を見つけたと胸をなで下ろしたのもつかの間…。
その人が戻ってくることはありませんでした。
初めての国連会議の取材。それは“想定外”の連続でした。
(国際部記者 能智春花)
向かったのは、ニューヨーク
これまで長崎放送局などで原爆の取材をしてきたことから、国際部に異動してからも、世界の核軍縮について取材してきた私。

8月の約1か月、ある会議を取材する機会をもらうことになりました。
その会議は「NPT再検討会議」。国連の会議の1つで、ニューヨークにある国連本部で開かれます。
初めて取材する国連会議。やや緊張しながらも、ニューヨークに向かいました。
そもそもNPT再検討会議って?
そもそもNPT再検討会議ってどんな会議なのか。その前に、まずNPTについての説明が必要です。
NPTは、Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsの頭文字をとったもので、日本語では「核拡散防止条約」と呼ばれ、1970年に発効した条約です。
条約は3つの柱からなっています。
1. 核不拡散
核兵器を保有する、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国を「核兵器国」と定める一方、核兵器を拡散させないために、そのほかの国には核兵器の開発や保有を禁止。
2. 核軍縮
条約の締約国に対して、核軍縮交渉を義務づける。
※ちなみに締約国は、191の国と地域で、国連に加盟する国と地域の数とほぼ同じです。非締約国は、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンです。北朝鮮は一方的に脱退を宣言したものの、認められていません。
3. 原子力の平和的利用
原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定。
そして、NPT再検討会議は、締約国の代表者たちが参加して5年に1度開かれる会議で、条約の履行状況を確認し、世界の核軍縮の方向性を議論します。
10回目となる今回の会議は、2020年に開かれる予定でしたが、新型コロナの影響で延期され、2022年、7年ぶりに開かれることになりました。
同時通訳は6つの言語?
前置きが長くなりましたが、会議の初日の8月1日、さっそく会場となっている国連の総会ホールに向かいました。会議が開幕するまで少し時間があったので、会場内を歩いてみることに。
議場の後方の上の階には、マスコミが会議の様子を撮影するためのメディアブースという小部屋があり、議場全体を見渡すことができました。代表団が次々と会場入りしているのが見えました。

ブースを出て少し歩くと、フランス語やスペイン語らしき声が聞こえてきました。
そこにあったのは通訳ブース。実は国連の公用語は、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語の6つがあります。期間中は同時通訳が行われますが、どの公用語で発言しても、ほかの5つの公用語に訳されているんです。
開幕直後から欧米とロシアが対立?
現地時間の午前10時すぎ、NPT再検討会議が開幕しました。
議長は、アルゼンチンのスラウビネン氏。元外交官だそうです。

議長の進行の元、「一般討論演説」が始まりました。それぞれの代表団が、問題提起をしたり、立場を表明したりするのですが、1週間ほど続きます。
前回7年前の会議、再検討会議は、中東に「非核化地帯」を設けるという案にアメリカなどが反対し最終文書を採択できずに決裂しました。
それもあってか、一般討論演説では多くの国から「今回こそ、最終文書を採択しなければならない」と、各国が歩み寄る必要性を訴える声が上がっていました。
ただ、今回はロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、欧米を中心に多くの国が、ウクライナに軍事侵攻し核兵器で威嚇を繰り返すロシアを非難していました。
「国の主権と独立に対する侵害を阻止するために、核兵器を持つ必要があると考える世界中の国々に、最悪のメッセージを送ることになった。強制や脅迫、恐喝に基づく核抑止を受け入れる余地はこの世界にはない」(アメリカ ブリンケン国務長官)
対するロシアは、強く反論。
「すべての主張に強く反論したい。ロシアの行動はすべて必要に応じたもので、『核による脅しだ』などという主張は言いがかりだ」(ロシア外務省不拡散・軍備管理局ビシネベツキー次長)
早くも雲行きが怪しい…。
最終文書はまとまるのだろうか、そんな一抹の不安を覚えながら、取材を続けることに。
交渉スタート
一般討論演説を終えると、2週目からは3つの分野に分かれて、最終的に全会一致での最終文書の採択を目指すことになります。
3つの分野とは、NPTの3つの柱と同じで、以下のようになっています。
・第1委員会「核保有国による核軍縮」
・第2委員会「核の非保有国への不拡散」
・第3委員会「核の平和利用」
これらの3つの委員会は複数の会議室で同時に進行します。それぞれの会合は午前と午後の部に分かれていて、約3時間ずつ開かれます。
2週目も、一般討論演説と同じように、各委員会では、ロシアを厳しく非難する欧米を中心とした国と、反発するロシアとの間で激しい応酬が続いていました。

特に、第2委員会と第3委員会で最大の懸案事項となっていたのが、ロシアが掌握するウクライナ南東部のザポリージャ原子力発電所でした。
原発やその周辺では断続的に砲撃が続いていて、原発の安全性への懸念が高まっていました。委員会では、ザポリージャ原発について最終文書にどのような文言を盛り込むか、激しい議論が行われていたのです。
本来議論すべき話ができていない?
NPT再検討会議には、代表団やマスコミのほかにも、数多くの国際NGOも会場に訪れていました。
ブースを設けて積極的に情報を発信したり、各国の外交官たちと今後の核の軍縮や不拡散について議論を交わすサイドイベントを開催したりしています。
そのサイドイベントに顔を出していると、参加者を通じて1人の女性と知り合いになりました。
国際NGOのアリソン・ピットラックさんです。

彼女は、世界の核軍縮について10年以上研究していて、今回も初日からNPT再検討会議に立ち会っているといいます。
今回の会議では、ウクライナ情勢によって議論の軸が変わり、「本来議論すべき話」ができていないと懸念を示していました。
「ウクライナ情勢がすべての委員会の議論に影響を与えています。ザポリージャ原発などウクライナの状況が悪化しているので、それが議論にいっそうの緊迫感を与えているように感じます。一方で本来議論すべき『核のリスク軽減への道筋』や『核軍縮に向けたステップ』を示す方向に進んでいません」(ピットラックさん)
会議は2週間が過ぎても、先行きを見通すことができない状況が続いていました。
場外乱闘ならぬ場外交渉?
取材をしている最中、最終文書の文言を調整する交渉が、委員会の“場外”でも行われていることが分かる一場面に出会いました。
「この議場の外でも話し合う用意があります。予算の上限はありますが、議論が必要な方にはビールをごちそうします」
こう発言したのはアメリカの代表。

会議の折り返しあたりの16日に開かれたある委員会で、“場外交渉”を提案していたのです。
実際にアメリカ代表団がビールをふるまったのかは確認できませんでしたが、水面下での交渉も行って、最終文書のとりまとめを目指そうという意気込みを感じました。
何度も書き直される最終文書の草案
3週目に入ると、各委員会では、委員長から最終文書の草案が示され、とりまとめに向けた議論がスタート。
ザポリージャ原発で激しい議論が行われていた第2委員会をのぞいてみると、原発に関する文言をめぐり、修正が何度も繰り返されていました。
こちらは、委員長から最初に示された14日の草案です。
「原発とその周辺での軍事活動などに重大な懸念を示す。ウクライナ当局の管理下に戻すよう求める」
しかし、これについてウクライナやヨーロッパの国などからは、原発の深刻な状況を、詳細に盛り込むべきだという意見が出されました。
一方のロシアは「一部の国による一方的な主張が書き込まれており、到底容認することはできない」と、草案そのものに反対。
1週間後の21日。草案は次のように修正されていました。
「原発やその周辺でのロシアによる軍事活動に重大な懸念を示し、ロシアの管理からウクライナ当局の管理下に戻すよう求める」
これについてもロシアの代表は「断じて受け入れられない」と猛烈に反発。結局、第2委員会では合意を得られないまま、最終週の第4週を迎えることに。
突撃取材も、撃沈…
第3週を終え、各委員会の議論はすべて終わりました。
最終週は全体会合が毎日開かれ、最終文書の文言を調整する交渉が行われます。
ただ、全体会合は、ほぼすべての会合が非公開。どんな議論が交わされているのか、最終文書はどう修正されているのか、全く明らかにされません。
そこで、内部の状況を少しでも聞き出すため、参加している外交官たちに突撃取材を試みます。
会場を出入りする人たちに片っ端から声をかけ続けるも…。

応じてくれる人はほとんどいません。
メンタルは強い方だと自負する私ですが、正直、心が折れそうになりました。
そんな中、ある国の代表に声をかけると…。
「取材に応じるけど、先に荷物を置いてこさせて」
やっと取材に応じてもらえる!
胸をなで下ろし、その場で待機しますが、待てど暮らせど、その代表が戻ってくることはありませんでした。
迎えた最終日
ようやく迎えた最終日。
午後3時から、最後の全体会合が予定されていました。
しかし、予定時刻になっても、一向に始まる気配はありません。
そんな中現れたスラウビネン議長。「開始時間を遅らせる」そのひと言だけを残して、会場を去ってしまいました。
何時に開会するのかは、分からずじまい。多くの人が会場に残らざるをえませんでした。
4週間も交渉を続けて、最後の最後で、会合が始まらない。そんな状況に、それぞれの代表団は、さぞかしいらだっているのではと、会場に目を向けると…。
何やら、演壇の近くに立つ人がちらほら現れ、スマホで撮影してる?

議長が最後の調整を行っている間は、自分たちにできることはないからということなのか、記念撮影をしているのでした。
ギリギリの交渉を続けている中でも、心に余裕を持つことができる。
“タフネゴシエーター”というのは、こういうものなのか。国際会議のリアルを実感した瞬間でした。
議長、再登場
予定時刻を過ぎること4時間以上。
スラウビネン議長が、再び議長席に現れます。そして、次のように述べました。
「残念ながら、ただ1つの国が異議を唱えている」
最終文書が全会一致で合意されなかったことを明らかにしたのです。
大きな議場は静まりかえり、外交官たちは肩を落として無力感に襲われているように見えました。
続けて、ロシアの代表が、最終文書の修正案を受け入れられない理由を説明。

「文書は、各国の立場を反映し、バランスが取れていなければならないが、残念ながら、この文章はそうなっていない」
議長はこのあと記者会見を開き、最終文書のとりまとめに至らなかった経緯について、次のように説明しました。
・議長は、各国が歩み寄れるという見通しを持っていた
・ロシアの代表団は、ウクライナの原発に関する文言について、重要な変更をしなければ賛成できないという立場を示した
・ロシアも受け入れられるような表現を探って、全体会合の開始時刻をずらしてギリギリの交渉を行った
・結局ロシアを翻意させることはできなかった
7年ぶりに開かれたNPT再検討会議。
たった1か国の反対で、全会一致による最終文書を採択できずに幕を閉じることになりました。
前代未聞のNPT
2度続けて最終文書が採択できなかったNPT再検討会議。
世界での核軍縮がさらに停滞するのは避けられず、NPTの元で本当に核軍縮が進むのか、NPT体制そのものへの信頼が揺らいでいると指摘する専門家もいます。
今回の会議に日本政府代表団のアドバイザーとして参加した、一橋大学の秋山信将教授は、次のように述べて危機感を示しました。

「今回の会議は、ある国家が別の国家に侵略行為を行い、戦争状態にあるという前代未聞の状況の中で開催されました。世界が“核軍拡”へと転じることが懸念される中、もはや失望している余裕はなく、NPTをいかに効果的に運用できるか考えなければなりません」
初めて取材したNPT再検討会議でしたが、その中で、核廃絶への道のりの険しさが、改めて浮き彫りになったことを痛感しました。同時に、国際社会は「核なき世界」の実現に向けて、対話を通じて、解決の合意点を見いだす努力を決してあきらめてはいけないということも、再認識することになりました。
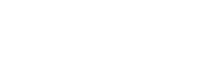





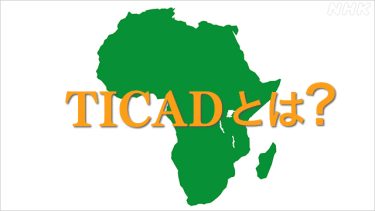





 国際ニュース
国際ニュース