2022年8月25日

「もし体調が急変したら、救急車を呼ぶ」
コロナに感染し自宅で療養する患者にとって「119番」は万一の時の心の支えだと思います。
しかし今、重症化して救急車を呼んでもなかなか搬送できない。そんな事態が相次いでいます。都内では高齢の患者が自宅から搬送できないまま死亡するケースも起き、現場の医師からは苦悩や、中には諦めの声も上がっています。
なぜこのような異常事態に?改善策は?
「第7波」の中、追い詰められる医療現場を取材しました。
ある男性の死
「僕らとしても力不足でした」
7月29日、都内の高齢夫婦の自宅。死亡が確認された83歳の男性を前に、主治医の田代和馬医師は静かに手を合わせました。
男性は末期の盲腸がんを患い、自宅で療養中でした。

「体調が悪化して、ちょっと様子がおかしい」
前日、妻からクリニックに連絡がありました。午後6時ごろに田代医師が訪問すると男性は意識がもうろうとした状態で、血液中の酸素の値、酸素飽和度も90%にまで低下していました。
新型コロナの感染が疑われ、その場で抗原検査したところ結果は「陽性」。
119番に電話して救急搬送を依頼します。
「消防庁です。火事ですか、救急ですか」
電話がつながるまでに1分か2分ほどかかりました。
「コロナウイルスで意識障害を伴う呼吸不全がみられます」
「救急車向かいますが、非常に救急要請が多いので到着まで1時間近くかかるかもしれないです」
「できるだけ早くお願いします」
このやり取りから20分ほどして救急隊が到着。
医師は病状などを伝えて引き継ぎ、別の患者の往診に向かいました。
「病院見つけられず申し訳ない」
3時間後の午後10時ごろ。
救急隊に確認すると、男性の搬送先はまだ決まっていませんでした。

「病院を100件以上あたっていますが搬送先が見つからない」(救急隊)
男性宅に戻った田代医師は搬送の結果を聞き、救急隊員に何度も頭を下げて礼を伝える妻を励ましながら、主治医として今後の治療方針を伝えました。
「今後どうなるかわからないけれど、僕らができるかぎりのことをします」
「病院を見つけられなくて申し訳ない」
そう伝えて救急隊は引き上げました。自宅で酸素投与を続けましたが、翌朝、男性の呼吸は止まりました。
午前9時すぎ、田代医師が死亡を確認。感染確認から半日ほどの出来事でした。
「入院できない原因 どこに」

田代和馬医師
「男性のがんは末期とはいえ、まだまだ体力には余力があり、病状は安定していました。適切なタイミングで入院すればよくなった可能性は十分あると思います。
残された時間を自分らしく過ごしたいと前向きな気持ちでいたのに、急にその時間を奪われてしまった。100%の医療を提供できず医療者として敗北感があり、本当に申し訳ない」
そのうえで田代医師は、都内の病床使用率がこの時期50%前後だったことを踏まえて、こうしたことが起きる状況に強く疑問を呈しました。
「東京都では50%ぐらい病床が空いているはずなのに、全く入院できない原因がどこにあるのか、現場は憤りを覚えています。入院すべき人が入院できないというのは医療が崩壊している状況で、いま一度入院のあり方を見直してほしい」
「病床に空き」=「入院できる」はずが…
男性の最期に向き合った田代医師の問いに、どう答えればいいのか。
私たちは8月、新型コロナの患者を受け入れる各地の医療機関を取材しました。その1つ、東京・新宿区にある国立国際医療研究センター病院です。

高度医療を提供する特定機能病院として、コロナ患者のうち主に「重症」「中等症」の患者を受け入れていて、8月に入ってからは確保している77病床のうち約50床が埋まる状態が続いています。60%を超える病床がふさがっていますが、数字上は20床ほどは空いていることになります。
しかし、取材を進めると「空いている病床がある」=「病床にゆとりがある」という状態ではまったくないことがわかってきました。
「第7波」で起きていること
実は、感染の「第7波」では「第6波」までにも増して、次のような現象が日々起きていたのです。
1、「病床が空いていてもなかなか受け入れられない」
どういうことなのか、杉山温人院長に聞きました。
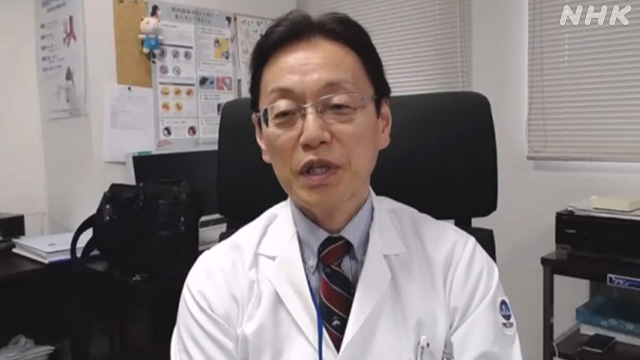
院長によりますと、背景にあるのは第7波の「ウイルスの感染力の強さ」だということです。
病院では7月以降、医師・看護師など医療従事者が感染したり濃厚接触者になったりして出勤できないケースが急増し、多い日で約120人にのぼったということです。
コロナ患者の治療には通常の1.5倍から2倍ほどの人手がかかりますが、出勤できないスタッフが続出したことで人手が確保できず、空いている病床はあっても、医療従事者が足りないためにすべてを稼働させられない事態が起きているということです。
もうひとつ、院長が指摘するのが
2、「いったん病床がふさがるとなかなか空かない」
病院では第7波に入ってからの受け入れ患者の3分の2は65歳以上の高齢者で、年齢の中央値は80歳を超えています。
多くは「中等症」の患者で、コロナによる肺炎で人工呼吸器が必要となるなど「重症」と診断される患者はほとんど出ていないということです。

高度医療を提供する医療機関に、なぜ重症度が高くない高齢患者が多く入院しているのか。
院長によりますと、患者の中にはコロナ感染をきっかけに発熱や脱水症状が起き、持病が悪化して入院が必要となったケースが多いということです。
高齢者は若い人に比べてどうしても体調が回復するまでの時間が長くかかり、入院期間も長くなる傾向があるため、結果として病床がなかなか空かない事態が起きてしまうということです。
こうした状況を踏まえて杉山院長は、重症度が高く緊急の治療を必要としている救急患者を確実に受け入れるための仕組み作りが必要だと指摘しています。
杉山温人院長
「それぞれの医療機関には役割があり、うちとしては急性期を診て、症状が良くなった段階で次の医療機関に移ってもらわないと現場は回りません。コロナによる肺炎で重症と診断されるケースがほとんどなくなってきている中で、コロナ患者のためにベッドをすべて開放してしまえば、脳梗塞や心筋梗塞といった本当の意味で緊急性の高い救急患者を受け入れられなくなってしまいます。
コロナだけを特別扱いせず他の病気と同じような視点で見たうえで、より重症度の高い患者を受け入れるために、その優先度を決める『トリアージ』を行う仕組みが必要だと思います」
ほかの病気・けがの患者が感染すると…
別の医療機関を取材すると、さらにほかの課題も浮かび上がってきました。
千葉県成田市にある国際医療福祉大学成田病院です。

取材したのはお盆の期間中でした。
各地の医療機関が休診する中で、救急外来では患者の受け入れ依頼が連日相次いでいて、その日も朝の時点で受け入れ可能だった病床が午前中のうちに埋まり、その後は断らざるをえない状況になっていました。
病院によりますと、感染拡大後に目立っているのは「病気やけがをした患者がコロナに感染していると搬送先がなかなか見つからない」という問題だといいます。
記事冒頭の、自宅から搬送されずに亡くなった83歳の男性も(※「千葉県」と「都内」と地域は離れていて、この病院と直接の関係はありませんが)がんの患者がコロナに感染したケースでした。
なぜこうしたケースでは、病床の確保が難しいのか。
病院によりますと、コロナ自体は軽症だとしても一般病床ではなくコロナ専用の病床で受け入れる必要があるため、感染者が増えてコロナ病床がひっ迫していると受け入れられる病床が限られてしまうためだということです。
「このまま搬送先が無かったら」
8月11日に搬送されてきた高齢の女性もそのケースの1人です。
女性はコロナに感染し自宅で療養中でしたが、転んで腰の骨を折り、救急車を呼んだということです。
20件以上の医療機関に断られたあと自宅から40キロ離れたこの病院に搬送されました。

女性は救急搬送や病床がひっ迫していることを聞いていたため「こういう時期なので救急車を呼んでもいいのかな」と一度はためらいましたが、限界が来て119番したといいます。
女性はちょうど空いていたコロナ病床に受け入れられました。
患者の女性
「救急隊が搬送先を探してくれましたが、症状よりもまず『コロナ陽性』と伝えると断られてしまう状況でした。このまま搬送先がなかったらどうしようと不安でした」
病院で救急科部長を務める志賀隆主任教授は、今の状況は通常の医療からはほど遠い異常事態だと指摘しています。

救急科部長 志賀隆 主任教授
「健康に過ごしている間は気がつかないが、ひとたび自分がけがや病気をしてしまうと受け入れてくれる病院が見つかりにくく、突然厳しい状況に直面するという状態です。もはや普通の医療はできなくなっている状態で、医療の現場はすでに限界を超えている」
そのうえで、今の率直な思いを口にしました。
「受け入れるのも大変だし、待っている患者さんを断るのも猛烈につらいので、どっちもつらいです」
搬送する救急隊は

救急隊も、限界に近づいています。
総務省消防庁によりますと8月21日までの1週間に、救急患者の受け入れ先がすぐに決まらない「搬送が困難な事例」は全国で6107件。「第6波」で最多となったことし2月の6064件より多く、コロナ感染拡大前の6倍余りにのぼっています。
東京消防庁の担当者は8月3日、次のように話しています。

救急管理課 小笠原英昭係長
「搬送先の医療機関がなかなか決まらず、救急隊は消防署に戻ることができないまま、連続して出動している状態だ。酷暑の中で全身に防護服を着て対応にあたっているが、感染リスクとも隣り合わせで、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積して非常に厳しい状況にある」
そのうえで、救急車を呼ぶ際には症状などに応じて判断してほしいとしています。
「通報が集中すると電話につながりにくくなったり、遠くから救急車を向かわせることになるため必要な救護が遅れたりしてしまう。119番するか迷った際には都の発熱相談センターなどの利用も検討してほしい」
「処方箋」はどこに
「第7波」の大波の中、医療の現場はすでに限界点を超えてしまっているようにも見えます。
厚生労働省は酸素投与が必要ない入院患者は自宅や宿泊施設での療養への切り替えや、リハビリを行う病院への転院などを進めるよう自治体に通知していますが、病床使用率の高止まりは続いています。
地域の医療体制を維持しながら、新型コロナへの対策も進めていくための「処方箋」はどこにあるのでしょうか。

私たちは「感染症対策」と「地域医療政策」の両方に詳しい、沖縄県立中部病院の高山義浩医師に話を聞くことにしました。
高山医師は現状について「第7波」でかつてない数の患者が医療を必要とする中で、医療機関どうしの連携の流れが滞ったり、病床を十分に運用できない問題に直面したりしているとしています。
当面の対策として高山医師が挙げるのは、沖縄県が取り組む「入院待機ステーション」の運用など、容体が回復した患者の受け皿を増やす取り組みです。
「目の前の対策」は

「入院待機ステーション」は本来、入院調整中の感染者に一時待機してもらうために整備されたもので、酸素投与など応急的な対応が行われています。
重症度の高い患者に病床を提供するため、沖縄県は容体が落ち着いた入院患者の療養場所としても運用しています。
そのうえで今後、中長期的には「必ずしも入院しなくてもいい患者」を医療機関以外で支える仕組みを強化していく必要があると指摘しています。
高山義浩医師
「必ずしも入院しなくてもいい患者さんを地域で支える『地域包括ケア』の仕組みをより強化することで病床が温存でき、本当に入院が必要な患者さんたちがすみやかに入院できる環境を作っていくことができます」
地域医療を「カスタマイズし直す」
高山医師は今回浮かび上がった課題は、実は今に始まったことではないと言います。
「たとえばインフルエンザが流行しただけでも満床状態になって入院が必要な患者さんが入院できないとか、救急でお断りが増えてしまうということが実はコロナ以前にも起きていたんですね。
ですから、今回コロナで特別な対応をするというだけではなく、コロナをきっかけに地域医療全体を改めてカスタマイズし直すという感覚が必要だと思います」
今後高齢化がさらに進み、病気や障害を抱える高齢者が安心して暮らし続けられる地域づくりを進めていくために、鍵を握る要素のひとつは、医療従事者の地域医療への積極的・継続的な関わりが可能になるかどうかです。
「たとえば今、各地の高齢者施設ではコロナ患者の施設内療養を多くの介護現場の方々が支えています。状態が不安定な高齢者に対して地域の開業医の先生方が訪問診療や往診で関わって施設療養を支援する。それだけで実は入院しなくても済む患者さんって結構いらっしゃるんですよ。
入院することは確かに理想なんですけれども、患者側からすると入院して隔離されてしまうとむしろ体の動きが悪くなってしまったり、ベッドで寝たきりになってしまうこともあります。施設で短期間で回復するんであれば、あえて入院せずとどまっていただくほうがいいこともあります。それをやるためには地域の診療所の医師が、施設での療養を支えることが必要になっているわけですよね」
関心を持つこと 目を向け続けること
都内で搬送できないまま自宅で亡くなった男性のケースをきっかけに「なぜ入院できないのか」と、その対策を取材してきました。
しかし振り返ってみると、私たちは「コロナで病床ひっ迫」の事態に直面するまで「自分が住む地域の医療・介護の体制」に今ほどの関心を持つことができていたでしょうか。
もしコロナ前から今ほどの関心を持ち、対策を打つことができていたら、今のような「限界」に直面することは避けられたはず、とも感じます。
さらに、新たな疑問も生まれてきました。
どうして国は「第6波」までの経験をもとに現在のような事態を想定して手を打つことができなかったのか、という根本的な疑問です。
「第7波」はまだまだ感染者が多い状況が続いていますが、「今」「これから」の地域の医療体制はどうあるべきなのか。そのためには何が必要で、国や自治体は必要な手をきちんと打っているのか。
私たち自身が積極的に関心を持って目を向け続けていくことが、最低限必要なことです。引き続き、取材を続けていきます。