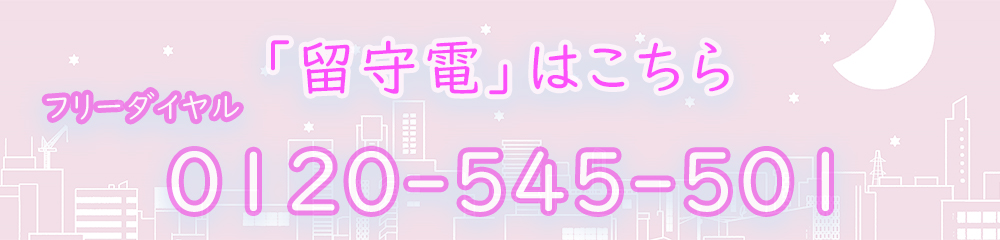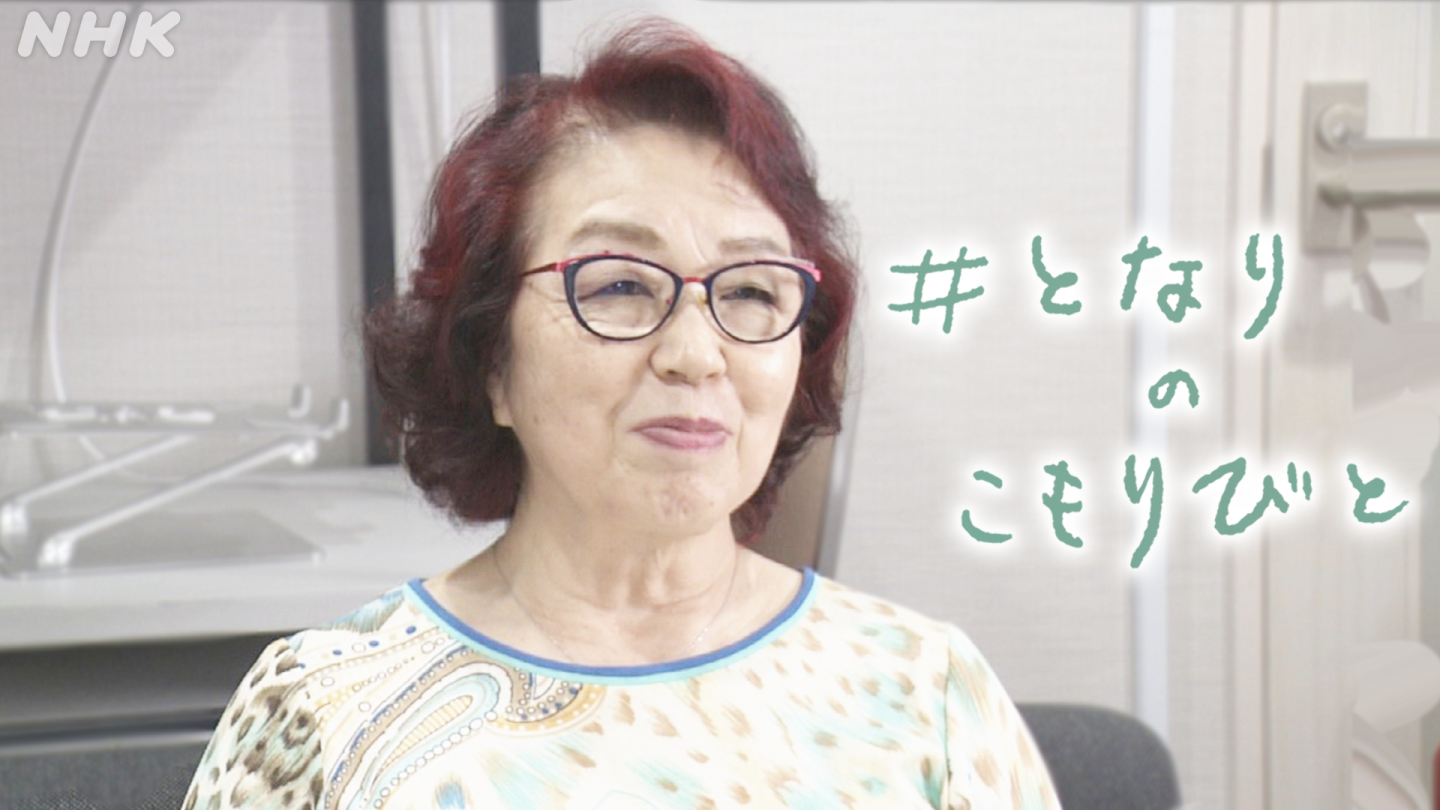
「“水くさい”と言われたら成功です」親と離れ自分の幸せをまん中にすえる方法
記事「“私は母のゴミ箱だった”ひきこもり母娘40年…たどりついた答え」や、あさイチ(「“毒親”と離れてわかったこと」(2023年9月28日放送)番組アンケートには、親との関係に苦しむ人たちからの声が多く寄せられました。その数は400件以上。見えてきたのは、親との適切な距離の取り方に悩み、自らの人生を取り戻そうともがく娘たちの姿でした。どうすればこうした苦しみから解放されることができるのでしょうか。
「“気づけない”娘たち」
意外にも多かったのは、「苦しさの原因が母親との関係にあると、気づいていなかった」という体験談でした。
私は今年の4月まで母親との関係は良好だと思っていました。でも私の生きづらさ、若い頃の摂食障害、色々な依存症はどうしてなんだろうと考えれば考えるほど両親、母親につながって…。よくよく考えてみると今まで本当の気持ちをぶつけたことはなかったのかもしれません。
大人になり、自分の生きづらさ、理由不明の罪悪感の根源をたどったとき、初めて“毒親”という概念を知り、母の様々な言動がピッタリ当てはまり、やっと「私が悪いわけではないんだ」と答えをえられました。
話を聞いたのは、親子関係に関わるカウンセリングを長年行っている、公認心理師の信田さよ子さんです。適切な関わり方に変えていくためには、まずは母から“されてきたこと”を自覚することが大切だと言います。
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
苦しさを「自分のせいだ」と考えている方はとても多くいます。お母さんとの関係が密接だと、「母が悪いはずがない」みたいなメッセージを毎日受けとっていたりして、洗脳状態のようになっていてなかなか気づけないっていうのもあります。さらに、本当はどこか気がついていても、母に原因があると考えてしまったら、それまで信じてきたものが全部壊れるような恐怖心もあると思います。
たとえばですが、洋服が選べない。「私は本当はどんな趣味なのだろう」とか、「私に似合う服って何だろう」とか一切わからないって人は多いですね。母親の好み以外の服を着ていると、母親から存在をけなされたりするのです。「似合わないよ、その変な服」とかね。そうなるとやっぱり母親が選んだ服がいいのかなって思って、そのまま行く人もいると思います。
まずは気づくことが第一歩だと思います。それは本人にとっては世界がひっくり返るような気づきで、苦しさが伴います。しかし、それはとても大切な気づきです。そうすることで初めて、親とどう付き合っていくか、もしくは親と距離を置くとか、ある程度は自分で選べるわけですから。
一方で、母との関係に気づいたとしても、距離を置くことに対して、罪悪感を抱いてしまうという声も寄せられました。
家を出る=家族を捨てるという思いから罪悪感を抱き、家族と離れたいと思うだけでも大罪のように感じてしまいます。
父が亡くなって20年。一人暮らしで寂しい気持ちもわかりますが、近づきすぎると苦しいので、一定の距離は取っています。そうすると「優しくないのでは?」「自分が悪いのでは?」という気持ちがどうしても抜けないのです。
「自分の幸せを真ん中にすえる」
距離を置くことへの自責の念に苦しむ人たちに、あえてきちんと伝えたいことがあると言います。
それは「自分の幸せを真ん中にすえてほしい」ということです。
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
苦しんでいる方の中には、自分の幸せよりも先にまず「母が幸せになんなきゃいけない」と、母親の幸せを優先する人が多いです。「母のために自分は生きている」みたいな意識ですよね。
親子関係に悩む子どもに「あなたの幸せを真ん中においてください」っていう話をするとびっくりしちゃう人が多いです。
「えっ?私の幸せですか?」って。「えっ?何だろう。私の幸せって。わかんない」っていうことにショックを受ける。そういう方たちは、母の幸せの中に自分の幸せも入っているんでしょうね。

それをきちんと分けて、自分を中心に置くっていうことをしないといけない。そうすることで、自由度も増すし、何よりも母を通して生きてきた自分から、自分を生きることに転換するわけですから、時には戸惑いもあるだろうし、大変なこともあるだろうけど、喜びもあります。だから、距離って本当に大事なんですよね。よく「自立しろ」とか言うけど、自立ってどういうことかって言ったらやっぱり距離をとって自分のことをやるってことだと思います。
「親孝行」という言葉の呪縛
こうした罪悪感を抱いてしまう背景には、「親孝行」という言葉に込められた、社会的な規範があると言います。
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
本来、親孝行っていうのは内発的なものですよね。正常な親子関係であれば、言われなくても、親を大事にしたいと思うはずなんです。
でも日本でいう親孝行っていうのは規律として存在していて、「親の言うことを聞くこと」「思い通りになること」という意味で使われていると思います。さらには、子どもが良い学校に入学してステータスを得ることによって、親自身のステータスが上がることを指すことすらあります。

だから、大人になってから親と距離を取ろうとするという行為は、社会的な規範に反することでもあるし、裏切ることでもあると思わされているので、子どもにとってはただただ苦しい。「母からこんなによくしてもらったのに、恨んだりしてひどい娘だわ」と思ってまた自分を責めると、それこそ本当にうつになったり、「自分は人間じゃない」みたいに思ってしまうそうです。親孝行してない自分は人間としておかしいんじゃないかみたいなことが思わされている。
だから、距離をとるときには「こんなふうにしていいのか」、「やっぱり私の一方的なわがままじゃないのか」という自責感の苦しみは必ず発生します。でも、これをなくそうと思ってはいけない。適切な距離を作るための「必要経費」だと思うしかないと思います。
母親を“メタ認知”してもう一歩前へ
親との適切な距離を置けるようになった後に、さらに気持ちを自由にするために効果的なのが「母親研究」という手法だと言います。
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
カウンセリングでは、「どうしてあの母親はああいう人になったのだろうか」ということを娘である自分が研究して、グループで発表して、みんなで共有するということをやっています。
その効果は、どう言ったらいいのかな。ここに変な昆虫がいますと。「うわー、怖い」ってなるでしょ。でもこの昆虫の生態を知り、どうやって卵からこうなったかっていうことを調べて、ある意味ではメタ認知(=自分の認知している内容を客観的に認知し直すこと)すると“怖い”にとどまらずに“理解”ができる。
つまり、親を俯瞰(ふかん)してみられるようになるってことですね。そうすると不思議なことに、何かあるごとに親の言葉でショックを受けたりする度合いが本当に減るのです。
たとえば、「母はおじいちゃんから虐待されているとかいろんなことがあって、結婚したらお父さんが女を作ったりして本当に苦労して、私しかいなかったんだな」ってことがわかるわけですよ。「ここでこうやっていたらもっと違ったのに」といったように、客観的な意見を持てるようになる。
母を歴史の文脈の1つで捉えることもできるし、ある種、“一家の中の母親という人間”をメタ的に見られるし、あとは自分と同じ女性としても見られるし、いろんな効果がありますよね。
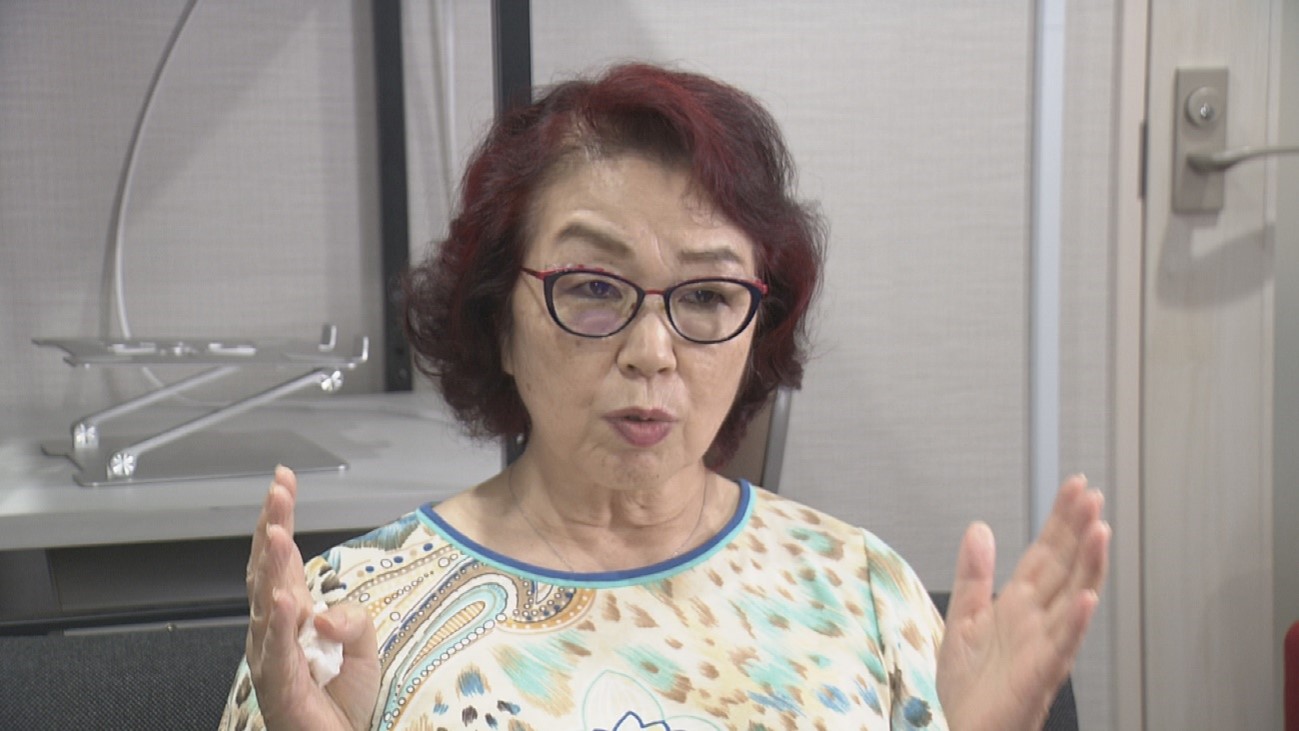
この「母親研究」は、母親本人に聞く必要はありません。たとえば、役所に行って、戸籍謄本をとって、お母さんの実家に行って、まだ生きているおじさんに会って話を聞いたりする・・・ということもできますが、実はみなさん小さい頃からいっぱい聞かされていますね。愚痴としてね。
「昔はこうだったのにこうなって、お父さんと出会ってだまされて結婚して、それであなたができちゃったから結婚したのよ」みたいなことをずっと聞かされているんです。だから周辺調査するまでもなく、すらすらでてくる人の方が多い。それを思い出すことにはまた苦しい感情が伴うけれど、文字にすることで客観視することができるので、文章にすることをおすすめしています。
許せなくても“親切”はできる
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
距離を置いてメタ認知が進めば、実際に会った時に親切にはできるようになります。道端を歩いていて、知らない人が転んだときに「手貸しましょうか」って言えるでしょ。あれと同じですよ。年老いた親が施設を探すときに一緒に探してあげるとか。母親と自分は別の人格だということを認めた上で、「他人行儀」で接することがポイントです。
もう一つが言葉づかいです。何か親がしてくれたら「ありがとう」と言う。「ちょっと私それできないんです」とかね。敬語を使うと、距離を保ちやすいです。そういう言い方をして親から「水臭い」と言われたら成功です。「水臭いって言われた。私、距離がとれているんだわ」って思った方がいいですね。
私はあえて「許す」「許さない」という言葉は使いません。なぜかと言うと、子どもは親を許したいに決まっているんですよ。許したほうが楽だからね。だけど、どうしても自分には納得いかないっていうのだったら、それはすごく大事なことだから、許す必要はないんです。
「許さなくても、親切はできる」ということを知ってもらいたいと思います。
苦しみの中にいるあなたへ
-
 公認心理師 信田さよ子さん
公認心理師 信田さよ子さん -
本来であれば親が気づいて変わってくれるのが一番で、子どもが努力するのっておかしいなと思います。そんな中でも、なんとかしたいと思って子ども側が行動に移すのは、自責感が伴うし、本当につらいことです。
だからこそ、自分の気づきを、「そりゃ当然ですよ」とか、「君の言うとおりだね」っていうふうに、同じように味方になってくれる人がいることが大切だと思います。今はSNSなどのネットのつながりもありますし、当事者の会やグループカウンセリングといった方法もあります。支えになってくれる人や場所をうまく見つけてほしいと思います。
あなたの声をお待ちしています
みんなでプラス「#となりのこもりびと」では、「この記事にコメントする」から、それぞれの記事にコメントが書けます。
記事へのコメントという形ではなく、私たちに体験談や思いを伝えたい方は、
「こちらから参加できます」から声をお寄せください。
「こうしたら生きやすくなった」という知恵、「こんなテーマを取材してほしい」といったアイデアだけでなく、あなたの暮らしの困りごとや楽しみなど、自由にお書きください。
あなたの声が、私たちを動かす力になります。どうぞよろしくお願いします。