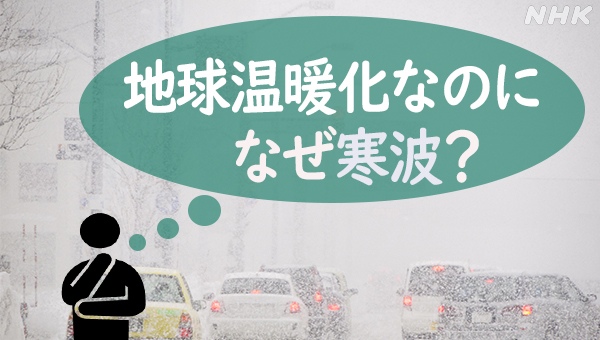注目の温泉地に学ぶ “温泉枯渇”の前にできること
温泉大国・日本。温泉は、私たちの体を癒やす存在として古くから親しまれてきました。
しかし、いま各地の温泉地で湯量や湯温が低下する、いわゆる“温泉の枯渇”が報告されています。温泉がいままでのようにくみ上げられなくなったことで、温泉旅館などが休廃業に追い込まれ、地域経済に大きな打撃を与えるケースもあります。
温泉の持続可能性が危ぶまれるなか、有限資源である温泉をいかに有効に使うかが求められています。そうした中、限りある温泉を利用し尽くす先進事例として国内外から注目を集める温泉地を取材しました。 (クローズアップ現代取材班)
全国各地から視察が来る注目の温泉地 福島・土湯温泉

福島市の西部、連なる火山に囲まれた温泉地「土湯温泉」。この温泉地に、全国各地から多くの人が視察に訪れています。
取材に訪れた日も、土湯温泉で行われている先進的な取り組みを自分たちの地域にも生かしたいという人たちが新潟県から視察に来ていました。私たちもその視察に同行し、取り組みを見せてもらうことにしました。
なぜ、この温泉地が注目されているのか。その背景には、日本に数ある温泉地が直面する問題があります。近年、各地で温泉の取れる量が減少したり、温度が低下するなどといった、いわゆる“温泉が枯渇する”という問題です。日本の文化として育まれてきた温泉の持続可能性が危ぶまれているというのです。
地熱発電所や新たな温泉施設の建設を目的に、地下にある資源量以上に温泉を掘削してしまうことがその原因のひとつにあげられています。
いまできる対策としては、くみ上げた温泉をいかに有効に使うことができるか。土湯温泉では取れた温泉を一つの目的だけで終わらせずに、何段階にもわたって地域の限られた資源を再利用しており、その取り組みが全国から注目されているといいます。
温泉として使う前に、まず温泉を使って発電
まず訪れたのは、土湯温泉から車で10分ほどの山中に建てられたある施設。この施設の中に土湯温泉の源泉のひとつがあります。

実は、この施設は「地熱発電所」。
土湯温泉では、もともと源泉から温泉街に直接流していた温泉を、旅館などに流す前に発電に利用できる仕組みを作りました。
これまで主流とされてきた、温泉を蒸気にさせて発電させる「フラッシュ式」では、温泉そのものの蒸気を使ってタービンを回すため、泉質や湯量などに影響を与えてしまうリスクがありました。
しかし、土湯温泉で使われている「バイナリー式」と呼ばれる発電方法では、温泉の熱を利用して、ペンタンやアンモニアのような水より沸点が低い液体を蒸気にしてタービンを回します。温泉は液体を温めるためだけに使われ、液体などに触れず、そのままパイプを伝って温泉街まで運ばれます。そのため、泉質が変わる心配もありません。

-
視察案内の担当者 佐久間富雄(さくま・とみお)さん
-
「発電するにあたって、土湯温泉では新たに井戸を掘っていません。発電のために新たに井戸を掘るとなると、温泉旅館の方々からいま使っているものに影響はないのかという懸念が出るかと思いますが、ここは元々温泉に使っていたお湯を発電に使うだけなので、発電に使った温泉は泉質も何も変わらずに、いままで通り使うことができるようになっています」

発電に使用した冷却水もそのまま捨てずに再利用
次に訪れたのは、発電所近くにある養殖場。ここでは発電の際に使用した冷却水を使って、エビの養殖が行われています。

発電所では効率よく発電するために、大量の冷却水が必要です。しかし、発電に使った水は20℃ぐらいに温まってしまうため、そのまま流してしまうと川の環境に影響を及ぼしてしまいます。
土湯温泉では、この温水をエビの養殖に利用しています。
養殖しているのは、東南アジア原産の「オニテナガエビ」。国内で養殖している事例は少なく、土湯温泉の新たな観光資源となっています。

-
新潟県から視察に訪れた人
-
「私たちの町でも温泉を利用した発電はしていますが、それだけで終わってしまっています。発電の先に、さらに観光資源を作り出しているというのは素晴らしいと思いました」
温泉を温泉だけで使うのではなく、発電に利用してから温泉として使う。また、発電に利用した冷却水も再利用し、新たな観光資源を生み出しています。
さらに、土湯温泉では無理なく持続的に使い続けられるように、湯量や圧力を毎日計測しています。温泉を何段階にもわたってあますことなく有効利用することで資源を守り、温泉という文化を次世代に伝えていくためです。
発電で得た収益は地域のために
2015年11月に地熱による発電が始まった土湯温泉。7年ほど経ったいま、約800世帯ほどの電気を発電しています。発電した電気は電力会社に売電していて、その売上げは1億円以上にも及びます。
その収益は、地域活性化のために使われています。例えば、温泉街の入り口にあるコミュニティカフェは、観光協会が移転して廃屋となっていたところを売電で得た収益で買い取って再生。いまでは、地域の人たちが集まる拠点となっています。

このカフェの一角では、発電に利用した水を使って養殖したオニテナガエビの釣り体験ができます。釣ったエビは、自分自身で串に刺して調理して食べることができ、観光で土湯温泉に訪れた人々が楽しめる観光拠点にもなっています。

さらに、売電による収益でバスの定期代を負担し、車の免許を持たない高齢者や福島市内に通学する学生たちに寄贈するサービスも行っています。定期代を負担することで交通機関の利用を促進するほか、バス会社にとっても安定した収入となるため、路線バスの廃線といった将来の不安を防ぐ効果もあるといいます。
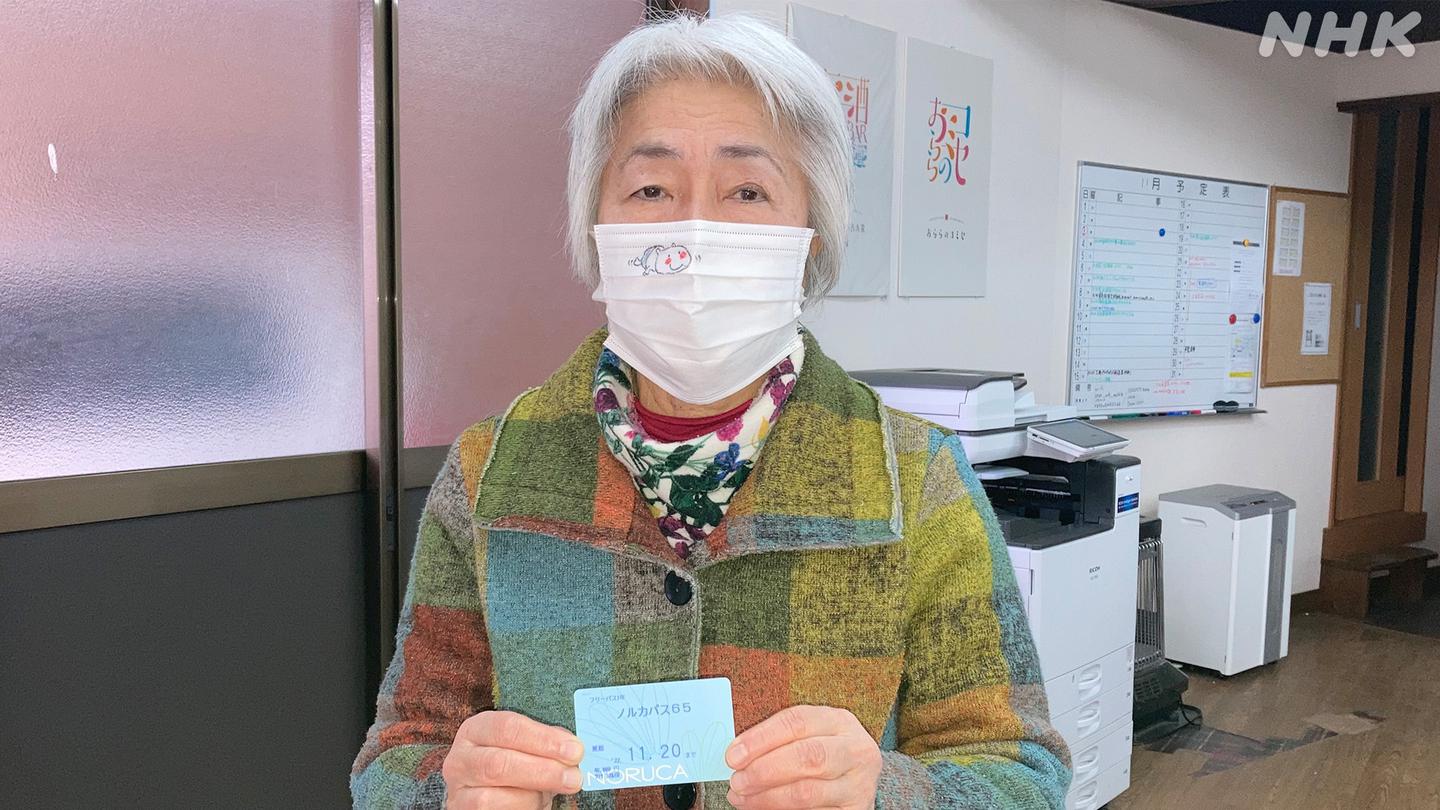
東日本大震災が地域の宝“温泉”を見直すきっかけに
こうした土湯温泉の事業を支えてきた、佐久間富雄(さくま・とみお)さんにお話を聞きました。佐久間さんたちが事業を始めるきっかけとなったのは、11年前の東日本大震災でした。

-
佐久間さん
-
「東日本大震災のとき、土湯温泉は3日間ぐらい停電状態になりました。地震が起きた当日、3月11日は金曜日だったので、旅館にも観光客の方がたくさんいて大変な思いをしました」
ようやく電気が復旧した後に、土湯温泉を襲ったのが原発事故による風評被害でした。時代と共にニーズが変わり、もともと観光客が減っていた土湯温泉に、さらなる追い打ちをかけた震災。観光客は震災前の3分の1ほどに激減し、地域の旅館も休廃業に追い込まれました。
-
佐久間さん
-
「当時の土湯温泉は物陰がないというか、人っ子ひとりいないというような状態でした。その時に地元の方が有志で集まって、このままでは風評被害が払拭したとしても10年後同じことが起きたんじゃないか。それがいまになっただけだって」
この機会に街づくりを見直そうと立ち上がり、まず乗り出したのが地域の宝である温泉を利用した発電事業。震災時の経験から、自分たちの電気を自分たちでまかないたいという思いから始まりました。
佐久間さんたちがこだわったのが、発電が温泉に悪影響を与えないこと。当時一般的だった「フラッシュ式」の発電方式では、新たな源泉を掘る必要があり、温泉の湯量などに影響を与える懸念がありました。そこで、当時まだ日本では数件しか導入されていなかった「バイナリー式」の発電所の導入に踏み切ることにしました。この仕組みであれば、これまで利用していた温泉で発電できるため、環境の影響が少なくてすむからです。
その後、温泉と発電が両立した持続可能な温泉地の取り組みが評判になり、2019年には震災前の8割ほどに観光客が回復。地域の宝である温泉の魅力を今後も伝えていくためにも、訪れた人々の心に残るような地域づくりを続けていきたいと話してくれました。
-
佐久間さん
-
「温泉を活用した発電やエビ養殖で地域を知ってもらう。そして、ここを訪れた方々に土湯温泉の魅力を伝える。温泉という地域の資源を中心に循環しながら、今後も町を盛り上げていければと思います。温泉がなければ町はなかったかもしれません。温泉は、地域の財産です」
取材を終えて 限りある資源と文化を両立させるには
地域の資源である温泉を発電、観光、さらには地域活性化と、あますことなく有効利用している土湯温泉。各地で“温泉の枯渇”が危惧されている中、地域の人たちが立ち上がって地域の財産である温泉を守るべく前向きな取り組みが進められていました。こうした取り組みが広がってほしいと感じました。
クローズアップ現代「ニッポンの温泉に異変!? 湯の“枯渇”を防ぐには」
2022年11月29日放送 ※12月6日まで見逃し配信
各地で増え続ける日帰り温泉入浴施設。今や7800施設に上る一方、各地の温泉では、湯量の減少やお湯の温度の低下といった“異変”が報告されている。地下1000mから温泉をくみ上げてきた青森の入浴施設では十分な湯量が得られない状況に陥り、廃業を決断。さらに大分県別府市では、市内の温泉を調査したところ、広い範囲で湯温の低下が起きる可能性も明らかに。わき出る温泉を使いすぎず上手に利用するための策に迫る。