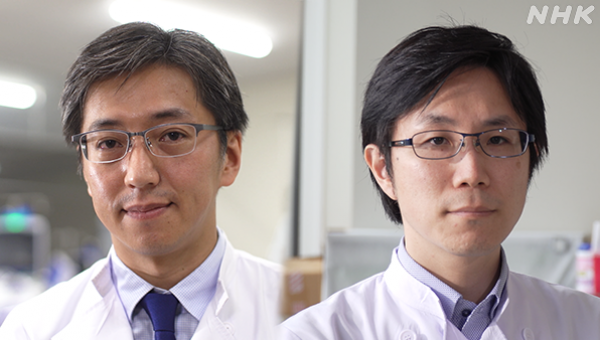その“医療健康本”、科学的根拠は? 読む前に6つのポイントをチェック!
気になる症状があったり治療法を知りたくなったりしたとき、インターネットだけでなく、「本」で情報を探す人も少なくありません。
「ネットより本が信頼できそう」という声が聞かれる一方、取材をすると、本の中にも科学的根拠が不確かな情報が潜んでいることが分かってきました。
命や健康に関わる医療情報を扱った本を手に取るとき、どうすれば信頼できるものを選び取れるのか。医師や司書、元出版社編集長らに聞いた6つのポイントをまとめました。
【関連番組】
フェイク・バスターズ「“出版の自由”と医療情報」
8月5日(金)夜10時放送(総合テレビ)

①“標準治療は最良の治療法”
医療に関する本の中には、「○○を食べれば治る」「この最新治療を行えば・・・」など、一見、希望を感じられるような言葉が並んでいることがあります。

しかし、20代のころに乳がんを経験した元民放テレビ局の記者、鈴木美穂さんは、治療中に自身も買い求めたこうした本には注意してほしいと話します。
-
 鈴木美穂さん 認定NPO共同代表
鈴木美穂さん 認定NPO共同代表 -
「『これさえあれば絶対に治る』『奇跡が起きる』っていうふうに言われると、何が自分にとって適切なのか正しいのか、全然判断できない状況になって、後から振り返って、当時自分が買っていた本を見て、本当にびっくりするほど信じられるものがなかったんです。
特定の治療法についてお勧めしている本は、いったん怪しいと思ったほうがいいと思います。また『切らずに治る』とか『抗がん剤をしなくて済む』とか“標準治療”を真っ向から否定するものも、一回疑ってかかって間違いはないかなと思います」
「標準治療」と聞くと、「並」の治療のように感じ、もっと他にいい治療があるのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、この標準治療について、国立がん研究センターのホームページにはこのように記載されています。
標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療。
医療において、「最先端の治療」が最も優れているとは限りません。
最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され推奨されれば、その治療が新たな「標準治療」となります
(国立がん研究センター がん情報サービス用語集「標準治療」より)
医療に関しては、たくさんお金を払えばいい治療を受けられるというものではありません。治療費が高くなることが多い「最新治療」や「最先端治療」は、あくまでまだ“検証段階”のもの。日本では、検証がされて最良の治療法と認められたものを「標準治療」と呼び、保険が適用され、医療機関で比較的安価に治療を受けることができるようになっていることを覚えておきましょう。
② “個人の意見に要注意”
医師が書いた本だからといって、必ずしも正しいことが書かれているとは限りません。

日々がんなどの治療に当たる外科医で、SNSで分かりやすい情報発信を続ける山本健人医師は、医療に関する情報を見極める際に、「エビデンスピラミッド」というものを頭に置いておくといいと指摘します。
-
「エビデンスピラミッド」とは
-
その研究や治療法が科学的にどれだけ信頼できるかの度合いを示した図です。難しい言葉が並んでいますが、上にいくほど信頼度が高くなり、下にいくと信頼度が低いということを示しています。特に注目すべきは一番下。具体的なデータに基づかない意見は、医師など専門家の言葉でも信頼度が低いとされています。

-
 山本健人さん 医師 "外科医けいゆう"
山本健人さん 医師 "外科医けいゆう" -
「患者さんの数が多い一般的な病気に関しては、このピラミッドの上のほうにあるものが『標準治療』だと思ってもらっていいです。逆に、例えば『私はたくさん経験があって、こうに違いない』と専門家が言ったとしても、専門家の個人的意見であれば、それほど信頼性の高いものではないということを知っておいていただきたいと思います。
それに加えて、お友達から『私のお母さんが、抗がん剤治療をやっていたんだけど全然効かなかったから、お勧めしないよ』と言われたとします。これは、正しいんじゃないかと思ってしまいがちなんですが、知人や著名人の個人的な意見はピラミッドにも入りません。友だちの言葉は、専門家ですらない、一個人の感想に過ぎないので信頼性が低いわけです」
③ “本は後ろから目を通す”
本の中には、健康への不安を過度にあおったり、今行っている治療への不信感をあおったりするような記述の後、特定のビジネスや商材に誘導するようなものがあります。

情報リテラシーに詳しい瀬尾傑さんは、本の特性から考えると、次のような方法で、ビジネスなどに誘導するような本は見極められると話します。
-
 瀬尾傑さん 元大手出版社 編集長
瀬尾傑さん 元大手出版社 編集長 -
「『本の後ろから見る』ということが大事だと思います。何かを売りつけるような本というのは、後ろを見ると、そこに商品の紹介が載っていたりするんです。そういう何かの勧誘になっていないかということから見ると、その本が信頼できるかどうかというところは、分かることがあると思います」
本の後ろには、他にも見るべきポイントがあります。
まず、本がいつ発行されたかです。医療は日々進歩しているため、ある程度時間が経過すると、情報が古くなっている可能性もあります。
そして、文献一覧など、引用元が丁寧に書かれているかという点です。引用されたもの自体に問題があったり、解釈が適切ではない使われ方をしたりしている場合もありますが、著者が自身の主張を「個人の意見」だけで話しているのか、根拠のあるデータに基づいて話そうとしているのかを見る上での一つの指標になります。

④“科学的根拠が不確かな本は図書館にも”
学校などで、「図書館の本を読んで勉強しましょう」と教えられた経験がある人もいると思います。しかし、「図書館には正しい本が並んでいる」という考え方には注意が必要だと、医療に関する図書を専門に扱う司書、小嶋智美さんは話します。

-
 小嶋智美さん 司書
小嶋智美さん 司書 -
「そう思ってしまうのはしかたが無いことですが、一概に図書館に置いてある本が、根拠がある信頼できる本であるとは言えないのが現状です。実際は図書も玉石混淆だったりするわけで、医師でない人が書いている医療本でも、医師が書いている医療本でも、「あれ?」って思うものもあったりするわけですよね。そういうものが図書館にも並んでいる。図書館としての姿勢というのは、あまねく本を置くということがベースとしてあると知っておいてほしいです」
図書館には「図書館の自由に関する宣言」と呼ばれるものがあり、図書館の最も重要な任務として「知る自由を持つ国民に資料と施設を提供すること」とされています。

つまり、医療に関する本の中で、科学的な根拠が不確かなものがあったとしても、人々の知る自由を守るという観点から、図書館が意図的にそれを排除することはしないことも知っておきましょう。
⑤“欲しい情報ばかり集めがち”
本を手に取るときの心構えとして、「自分は見たいもの、欲しい情報ばかりを集めようとしているかもしれない」と、立ち止まって考えることも重要だと言います。
-
 瀬尾傑さん 元大手出版社 編集長
瀬尾傑さん 元大手出版社 編集長 -
「特に健康とかになると、わらにもすがる思いで『こういう方法がないか』と情報を探していると、どうしてもその思いに合う本ばかりにひきつけられていく懸念があると思うんです。やっぱり人間は、見たい現実しか見ない。ある種の情報バイアスが働くってことも考えないといけないと思います」
さらに、欲しい情報を求めるあまり、特定の価値観の本にのめり込んでいく危険性があるとの指摘もあります。
-
 山本健人さん 医師 "外科医けいゆう"
山本健人さん 医師 "外科医けいゆう" -
「私自身も本が好きだからよく分かるんですが、自分の考えがその本の内容に置き換わっていくかのような本の持つ特殊性みたいなものは、実は結構怖い。誤った情報だったとしても、それが心を侵食していくように染み込んでいくことがあるんですよ。本を読んでいると、そういうことも起こりうるというのは知っておいたほうがいいと思います」
⑥ “本だけに頼らず専門家に相談を”
本は読み進めていくと、読者が筆者の主張と孤独に向き合うことが多くなる性質もあります。これは、自身の考えを整理したり、より深い考察を行ったりする読書の醍醐味である一方、誰にも相談しないまま、偏った認識に陥ってしまう危険性もあります。
本と上手につきあっていく上で、司書の小嶋さんと自身もがんを経験した鈴木さんは、「1人で悩まずに、相談してほしい」と言います。
-
 小嶋智美さん 司書
小嶋智美さん 司書 -
「図書館は本を借りる場所というだけではなく、情報を得たいと思っている方の相談に答える参考調査のサービス『レファレンスサービス』というものも行っています。本を1人で読んで解決するのではなく、困っていることを調べる方法や資料を提示したり、SOSが出せるような関連機関を提示したりすることもあります。本を借りたり返したりするだけではない図書館の機能も是非活用していただきたいと思っています」
-
 鈴木美穂 認定NPO共同代表
鈴木美穂 認定NPO共同代表 -
「なかなか病院では、お医者さんも忙しそうだしゆっくり話せないというときに、例えばがんについてであれば、全国に『がん診療連携拠点病院』が400か所以上あり、そこに『がん相談支援センター』が設置されています。そういったところに連絡をしたり、NPOに相談したりして、いったんその本が大丈夫かってことも含めて、心配に思うことをなんでも相談してみてもらえたらいいなと思います」
医療に関する本は、時に難しく、理解できないこともあります。また、とても分かりやすく書かれていて、「やっと理解できた、もう大丈夫」と思ったものが実際は間違っているということもあります。1人で本を読んで結論を急ぐのではなく、相談窓口や医師など専門家の意見を聞くことがとても大切だということを頭に置いておきましょう。
最後に、自身も本を出版し、批評誌の編集長を務める宇野常寛さんは、本を見極める上で覚えておいてほしいことがあると言います。

-
 宇野常寛さん 批評誌の編集長
宇野常寛さん 批評誌の編集長 -
「『これで解決する』って書いてある本ってあんまりいい本じゃない。答えが書いてある本ってもう既に分かりきっている問題とか、みんなが聞きたいことを想像して書くだけなんで、書くのが楽なんですよ。でも、ある程度複雑な問題で、解決方法が完璧に分かってることなんて基本ないんです。
本当にいい本には、分かりやすい答えは書いていなくて、新しい問いかけができています。『あとは、あなたが考えてください』って書いてある。そんな本のほうが、誠実な本なんですよ。だから、そのことを忘れないでほしいなってふうに、1人の物書きとして僕は思います」
【次に読むなら】真偽判断は極めて困難・・・ “AIフェイク”氾濫の時代を生きる術とは

※画像をクリック
【関連記事】真偽判断は極めて困難・・・ “AIフェイク”氾濫の時代を生きる術とは
簡単な指示を打ち込むだけで、文章・画像・動画・音声まで作ることができる『生成AI』。生活を便利にしてくれる一方、フェイク情報の作成や拡散にも使用されています。身の回りにフェイクが潜む“ウィズフェイク”の時代。その実態とすぐに実践できる対策を専門家に聞いた記事も合わせてご覧ください。