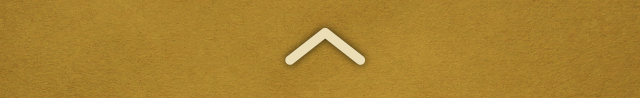先崎彰容
(せんざき・あきなか)
日本大学危機管理学部教授
1975年東京都生まれ。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院文学研究科日本思想史専攻博士課程単位取得修了。フランス社会科学高等研究院に留学。文学博士。日本大学危機管理学部教授。専攻は近代日本思想史・日本倫理思想史。主な著書に、『ナショナリズムの復権』(ちくま新書)、『違和感の正体』『バッシング論』(ともに新潮新書)、『未完の西郷隆盛── 日本人はなぜ論じ続けるのか』(新潮選書)、『維新と敗戦』(晶文社)など。現代語訳と解説に福澤諭吉『ビギナーズ日本の思想文明論之概略』(角川ソフィア文庫)などがある。
◯『共同幻想論』 ゲスト講師 先崎彰容
なぜいま、『共同幻想論』なのか
現代社会は、極めて「多忙な時代」になっています。理由の一つに、社会科学の用語で言う「社会的包摂性」がなくなってきていることが挙げられます。かつては、ご近所さんや親類縁者など、醬油の貸し借りから家庭内のもめごとの仲裁にいたるまで、私たちを見守る存在が周囲にいました。たとえ都会の団地であっても、盆踊り大会などで人々のつながりは保たれていました。また社会の中でセーフティ・ネットが機能して、弱者や貧困層に対して社会保障が安心感を与え、企業戦士は会社という所属先がなくならないことを自明の前提としていました。つまり地縁・血縁による柔らかな「社会的包摂性」を、国家・社会が補足する制度的な網が存在していました。
それらが一九九〇年代以降、どんどん縮小・崩壊し、殺伐とした個人間の競争社会になっているのが現代社会です。その結果、日本を含めた先進国では富裕層と貧困層の格差が拡大し、「二極化」が進み、社会的分断が進みました。社会的紐帯はバラバラに解体され、個人が砂粒のようになっています。社宅の盆踊りは廃れ、会社のイメージは終身雇用から非正規雇用へと反転しました。砂粒同士がグローバルな市場競争に丸裸のまま放りだされ、しのぎを削る競争社会こそ「多忙な時代」をなによりも象徴しています。
もう一つが、インターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及拡大による多忙です。好例はアメリカのトランプ政権誕生後、しばしば聞くようになった「民主主義はポピュリズムである」という言葉です。人々の対話と熟議をなにより重視する民主主義は、本来、時間性を特徴とします。時間をかけてでも他者の意見を尊重し、すり合わせ、最終的には多数決の原則にしたがうのが民主主義のルールです。
ところがSNSの普及は、民主主義の表情を変えてしまいました。
いつでも瞬時に、有権者の反応が分かってしまうため、民意は情緒的な情報に一喜一憂し、左右されやすくなっています。反応速度はみるみるあがり、情報にたえず影響を受ける時代。何かに反応し続けることを余儀なくされる現代は、まさしく「多忙な時代」そのものでしょう。
以上から分かるのは、高速度化する現代社会は、安定した人と人とのつながりが非常につくりにくいということです。インターネットの「炎上」という言葉が示すように、人々が一瞬燃えあがって話題にすることで、共通の話題ができたとしても、消費されすぐにポイ捨てされてしまう。一週間単位で事件や物事への関心や意見が変化し、バッシングと忘却をくり返す現代社会を、かつて私は「一億総週刊誌化」社会と呼んだことがあります(拙著『バッシング論』新潮新書ほか参照)。孤立感を深めたバラバラの人たちがつながる方法が、一時的で感情的なものになってしまっているのです。
またネット上には夥しい数の「論客」が出現し、他者に心ない批判や罵倒を浴びせかけるバッシングが猖獗をきわめている。自分は傷つかない場所から他者を糾弾し、小粒化した正義観が社会を覆う今、日本はとても窮屈で生きにくい社会になっていると思います。
今、私たちがなすべきことは何でしょうか。
自分の正義観を信じ込んで、善意の斧を振りあげることではないでしょう。こういう時こそ、「私たちはどのような人間関係をつくるべきか」、「自分は、独善に陥っているのではないか」といった問いに戻る必要があると思います。世間が騒がしい時代ほど、何か気の利いたことを言いたくなり、したくなる。そうした「多忙な時代」の忙しい心を脇に置き、もっと原理的・本質的な問いを立てる「勇気」が必要なのです。
「多忙な時代」に待ったをかける独自の迫力と深さをもった一冊の書物が、再び注目されています。一九六八年に出版された吉本隆明の『共同幻想論』です。
一九六八年とは、全共闘運動が盛んに行われていた時代です。「最後の政治の季節」とも呼ばれるように、若者たちが政治や国家という大きな問題に関心を抱いた、最後の時代とも言えるでしょう。二〇二〇年が没後五十年となる小説家・三島由紀夫が、東大の学生と討論している映像(一九六九年五月)を観たことがある人もいるかもしれません。
この本は、そんな時代の真っ只中に登場して、若者たちの心を一気にとらえました。当時学生だった人たちの多くが、『共同幻想論』がどんなに自分に影響を与えたか、あるいは吉本隆明という思想家にどれほどのめり込んだかを、後に回顧しています。ただ当時、たしかにこの本を読んだものの、自分は半分も理解していないのではないか、こうした不安を口にする年配の方々に出会います。一方で、吉本隆明に入門しようと手にとって、難解な内容に挫折した経験をもつ若い読者もいるものと思われます。
『共同幻想論』とは、いったいどんな本なのでしょうか。これからじっくりと探っていきますが、ごく簡単に言っておけば、私たちにとって「国家」とは、「共同体」とは、「法」とはなんなのか──それらと人との関係を問い質し、最終的には国家と個人の関係を考察した本だと言えるでしょう。とりわけ国家がどのようなプロセスで誕生したのかを、きわめて独自の手法で描きだそうとしました。
この著作の原点には、吉本自身の敗戦体験という切実な問題意識があります。そこから吉本は、人間へのどうしようもない興味を植えつけられ、取り憑かれたように思索を深めていきます。時代が課した宿命を全身で受けとめ、挑んでいく気迫が『共同幻想論』を書かせました。六〇年代後半は敗戦から二十年以上経っていた時期ですが、安保闘争やベトナム反戦運動など、まだまだ国家や政治に関わる重大な問題が社会を揺り動かしていました。
当時はマルクス主義による国家批判が大きな力をもっていましたが、吉本はまったく異なるアプローチから国家の本質に迫りました。ヨーロッパ思想からの借り物の方法によるのではなく、日本人によるきわめて独自な到達点を示すものであり、手探りで暗闇を進む手つきがそのまま作品に結晶したような印象があります。圧倒的な問題関心と、強い動機、そのリアリティがもたらす迫力が筆に乗りうつり、当時の若者たちを虜にしたに違いありません。
本書を一躍有名にしたのが、「個人幻想」「対幻想」「共同幻想」という独自のキーワードです。テキストと番組でもこの概念の解説を軸にしながら、個人と共同体との関係を問い直していきたいと考えています。
吉本隆明は詩人として出発しながら、同時に詩人論や作家論、具体的な状況に即した政治評論や文化評論、また今回読んでいくような原理的・哲学的な著作を数多く著した、戦後最大の知識人の一人です。『共同幻想論』のほかにも、年代順に挙げれば『高村光太郎』(一九五七)、『芸術的抵抗と挫折』(五九)、『擬制の終焉』(六二)、『言語にとって美とはなにか』(六五)、『心的現象論序説』(七一)、『最後の親鸞』(七六)、『マス・イメージ論』(八四)、『アフリカ的段階について』(九八)など、代表作は数多くあり、最近も全集が刊行されるなど、再評価の兆しが見られます。
一九九九年に大学を卒業した筆者は、吉本の直接の影響下にはありませんでした。ただ、今から四半世紀前、大学図書館で吉本の対談集を読んだことがきっかけで、彼の言葉を追いかけるようになりました。吉本が社会や文学作品を、己の感受性一つでつかみ取り、私にむかって差しだしているように思えたのです。たとえば「関係の絶対性」という難解でしられる概念も、彼の戦争体験にじっくりつき合うと、すっきりと理解できました。また彼の天皇や原発問題にかんする発言でも、他の論客にはない鋭利な分析に驚き、舌を巻きました。
とりわけ吉本への信頼を深めたのは、筆者が東日本大震災を直接被災したことに関わりがあります。千年に一度の大災害に直面し、躁鬱状態になっている日本人を前にして、筆者は吉本の言葉を生きていく縁として日々を過ごしました。「頑張ろう、福島!」の貼り紙がいたるところに貼られ、人々が一斉に自粛モードに入り、会津産の米が、買い手がつかないという理由で勤務先の食堂で無償提供されている状況とは、いったいなんなのか。異様に蠢く人々をどう理解したらよいのか──吉本隆明の声が、私の心に響き渡ったのです。
今回、「NHK100分de名著」で、彼の主著である『共同幻想論』を読むことによって、発刊当時の衝撃をしる読者にも再入門してもらうと同時に、戦争体験も一九六八年の熱気もしらない世代、SNSでの関係性が当然となった現代に生きる若い世代にも、吉本隆明の思想に入門してもらうことを願っています。
皆さんと一緒に『共同幻想論』の核心を読み解きながら、国家の起源と本質に迫っていこうではありませんか。また人間にとって「信じる」とはどういうことなのか、個人を突き動かす精神活動の不思議に、迫ってみようではありませんか。そしてあるべき人と人とのつながり方へのヒントを、見つけだそうではありませんか。