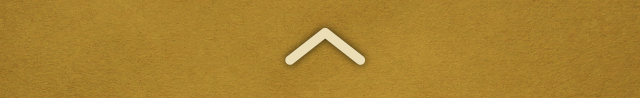和田忠彦
(わだ・ただひこ)
イタリア文学研究者、東京外国語大学名誉教授
1952年、長野市に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専攻はイタリア文学。京都大学文学部助手、名古屋芸術大学助教授、神戸外国語大学教授を経て東京外国語大学教授となり、2009年より同大学副学長を務めた。著書に『遠まわりして聴く』(書肆山田)、『ファシズム、そして』(水声社)、『声、意味ではなく』(平凡社)など。ウンベルト・エーコ、イタロ・カルヴィーノ、アントニオ・タブッキをはじめ、イタリア近現代文学の訳書多数。19世紀児童文学の翻訳にデ・アミーチス『クオーレ』(岩波文庫)、次いで『ピノッキオの冒険』(同、近刊予定)がある。
◯『ピノッキオの冒険』 ゲスト講師 和田忠彦
既存のイメージを覆す型破りな物語
十九世紀後半、中世以来の統治体であった都市国家の衰退に伴い、侵出してきた外国勢力の支配による公国や王国などから成っていたイタリアが、とにもかくにも国家統一を成し遂げました。イタリア王国の誕生です。はじめて「イタリア」が国の名前を表すことになったのです。統一完了からおよそ十年後の一八八一年、イタリアではじめてとなる子どものための週刊誌が創刊されます。「子ども新聞」というその雑誌の創刊号(一八八一年七月七日)から連載が始まったのが、ピノッキオの冒険』でした。作者はカルロ・コッローディ。本名はカルロ・ロレンツィーニ。文筆家として、批評や風刺、戯曲、さらには児童向けの教科書を精力的に執筆していた人物です。あらたに子ども向けの物語を書くにあたって、母方の祖父の故郷の村の名を名乗ることにしたのです。
『ピノッキオの冒険』は、「子ども新聞」での二年余りの連載を経て、一八八三年に単行本として出版されます。その道のりはしかし順調だったわけではなく、連載の途中で二度三度と、物語が中断するという出来事もありました。とりわけ一回目の中断は、実は中断ではなく物語の「終わり」でした。主人公ピノッキオが、みずから犯した過ちのゆえに、樫の木に首を括られて命を落とすという衝撃的な結末で、物語が終わってしまったのです。これは、単行本となった『ピノッキオの冒険』全三十六章のうちの第十五章にあたる部分で、いまのわたしたち読者からすれば、「え? ここで終わるの?」と思ってしまうくらい、なんとも唐突であっけない幕切れです。
幸い、連載は再開されてピノッキオは生き返り、物語はつづくことになりました。その背景にあったのは、主たる読者である子どもたちの声でした。樫の木に吊るされて命を落としたピノッキオはかわいそうだ、救ってあげて、という声が、多くの子どもたちによって直接出版社に届けられたのです。付き添ってきた親たちも、同様に連載の再開を望んだといいます。その結果として、いまわたしたちが読むことができる『ピノッキオの冒険』という作品は完成しました。このエピソードは、特に二十世紀以降の小説と読者のあり方(すなわち、読者の読書経験のなかではじめて小説は完成する、という文学批評の流れ)を考えたときに、まさに先駆的で象徴的な出来事だったと言えるでしょう。とりわけ、十九世紀フランスのアレクサンドル・デュマやウジェーヌ・シューの新聞連載大衆小説を支え、ときに物語の運びそのものまで変えることもあった読者たちのあり方を思い浮かべないわけにはいかないからです。読者の参加によってはじめて物語が完成する──そんな物語と読者の関係を、子どものための物語で体現したはじめての作家がコッローディであったと言えるかもしれません。
ピノッキオが首を括られて一度死んだという展開を聞いて、「わたしたちの知るピノッキオのかわいらしいイメージと違う」と感じた方は少なくないでしょう。『ピノッキオの冒険』には、実はほかにも大胆不敵なエピソードが満載で、ピノッキオのいたずらっ子ぶりはかわいいを超えて桁外れなところがあります。おまけに作者コッローディは、教科書執筆に熱心に取り組む勤勉さを持ちながら、賭け事が大好きでした。彼がギャンブル依存症だったことと『ピノッキオの冒険』の誕生には深い関係があるのですが、これについてはこのあと詳しくふれることになると思います。
とにかく、ピノッキオはおそらく世界でもっともよく知られた人形キャラクターでありながら、その物語全体を正確に知っている人は、実はきわめて少ないと言えるでしょう。最近の統計でも確認されているのですが、『ピノッキオの冒険』は、イタリアが生んだ文学作品のなかでもっとも多くの外国語に翻訳されている、世界有数のロングセラー作品です。それだけ世界で紹介されていながら、元の物語を知っている人は少ない。その理由は言うまでもなく、一九四〇年にウォルト・ディズニーがこの物語を下敷きにしてつくったアニメーション映画『ピノキオ』の絶大な影響にあります。この映画は原作に忠実なものではまったくなく、ウォルトが原作の残酷さや両義性を実に上手に取り除いて誰もが感動する冒険ファンタジー作品に仕上げたものでした。そして一九四〇年代以降は、元の物語を知らずにディズニー版のピノキオだけに触れて育つ子どもたちが、世界各国で、果ては本国イタリアでさえも、生まれつづけたのです。
今回は、ピノッキオの本当の物語はどんなものなのか、また、ディズニーの功罪があるとはいえ、これだけ世界に広まったピノッキオの物語の魅力とは何なのかを、その受容の歴史にも折々にふれながら、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
わたしと『ピノッキオの冒険』との出合いは、小学校一年生のときに遡ります。当時、わたしの家では講談社の「少年少女世界文学全集」を購読していて、そのなかの一巻に、『ピノッキオの冒険』と、同時代にイタリアで発表されて爆発的に売れた児童書『クオーレ』というふたつの作品が収められていたのです。『クオーレ』は、日本では「母をたずねて三千里」の物語が収録されている児童書として知られています。『クオーレ』と『ピノッキオ』はあまりにも対照的な物語でした。簡単に言ってしまえば、前者は「良い子」、後者は「悪童」の物語で、圧倒的に『ピノッキオ』のほうがおもしろかった。読んでいてワクワク、ハラハラしますし、ピノッキオがとる無鉄砲で破茶滅茶な行動は、もしかしたら自分も明日やってしまうかもしれないと思うほど、近しく感じたのです。
そうしてわたしは世界のいろいろな物語を子どものころに知り、長じてイタリア文学を研究・翻訳するようになりました。では、かつて子どもだった大人たちが、あるいは現代に生きるわたしたちが、『ピノッキオの冒険』をいま読む意義はどんなところにあるのでしょうか。
わたしたち人間は、子どもから大人へと成長し、良くも悪くも成熟していくという変化の過程を生きています。その変化と自分はどう付き合っていくのか。そんなことを考えたときに、答えをいちばん雄弁に語ってくれる物語が『ピノッキオの冒険』であるとわたしは考えています。ピノッキオという存在は、はじめは一本の「まるたん棒」でした。それがジェッペットという男の手に渡り、あやつり人形になっていくのですが、よく読むと、ピノッキオは人形になる前の棒っきれの段階から言葉を有しています。すなわち、自分の意思や個性を持っている。さらに言えば、ピノッキオという存在は、この世に生まれ落ち、幼少期、成熟期を経て死に向かうという、人間がたどるであろう一生のプロセスを最後まであらかじめ体現する存在として、物語に登場しているのです(元がまるたん棒ですから、そこには年輪が刻まれていることが象徴的かもしれません)。まるたん棒から人形へ、そして人間の男の子へ。ピノッキオはその変身譚のなかに、人生そのものを見せてくれていると言えます。
誕生から百四十年になろうとするあやつり人形の物語がいまもなお読み継がれていることに理由があるとすれば、それは「ピノッキオはわたしだ」と、読みながら、そして読み終えたときに、痛切に感じるからではないでしょうか。わたしたちそれぞれが自身のすがたを、過去にせよ、現在にせよ、未来にせよ、見出してしまう物語、それが『ピノッキオの冒険』最大の魅力なのかもしれません。
さてもう一つ、ピノッキオは、いまの感覚で言えばロボットになぞらえられる存在です。人形ですから生物ではなく、その一方で、あやつり人形とされながらも誰かに糸で操られているわけではなく、ワイヤレスで自律的に動き、考えることができる。現代における、テクノロジーが生んだ物体と人間との関係を考えるにあたって、何か類似的なものをそこに見ることができるかもしれません。
物語のタイトルは『ピノッキオの冒険』です。まるたん棒から生まれたピノッキオは、どんな人生の冒険をしたのか、読者のみなさんもいっしょに体験してみることにしましょう。