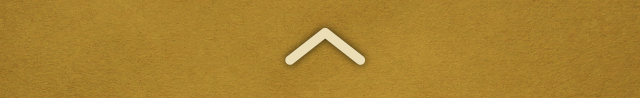瀬名秀明
(せな・ひであき)
作家
1968年静岡県生まれ。東北大学大学院薬学研究科博士課程修了。薬学博士。在学中の95年、小説『パラサイト・イヴ』(新潮文庫)で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。SF小説をはじめ、ロボット学や生命科学など科学に関する著作多数。小説作品に『BRAIN VALLEY』(新潮文庫、第19回日本SF大賞受賞)、『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団』(原作=藤子・F・不二雄、小学館)、『魔法を召し上がれ』(講談社)など、ノンフィクション作品に『ロボットとの付き合い方、おしえます。』(河出書房新社)、『科学の栞』(朝日新書)、『ミトコンドリアのちから』(共著、新潮文庫)などがある。最新作は、AI(人工知能)と人間の未来を描いた『ポロック生命体』(新潮社)。
◯『アーサー・C・クラーク スペシャル』 ゲスト講師 瀬名秀明
科学技術と物語の豊かな未来
イギリスの作家アーサー・C・クラークは、SFの代表的作家の一人です。本書では彼のよさが充分に発揮された四作品を厳選し、発表年代順に読んでゆくことで、作家クラークの特徴とSFの持つ大きな可能性を考えてゆきます。
クラークは、一般的にはスタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』(※注)の原作者として知られています。クラークの本は読んだことがなくても映画『2001年』は観たことがある、という人は多いでしょう。一九六八年に公開されたこの作品は、いまも映画史に燦然と輝く名作中の名作であり、SF映画の最高峰といえるでしょう。キューブリックとクラークはこの映画でアカデミー脚本賞にノミネートされました(受賞は逃しています)。
※「2001年宇宙の旅」
映画の脚本はクラークとキューブリックが担当し、原作となる長編小説はクラークが先行して書き始めた。しかし制作はときに難航し、映画の公開が1968年4月、小説の刊行がふた月遅れの6月となった。とくに映画版は不朽の名作と名高い。
この映画が公開された年にぼくは生まれました。翌年の一九六九年、人類はアポロ11号によって初の月面着陸を果たします。ぼくの知人男性に話を聞くと、彼は当時中学生で、学校の新聞部で号外を出すためテレビにかじりついていたそうです。月面からの映像は全世界に放送されましたが、それを可能にした通信技術は、実はクラークと無縁ではありません。
またアポロ月面着陸や映画『2001年』の前後には、一九六六年に映画『ミクロの決死圏』が、一九七一年に『アンドロメダ…』が公開されています。前者のノベライズを手がけたのはやはり著名なSF作家アイザック・アシモフ。後者の原作者はのちに『ジュラシック・パーク』を書くマイクル・クライトン。知人は当時『2001年』を含めたそれらの映画を観て「人生で初めてSFの面白さを知った」と感慨深げに語っていました。
本番組「100分de名著」のプロデューサーさんは、クラークを読んで高校時代に宇宙に憧れ、天文学者になりたいと思ったのだそうです。ぼくはそうした話を聞くといつもうらやましく思います。残念ながらぼくには少年時代にクラークを読んだ記憶がなく、「クラークを読んで人生が変わった。クラークを読んだおかげで科学者や技術者を目指した」という感動的なエピソードを披露できないからです。
どちらかというとぼくは日本SFが好きで、小松左京や眉村卓、光瀬龍の作品に親しみ、中学からは創刊されたばかりの雑誌「ニュートン」を読んで育ちました。父と母は薬学出身、妹は農学部を出ました。妹は大学院時代にアメリカへ留学し、そのとき映画『スター・ウォーズ』に嵌はまっていまも大好きです。父は大学の薬学研究者で、テレビの科学番組をよく観ますが、SFには興味がないようです。母にかつて「SFってどんなイメージ?」と尋ねたことがあります。答は「なんか宇宙でごちゃごちゃやってる」でした。ある意味、あまりに的を射ているので、大笑いしてしまったことを憶えています。
SFとは何か──これに答えるのは「日本料理とは何か」「フランス料理とは何か」という問いにひと言で答えるのが難しいのと同様に極めて難しい。どのレベルに焦点を合わせるかによって、いかようにも答えられるからです。
文化の発展・成熟過程とともにそうした議論の内容も変わり、洗練され、深まってきたはずです。たとえば「日本人として生まれてこなかったアメリカ人に真の寿司は握れるか」という問いはかつてあり得たかもしれません(ひょっとしたら個々人の心情的にはいまもあり得る)。それと似て「〝SF者〟でない人に真にSFの感動が理解できるのか」という主旨の議論はありました(あります)。これは「真にその人がSFを読めるかどうか」は生得的に決まっている、わからない人は永遠にわからないのだ、という主張にも聞こえます。ですからこうした問いも含めて「SFとは何か」について論じるならば、それは「ぼくたちの人間性とは何か」という大切な問いに真正面から向き合い、考えることに等しい。
SFとはサイエンス・フィクションの略語であり、昔は「空想科学小説」と呼ばれました。もともとはアメリカの無線技術者で作家・編集者のヒューゴー・ガーンズバックが世界初のSF専門雑誌「アメージング・ストーリーズ」を立ち上げたとき「サイエンティフィクション」という言葉をつくり、それがいいにくいということで「サイエンス・フィクション」として定着したものです。
ガーンズバックは未来の科学技術がどうなるかといった予測小説を書いた人で、当初のSFとはつまり「ぼくのかんがえた未来社会」を読者にわかりやすく提示するための物語装置だったのです。そうした未来想像図はフランスの画家・作家アルベール・ロビダが十九世紀末に描いて得意としていました。フランスの作家ジュール・ヴェルヌやイギリスのH・G・ウェルズもSFの先駆者であり、さらに遡ってSFの元祖をメアリー・シェリー『フランケンシュタイン』に求める評論もあります。
これまで「100分de名著」では『ソラリス』のスタニスワフ・レム、『日本沈没』などの小松左京が取り上げられてきました。あえていえば、レムや小松左京はSFの枠を越えて、より広い観点から論じることもできる作家です。レムは「アメリカ産のぺかぺかとした通俗SFに終始否定的態度を示しつつ、科学技術の未来について独自のスタンスで哲学的に考え続けた作家」といえますし、小松左京は「戦後の日本社会や科学技術のあり方を(関西人としての〝うかれ〟の精神を大切にしつつ)追求し続けた作家」ともいえます。
しかし今回取り上げるアーサー・C・クラークは、SF作家としかいいようがない作家です。彼は一作だけ非SFの航空小説『着陸降下進路Glide Path』を書いていますが(未邦訳)、それ以外の膨大な数の著作はほとんどすべてSF小説、あるいは科学技術一般・宇宙開発・通信・海洋に関するノンフィクションです。ですから、「クラークはSF作家ではない」といういい逃れはどうあっても成立しない。クラークを読むということは、SFを読むということとほぼ同義なのです。
しかしそれゆえに、クラークの業績は既存の価値観に縛られてきてしまった面もあったとぼくは考えます。いまもときおり「ハードSF」という言葉が使われます。科学・技術(サイエンス&テクノロジー)の成果を真正面から取り入れて未来を描き出すSF作品を指す言葉ですが、これまでクラークはハードSFの代表的作家と見なされ、そしてそのこと自体は決して間違いではないのですが、一方では科学技術と小説(物語)の関係性にある種の固定観念を植えつけ、広めてしまうという、現代の視点から振り返ると非常に惜しい影響も残してきてしまった作家に思えるのです。
クラークは一九一七年に生まれ、戦後の一九四六年に作家デビューし、二〇〇八年に亡くなりました。最晩年まで自分の後継者である作家たちと共著のかたちで小説作品を世に送り続けました。作家としての活動期間は六十年あまり。その間にぼくたち人類の「科学・技術」と「小説・物語」の関係、つまり科学や技術をいかにフィクションとして描くか、どのようにぼくたちは未来を想像し、それをかたちにしてきたかといった理想や希望は、地道な歩みでありながらも着実に発展し、成熟を遂げてきました。クラークを読むことはSFを読むことですが、それはすなわち人類が「科学・技術」と「小説・物語」の関係性をどう育んできたかを辿り、考え直す格好の契機でもあるのです。その先にはぼくたちの社会がこれからつくる「科学・技術」と「小説・物語」の未来がきっと見えてくるはずです。
本書では、ときに従来のSF評論の価値観とは異なるクラークの読み方を提示しています。これからSFを読み始める人にも、いまの視点からクラークとSFの楽しさを発見していただきたいと願うからです。「SFは専門用語がたくさん出てきて難しい」と苦手意識を持つ方もいらっしゃるでしょう。「どうせSFはウソを書いているんだから、それなら学術論文を読む方がよっぽど有益だ」とお考えの人もいるでしょう。そういう方にこそいまクラークを手に取って、科学技術と物語の豊かな未来を目にしていただきたいのです。クラークはSF界きっての名文家でした。独特のユーモアも持ち合わせていました。そして何より、本当に美しいものをきちんと美しく書ける稀有な才能の持ち主でした。
一九六一年、クラークはUNESCOが運営するカリンガ賞を科学普及の功績で受賞し、翌年の記念スピーチでこう語りかけました。「SFは実際のところ科学普及にどんな役割を果たしているでしょうか? 私が思うにその主な価値は、教育的であるというより、人の創造性を鼓舞する[inspirational]ことです。いったいどれほど多くの若者がヴェルヌとウェルズの小説から世界の不思議を知り、目を開かされて、科学の道に進んだことか?」「(SF作家は)読者に対して心の柔軟性を、変化への心構えと〝ようこそ〟という気持ちを──ひと言でいえば、適応性を促すのです」(著者訳)──確かにこの展望は正しい。しかし本書ではクラーク自身の作品群を読み解き、さらにその前提の先まで進みたい。
ぼくは本書をお読みの皆様に、「センスのよい好奇心」を育み続けることが生きる上で何よりも大切なのだ、とお伝えしたいのです。
たんに「好奇心を持つ」だけでは充分ではありません。「センスのよい好奇心」こそが、科学や文学の垣根を取り払って未来をつくることができる、ぼくたち人間のかけがえのない力だといいたいのです。誰もが「センスのよい好奇心」を育むことはできる、とぼくは考えます。
では「センスのよい」とはどのようなことか。センスを言葉にするのは難しいものですが、皆様が本書を読み終えるまでに「たぶんこういうことなんじゃないかな」と感じていただけるよう書き進めたいと思います。
クラークも「よいセンス」と「そうとはいえないセンス」の間で生涯揺れ動いた作家だったと思います。その揺れこそがぼくたちの人間性の宿命であり、科学技術と物語の間にある希望の本質でした。そして本当に「センスのよい好奇心」を発揮したときの彼は、誰にも負けないほど見事で、そして美しいSF小説を書きました。
そこにこそ、ぼくたちが目指す未来があるのです。