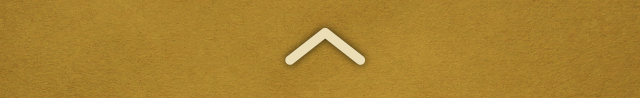宮崎哲弥
(みやざき・てつや)
評論家
1962年、福岡県生まれ。相愛大学客員教授。慶応義塾大学文学部社会学科卒業。専門は仏教思想・政治哲学。サブカルチャーにも詳しい。近著に、『仏教論争――「縁起」から本質を問う』(ちくま新書)、『ごまかさない仏教――仏・法・僧から問い直す』(新潮選書、佐々木閑氏との共著)、『知的唯仏論─マンガから知の最前線まで――ブッダの思想を現代に問う――』(新潮文庫、呉智英氏との共著)、『さみしさサヨナラ会議』(角川文庫、小池龍之介氏との共著)、『宮崎哲弥 仏教教理問答』(サンガ文庫、白川密成・釈撤宗・勝本華蓮・南直哉・林田康順の各氏との共著)、『日本のもと 憲法』(監修、講談社)など多数。
◯『小松左京スペシャル』 ゲスト講師 宮崎哲弥
戦後日本SFとは何だったのか─―小松左京を通じて
小松左京という名前を聞いて、多くの人々の脳裡に浮かぶのはまず『日本沈没』『復活の日』ではないでしょうか。日本と世界とが未曾有の災厄に見舞われ、滅亡の淵に追い遣られてしまう二つの物語は衝撃性、規模の巨大さ、リアリティで読者を圧倒しました。
前者は上下巻合わせて四百六十万部にも及ぶ大ベストセラーとなり、三度映像化され、少なくともタイトルを知らない者はいないというほど広く知れわたったのです。
未知のウイルスのパンデミックによる人類と多くの脊椎動物の死滅を描いた『復活の日』は、似たアイディアに基づくバイオ・パニックものの古典、マイケル・クライトンの『アンドロメダ病原体』に五年先んじる一九六四年に出版されました。しかしクライトンの小説は、強い緊張感を孕(はら)みながらサスペンスフルに展開していく傑作ではあるものの、作品の規模、文明論的な深度などからみて『復活の日』を超える作品ではありませんでした。
『復活の日』は小松作品としてはごく初期のものであり、同年発表の『日本アパッチ族』とともに、小松SFの豊饒な世界がここに始まる、といっても過言ではありません。
日本SFの流れに多少なりとも詳しい人であれば、小松が星新一や筒井康隆と並んで「SF御三家」と呼ばれ、戦後のSF界の基礎を築き、その可能性を大きく押し広げる偉業を成し遂げた人物であることをご存じでしょう。
『日本沈没』については番組第2回で詳しく考察しますが、その構想のスケールの大きさ、道具立てのリアルさ、そして物語の背景にある問題意識の深さは、発刊から四十五年以上を経た今日でも少しも古色を帯びていません。
『日本沈没』は戦後SF最大のベストセラーになりました。高度経済成長に陰りがみえはじめた時代状況に後押しされたという要素も無視できませんが、何といってもこれが単なる「近未来小説」とは違って、SFの強みが遺憾なく発揮された作品であったがために、多くの読者を得たといえるでしょう。
そもそもSFとは何でしょうか。この問いに対しては、単純に「サイエンス・フィクション、即(すなわ)ち空想科学小説」などという通り一遍の訳語を示すだけではすまない「定義し難(がた)さ」について語らねばなりません。
仮にSFのSが「サイエンス」の略だとしても、この「サイエンス」とは一意に自然科学を指すのでしょうか。世の通念ではそうかもしれません。しかし多くのSFの書き手、熱心な読み手はこの「定義」におそらく満足しないでしょう。そこで「サイエンス」を「合理的に体系化された諸学」、即ち近代以降の自然科学、社会科学、人文(科)学の総体を示すと解釈し、SFとはその総体を主題とする小説である、と看做(みな)すならば、かなり満足水準に近づくかもしれません。
けれどもまだ十全には遠い。それではまだ、SFの根源的な批判性や自在性を表し尽くせていないように思えるからです。あえていえばSFは、その組織化され、テリトリー化された学知の根拠、「合理性」や「体系性」に批判的です。あるいはそれらを支える「近代性」や「知性それ自体」をも批判的に捉え、相対化できるのです。今日のSFが「トランスサイエンス」の領野、つまり「サイエンス」が未だ答えを出せない問題域に入っているといわれるのはこうした理由からです。
あるいはまた、「サイエンス」を体系化された諸学と捉え、SFはそれらを横断しながら進んでいく「物語」であるとしても、その対象に人文(科)学が含まれていることから、SFは哲学や宗教、もっといえば人間の実存の問題(「私は『在(あ)る』のか」「私は何故(なにゆえ)にここにこうして在るのか」「私を在らしめているのは何か」「私達は何を求め、いずかたに行くのか」等)をも問うことができるといえます。抽象的にも、具象的にも。いやむしろ、その抽象と具体を架橋する「物語」として提示できる。第1回では、その例証として『地には平和を』を挙げ、小松が自身の戦時や敗戦直後の生々しい体験を、物語を通じて、いかに普遍的、抽象的な問題に変換してみせたかを確かめます。
さらには他の「サイエンス」、例えば科学技術や経済構造と個の実存問題との関連や無関連を「物語」の形式で描き出すことができる。この類(たぐ)い稀(まれ)な自在性こそがSFの真骨頂といえます。
小松左京はSFの自由さに当初から気付いていました。一九六三年に書かれた、宣言的文書『拝啓イワン・エフレーモフ様─―『社会主義的SF論』に対する反論─―』には当時としては非常に先鋭的なSF観が盛り込まれています。ソビエト連邦の作家による硬直的な社会主義的SF観に対する論駁(ろんばく)のかたちを取りながら、これは、その後のSFの進程(しんてい)を予見するものです。と同時にこの論考にはその後の、つまり六四年に本格的に開幕する小松左京のSFの設計思想(デザイン・フィロソフィー)が惜しげなく明かされており、その作品世界の格好の見取り図となっているのです。この実作家の手になる非常に重要な評論文は折に触れて紹介していきます。
宇宙の構造と人間型知性のあり様(よう)、そして個の存在の意味を繋(つな)ぐ「物語」としてのSF。これは小松SFのメインストリームである、いわば「宇宙構造探究系」の作品に共通する根源的なテーマです(この系列にある作品『ゴルディアスの結び目』『虚無回廊』については第3回、第4回で紹介します)。
ここで私達はある逆説に突き当たります。自然科学をはじめ、先端的なテクノロジーや哲学、心理学、認知科学、言語学、論理学、社会学などを横断的に素材として取り込んできたSFが、機能としては古代から伝承されている神話や宗教的説話に近づいているという逆説です。
神話や説話、叙事詩(以下、「神話類」と総称する)の多くは、世界の起源、宇宙の開闢(かいびやく)を描き出しています。しかもそれは往々にして、神などの超越的、外部的、あるいは形而上的な存在の「御業(みわざ)」によると説かれた。そうして創造された世界(宇宙)において、個々、各私の生存の起源や由来、意味が定位される。「神話類」とは、このようにマクロな世界観からミクロな個々の生の意義までを一貫して基礎付け、総体的な世界構造を示唆する「大きな物語(グランド・ナラティヴ)」です。
SFが「神話類」に近づいているといっても、「神の死んだ」現代において、古(いにしえ)の神話説話や中世の叙事詩がそのまま反復されるわけではもちろんありません。けれども、世界の存在理由、宇宙の存立構造を解き明かすことで個々の実存の意味を定める、という古来「神話類」が果たしてきた役割を、近現代において担ってきたのはSFなのです。
元来、広義の文学は神話説話や宗教叙事詩を含み、かかる機能性を具備(ぐび)していたのですが、近代文学の成立とともに「神話類」が駆逐されてしまいます。文学が言語による芸術であることが強調されるとともに、主題も専らミクロな個人の心理や情感、意思の描写に重きが置かれていきます。その個を取り巻く状況を描いても、せいぜい家族や社会、国家や政治といった世俗の目路(めじ)の限りに留まり、宇宙や地球全体、生命圏や全時空間といった「浮世離れ」した領域にまで説き及ぶことはまずなかった。戦後文学でいうなら、埴谷雄高(はにやゆたか)の『死霊』のような優れて思弁的な小説や、大江健三郎の神話性が濃密に立ちこめる幾つかの作品を例外として、主流派の文学は全宇宙の意味や知性の存在理由といった哲学的、宗教的な問いをなかなか主題化できませんでした。また、仮にそれら超越的、超巨視的な事象に書き及んだとしても、既存宗教の、細々と余喘(よぜん)を保っているリアリティに事寄せてする場合がほとんどで、アクチュアルな、主体的なテーマになることはありませんでした。
ちなみに小松が少年時代に最も影響を受けた文学作品がダンテのキリスト教叙事詩『神曲』であり、青年時には埴谷の『死霊』に傾倒したというのは象徴的です。逆に読書欲が旺盛な時期にも自然主義文学や白樺派には「全く興味がなかった」と切り捨てています(『SF魂』新潮新書)。
近代において「神話類」が退場した後の空位を、「サイエンス」やテクノロジーのリアリティを用いながら占めていったのがSFだったのです。しかしながらSFは、先にも述べたように「神話類」の単なる機能的代替物ではありません。「神なき時代」における神話の可能性を探り得ると同時に、まさにそのことを主題化するが故に 、神話を求める志向そのものを徹底的に相対化してしまうことも、またSFにおいて可能なのです。
小松自身も前出の『拝啓イワン・エフレーモフ様』に、「SFの視点にたてば、あらゆる形式の文学を、─神話、伝承、古典、通俗すべてのものを、相互に等価なものと見なすことができる。このことはやがて〈文学の文学性〉を、実体概念でなく、機能概念として見る見方に導く」と明記しています。
ここにみられるモーティヴ(動機)、設計思想が小松左京の作品にいかに反映しているのか。『地には平和を』『日本沈没』『ゴルディアスの結び目』『虚無回廊』を中心に据えながら、適時、他の作品や論著にも言及しつつ、また作者のものの見方を培った生い立ちや来歴、時代背景も参照しながら、これから四回にわたって案内していきたいと思います。