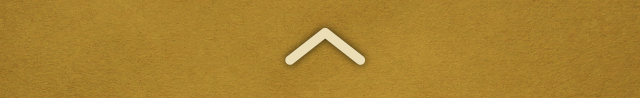阿部公彦
(あべ・まさひこ)
東京大学教授
1966年横浜市生まれ。東京大学文学部卒。同大学修士課程を経て、ケンブリッジ大学で97年に博士号取得(博士論文はWallace Stevens and the Aesthetic of Boredom 「ウォレス・スティーヴンズと退屈の美学」)。現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。98年、小説「荒れ野に行く」で早稲田文学新人賞受賞、2013年、『文学を〈凝視する〉』(岩波書店)でサントリー学芸賞受賞。英米文学研究と文学一般の評論に取り組む。著書に『英詩のわかり方』『英語文章読本』『英語的思考を読む』(以上、研究社)、『小説的思考のススメ』『詩的思考のめざめ』(東京大学出版会)、『名作をいじる』(立東舎)などの啓蒙書、『モダンの近似値』『即興文学のつくり方』(以上、松柏社)、『スローモーション考』(南雲堂)、『善意と悪意の英文学史』(東京大学出版会)、『幼さという戦略』(朝日選書)などの専門書があり、翻訳に『フランク・オコナー短編集』、マラマッド『魔法の樽 他十二編』(以 上、岩波文庫)などがある。
◯『夏目漱石スペシャル』 ゲスト講師 阿部公彦
夏目漱石と「出会う」ために
夏目漱石は食いしん坊でした。甘いものやこってりしたものが大好き。ステーキの味を覚えたのはロンドン留学の間でしょうか。お菓子にも目がなく、ジャムを舐(な)めるのも大好き。お腹に悪いから食べ過ぎないように、と鏡子夫人は戸棚の奥に菓子類を隠したそうです。美食というより、B 級グルメといったほうがいいかもしれません。
実は、漱石のこんな「食べっぷり」は、彼の作品を読むヒントにもなると私は思っています。文は人なりと言ったりしますが、人間というものは思わぬところで性格が出たり、特徴ある行動パターンを示したりする。だから、食べっぷりと書きっぷりが似ることもある。体の動きが俊敏な人は、考えるときも俊敏かもしれない。病気を抱えた人なら、その病気に応じた頭の使い方や、文章の書き方をしてもおかしくない。食いしん坊は食いしん坊らしい小説を、胃弱の人は「胃弱な小説」を書くかもしれないのです。
漱石の小説家としてのデビュー作となったのは『吾輩は猫である』でした。設定からして、とにかく楽しい作品です。出版物としても人気で、よく売れた。漱石にはエンターテイナーとしての天性の才能があったのでしょう。当時のトップエリートとしての道を歩んだはずの彼が、通俗的にアピールする力を備えていたというのはおもしろい。「B 級」の感性のおかげかもしれません。
しかし、売れる作家としてデビューしたことは、漱石にとっては重荷にもなった。一度売れてしまった人は、つねに「売れねばならない」という期待を背負いがちだからです。おもしろおかしく書くことができる才能があっても、そう書かねばとなれば縛りになる。
漱石の作品を読むと、「B 級」の匂いが強くすることがあります。そこは漱石の大事な魅力の一部。しかし、同時におもしろいのは、漱石がそうした「B級」性に安住せずに外に出ようとしたとき、とても創造的にもなったということです。彼は作家として、つねに挑戦的な人でした。読者に喜んでもらうことも大事だったでしょうが、譲れない部分もあった。漱石の魅力を味わうにはこうした機微に注目する必要があるでしょう。そんなことを頭に入れながら、あらためて漱石という作家に向きあってみたいと思います。
現代人にとっては、漱石はきちんと「出会う」のが難しい作家です。私たちが小説を読もうとすると、いろいろ邪魔が入ります。たとえば作家の名前。「これは夏目漱石の書いた小説です」と言われれば、私たちはその作品を読んでもいないのに読んだような錯覚に陥ったり、あらすじだけで何かをわかった気になったりする。とりわけ『三四郎』や『道草』など、漱石の代表作とされる作品を前にすると、「未読であるのは恥ずかしい」、「古典的名著なのだから、私は感動すべきだ」と、自らを不自由な暗示にかけたりもします。文学を重要視するマジメな人ほど、その傾向が強まる。作家の名前による先入観から、予断を持ってしまうのです。
では、作品と本当に「出会う」にはどうしたらいいのでしょう。
小説を読むというのは、全身的な行為だと私は思っています。頭や感情ももちろん関係する。しかし、体も忘れてはいけない。胃腸や、呼吸や、背骨も大事。感触を味わい、文章のリズムに身を委ねたい。笑ったり、ツッコミをいれたり、顔をしかめたり。場合によってはぜえぜえあえいだり、踊り出したり、地団駄踏んだり。
そんな出会い方をするためのヒントを、以下の四つの回で示していきたいと思います。そのために、みなさんにずんずん歩く心地や、胃腸の気持ち悪い感じを想像してもらうこともある。「真相究明するぞ」とばかりに目を剥いてもらうこともあるかもしれない。漱石はそんなふうに全身を使って読むに値する作家なのです。
おそらく何歳のときに読むかによって、漱石から受ける印象は異なるでしょう。若いころのほうが直観的にわかる部分もある反面、歳をとってからでないとわからない微妙な部分もある。ひとつの作品を同じ人間が読んでも、時期によって見える顔が違うのです。私自身、高校生のときに読んだ漱石と、今読む漱石はかなり違う。だから何度でも読める、何度でも出会える作家なのです。一粒で二度、三度とおいしい。
漱石は日本でどう小説が書かれ、読まれてきたかを理解するのに、うってつけの作家でもあります。生まれは一八六七(慶応三)年ですが、本格的に小説を書き始めたのは、『吾輩は猫である』を発表した一九〇五(明治三十八)年以降。四十歳近くになってデビューした、遅咲きの作家なのです。
明治という時代は、日本に西欧の近代小説が輸入され、日本語で小説を書くことに多くの作家たちが挑戦した時代でもあります。漱石もまた、さまざまな小説スタイルを取り入れ、消化し、多様な作品に結実させました。漱石作品を読めば、彼が日本語と日本文化のなかに小説という新しいジャンルを根づかせようと頑張ったさまを見て取ることができます。近代小説が生まれたこの時期ならではの苦労の数々が、一人の作家の作品に現われているのです。
『夢十夜』などに顕著ですが、漱石が小説という新興のジャンルを完全に信じることができず懐疑的になっていたと感じられる作品もある。冒頭でも触れたように、おもしろおかしいものを求めようとするB 級性も漱石にはあった。単にエリートとして、近代小説の様式にどっぷりつかっていたわけではないのです。冒険を試み、ときに、ちょっと変なこともした。
漱石は職業作家になる以前は、当時の中学・高校や大学で教育と研究にたずさわっていました。その後、文部省から国費での留学を命ぜられ、渡英します。イギリスにおいても、アカデミズムのなかで英文学研究が成立したのは十九世紀の終わり、しかもイングランドではなくてスコットランド周辺からです。漱石は、英文学研究のやり方が今のように確立する前から、英文学とは何か、ひいては文学とは何か、という問題とも一人で向きあっていました。その立場から、日本の文化・文明、明治という国家、近代小説、英語教育、さらには日本の発展という問題にも直面しました。私たちが近代日本の意味を問い直す際、漱石作品と向きあうことは非常な助けとなります。
漱石はわずか十二年という短い作家生命の間に、十五の長編作品と三つの短編集、そして評論と随筆を世に送り出しました。これらの作品の文体はすべて異なりますし、読者が受け取る文章の感触もちがいます。今回の漱石スペシャルは、私の独断で『三四郎』、『夢十夜』、『道草』、『明暗』を選びましたが、もちろん他の選択もありえた。なぜ私がこの四作を選んだのかを、以下、簡単に説明しておきましょう。
『三四郎』は、彼が職業作家として、近代小説を自分の方式で洗練させようとした最初の作品です。近代小説という輸入物の様式をはじめて本格的に使ってみた。だから、いろいろと「初物づくし」のところがある。そういう意味では記念碑的な作品と言えるでしょう。
『夢十夜』は、輸入物の近代小説を受容した『三四郎』のスタイルとは逆に、むしろそこからの逸脱を目指している作品に見えます。両者を読み比べれば、漱石の幅広さや挑戦も感じられるはずです。
『道草』は、漱石と対立すると考えられていた自然主義リアリズム小説の一派に対する、一種のジェスチャーと読める作品。「俺だって自然主義をやれるぞ」とばかりに、どちらかというと自然主義に近い書き方をしている。読者をおもしろがらせるようなプロットの要素は控えめで、「片付かないままの」混沌とした日常を露出させた、自伝的な小説です。
しかし、私がこの小説に注目するのは、「胃弱」という漱石にとっての宿痾をもっとも小説的に明確に表現しているからです。得も言われぬ不安や恐怖に、胃弱という具体的な形を与えることで、『道草』の漱石は精神の平安をえたのではないかと私は考えます。
『明暗』は、漱石の絶命によって未完に終わった遺作。とにかく心理のからみあいが濃厚で、スパイ小説のような趣さえあります。読みどころは、主人公の津田と女性たちとの「対決」シーン。彼は女たちに出し抜かれたり、そそのかされたり、助けられたりしながら、最終的には他者に負けることでこそ、他者を知る。そこに漱石の達した最終的な境地を見て取ることもできるでしょう。興味つきない作品です。
夏目漱石という作家は、さまざまな意味でパイオニアでした。まだそのシステムが完成してもいないのに、そのシステムを生きなければならない苦しさを、いやというほど味わった人。手探りで近代小説にぶつかっていった彼の軌跡を追えば、小説とはどういうものなのか、その本質が見えてくるかなと思います。
それでは、前口上はこれぐらいにして、『三四郎』から読んでみましょう。
【推薦図書】漱石関係の資料は膨大だが、最初の一歩として役立つのは『漱石辞典』(小森陽一・飯田祐子・五味渕典嗣・佐藤泉・佐藤裕子・野網摩利子編、翰林書房)。また、漱石作品のこれまでの解釈に興味がある人には石原千秋『漱石はどう読まれてきたか』(新潮選書)が便利。