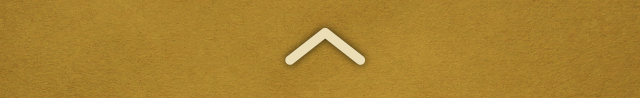「マレビト」「常世」といった独自の概念を生み出し、戦前、戦後を通じて、国文学と民俗学に決定的な影響を与えた折口信夫(1887―1953)。二十年来の研究を集大成し「折口学」と呼ばれる学問構想の全容を示した代表作が「古代研究」です。来年、没後70年を迎えるタイミングで、折口についての様々な研究書や読み物が出版され、一般の人々の間でも関心が巻き起こっています。そこで「100分de名著」では、難解といわれる折口の思想に現代の視点から新しい光を当て「古代研究」を読み解くことで「日本文化とは何か」をあらためて見つめなおします。
「古代研究」といっても歴史学の書ではありません。古代人の心性に論理を超えた直観で迫りながら、日本文化の基層にあるものが何なのかを明らかにしようという野心的な著作です。そこでは、万葉集から新古今集に至る国文学の生成発展から、古代人の生活、聖賤入り混じる日本の芸能史、神道や伝説の深層まで、「マレビト」という鍵概念をベースにした、縦横無尽な探索、論考が行われ、既存の学問的枠組みを超えた壮大な試みが展開されています。
「古代研究」を読み解いていくと、茶道や華道といった芸道や「おもてなし」に象徴される日本文化の隅々にまで、古代的な心性の深い影響が及んでいることがわかります。また、ごく日常的な営みにも現れる日本人ならではの感受性が歴史を通じてどう育まれていったかを知ることもできます。いわば「古代研究」は日本人の心性の原点を探りだす著作なのです。
万葉集研究の第一人者であり折口信夫の研究でも知られる上野誠さんは、「古代研究」を現代に読む意味が「近代化の中で表面的には忘れ去っているようにみえるが、無意識のうちに我々を規定している日本文化の基層に触れることができること」だといいます。上野さんに「古代研究」を現代の視点から読み解いてもらい、折口信夫が明らかにした「日本文化の深み」に迫っていきます。
各回の放送内容
第1回「他界」と「マレビト」
折口にとって古代の世界観の根底となるのが「他界」の問題だ。かつて日本列島に移り住んできた祖先たちが離別してきた出立の地を懐かしんだり憧れたりする心性が「他界」を生み出したのではないかと折口は考えた。更に折口は、南方諸島の祭祀などに見られる、他界から時を定めてやってくる存在を「マレビト」と呼び、日本における神の原初的形態だという。人々はマレビトを畏怖をもって迎え饗応し、マレビトは豊作などを予言して他界へ帰っていく。この構造が、茶道や華道などの芸道や「おもてなし」に象徴されるの日本文化の隅々に影響を及ぼしているというのだ。第一回は、折口が唱えた「マレビト」や「他界」という概念を解き明かすことで、日本文化の基層にあるものに迫っていく。
【指南役】上野誠(國學院大學教授)…国文学者。著書に「折口信夫 魂の古代学」「折口信夫『まれびと』の発見」など
【朗読】渡辺いっけい(俳優)
【語り】小坂由里子
第2回 国文学の発生
人々がマレビトをもてなすのは、マレビトが他界からのメッセージを伝えてくれるからだ。「呪言」と呼ばれるその言葉が、記憶に残るよう一定の形式をもって伝えられてゆく中で、和歌や物語の原型が形作られていく。その際に「うたう」「かたる」という二つの方向性があり、それぞれが叙情詩、叙事詩に発展していくという。第二回は、「マレビト」についての考察を発展させた折口の洞察から、国文学発生の現場に迫り、和歌や古典の物語が私たちにとってどんな存在なのかを明らかにしていく。
【指南役】上野誠(國學院大學教授)…国文学者。著書に「折口信夫 魂の古代学」「折口信夫『まれびと』の発見」など
【朗読】渡辺いっけい(俳優)
【語り】小坂由里子
第3回 ほかひびとの芸能史
折口の理論は「芸能史」にも新たな視角を与えてくれる。芸能は元来マレビトの言葉やふるまいを模倣する行為「もどき」から始まったという。それは日常性を超えた異世界性を帯びているが故に、聖性をもち、その裏返しとして賎性をも合わせもつ。諸国を流浪する念仏踊りの聖や琵琶法師、門付け芸人らは、聖人的な側面をもちつつも「河原乞食」とも蔑称され疎外されてきた。こうした聖と賤が入り混じったダイナミズムこそが日本の芸能の特質なのだ。第三回では、折口の芸能についての論考から、現代の芸能文化や風俗にまで深く影響が及んでいる「聖と賤のダイナミズム」に迫っていく。
【指南役】上野誠(國學院大學教授)…国文学者。著書に「折口信夫 魂の古代学」「折口信夫『まれびと』の発見」など
【朗読】渡辺いっけい(俳優)
【語り】小坂由里子
第4回 「生活の古典」としての民俗学
戦後の学問は、分野ごとに明確に線引きされ論理と実証のみによって事象を解き明かすことが主流になっていた。しかし折口は、そのような細分化した学問では人間の心性を探ることはできないと真っ向から批判する。文献のみに頼る研究だけではなく、身近な年中行事や日本各地に残る祭礼を掘り下げ、古代人の心を肌で実感し思考することの大切さを訴えたのだ。その背景には、私たちの心は深いところで古代人と繋がっているという「実感」こそが、私たちの心を豊かにしてくれるという折口の信念があった。第四回は、折口が「生活の古典」と呼んだ、私たちの生活に沁みとおった文化の基層としての「民俗」に迫っていく。
【指南役】上野誠(國學院大學教授)…国文学者。著書に「折口信夫 魂の古代学」「折口信夫『まれびと』の発見」など
【朗読】渡辺いっけい(俳優)
【語り】小坂由里子
ほかひを携へ、くぐつを提げて、行き行きて、又、行き行く流民の群れが、鮮やかに目に浮かんで、消えようとせぬ。此間に、私は、此文章の綴めをつくる
(「国文学の発生(第四稿)」より)
30代前半、折口信夫「古代研究」を読んだときに鮮烈に記憶に刻まれた一節です。さらっと読み飛ばしてしまってもいいような文章に見えるかもしれませんが、なぜかそのとき私の原体験を照らし出してくれる一節に思えたのです。
大分県中津市という、どちらかといえば田舎の街の端っこに生まれた私は、幼い頃、近所の神社で毎年おおみそかに奉納される「植野神楽」という神事に魅了されていました。おそらく岩戸神楽の一種であろうこの神楽ですが、幼心に全く意味もわからず、時に退屈をしたりもしてたのですが(全部を観終えたことはおそらくないと思います)、ときどきなんともいえない神々しさがひらめくことがあり、そうかと思うと、なんだか猥雑でエロティックな場面にどきどきすることもありました。当時は全く言語化などできず、神々しさと猥雑さがないまぜになったこの神事はいったい何なのだろうと、混沌の中に投げ込まれたような気分だったのです。
もう一つ、私と同世代の人たちには同じような記憶があるかもしれませんが、年に一度、旅回りのサーカス団が街を訪れ興行を行っていました。それを観にいく日はまさに「ハレの日」でした。ところが、楽しいはずのサーカスの中に、何か哀愁のような、切なさのようなものをときどき感じるのです。驚愕するような雑技の数々に高揚しながらも、薄暗いテントの中に宿る旅芸人たちの哀切のようなものを感じていました。
私の中に、「芸能」という、相反する二極がないまぜになった不思議な魅力をもった存在が刻み付けられた二つの原体験です。時を隔てて四半世紀、この不思議な体験が、折口の言葉によって、ぱっと照らされたような心持ちがしたのです。
ですので、私にとって折口は、「芸能の謎」に光を当ててくれた人…という印象がとても大きかった。一般の「折口読みの人」と比べると、かなり異端的な読みをしていたのではないかと思います。
そんな強烈な印象をもたらしてくれた折口ですから、この番組のプロデューサーに就任してから、取り組んでみたいと思っていました。中沢新一さん、安藤礼二さん…等々、優れた折口論を書いた人はたくさんいらっしゃいます。どれも魅力的だったのですが、いずれも私が求めていた「芸能論」についてはそれほど注力されていませんでした。いつか自分と同じような読み解きをしてもらえる人に出会えるのだろうか……私はひたすらその時を待っていたような気がします。
ひょんなことから、そのきっかけは現れました。書籍のプロモーションを仕事にしているHさんから一冊の本が送られてきたのです。上野誠著「折口信夫 魂の古代学」という本でした。かなり前に出た本ですので、プロモーション目的ではなく愛読書を送ってこられたのだと思いました。しかし……上野誠さんといえば、万葉集研究の第一人者。もちろん折口も「口訳万葉集」を手掛けた万葉集研究者ですから、通じているところはあるとは思いつつ、「折口で一冊本を書かれているのか」と意外な印象でした。
……ところが! 一読、面白い!
折口信夫と上野誠さんの架空の対談から始まるという冒頭の斬品さ。そして、折口の生涯を逆順にたどりながら、さまざまな謎にメスをいれていくという手法の鮮やかさ。あっという間に魅了されてしまい、わずか3日間で読み終えました。…そこに、あったのです! 折口の「芸能論」が!
しかも、私が年来思い続けてきた「折口はなぜあんなに独自な芸能論を展開しようと考えたのだろう」という疑問が氷解するようなエピソードも記されていたのです。番組でも紹介しましたが、折口の父親が懇意にしていた芸者「寅吉」のエピソードです。
老いて醜くなったわが身をはやしたてる大人や子供たちに対して「これやよつて、素人はどむならんねん。あほらしい。四十面さげて子どもと一処に、大声で、人の顔の讒訴や」と、矜持をもっていい放つ寅吉。そのかっこよさに痺れました。
そうか、折口の芸能民の原像はここにあったのか…と、ようやくすべてが腑に落ちました。そして、折口は、どこか自分の姿を彼ら芸能民に重ね合わせているのではと直観しました。
やや下手くそで恐縮ですが、私なりに折口の芸能論をつづめていうとこんな感じでしょうか?……芸能は元来マレビトの言葉やふるまいを模倣する行為「もどき」から始まった。それは日常性を超えた異世界性を帯びているが故に、聖性をもち、その裏返しとして賎性をも合わせもつ。諸国を流浪する念仏踊りの聖や琵琶法師、門付け芸人らは、聖人的な側面をもちつつも「河原乞食」とも蔑称され疎外されてきた。こうした聖と賤が入り混じったダイナミズムこそが日本の芸能の特質なのだ、と。
折口は、芸能に親しんできた人間とはいえ、芸能民ではありません。ですが、学術の世界では、どこか異端的であり、決して主流にはなれない存在でした。ですが、誰が認めずとも自らの「実感の学問」こそが、データ偏重の近代的な学問では決して解き明かせない古代人の心性や、そこから私たち現代人が受け継いでいる心性に迫ることができるのだという矜持を持ち続けていたのだと思います。「これやよつて、近代的な学問はどむならんねん。あほらしい。学者づらさげてデータや物証とやらだけを頼りに、大声で、人の『実感』の讒訴や」……そんな声が「古代研究」の端々から聞こえてきそうです。
上野さんが抽出してくれた折口信夫のこうした「芸能論」を第三回の中核に据えたことは、番組をご覧になった方は既におわかりかと思います。上野さんに最初の構成案をお持ちしたときは、はじめは少し驚かれていましたが、非常に面白がってくださったのをよく覚えています。今回の企画の発端には、こんな流れがあったのでした。その結果、これまでの放送にはなかった、オリジナルな折口論が番組で展開できたと思っています。
番組では上野節炸裂でした。万葉集に記録された祝福芸の一例を、旅芸人の口上風に語る一席を披露してくれたり、折口の学問像を円環上に図示した模式図で見事に表現してくれたりと学ぶ楽しみにあふれた解説でした。上野誠さんのパフォーマンス自体が折口の学問を体現しているのではないかとさえ思えます。
そんな魅力的な解説にほだされるように、司会の伊集院光さんはいつも以上に前のめりでした。そしてラスト近く、こんな鮮烈な言葉を述べてくれました。
「(弟子たちと一緒に興じたという)お化け行列のくだりなどを聞いているとね、本当にこの人を民俗学というものが救ったんだなあと思うんです。おそらくこの人は相当はみでたんだろうなという感じがするんですよ。理屈でいうと、自分が存在しちゃいけないんじゃないかと思うような局面がいっぱいあったんじゃないか。それをどうにか存在させてもらえたというような意識が常にあって、『小さな集落の中であぶれた人たちってどんな気持ちなんだろう?』という問いがいつもあるような気がして。時々ぐっときて、泣きそうになるんです」
「民俗学が折口信夫を救った」…この言葉は、今回のシリーズのある核心を凝縮したような言葉で、震えました。上野さんも心から嬉しそうな笑みをたたえられていたのが忘れられません。
こんな瞬間に出会えることが、この番組の醍醐味です。私自身も、決して主流ではない異端だからこそ、今後も折口信夫の著作に救われることでしょう。こんな素敵な感慨にひたれるような、見事な解説を繰り広げてくれた上野誠さんに心から感謝するとともに、それを番組として結晶させてくれた、ディレクターをはじめとするすべての関係者にこの場を借りて御礼をさせていただければと思います。
今回、スポットを当てるのは『川口恵里(ブリュッケ)』

<プロフィール>
演出・イラスト:川口恵里(ブリュッケ) 多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。2016年より株式会社ブリュッケに所属。アニメーション作家/イラストレーターとして、TV番組、企業CM、音楽PV、ワークショップ等、幅広く手掛ける。線画台を用いた、空間と光を活かした画づくりが得意。

川口恵里さんに“古代研究”のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。
今回の「古代研究」のアニメパートを担当するにあたって難しいと感じたことの一つは、
この難解な書の鍵概念と言われる「マレビト」をどのように描くかという点でした。
番組でもあったように、「古代研究」の「古代」という言葉は、純粋に年代としての古代では
ないため、特定の年代に絞って服装等を描かないようにすることと、神と人との境界が必ずしも明確でない考え方ということもあったので、どこまで人を感じられるように描くか?という点についても悩みました。
悩んだ末に、顔や肌を黒い影として描くことで、表情や性格、人種、人柄の見えない姿として描き、服装についてはディレクターと話をし、蓑と笠を被っているだけとしました。
個人的感覚ですが、少し怪しくすらみえる「マレビト」も
簑と笠をかぶっているだけで
悪いものでは無い気がしますし、それを身につける「マレビト」も
なんとなく、人の手
によって守られているように思いました。
全体の絵を構成する際も、そんな人でも神でもあるような表現で描いた「マレビト」が、恐れられるような存在ではなく、ただ、そこに実在するだけと感じられるように静かな絵作りを心がけたつもりです。

次に、難しいと感じたのが、「マレビト」がその土地に住む住民たちのしあわせを願い唱える「呪言」をどのように描くかという点でした。「呪言」は元々、意味をなさない音の反復だったものが、徐々に意味や音が整理されて、「五七五七七」のような律分の形をとっていったようです。
この変化をアニメーションで描くにあたり、最初は、波長が揺らめいている様を描き、それが楽譜のような感じに変化することで、音階を持っていくイメージを出し、最後に、
「五」や「七」の漢数字を出すことで、律分に進化していくことを表現してみました。
以上の箇所も少し気にして見て頂けると嬉しいです。