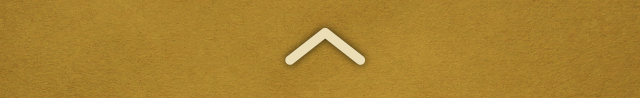「100分de名著」では、2022年の夏休み、「100分de名著 for ティーンズ」というスペシャル・シリーズを、ファミリーで楽しめる特別版として立ち上げます。
「夏休み」といえば、読書の季節。でも若い親世代にとっては「子どもたちにどうやって本を読ませるか」は大きな課題。そこで番組では、通常放送よりも「敷居を低く」、ティーンネイジャーが親子で視聴しながら「なるほど、そうだったのか」と頷けるような解説を展開。「思春期の悩みに響く文学作品」「知的好奇心をそそる科学読み物」「社会のしくみがよくわかる経済入門」「心をぐっとつかまれる古典作品」といった普段扱わないジャンルの名著を取り上げ、「親子で楽しめる」知的エンターテインメント番組を目指します。
ラインナップは以下の通り。
第1回 トルストイ「人は何で生きるか」×若松英輔
第2回 ポール・ナース「WHAT IS LIFE? 生命とは何か」× 竹内薫
第3回 バルファキス「父が娘に語る経済の話。」× 中山智香子
第4回 「竹取物語」× 木ノ下裕一
<出演者>
【司会】加藤シゲアキ(作家・タレント)・安部みちこアナウンサー
【生徒役】鈴木福(第1回・第2回)、本田望結(第3回・第4回)
各回の放送内容
第1回「人は何で生きるか」トルストイ
ある雪の日、行き倒れの青年を引き取ることになる貧しい靴職人の夫婦。さまざま出会いにより少しずつ何かに気づいていくその青年から、やがて夫婦は人生にとって最も大切なことを教えてもらうことに。誰でもわかる易しい言葉で語られたこの物語を、単に自分の外側の物語ではなく、自分の内面の物語ととらえると、深い真実が見えてくるという批評家・若松英輔さんの読みを通して、「人生にとって一番大切なものは何か」を学んでいく。
【指南役】若松英輔(批評家・随筆家)
【生徒役】鈴木福
【朗読】花澤香菜 下野紘
【語り】目黒泉
第2回 「WHAT IS LIFE? 生命とは何か」ポール・ナース
不意に庭を訪れた蝶々の美しさに打たれた少年は生物学者を志す。彼こそ、やがて生物学の歴史を変える大発見を行いノーベル生理学・医学賞を受賞することになったポール・ナースだ。彼自身が直面した「生きるって何だろう」「生命って何だろう」「どうして蝶々はこんなに美しいんだろう」といった素朴な疑問が、生物学や遺伝学の最先端を使って鮮やかに解き明かされていく。サイエンスライターの竹内薫さんに読み解いてもらうことで、「科学することの喜び」「すべての生命のつながりや尊さ」を学んでいく。
【指南役】竹内薫(サイエンス・ライター)
【生徒役】鈴木福
【朗読】下野紘
【語り】目黒泉
第3回「父が娘に語る経済の話。」バルファキス
「格差は生まれるのはなぜ?」「どうして全てのものに値段がつくの?」「景気・不景気があるのはなぜ?」等々、誰もがこんな素朴な疑問にぶつかったことがあるはず。ギリシャの元財務大臣の父親が、十代の娘に向けて、シンプルで心に響く言葉で経済の本質を語り、それらの謎を解く糸口を与えてくれる。経済学者の中山智香子さんの指南で、経済は専門家だけのものだけでなく皆が向き合わなければならない問題だと考える姿勢を学びながら、私たち一人ひとりにとっての「等身大の経済学」を学んでいく。
【指南役】中山智香子(東京外国語大教授・経済学者)
【生徒役】本田望結
【朗読】花澤香菜 下野紘
【語り】目黒泉
第4回 竹取物語
誰もが子どもの頃に語り聞かせてもらう定番の昔話「かぐや姫」。その原型が「竹取物語」だ。だが、「そんな話もう耳にタコだよ」と思うなかれ。そのディテールには、びっくりするようなエピソードが満載。さまざまな人間ドラマが巧みに織り込まれているのだ。この作品をSFととらえると、その楽しみ方が何倍にもなるという木ノ下裕一さんに、古典作品のとてつもない豊かさを教えてもらう。
【指南役】木ノ下裕一(「木ノ下歌舞伎」主宰)
【生徒役】本田望結
【朗読】花澤香菜 下野紘
【語り】目黒泉
10代向けに特化した夏休みスペシャル「100分de名著forティーンズ」をあらためて企画しようと思ったきっかけは、「今、メディアにできることって何だろう」という自身への問いかけからでした。年々不信が高まるメディア、とりわけテレビのあり方。本当の情報はネット上にあるのであって、もはやテレビにはないのではないか。それどころか、テレビは、真実を隠蔽する働きすら果たしているのではないか。そんな意見を数多く聞くようになりました。
私自身、真摯に番組作りに取り組んできたつもりでしたが、身近な知人、友人の間でも「最近、テレビはどうかしているのではないか」との意見を聞くようになりました。それどころか「もうテレビを見なくなっている。動画でみるのは、もっぱらYouTubeに代表される、短時間かつ見たいときにみることができるコンテンツ」という意見が、特に若い世代からよく聞かれます。
テレビの役割はもはやなくなってきているのだろうか。ネット上のコンテンツで十分なのではないか。そんな疑問が折に触れてわきあがってきます。そんな折、あるトークイベントで、年配の方からこんな意見をいただきました。
「『100分de名著』という番組に生きる力をいただいている。80歳を越えて、ますます何かを学びたいという意欲を刺激されている。これからもずっと続けてください」。
救われるような思いでした。とともに、番組に対して、こんなことを感じていただけるようなポテンシャルがあるとすれば、もっともっと若い世代にもみてもらうように努力しなければと痛感しました。その中で、今後テレビが果たしていくべき役割も見いだせるのではないかとも思いました。
では、若い世代に対して、この番組は何ができるのか? 真っ先に思いあたったのは、ある悲しいニュースのこと。9月1日という日に、青少年の自殺が著しく増加するという統計です。夏休みが終わり再び登校が始まる際、大きなプレッシャーがのしかかるのが原因の一つだとのことでした。番組がもっている力など、わずかなものにすぎないかもしれない。でも、こうした人たちの生きづらさを少しでも取り除き、明日を生きる力になるような番組が作れたら……。そんな思いがきっかけとなり、企画が立ち上がったのです。
こうした理由から、実は、4冊の本を選ぶ際に基準とした裏テーマを設けました。それは、本のジャンルは違えど、「いのちのかけがえなさ」を伝えてくれる本を選ぼうというものです。
若松英輔さん、竹内薫さん、中山智香子さん、木ノ下裕一さん、いずれの講師の方も、この思いの部分を共有してくださり、それぞれの専門の立場から、見事にこの「いのちのかけがえのなさ」というテーマにつながるお話をしてくださいました。
深く感謝したいのは、生徒役になってくれた、鈴木福さんと、本田望結さん。ふだん感じている等身大の生活感覚から、ティーンズのみんながきいてみたいと思うような的確な質問を繰り出してくれました。朗読の下野紘さん、花澤香菜さんは、プロの声優の技を駆使して、キャラクターごとに七色の声を当ててくださり、各アニメーターの優れたアニメーションとも相まって、それぞれの物語、世界観が立体的に立ち上がっていきました。
そして、何よりも、今回、初司会を担当してくれた加藤シゲアキさん。ご縁あって、小説やコンサート、自身が脚本・演出を担当したお芝居を拝見し、その才能に驚くともに、多くの若い人たちを惹きつけていく力に瞠目した私は、この力を若い世代向けの番組作りのためにお借りできたらと願っていました。今回の番組で、自分の家族のエピソード、作家として深く考えていることなどを折に触れて交えてくださり、ティーンズに寄り添う司会として大きな役割を果たしてくださいました。深く感謝したいと思います。
おかげさまで、番組は大きな反響をいただくことができました。最初の問いでもあった「今、メディアにできることって何だろう」という問いに対しても、少しだけ答えにつながるものを見出すことができました。厳しい競争の中、仕方のない部分でもあるのですが、今、メディア界では、視聴率中心主義、短期的な成果のみを追い求める傾向が席捲しています。それを受けて番組も短時間化が急速に進んでいますし、デジタルによる配信へのシフトが進んでいます。激流にもまれる中、ともすると、一瞬の視聴率を上げるために大事なものを見失ってしまうようなことや、質よりも数値に置き換えらる成果のみが一人歩きするようなことも生じがちです。
今回の「ティーンズ」での制作体験は、厳しい競争の中でも、大事なものは絶対見失わないという原点を確認することができました。今後も、この原点を忘れることなく、真摯に番組作りに取り組んでいきたいと思っています。
第1回の担当は『ケシュ#203』

<プロフィール>
ケシュ#203(ケシュルームニーマルサン)
仲井陽と仲井希代子によるアートユニット。早稲田大学卒業後、演劇活動を経て2005年に結成。NHKEテレ『グレーテルのかまど』などの番組でアニメーションを手がける。手描きと切り絵を合わせたようなタッチで、アクションから叙情まで物語性の高い演出得意とする。『100分de名著』のアニメを番組立ち上げより担当。仲井希代子が絵を描き、それを仲井陽がPCで動かすというスタイルで制作し、ともに演出、画コンテを手がける。またテレビドラマの脚本執筆や、連作短編演劇『タヒノトシーケンス』を手がけるなど、活動は多岐に渡る。オリジナルアニメーション『FLOAT TALK』はドイツやオランダ、韓国、セルビアなど、数々の国際アニメーション映画祭においてオフィシャルセレクションとして上映された。

ケシュ#203さんに“人は何で生きるか”のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。
ロシアがウクライナを侵攻しておよそ半年が経ちました。
私たちがトルストイの作品を担当するのは「戦争と平和」以来、およそ10年ぶりの二回目です。今このタイミングで非戦・非暴力を訴え続けたロシアの作家と向き合うことは、作品の内容のみならず大きな意味を持つと思い、制作に臨みました。
今回は「forティーンズ」ということで、十代にも親しみやすいようにキャラクターは可愛くデフォルメして描きました。また、キャラクターたちのやり取りも心情がきちんと伝わるよう、感情豊かな演技をつけています。


素朴なストーリーですが、大切なことが伝わるように心を砕いて制作しました。「人は何で生きるのか」、そのメッセージが今を生きる若者たちに伝わり、改めて平和について思いを巡らせるようなアニメーションになっていれば幸いです。

100分de名著 for ティーンズは大変な長編であり、凄惨な場面もあれば亡霊や妖怪も出てくるので、忠実に表現すべきところは細かく真摯に描写することに努め、説明が難しいところはアニメならではのギミックを使い、簡潔に且つユニークに表現できるようにこだわって制作しました。
第2回・第3回の担当は『川口恵里(ブリュッケ)』

<プロフィール>
演出・イラスト:川口恵里(ブリュッケ)
多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。2016年より株式会社ブリュッケに所属。アニメーション作家/イラストレーターとして、TV番組、企業CM、音楽PV、ワークショップ等、幅広く手掛ける。線画台を用いた、空間と光を活かした画づくりが得意。

川口恵里さんに“WHAT IS LIFE? 生命とは何か”と“父が娘に語る経済の話。”の、アニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。
ロシアがウクライナを侵攻しておよそ半年が経ちました。
私たちがトルストイの作品を担当するのは「戦争と平和」以来、およそ10年ぶりの二回目です。今このタイミングで非戦・非暴力を訴え続けたロシアの作家と向き合うことは、作品の内容のみならず大きな意味を持つと思い、制作に臨みました。
今回は「forティーンズ」ということで、十代にも親しみやすいようにキャラクターは可愛くデフォルメして描きました。また、キャラクターたちのやり取りも心情がきちんと伝わるよう、感情豊かな演技をつけています。


第3回「父が娘に語る経済の話」では、市場社会における銀行の役割を解説するために、企業家を「タイムトラベラー」、銀行家を「ツアーガイド」と見立てています。
これらの見立てをそのままアニメーションで活かし、且つ、短い尺で銀行家の役割のイメージを持ってもらうための工夫として、事業家と銀行家が、事業計画の中を旅するような世界観を構築しました。拡大していく事業のイメージは、具体的な倉庫・店舗・工場の組み合わせで表現し、その後ろで業績グラフが伸びていくようにしてみました。そんなところもご覧頂けると嬉しいです。

100分de名著 for ティーンズは大変な長編であり、凄惨な場面もあれば亡霊や妖怪も出てくるので、忠実に表現すべきところは細かく真摯に描写することに努め、説明が難しいところはアニメならではのギミックを使い、簡潔に且つユニークに表現できるようにこだわって制作しました。
第4回の担当は『高橋昂也』

<プロフィール>
高橋昂也 1985年 愛知県生まれ。
東京藝術大学大学院デザイン科修了。
アニメーション作家・イラストレーター。フリーランス。
テレビ、博物館、ゲームなどの分野で活動する傍ら、自主作品の制作も行なう。

高橋昂也さんに“竹取物語”のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。
これまで「100分de名著」でアニメを作らせていただいた中で、いつもモチベーションの一つとして目指してきたのが、(自分の主観ですが)誰よりも原書に忠実に視覚化することでした。しかし今回は「for ティーンズ」で「竹取物語」ということで、いつもと違う姿勢で向き合うことになりました。
誰もが知る日本最古の物語でありながら、時代を超越したテーマを扱っているこの作品。原書に忠実にという方針は無くした方が面白くなるという確信が湧きました。
平安時代に限定した話に見えないよう、自由に解釈した現代の若者向けのアニメを目指しました。サブカルチャー寄りの描写を多用して、こんな竹取物語もありなんだ、という幅を見せることで、夏休み終盤の憂鬱な時期、空想の飛躍を肯定するようなアニメにできていればいいなと思います。