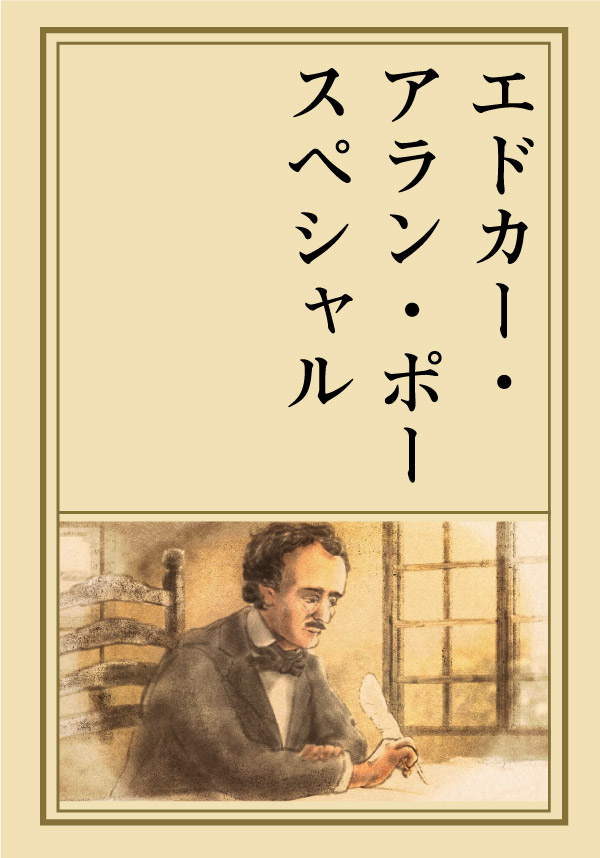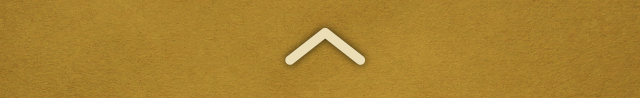19世紀半ば、アメリカ文学の黄金時代を担った作家の一人、エドガー・アラン・ポー(1811-1849)。世界初の名探偵が活躍する推理小説、ゴシック風ホラー、SF海洋冒険小説、思索と哲理に満ちた詩等々…さまざまなジャンルをたったひとりで切り開いていきました。その耽美的で退廃を極めた華麗な文体の作品群は、今も多くの人たちに愛され、読み継がれています。ポーの代表作「アッシャー家の崩壊」「黒猫」「モルグ街の殺人」「アーサー・ゴードン・ピムの冒険」などの作品を通して、「欲望とは?」「美とは?」「人間とは?」そして「文学表現の可能性とは?」…といった奥深いテーマをあらためて見つめなおします。
ポーのデビュー小説ともいえる「瓶の中の手記」は1833年、24歳のとき。雑誌の創作コンテストで一位を獲得し一躍人気作家に。作品ごとに自在に変幻する作風は他の追随を許さず、19世紀アメリカ文学を代表する作家のひとりに数えられるまでになりました。そんなポーの作品群には彼自身の人生が色濃く反映しています。幼くして母を失い父も行方不明。育てられた養父からも途中で見捨てられ天涯孤独の中、文学でひとり身を立てようとしたポー。その後も、雑誌社からの解雇、妻との死別、新たな恋人との間の婚約破棄など不幸は続きます。しかし、そうした人生を栄養分にするかのごとく、自身の文学性を高めていきます。
ポー作品の魅力はそれだけではありません。ポーは、創作者にして批評家という才能だけではなく、卓越した編集者としての能力も大いに発揮しました。何よりも「読者」を読み、同時代の読者たちが好む文学ジャンルの約束事を読み取ってはそれをずらして新奇を狙い、これまで存在していなかったジャンルを次々に創造していったのです。そんなポーの活躍は、やがてボードレール、ジュール・ヴェルヌ、ナボコフ、スティーブン・キング、江戸川乱歩といった世界中の作家たちに大きな影響を与えることになるのです。
番組では、アメリカ文学者の巽孝之さんを指南役として招き、ポーの文学を分り易く解説。代表作4冊に現代の視点から光を当て直し、そこにこめられた【人間論】や【美学】【文学表現の奥深い可能性】など、現代の私達にも通じる普遍的なテーマを読み解いていきます。
各回の放送内容
第1回「ページの彼方」への旅~「アーサー・ゴードン・ピムの冒険」~
SFの起源の一つともされる本作品の主人公アーサー・ゴードン・ピムは冒険心やみがたく捕鯨船に密航。ところが、船員の反乱、暴風雨との遭遇…と数々の困難にぶつかる。なんとか生き残ったピムは救出されたものの、そのまま南極探検に向かうことに。その果てに驚くべき光景を目にすることになるのだった。さまざまな壁にぶつかる主人公の旅自体が、作家ポー自身の人生と重なる。ピムが最後に遭遇する真っ白な瀑布は、自分を解雇したホワイト氏への揶揄でもあり、物語の成立条件そのものを飲み込み「ページの白」の彼方へと読者を送り込む仕掛けとも読めるのだ。第一回は、ポーの人生と創作過程を象徴するピムの冒険行を読み解き、「ポーにとって文学とは何か」という根源的なテーマを解き明かしていく。
【指南役】巽孝之(慶應義塾大学名誉教授)
【朗読】北村一輝(俳優)
【語り】よしいよしこ
第2回 作家はジャンルを横断する~「アッシャー家の崩壊」~
陰鬱な屋敷に旧友を訪ねた語り手の「私」。神経を病んで衰弱した友と過ごすうち、恐るべき事件が次々に起こっていく。病み衰えて死んだはずの妹の甦り、あたかも詩の朗読にリンクするように崩壊を始める屋敷……。ゴシック風ホラーの傑作といわれるこの作品は、「散文」と「詩」が見事に融合し、驚くべき効果を発揮している。いわば、雑誌編集者としてさまざまなジャンルを横断し続けたポー自身を象徴するような物語だ。第二回は、「アッシャー家の崩壊」の執筆背景も合わせて掘り下げ、文学ジャンルを横断し融合させながら新たな表現の可能性を切り開いたポーの創造力の秘密に迫っていく。
【指南役】巽孝之(慶應義塾大学名誉教授)
【朗読】北村一輝(俳優)
【語り】よしいよしこ
第3回「狩るもの」と「狩られるもの」~「黒猫」~
妻と一緒に可愛がっていた一匹の黒猫。アルコールの痛飲によって精神をむしばまれた男は、その猫を虐待するようになり発作的に殺してしまう。だが男は、その猫の呪いを受けるかのように破滅していくのだった。執筆当時のアメリカは禁酒運動が盛んな時代。徹底的に欲望が抑圧される社会の中で、いびつに歪んでいく人間の精神をこの物語は見事に象徴化して描いているという。第三回は、「黒猫」を読み解くことで、抑えつければ抑えつけるほど歪んだ形で噴出してしまう人間の欲望の怖ろしさについて考察する。
【指南役】巽孝之(慶應義塾大学名誉教授)
【朗読】北村一輝(俳優)
【語り】よしいよしこ
第4回 ミステリはここから生まれた~「モルグ街の殺人」~
パリの町で真夜中に母娘が殺された。殺人現場は鍵がかかっていて窓も閉まったまま。この不可解で残酷な事件の解決のために世界文学史上初の名探偵デュパンが登場。その鋭い分析的知性は彼のビジネスの武器でもあった。推理の果てに浮かび上がるのは想像もしないような犯人。その犯人像には、当時アメリカ南部を席捲していた黒人差別の状況が色濃く反映していた。最終回は、世界初の推理小説を読み解くことで「人種差別の問題」や分析的知性すら資本と化す資本主義の根深さに迫っていく。
【指南役】巽孝之(慶應義塾大学名誉教授)
【朗読】北村一輝(俳優)
【語り】よしいよしこ
個人的な話になり恐縮ですが、エドガー・アラン・ポーとの出会いは、中学2年生の頃でした。真っ黒い装丁だったので、おそらく創元推理文庫の「ポオ小説全集」だったと思います。きっかけは、とある少年向け雑誌で組まれた推理小説特集。世界の名探偵が挿絵入りで紹介されていました。シャーロック・ホームズのシリーズは、もちろん夢中になって読んでいたのですが、彼に先駆けて誕生したのがオーギュスト・デュパンだということ、ホームズの設定はことごとくデュパンに影響を受けていることをその記事で初めて知りました。「これは何としても読みたい」と思って図書館で探し出したのが「ポオ小説全集」だったのです。
「モルグ街の殺人」がポー作品で初めて読んだ作品。なんといっても、貴族的な雰囲気を醸し出す、どこか退廃的なデュパンがかっこよかった! その後「マリー・ロジェの謎」「盗まれた手紙」を興奮しながら続けざまに読んだのをよく覚えています。まだまだあるのだろうと思ったら、こちらで打ち止め。どうしてもっと書いてくれなかったんだ!と地団太を踏みました。ホームズにはまっているクラスメイトに自慢げに、「ホームズは実はデュパンの真似なんだよ」と得意げに吹聴しましたが「誰それ?」という冷たい扱い。かえって、私のデュパン熱が燃えあがっていきました。
とりわけ私の印象に残ったのは、デュパンの次の台詞。
「真実というものはたえず表層に存在するものだ」
普通、真実は、深層に存在すると思うのが常識。当然、その頃の自分もそう思っていました。だから、深い意味がわかったわけではないのですが、この逆ばりにとても痺れました。その後も、ずっと心のどこかにはりついたまま、何か物事を考えるのに行き詰ったときに立ちもどる原点として、働き続けた言葉だったように思います。もちろん真実は深層にあるかもしれないが、それに迫っていくためには、まずは表層に徹底的にこだわり、思考しぬくこと。最初から深層なるものを勝手にイメージしてはいけない。表層にこそ鍵がある…そんな風に、私はとらえました。これはデュパンが物事を推理する根本姿勢。もしかしたら、ポー自身が作品を書いたり、編集者として仕事をする上での信条だったのかもしれません。
デュパンに再会したのは、意外なことに、ジャック・ラカンというフランスの精神分析医の著作の中ででした。ラカンをいつか番組企画に…という野望をもって少しずつ読み続けているのですが(…といっても、難解すぎて道のりははるかに遠そうです)、彼の分析の中の一つにデュパン・シリーズの「盗まれた手紙」の分析があって、これがとんでもなく面白い。これを説明しだすと、ほとんど紙幅が尽きてしまいそうなので省きますが、ラカン理論のあるエッセンスが凝縮したような論文で、ここまで深読みさせてしまうポーという作家って!と驚愕しました。ポーの作品を個人的な楽しみだけにとっておくのはもったいない。番組企画を考えてみようと思ったのでした。
ポーの代表作を何作か読み進めていた数か月後、不思議な巡り合わせがありました。英文学者の小川公代さん(「100分deパンデミック論」で「ダロウェイ夫人」を解説してくださった研究者です)のお誘いで、研究者同士で交流する食事会に参加することになったのですが、その会の中心にいらしたのが、今回、講師を担当した巽孝之さんだったのです。私自身は、浅学なものですから、巽さんのお仕事を「SF評論家」メインだと思い込んでいて、たしか、このときも、自分の好きなサイバーパンクだとかフィリップ・K・ディックの話ばかりしていたような記憶があります。ポーの研究がライフワークの一つだということを全く存じ上げず、大変失礼なことをしてしまいました。
後日あらためて研究室をお訪ねしたときも、開口一番「フィリップ・K・ディックの作品を4つ並べて解説なんてどうでしょう?」という依頼をしてしまいました。ところが、巽さんの口から「私個人として、まずどうしてもやりたいのは、エドガー・アラン・ポーなんです」という言葉が飛び出しました。お恥ずかしながら、この瞬間に初めて、巽さんのポーへの情熱を知ったのでした。
巽さんの解説の魅力は番組ですでにご覧になっているので、今更一つひとつを振り返りませんが、なんといっても、膨大な背景知識の情報量の凄さでしょう。作品を読んだだけではわからない執筆背景、ポーが置かれた時代状況、そしてポー自身の人生…。その圧倒的に細やかな知識に支えられて、作品にこれまでとは異なる角度から光が当たり、今までにない深読みができたと思います。紙面を借りて、巽さんに深く感謝します。
私が偏愛するデュパンに関していえば、「ポー=デュパン説」を展開してくださったことに痺れました。当時、「読み書き能力」というものが、新たなビジネスの武器として注目され始めた時代。ポーも自らも雑誌編集者(マガジニスト)として、あるいは作家として、この「読み書き能力」を武器に商売を始めたのだと思います。あらゆるジャンルを渉猟し、その網の目を読むようにしてヒット作を雑誌で掘り起こす編集者としての能力、そして、その能力は、作家としても遺憾なく発揮されます。名探偵デュパンよろしく、「表層」に目を凝らし、人々が今、何を求めているかを「読む」。その徹底した解析を通して、表現方法を磨きぬき、これまで誰も生み出したことがないような「詩と小説の融合」「SF」「推理小説」「ホラー小説」といった全く新しいジャンルを生み出していく。そこにこそ、ポーの天才性があったのではないか。
ポーの人生と時代背景と作品の網の目を巽さんが読んでくださったおかげで、ポーの新たな側面が浮かび上がりました。その意味で、巽さんご自身も「読みの達人」であり「マガジニスト」ではないか。さらに言えば、私が担当しているプロデューサーという仕事も、極めてデュパン的です。私自身も、デュパンやポーにあやかって、ジャンルの網の目を深く読める眼力と思考力をもちたいと切に願っています。
今回、スポットを当てるのは『川口恵里(ブリュッケ)』

<プロフィール>
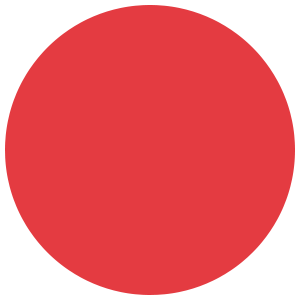
川口恵里さんに「エドガー・アラン・ポー スペシャル」のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。
今回「アーサー・ゴードン・ピムの冒険」、「アッシャー家の崩壊」、「黒猫」、「モルグ街の殺人」4作品をすべて担当させていただきました。
私は、最初に読んだ「アーサー・ゴードン・ピムの冒険」で、ピムとポーの共同執筆という書き出しを信じて、最後まで、ピムが実在する人物と思っていました・・・
4作品を通して、ポーの文章における場面描写は、非常に緻密かつ鮮明と感じられる箇所が多く、ポーの描く世界観には説得力のある画が重要なのだろうなと考え まずは、じっくり描きおこしていくことにしました。
とはいえ、どの作品にも、脳天をかち割られたり目をくり抜かれたり眼球が飛び出していたり・・・残虐な殺害や死が多く登場し、どこまでどう描いたら良いかなと悩みました。
結局、作品を読み進めていくうちに、ポーの描写の生々しさグロさを詳細に再現することで、痛々しさや気味の悪さを強調する方向ではなく、ストーリーの展開やキャラクターに感情移入できる画を目指すことなのかと感じるようになりました。
例えば、
壁の中に塗り込まれた妻、棺桶に入れられたマデライン、煙突に押し込まれた娘、木に吊るされた猫 等のキャラクター達の無言の主張が伝わるように、出来事の形跡と空気感で展開を楽しめるように小気味良い恐怖を描けるように目指しました。