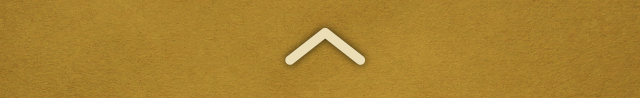武田将明
(たけだ・まさあき)
英文学者、東京大学准教授
1974年、東京都生まれ。専門は18世紀イギリス小説。東京大学大学院人文科学系研究科を経て、ケンブリッジ大学でPh.D. を取得。現在、東京大学総合文化研究科准教授。2008年に「囲われない批評 東浩紀と中原昌也」で第51回群像新人文学賞評論部門を受賞し、日本の現代文学についても批評活動を繰り広げている。訳書にダニエル・デフォー『ペストの記憶』(研究社)、同『ロビンソン・クルーソー』(河出文庫)、サミュエル・ジョンソン『イギリス詩人伝』(共訳、筑摩書房)など。共著に『二〇世紀「英国」小説の展開』(松柏社)、『イギリス文学と映画』(三修社)、『『ガリヴァー旅行記』徹底注釈注釈篇』(岩波書店)など。
◯『ペストの記憶』 ゲスト講師 武田将明
パンデミックと記録文学
『ペストの記憶』は一七二二年にイギリスで出版された書物です。原題はA Journal of the Plague Year。「ペストの年の日誌」の意で、日本でもこれまで『ペスト』や『疫病流行記』などの訳題で読まれてきました。
内容は、H・Fという架空の語り手が、一六六五年に実際にロンドンで発生したペストに関する見聞を記録し、そこに自分の意見や批評を加えたもの。ペストによる死者の数や、当時の法令などがそのまま引用されていて、何も知らずに読めばペストを体験した人の手によるルポルタージュ(記録文学)だと思うでしょう。一方で、短篇小説になり得るようなドラマチックなエピソードや、ある人物の胸が張り裂けそうな悲しみに感情移入した箇所などもあり、単なる記録からは逸脱していることも事実です。
『ペストの記憶』は、『ロビンソン・クルーソー』(一七一九年)の作者として知られるダニエル・デフォーが、同書刊行の三年後に発表した文学作品です。一六六〇年にロンドンで生まれたデフォーは、六五年のペスト流行時はまだ五歳。しかもそのときは家族と共に地方に避難していたため、実際にはペスト流行を体験してはいません。そんなデフォーが六十歳となった一七二〇年、隣国フランスのマルセイユでペストが発生します。ロンドンにも危険が及ぶのではないか。過去のペスト流行から学べることはないか。そんな危機感と使命感を持ってデフォーが執筆に取り組んだのが、『ペストの記憶』なのです。
フィクションでもありノンフィクションでもあるようなこの作品には、実際にペストを体験した人でなければ書けないような迫真の描写と、事実そのものの力があふれています。彼はなぜ、このような作品を書くことができたのでしょうか。そこには、十七~十八世紀のロンドンに生きたデフォーという怪物的な人物の生き方も大いに関係しているように思われます。詳しくはのちほど解説します。
さて、デフォーといえば、さきほど書名を挙げた『ロビンソン・クルーソー』が圧倒的によく知られています。二十八年間、南米の無人島で生活した一人の男の記録として書かれたこの本は、伝統的な道徳や価値観の通用しない場所でサバイブする個人を描いたという点で、近代小説の誕生を告げる作品とも言われます。また未知の世界への冒険を描いた児童文学としても親しまれてきました。
ところが二十世紀に入ると、「ヨーロッパ人が『未開』の地に赴く」という構図から、同書は植民地主義の問題と絡めて活発に議論されるようになります。『ロビンソン・クルーソー』を批評的に読み換えた作品も多く発表され、例えばノーベル文学賞を受賞した南アフリカ出身の作家J・M・クッツェーによる『敵あるいはフォー』(一九八六年)という名作があります。『ロビンソン・クルーソー』は、時代の流れの中でしばしば批判を受け、様々な改作も試みられました。しかし、そうした反応を引き起こしながら読み続けられていることこそ、生きた古典である証とも言えるでしょう。
『ペストの記憶』もまた、時代を超えて読み継がれてきました。同じく感染症を題材にしたアルベール・カミュの小説『ペスト』(一九四七年)に影響を与えたことは間違いないでしょう。カミュは『ペスト』のエピグラフ(巻頭に記す題辞)にデフォーの著作(『ペストの記憶』ではないですが)の一節を引用しています。
『ロビンソン・クルーソー』が常に同時代の視点で読み直されてきたように、いま私たちが『ペストの記憶』を読むにあたっては、当然ながら、二〇二〇年に世界を席巻した新型コロナウイルス感染症との関係に思いを馳せないわけにはいきません。隔離生活、ソーシャルディスタンス、失業の問題……読んでみると驚くのですが、『ペストの記憶』に記された逸話の多くは、私たちにとってあまりに馴染みのあるものです。
しかしここで、一六六五年のロンドンと二〇二〇年の日本との驚くべき類似性を発見し、「三百五十年を経ても人間の行動パターンは変わらないな」といった教訓だけを得ても、この作品を一時的な興味で消費することに終わってしまいます。せっかく読むのであれば、パンデミックという異常事態に置かれた人間の生々しい姿を『ペストの記憶』から取り出し、十七世紀のロンドンの人々のうちに人間の本質を読んでみたい。私はそう考えています。
また『ペストの記憶』の特徴は、ペスト流行に苦しみ、不安に苛まれる人々の姿を描くだけでなく、感染の拡大を防ぐために様々な施策を実行し、外出できない市民の生活保護にも気を遣う当時の行政や、反対にパニックを逆手にとって儲けようとする連中、世迷言を叫んで人々を惑わせる狂信者の姿も描いている点です。つまり、危機に立ち向かう個人の感情・思考だけでなく、危機における行政のあり方や、人間同士の関係のあり方についても、この本は多角的な示唆を与えてくれるのです。
それらは、私たちが現在置かれている「コロナ危機」という状況が何なのかを、冷静に見直すための助けとなるでしょう。本講では、第1回で個人の内面、第2回で市民生活、第3回で市民と行政、第4回で危機を記録することの意義を考えることで『ペストの記憶』の持つ多面性を解き明かしていきます。
私にとってデフォーは、長年仇のような存在でした。というのも、私はジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』を読んだことをきっかけに十八世紀英文学を専攻するようになったのですが、同時代人だったスウィフトとデフォーは実は非常に仲が悪かったのです。しかし、スウィフトとは様々な面で対照的なデフォーにも徐々に魅力を感じるようになり、イギリス留学中に膨大な彼の著作を読み漁りました。その後、縁あってまずは『ロビンソン・クルーソー』を訳し、次いで二〇一七年、『ペストの記憶』の訳書を上梓するに至りました。
さきほど、デフォーはある種の使命感を持って『ペストの記憶』を執筆したと述べました。彼の強烈な意志の力には遠く及ばないものの、私も二十年以上デフォーと付き合い、そしてコロナ危機を体験することになった研究者としての使命感を胸に、この『ペストの記憶』をみなさんに紹介したいと思います。