これまでの放送 2016年5月21日(土)の放送
 躍動感あふれる2台のピアノのための組曲「スカラムーシュ」。
躍動感あふれる2台のピアノのための組曲「スカラムーシュ」。
フランスの作曲家ダリウス・ミヨーは、思いがけないことを
きっかけにこの曲を作り上げました。いったい彼に何が起きたのか…。
思わず踊り出したくなるようなノリノリ音楽の秘密に迫ります。
“リオ”の旋律に燃えた男
~ミヨーの「スカラムーシュ」~
躍動感あふれる2台のピアノのための組曲「スカラムーシュ」。フランスの作曲家ダリウス・ミヨーは、思いがけないことをきっかけにこの曲を作り上げました。いったい彼に何が起きたのか…。
思わず踊り出したくなるようなノリノリ音楽の秘密に迫ります。


“ありもの"で大サービス!?

ミヨーの「スカラムーシュ」は、実は、書き下ろしではありませんでした。パリ万博が開かれた1937年ころ、多忙を極めていたミヨーは、2人の人気女性ピアニストから「万博のコンサートで演奏する曲を書いてほしい」との依頼を受けます。考えあぐねた彼は、既に書き上げた劇用音楽を流用することを思いつきます。
モリエールの演劇『空飛ぶ医者』のBGMとして書いた音楽を用いて、「スカラムーシュ」の第1楽章と第3楽章を書き、シュペルヴィエルの演劇『ボリヴァール』のBGMとして書いた音楽を用いて、第2楽章を作曲。
そしてこれら3つをまとめ、2台のピアノのための組曲に仕上げました。当時、コメディを上演し、パリの人々を楽しませていた劇場「スカラムーシュ」の名に因んで、曲の題名を「スカラムーシュ」と名付けたのです。ミヨーは、コメディのために書いた音楽を中心に構成することで、人々を楽しませることが出来ると考えたのかもしれません。
異国のメソッドに開眼

エクサン・プロヴァンスに生まれたダリウス・ミヨーは、幼いころから勝手きままにピアノを弾くのが好きでした。
父親に勧められ音楽院でバイオリンを学び始めますが、型にはまった伝統的な音楽教育に嫌気がさし、バイオリニストの道を放棄。作曲家になることを決意しますが、音楽院での講義は退屈でした。彼は在学中から、伝統にとらわれない独自のユニークな作品を書き始めていたのです。自由でおおらかなミヨーの周りには、ジャンルを超えた様々な交友関係が広がっていきました。
そんな彼の友人の一人、外交官のポール・クローデルから、「ブラジルに駐在する秘書として一緒にリオデジャネイロに同行してほしい」との依頼が寄せられます。
およそ2年間リオに滞在したミヨーは、現地の音楽や、それを楽しむ人々の熱狂に衝撃を受けました。
帰国後、彼は、ブラジル音楽の持ち味を取り入れたいくつもの作品を生み出していきます。その特徴を最も色濃く打ち出した作品の一つが「スカラムーシュ」でした。西洋の作曲家には珍しかったブラジル音楽を通しての体験は、ミヨーの作品に、彩りと輝きを与えたのです。
体感!ノリノリワールド


「スカラムーシュ」の中で特に有名な第3楽章「ブラジルの女」に注目。思わず踊りだしたくなるノリノリを感じるのはなぜか…。
【ノリノリポイント![]() 「リズム」】
「リズム」】
ミヨーは、ブラジル音楽の様々なリズムをこの曲に盛り込んでいます。ブラジル北東部の人たちがよく演奏している音楽「バイアォン」のリズムや、ブラジルの格闘技などで聴かれる音楽「カポエイラ」のリズムが、ピアノの旋律によって表現されています。
【ノリノリポイント![]() 「シンコペーション」】
「シンコペーション」】
ミヨーは、拍子の強弱を変化させる技「シンコペーション」も取り入れています。例えば、「タンタン・タンタン…」という拍子を「ンタンタ・ンタンタ…」といった具合に変化させる手法です。ミヨーは、この「シンコペーション」を「スカラムーシュ」の随所に散りばめていますが、冒頭の主旋律で聴くことが出来ます。
【変身!日本の歌も乗り乗り~】
身近な日本の曲を題材に実験してみてください。ブラジル音楽のリズムで躍動感が出て、さらに、シンコペーションによって躍動感が増してノリノリになっていくことが実感出来ると思います。
ゲスト

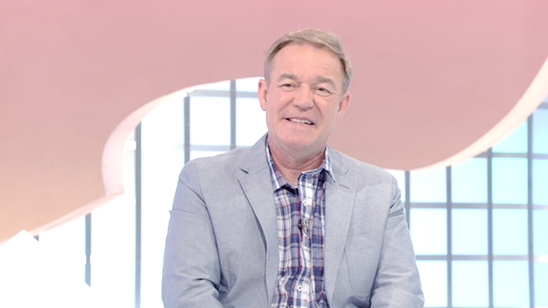
ダニエル・カール(タレント)
profile
山形弁研究家
日本に来てかれこれ40年
楽曲情報
- 「スカラムーシュ」から 第1楽章・第3楽章 ブラジルの女
- ミヨー
- 下山静香(ピアノ)、高木洋子(ピアノ)

「シンコペーションですよ「ンダンダ」の山形弁が…」