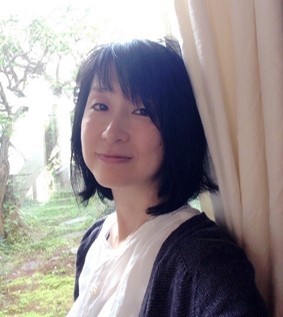名脚本家が見た「福島」、そして10年目の春
こんにちは!
FMシアター『はるかぜ、氷をとく』演出の小林です。
今日は昨日もここでお知らせした通り、
今作の脚本をご担当いただきました、
渡辺あやさんのコメントを公開させていただきます!
渡辺さんは2003年に映画『ジョゼと虎と魚たち』で脚本家デビューを果たしたのち、映画『メゾン・ド・ヒミコ』『天然コケッコー』などを手がけ、NHKドラマでは連続テレビ小説『カーネーション』や阪神・淡路大震災15年特集ドラマ『その街のこども』といった名作を世に送り出してきました。
2018年にNHKで制作した大学の自治寮の存廃問題を取り上げた京都の地域発ドラマ『ワンダーウォール』は、SNSなどを中心に話題を呼び、劇場版も公開されるほどの人気となりました。
そんな渡辺さんが、今回ご自身(ほぼ)初のラジオドラマへの挑戦で、原発事故から10年となる福島を描くことを決めた背景にはどんな思いがあったのか、今回の作品にはどのような思いを込めたのか、聞きました。
――最初に今回の作品の提案を受けた時、
どのように感じましたか?
なぜ脚本執筆を引き受けようと思われたのでしょうか?
最初は小林ディレクターから脚本依頼のメールとともに企画書が送られてきたのですが、一読してとてもむずかしく、けれどもとてもいい企画だと思いました。
東日本大震災や原発事故というとてつもなく複雑で大きな出来事を背景にしながら、あくまでも描こうとしているのが母親や子供ひとりひとりの心の動き、関係性であること、そしてそこにしっかり視点を据えた上で丁寧な取材を重ねてこられたことがよく伝わってきました。
とはいえ脚本家としては、まずそのむずかしさの方にビビってしまい「自分が引き受けられるかどうかはわかりませんが、すばらしい企画だと思うので絶対がんばってください」みたいな逃げ腰の返事をしたのを覚えています。
――12月には実際に福島を訪れて、取材もされました。
それまで渡辺さんの中で抱いていたイメージや見方が
変わった部分などはありましたか?
「当時あの事故をどうとらえ、この10年どのように考えてこられたのか」ということについて、福島の親御さん側のことは小林ディレクターの取材が充実していたのと、私自身もほぼ同世代の母親でもあるせいかよく理解できたのですが、一方子供たち側がどうだったのかは全く想像がつかなかったので、福島に行って直接インタビューをさせてもらいました。主に高校生さん10人くらいに話を聞かせてもらったのですが、結果いかに自分がこれまで「被災地」という雑な前提だけで福島やその子供たちをながめていたかに気付かされる瞬間が多々ありまして、その中でももっとも深く心に残ったのは、彼らの軽やかさや明るさ、そして優しさでした。この子たちを、今日まで福島の親御さん方は本当によく守り育ててこられたなあと胸がいっぱいになって、その感動がそのまま作品に反映されたと思います。
――そうした気づきや発見を受けて、
今回のドラマでは何を、どのような視点で
伝えたいと考えたのでしょうか?
実はこの作品の執筆中に、私自身も人生においてとても大切なものをひとつ失くすことになりました。そのタイミングがここであったことに妙な縁を感じつつ、物語を書きながら私も登場人物たちと一緒に戸惑い、悩み、考え続けることができました。
「はるかぜ」が「氷をとく」とき、そこには破壊と再生が同時に起こっているのだと思います。
なにかを失くした時、私たちは必ず新しいなにかを得てもいるとも言え、心からそう信じられる人間になることが、人生というむずかしいものを豊かに生きていく唯一の道なのかもしれません。
そんなことを登場人物たちの上からでも下からでもなく、同じ地平で語り合えた時間は本当にありがたいものでした。願わくば私以外の方にとっても、この作品が少しでも心の友のようなものになれたら、こんなに嬉しいことはありません。
渡辺さんのコメントがあまりに素晴らしいので、もう私から言うことは何もありません。というか、何も書けません。
明日はご出演の皆さんのコメントをご紹介します。
そちらも、お楽しみに!!
お知らせ FMシアター はるかぜ、氷をとく ディレクター ラジオドラマ 番組
投稿時間:12:00