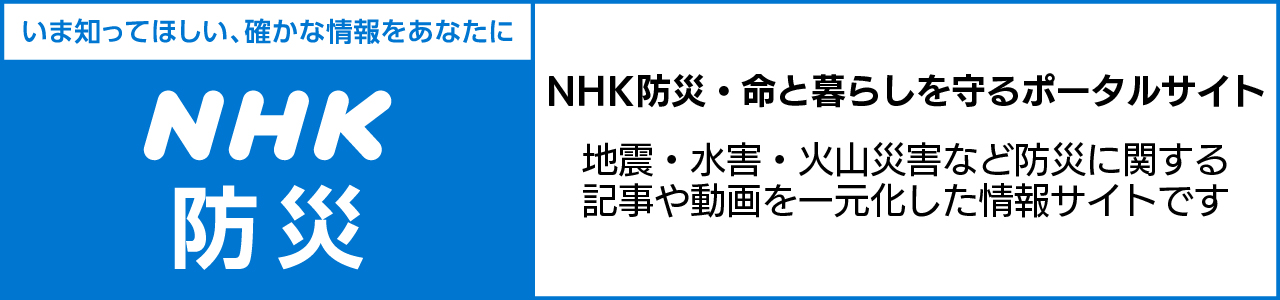77人が犠牲になった広島土砂災害の発生から今年で10年。広島では防災マップ作りや防災を学ぶ運動会など、住民が主導する命をまもる取り組み「わがまち防災」が広がっています。
▼関連記事はこちら
土砂災害から身を守るには? ハザードマップ 避難の3つのポイント
“線状降水帯”による大雨 土砂災害で77人が犠牲に
2014年8月20日の未明、広島市を襲った突然の豪雨。わずか3時間で平年1か月分の大雨が降り、市内166か所で土石流やがけ崩れが発生。多くの人が逃げる間もなく被害にあい、77人が犠牲となりました。

8月19日、広島市では夕方から断続的に雨が降っていました。
特に被害の大きかった安佐南区八木地区の雨量を見ると、日付が変わるころ、雨はいったん弱まっていました。しかし、20日午前1時すぎから雨が強さを増していきます。

広島市の上空で、雨雲が急激に連続して発達していきました。「線状降水帯」です。

午前1時15分、気象台と県は「土砂災害警戒情報」を発表。
午前2時すぎ、猛烈な雨が降り始めました。

特に被害が大きかった安佐南区八木地区は、午前3時ごろから次々と土砂崩れに見舞われました。
山沿いに建つ団地にも突然、土石流が流れ込みました。窓を突き破った土砂が部屋を埋め尽していました。

この時の土砂災害の犠牲者は広島県の調べで、関連死含め77人。家屋損壊は500棟以上。床上・床下浸水は4000棟以上にのぼりました。

被害拡大の3つの要因は?
非常に大きな被害が出た広島土砂災害。その要因は何だったのか。
広島大学 防災・減災研究センター長、海堀正博さんは3つの理由をあげています。

① 住宅が密集する山のふもと
「写真や映像でわかるように、山のふもとに多くの住民が家を構えて住んでいます。土石流やがけ崩れの土砂が、すぐ住宅地にまで及んで被害を出してしまう環境ができていました」(海堀さん)

② 短時間で記録的な大雨
「線状降水帯が発生し、ものすごい量の雨が短時間で降り、がけ崩れや土石流が集中的に発生しました」(海堀さん)
③ 対応の難しい深夜
「災害の発生した時間帯が、避難行動などの対応が難しい真夜中でした」(海堀さん)
こちらのグラフは、災害が発生した日の雨量の10分ごとの推移を表したものです。

「8月20日になっても、降った雨の合計はまだ50ミリに達していない状況。ところが、午前1時半頃から突然増え、あとは強くなる一方。そして土石流やがけ崩れが集中発生する時間帯を経て、4時過ぎぐらいに避難勧告(当時)が発令されるという状況だったのです」(海堀さん)
このような深夜の状況では、避難するのか、家にとどまるのか、判断は非常に難しいと海堀さんは指摘します。
「例えば自分の家が谷の出口で、土石流が小さい規模で来ても直撃するような場所だったら、家にいたら危険です。こういうときは近くの別のお宅に逃げるだけでも全く違います。また、家の中で2階などのより高い場所への“垂直避難”といった、その場で命を守ることのできる最善の行動をするというのも大事な選択肢になります」(海堀さん)
平時から、自分ならどうするか考えて、シミュレーションしておくことが非常に大切です。
進められる土砂災害への対策
広島では施設を整備するなど、土砂災害への対策が進められています。
■防災ライブカメラの設置
がけ崩れや土石流の前兆をいち早く捉えるため、危険箇所にライブカメラの設置が進んでいます。夜でも撮影できる赤外線カメラで、24時間確認できます。周辺の人たちの逃げ遅れを防ぐことが目的です。

現在、広島市のホームページや防災アプリでは、14か所の映像を見ることができます。

■住民による雨量計の設置・運用
住民が雨量計を自ら設置して、町内会で運営する取り組みも始まっています。データはインターネットで配信され、リアルタイムで雨量を確認できます。自分が住む場所の詳しい状況をピンポイントで知ることができるのです。

■砂防ダム・雨水管の建設
防災に向けた施設の拡充も進められています。10年前の土砂災害で最も多くの犠牲者を出した安佐南区・八木地区では、山の斜面に砂防ダムが33か所つくられました。

地下には、2万2000立方メートルの雨水がためられる雨水管が設置されました。

■新たな広域避難路の建設
八木・緑井地区で進められているのは、新たな広域避難路の建設です。2車線の道路で、住民の避難や緊急車両の通行をスムーズに行うためです。

すでに1.5キロが開通。令和6年度中には、新たに400メートルが完成し、国道とつながる見通しです。

■行政の対応も改善
また当時、行政の「避難勧告(当時)」が遅かったという指摘がありました。海堀さんは、「深夜、非常に多くの住民に指定避難所や指定緊急避難場所に行ってもらうことは、途中の危険も考えると、なかなか発令できないという躊躇(ちゅうちょ)が行政にあったのでは」と分析しています。
土砂災害のあと、行政の対応も改善されました。
「避難の基準雨量をしっかり定めて、避難指示を発令する仕組みもできました」(海堀さん)
■砂防ダムの防災効果 過信は禁物
この10年間で国や県などは、広島市内でおよそ140基の砂防ダムをつくりました。
砂防ダムの防災効果は大きいものがありますが、海堀さんは “過信はしないよう” 注意を促します。
「基本的に砂防ダムで止められるのは土石だけで、水は止めらない。想定以上の雨が降れば、影響範囲は大きくなりうるので、ダムができても過信してはいけない」(海堀さん)

住民主導で命を守る取り組み「わがまち防災」
地域コミュニティでの自主的な防災活動も見直されています。
広島市安佐南区の伴(とも)学区。山あいにおよそ1万2000人が暮らしています。2021年8月、豪雨によって土石流やがけ崩れが発生しました。
被害のあった家屋では、裏山の一部が崩れ、大量の土砂が襲いました。

家族は避難して無事でしたが、家には大量の土砂が流れ込みました。あと片づけには、地域の人たちがたくさん集まり、5日間かけて泥や石を取り除きました。

主導したのは、自主防災会です。この地域では、1999年の土砂災害をきっかけに自主防災会の活動が盛んになりました。およそ50人の防災士が中心となり、「わがまち防災」に取り組んでいます。

わがまち防災① 独自の防災マップ「わがまち防災マップ」を作成
防災会が4年前から作成している「わがまち防災マップ」には、地域の防災情報がきめ細かく記載されています。
ハザードマップを元にして作られているので、自分の家が「土砂災害警戒区域」に入っているのかを把握できます。番号がついているのは避難所。想定される避難ルートも示されています。

防災会が運営する自主避難所も記載。「家から避難所が遠く、避難が難しい」という住民の声をまとめ、防災会が関係機関に掛け合いました。

災害時に役立つ公衆トイレやAED、公衆電話の場所も記載しています。

安佐南区伴学区の自主防災会の会長・加藤栄治さんは「わがまち防災マップ」の活用方法を説明します。
「皆さんの家に全部1枚ずつ配って、廊下や玄関など見やすく目のつくところに貼ってもらう。毎日それを注意して見ることによって、避難場所や避難ルートを頭の中に入れていただく」

わがまち防災② 指定避難所から家が遠い人のために自主避難所を設置
自主防災会では、行政とも協力しながら、集会所やごみ処理施設などあわせて5つの自主避難所を設けています。

「とりあえず一時避難場所をつくろう、気軽に自主的に避難できる場所を確保しようということから始まった。そこに防災士が駆けつけて態勢を整えます」(伴学区自主防災会の水嶋節郎さん)
わがまち防災③ 防災かまどベンチ・まきや食料の備蓄場所を設置
ふだんはベンチで、緊急時には炊き出しができる“防災かまどベンチ”。過去の避難所での経験をきっかけに設置を決めました。
「行政が食べ物を用意したのが(避難した)次の日の昼ごろだった」
「“共助”で、ともに助け合ってその場をしのごうと」
現在、防災かまどベンチと、まきと食料の備蓄場所を、2か所設けています。今後も増やしていく予定です。


わがまち防災④ 住民が楽しめる防災イベントを開催
かまどベンチの使い方を防災士が教え、炊き出しをふるまうイベントも開催。地域の人たちが親睦を深める機会にもなりました。
「楽しいことをしないかぎり人は来ない。一方的な話を聞くだけじゃおもしろくない。喜んで参加・体験できないといけない」(防災会・水島さん)

わがまち防災⑤ 災害時に役立つことを体験する「防災運動会」
2019年には、新たに防災運動会も始めました。担架を使ったり、土のうを作ったり、災害時に役立つことを運動会の種目として体験します。

災害時に助けを呼ぶ予行練習、「大声競争」もあります。
子どもから高齢者まで、楽しみながら防災力を高める。それが、ここの「わがまち防災」です。
自主防災会会長の加藤さんに、地域が協力して防災に取り組む「わがまち防災」の原動力はどんなところにあるかを聞きました。
「(2021年の豪雨で被害となった)たった1軒の家の土砂災害に延べ200人を超える人が集まりました。地域の皆さんのご協力でできたので、非常に感謝しております。“わがまちのことはみんなで守る” という心です」(加藤さん)

この記事は、明日をまもるナビ「広島土砂災害10年 命をまもる わがまち防災」(2024年5月26日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。