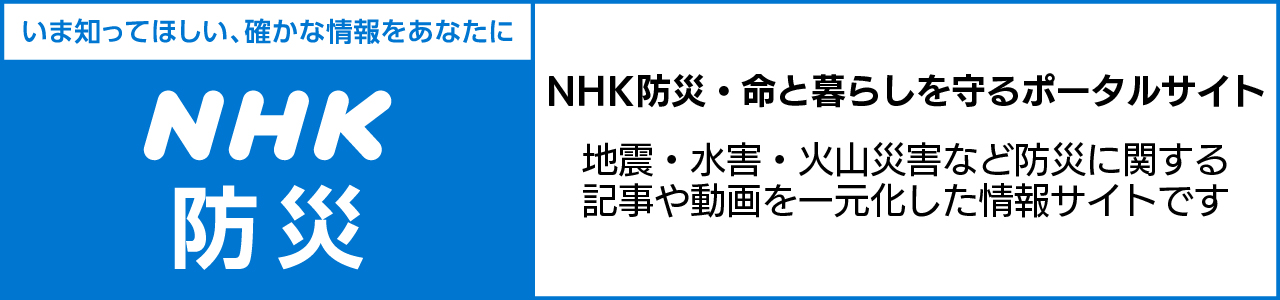能登半島地震でも大きな被害をもたらした「液状化現象」。 実は、液状化のおそれがある場所は全国各地に存在します。埋め立て地のみならず、内陸部でも起こる可能性も! 固い地面がなぜ液状化するのか、実験で再現。 身近な場所での発生傾向を調べる方法についてもわかりやすくお伝えします。
▼関連記事はこちら
「液状化現象」もし起きたらどうする? 事前の対策は?
液状化のおそれがある場所は全国各地に
2024年元日に起きた能登半島地震。液状化現象が広い範囲で発生し、甚大な被害が出ました。
中でも住宅被害が集中した新潟市西区。地震が発生したときの防犯カメラの映像です。
歩道橋の柱の根元から水が湧き出る様子がとらえられていました。
水はまたたく間に広がり、15分後には片側の道路が冠水しました。
こちらの地図は、震度6弱で液状化が発生するおそれのある場所とその確率を表したもので、防災科学技術研究所の先名重樹主任研究員などがまとめました。赤や紫など色が濃い部分が、発生確率の高いところを示しています。

液状化は日本全国のさまざまな場所で発生するおそれがあります。
液状化を中心に地盤災害の研究を長年続けている東京電機大学名誉教授の安田進さんは、「液状化現象」への正しい理解が必要だといいます。
「現在では“液状化”という言葉はよく知られていますが、どんなことが起きるか、リスクはあまり知られていません。ぜひ正しい知識を身につけていただきたい」(安田さん)

「液状化」とは? 発生のメカニズム
安田さんは、液状化が起こるのには「3つの条件」があるといいます。
① 砂の地盤
② 砂がゆるく堆積している
③ 地下水位が浅い

「(ことし1月の能登半島地震で)新潟・石川・富山で被害を受けたところは、この3つの条件がそろっている。こうした場所を震度5弱以上の地震が襲うと液状化するのです」(安田さん)
また今回、被害の大きかった新潟市では、60年前の新潟地震(1964年)でも同じ地区で液状化が起きていました。
「“再液状化”と言いますが、同じような地盤のところで起きているのです」(安田さん)
■液状化を実験で再現
どのように液状化現象が起きるのか、実験で再現します。
こちらは、透明な容器の中に砂と水を入れ、「砂の地盤・ゆるく堆積・地下水位が浅い」の液状化の3条件を再現したものです。
砂の上にはミニチュアの家と車を載せてあります。砂の表面は固まっています。
容器を載せたテーブルをたたいて、振動を加えます。すると、すぐに水が出て、車が沈み、家も傾きました。
表面がかたい地面でも、条件が重なると地震などの振動によって、このように地盤が液状化するのです。
「地震によっては、これがもう2秒から4~5秒で実際に起こります」(安田さん)
そのメカニズムをイラストで解説します。

① 通常時
「通常時の地盤は、茶色い部分は砂粒で、水色の部分は水で、砂粒の隙間のところに水がある状態です。建物の重さを砂と砂のかみ合わせで、ぐっと支えています」(安田さん)

② 液状化発生
「地震がやってくると横方向に揺すられ、この砂粒どうしのかみ合わせがぽっと外れます。かみ合わせがバラバラになると、これは水の中に砂粒があるだけであり、泥水のような状態になります」(安田さん)

③ 沈下・傾斜
「この泥水のような状態で、その上に家などの重いものがあると沈下し、軽いものは浮き上がる。これが液状化した状態です。この状態では水の圧力が高くなって水がふき出し、砂も一緒にふき出して、地盤全体が沈下してくるということになる」(安田さん)

液状化の影響 健康被害も
今回、新潟県では、家が傾くなどの住宅被害は、およそ9500件にのぼるとみられています。
新潟市西区の男性の自宅も、液状化により亀裂が入りました。玄関の扉は外れて、直すことができません。床が傾く中での生活は、心と体に大きな負担がかかるといいます。

自宅の裏では、隣の家の土台が崩れかけています。
「ここにはもう住めない。(地震が)もう一回来たら、完全にやられる。それでは遅すぎる」

こちらの女性が住む2階建ての住宅は、廊下が少し傾いていますが、建物に大きな被害がなかったため、今も家族と住んでいます。
しかし地震のあと、体調がすぐれず、家が傾いていることが原因ではないかと考えています。
「家が傾いていると、精神的に…。頭痛がひどくなった。歩いていると、家が傾いているから、(感覚が)おかしくなります」

■健康に影響を及ぼす “家の傾き”
家の傾きと健康への影響をまとめました。(日本建築学会「液状化被害の基礎知識」から)
傾きの大きさによって、めまいや頭痛、吐き気、睡眠障害などの健康への影響が挙げられています。

「健康被害が明らかになったのは、2000年の鳥取県西部地震。住民から“どうもおかしい”という声があがり、自宅の傾きを測ったら、このような関係がわかりました」(東京電機大学・安田さん)
緩やかに傾斜した地盤では大きな被害も
日本海に面した石川県内灘町では、ことし1月の地震で、建物が傾き、道路が大きく変形するなど甚大な被害が出ました。

地盤工学に詳しい、高知大学の原忠(はら・ただし)教授が、現地の調査を行いました。

町の北側に位置する西荒屋地区では…。
「80センチくらい移動している。ベランダの基礎はここにあったが、土がすべって下流側に向かっていってしまったんですね」(原さん)

これは「側方流動」という現象です。
液状化により、ゆるやかな斜面が、平らになろうとして地盤が動いたと考えられています。

内灘町は能登半島地震の震源域から100キロほど離れています。
なぜ、大きな被害が出たのか?謎を解く鍵が「側方流動」です。
内灘町の現地調査に入った東京電機大学・安田さんも、被害が出た場所の地形の特徴に注目しました。
「緩やかに傾いている地盤です。そこに住宅を建てたので、土地が段になっています。液状化して、傾斜している地盤は水平になろうとして、水平方向に動いたのです。通常の液状化の場合は、重いものが沈み、軽いものが浮き上がる、鉛直方向の動きだけなのですが、さらにそこに水平方向の動き、地盤全体が水平に動く “側方流動”が起きたと考えられます」(安田さん)

2011年の東日本大震災では、液状化の被害は、主に海沿いの埋め立て地で発生しました。
ところが内灘町の液状化現象は、海沿いではなく、内陸に集中。とくに被害が大きかったのは、風によって運ばれた砂が堆積した「砂丘」に分類される地域でした。
調査にあたった防災科学技術研究所の先名重樹(せんな・しげき)主任研究員の分析です。
① 「日本海側は非常に砂が多い地形が多くあります。季節風で常に砂が飛ばされているので、この内陸部の方にやわらかい砂が堆積します」

② 「地下水位が高い(浅い)こと、あとは地震動の継続時間が長い。こういったものが合わさると液状化しやすい」

「砂丘の背後で起きる側方流動は、1983年の日本海中部地震でもたくさん起きて、測量すると5メートルほどずれていたことがわかりました。 ただ、その後、それだけの大きな被害が起きていなかったこともあって、実は対策が遅れていました」(安田さん)
阪神淡路大震災での液状化
地盤全体が移動する側方流動には、もう一つのタイプがあります。
1995年に発生した阪神淡路大震災。神戸市のポートアイランドでの様子です。
「護岸や岸壁で支えられている人工島の地盤が、液状化や振動の影響で、水平方向に最大5メートルぐらい押し出された。工場施設や橋などに甚大な被害が出ました」(東京電機大学・安田さん)


その後、護岸の側方流動の対策が研究され、神戸の復旧や、東京の首都高速道路の護岸でも対策が行われました。
液状化のリスク 身近な場所での“発生傾向”を調べる
では、一軒家の購入や新築するときに、液状化のおそれはないかどうか、知る手がかりはないか。
実は、地盤の液状化についてインターネットで簡単に調べることができます。
今回は国土地理院の「重ねるハザードマップ」を使います。いろいろな災害のリスクを調べることができますが、今回は石川県内灘町を例に、「液状化」の発生傾向を調べてみます。

国土地理院HP「重ねるハザードマップ」
※NHKサイトを離れます
① まず「石川県内灘町」と入力します。
「重ねるハザードマップ」の左側の項目を選択していきます。
② 「すべての情報から選択」から「土地の特徴・成り立ち」を選び、「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を選択すると、地図に色がつきます。


③ 地図の色がどのような発生傾向を表しているのか、凡例を見るとわかります。(画面左「解説凡例」⇒「くわしい解説」を選択)
紫・赤と色が濃くなると液状化の発生傾向が高まります。

内灘町を見ると赤色・紫色が目立ちます。
「とくにこの紫色の線上になっているところは、今回の地震で甚大な被害を受けたところです」(安田さん)

「重ねるハザードマップ」では地形も調べることができます。
① いったん「選択情報のリセット」を選びます。

② 次に左側の「地形分類」を選択します。

この黄色い部分が「砂丘」です。選択すると、土地の成り立ちや自然災害リスクの情報も表示されます。

先ほどの画像と見並べて比較することもできます。
左側が「地形の特徴」、右側が「液状化の発生傾向」です。

「例えば、家が建っていてアスファルトになっている下に、砂丘や砂の緩い地盤があることもある。いまこういった情報がネットで見られるようになっているので、ぜひ見ていただきたいです」(安田さん)
最新の情報は、自治体から出ている「液状化危険度マップ」も参考になります。

自治体の「液状化危険度マップ」と、今回ご紹介した国土地理院の「重ねるハザードマップ」、両方を活用して液状化のリスクについて、調べてみましょう。
この記事は、明日をまもるナビ「知っておこう 液状化現象」(2024年5月12日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。