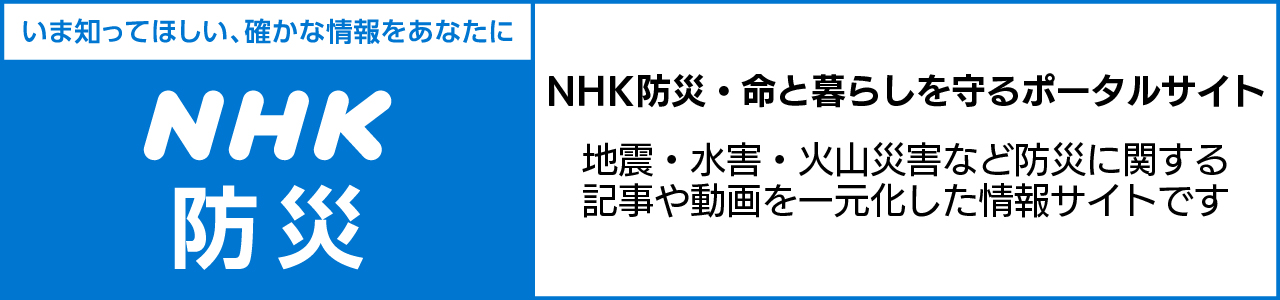この30年間で、最大震度7を記録した地震は6回も発生しています。首都直下地震で想定される負傷者の約85%は建物倒壊と家具類等の転倒・落下によるもの。揺れ対策を徹底することが、自分や大切な人の命を守るカギとなるのです。自宅を耐震強化する重要性と、身近な器具を使った室内の危険防止策を紹介します。
この記事は、明日をまもるナビ「大地震 揺れからのサバイバル」(2021年5月16日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。
これだけは知っておきたい、大地震から身を守るポイント
▼自宅の耐震性がどうなのかを知り、必要に応じ耐震強化を。
▼家具は正しく固定し、置き場所にも注意。
▼キッチンには危険が多いことを理解し、コツコツ対策。
自宅の“災害リスク”を知っておこう
突然襲ってくる大地震。1995年の阪神・淡路大震災では、犠牲者の死因の8割が、建物の倒壊、家具の転倒などによる“圧死”でした。倒壊した建物のほとんどが、1981年以前の旧耐震基準の家屋だったのです。1981年6月以降は、“最大震度6以上でも倒壊を免れるよう”に強化された「新耐震基準」が設けられていました。そして、阪神・淡路大震災の教訓を基に、さらに2000年に耐震基準が見直され、木造建築で土台、柱、梁(はり)の接合部を金物で固定するなどの「さらに強化された耐震基準」になりました。
その後に発生した熊本地震では、新しい耐震基準の建物とそれ以前のものでは、倒壊した割合に、やはり、大きな差が出ています。1981年5月以前の「旧耐震基準」の建物はほとんどが被害を受け、倒壊・全壊は3割近くに及びます。

防災の指導に取り組んでいる首都大学東京・東京都立大学名誉教授の中林一樹さんは、自宅の耐震性がどうなのかを知ることが大切だと説きます。

「木造建築の場合、ほとんどの自治体で耐震性を上げるための制度があり、耐震診断を無料で行う自治体も多くあります。まずは自治体に診断してもらい、必要なら工事をしてもらう。目安として150~200万円くらいかかります。自治体によって異なりますが、工事費の半額、あるいは一定金額まで助成などの補助があります。家族の命が守れるとしたら決して高くはありません。自宅の耐震強化が地震対策の第一歩。自分の家が壊れて命を落とす、こんな悲劇はありません」(中林さん)
室内の危険から命を守る!8つの対策
建物の耐震補強をしていたとしても、家の中には危険がたくさんあります。
熊本地震ではテーブルが倒れ、食器などは散乱、足の踏み場もない状態になりました。倒れる家具にも注意が必要で、その威力を大阪市立大学教授の宮野道雄さんが実験で確かめています。

人体模型にセンサーを取り付け、タンスが倒れたときに受ける衝撃を計測。タンスの重さは中身が入ると約150kgありますが、その衝撃の威力は4トン以上と判明しました。室内にはさまざまな危険があり、ケガをするだけでなく、場合によっては命に関わるのです。室内の危険から命を守るために、8つの対策の対策を紹介します。
①つっぱり棒


多くの家庭で利用されている揺れ対策が“つっぱり棒”。取り付ける位置に注意しましょう。タンスが地震で揺れるとき、手前の部分が支点になるため、手前に取り付けると、揺れたときにタンスとつっぱり棒の間に隙間ができて外れてしまいます。奥に取り付けるのが正しい使い方で、揺れてもつっぱり棒が動きを抑えるため、タンスは倒れません。


注意点は天井板の裏に木材があるところなど、強度の高い部分に取り付けることです。天井に大きめの板をあてることで強度を補うことができます。家具の下に入れるストッパーを併用すると、さらに倒れにくくなります。
②L型金具

つっぱり棒は強い地震に対して万全ではありません。家具の転倒防止には、壁や柱に直接固定する“L型金具”が最も確実。最近は賃貸でも許可される場合も多いですが、取り付ける際は事前に管理者などに確かめましょう。固定する際に大事なのは「倒れてもいい場所」に配置して固定することです。
③滑り止めテープ

本棚をしっかりと固定しても、大地震では本が飛び出してくるので危険です。滑り止めテープを本棚の前端に貼るだけで、本が出してしまうのを防止します。本は同じ高さでそろえ、棚板の高さも合わせることでも飛び出し防止になります。

④家具の配置

家具を固定しても大地震では倒れることがあります。倒れても命にかかわらない安全な場所に配置してから固定するのが大事です。ドアの近くに家具を置くと、倒れてドアが開かなくなるので注意しましょう。
⑤倒れた家具をすぐに起こさない
大きな地震は何度も続けて起きる可能性があります。もし家具が倒れても、すぐに起こすとまた倒れてしまうこともあり危険です。しばらくは倒れたままにしておきましょう。
⑥逃げ込みスポットを確保する
寝室やリビングなどの長く滞在する部屋では、いざという時に逃げ込めるスポットを確保する。直下地震対策として1~2秒でたどり着ける安全な場所を家族全員が覚えておくこと。
⑦寝室にスニーカーを用意
大地震の揺れがおさまった後の生活を考えると、足を守ることも大事です。片足でもケガをすると動けなくなります。寝室にスニーカーを用意しておけば、家の中が散乱したなかを歩いてもケガの防止になります。
⑧寝るときはカーテンを閉める
大きな揺れでガラスが割れる可能性があります。室内に飛び散るのを防ぐために、寝るときはカーテンを閉めておきましょう。

「地震対策の基本は、最初に来る揺れに対してどう備えるか。そこで命が守られたら次がある。建物の耐震化、家具の固定、家具の配置をしっかりと備える。防災を忘れないこと、忘れる災害も“忘災”です。忘れずに “防ぐ”防災に取り組んでほしい。」(中林さん)
キッチンが危険!?今すぐできる揺れ対策グッズ
自宅を究極の防災基地にしているのが、危機管理アドバイザーの国崎信江さん。物は徹底的に置かないようにするのはもちろん、家具は備え付け、テレビは壁掛けにするこだわりようです。
国崎さんが大地震が起きると家の中でいちばん危険な場所だと指摘するのがキッチンです。例えば電子レンジは、重さ20キロ近いものもあるので、足元に市販の滑り止めマットを入れてがっちり固定。包丁はもちろん、使った道具はすぐに洗って収納しています。
さらに大切なのが、引き出しや扉から中身の飛び出しを防ぐこと。引き出しが飛び出すと逃げ道がなくなってしまうため、国崎さんはさまざまな対策をしています。

①引き出し

押すと解除されて開く、子どもの指はさみ防止器具を活用。
②冷蔵庫の扉

パチンとはめ込むタイプのストッパーを活用。
③食器棚の取っ手

ヘアゴムをねじってつけることで、飛び出し防止グッズに。
④棚のガラス

割れたときにガラスが飛び散るのを防ぐため、飛散防止フィルムを貼る。
⑤食器

滑り止めシートを活用。サイズの違う食器の間に挟むと飛び出しにくくなる。
どれも市販されている身近なもので防災対策ができるのです。

「例えば防災費を毎月3000円など一定額決めて、今月は飛散防止対策をしよう、来月は家具の固定をしようと決める。できるところから『コツコツ防災』で安全を積み重ねていっていただきたいと思います」(国崎さん)
新たな脅威“長周期地震動”
2011年の東日本大震災では、新宿などの超高層ビルがユラリユラリと大きく揺れました。日本の超高層ビルが初めて“長周期地震動”に見舞われた瞬間で、こうした揺れはマグニチュード8クラスの巨大地震で起きる特有の現象だといわれています。
長周期地震動は、震源から何百キロも離れた遠い地域まで伝わり、平野部では長時間にわたって続くのが特徴。東日本大震災では、東京からさらに400キロ離れた大阪市の超高層ビルも大きな揺れに襲われました。市内の52階建てのビルでは、およそ10分間、最大1メートル以上の揺れが確認されています。
揺れの周期によって被害を受ける建物は異なります。ガタガタとした小刻みな短い揺れの場合、高層ビルは揺れを吸収し、大きく揺れて被害を受けるのは低い建物です。
一方、周期が2秒から10秒という長い揺れの長周期地震動では、高層ビルは一撃で大きく揺れます。超高層ビルが林立する現代、長周期地震動は新たな脅威となっています。
長周期地震動では、高階層ほど家具の転倒、落下、移動が多発するというデータがあります。

「高層ビルは揺れ対策として『制震』装置などを導入して、ポキッと折れるようなことは絶対ないようになっています。ただ、マンションでも上層階は揺れが大きいので、家具の転倒対策は万全にしておくことが大事です。大地震が起こるとエレベーターは必ず止まります。上層階に住んでいる人は移動が大変なので、1週間は下りなくても生活できるように、食料、水、携帯トイレなどの備蓄があると安心です」(中林さん)
長周期地震動が起きたらどうするか?大きな揺れがきたらどうするか?日頃からしっかりとイメージして、対策しておきましょう。もしものときに備えて、今すぐ準備したい10の備蓄品もぜひご覧ください。