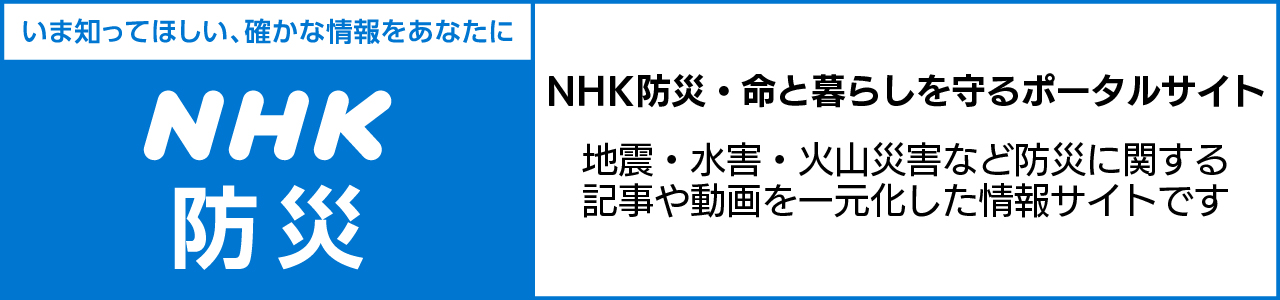防災力向上に向けてアクションするヒントをお伝えしている「チャレンジ!BOSAIアクション」。今回のテーマは「わが町の防災を考えよう」。子どもと大人が一体となった、ユニークな取り組みを紹介します。佐賀県大町町での親子参加の防災イベント。神奈川県逗子市では、地元のハザードマップをもとに小学生が防災アプリを開発。京都では、子どもたちが町を歩いて防災を学ぶ「ミッションX」が行われました。地域の防災に役立つヒントを楽しみながら見つけましょう!
「チャレンジ!BOSAIアクション」は視聴者の皆さんが自ら防災力向上に向けてアクションするヒントをお伝えしているシリーズです。第6弾の今回は「わが町の防災を考えよう」というテーマで、防災キッズ団の皆さんと一緒にお伝えします。
まーちゃん(12歳)とおーちゃん(10歳)は福島県在住。家族で作成した動画が人気のクリエーターです。鈴木楽(たの)さん(10歳)はいつもはお姉さんの夢さんと一緒ですが、今回はひとりでの参加です。

防災の化身・ヤモリン博士(京都大学防災研究所 矢守克也教授)のナビゲートで楽しく勉強しましょう。
今回のテーマは「わが町の防災を考えよう」です。
「わが町といっても、住んでいる町によって様子が違う。海がある町・ない町、川が流れている町・いない町。町によって災害の特徴も違ってきます。いろいろな地域の取り組みをヒントに、自分の町の特徴をよく知って、防災のことを考えていきましょう」(ヤモリン博士)

皆さんも自分の町だったらどうか当てはめて考えてみてくださいね。
被災体験を受け継ぐ 親子防災イベント(佐賀県大町町)
最初は佐賀県大町町(おおまちちょう)で行われた、親子で防災を考えるイベントを紹介します。
大町町は、たびたび水害に見舞われています。2019年8月、線状降水帯が原因で起こった佐賀豪雨。1時間に100ミリ以上の記録的な大雨で佐賀県内では3人が亡くなったほか、一時、3000人近い人が避難を余儀なくされました。

大町町では、1メートルを超える浸水で救助要請が続出。工場の油も流出し、甚大な被害をもたらしました。

さらに、その2年後。およそ1週間にわたって大雨が降り、再び町の広い範囲が浸水しました。

今回の防災イベントは、こうした体験をもとに企画。まず当時を振り返り、何が一番大変だったのか話し合いました。
企画者「水が家の中に入ってきている様子です。リビングなどが水浸しになって、みんながふだん使っている電気・ガス・水道が止まってしまいます。これらが使えなくなったら生活できますか?」
女の子「しんどい…」

イベントを企画した公門寛稀さん(大町町・地域おこし協力隊)は、「知識を得たり、体験を通じて、身につけてもらって、助け合える人材になってほしい」と狙いを話しています。
この日は、親子でキャンプを体験。避難生活で役立つ術を学びました。

初めての体験に子どもたちからは「楽しい」との声が。とくに盛り上がったのは、火おこしです。

「まず楽しむ。それが自分のことになり、そして家族を守れる。まずやってみて、できたという体験があればいいと思います」(アウトドアインストラクターの羽白卓馬さん)
防災に役立つ!地理院地図を使ってみよう!
「災害はその土地の特徴によって違ってきます。ハザードマップの“ハザード”とは“危ない”という意味。水害や土砂崩れなどの危ない災害がどこで起きやすいかを示してくれている地図です。もう一歩進んで勉強してほしいのは、昔のわが町がどんな土地だったかを知ることです」(ヤモリン博士)
昔はどんな土地だったのかを知るにはどうしたらよいのか?
国土地理院のホームページ「防災にも役立つ地理院地図の使い方」で手軽に調べられます。
「土地の成り立ちから災害リスクを知る」(国土交通省・国土地理院)
※NHKサイトを離れます

今回は、佐賀県大町町を例に調べてみます。
改めて水害の時の写真を見てみると、大きく曲がりくねっている白い道路のようなものが見えます。これは六角川という川です。

■国土地理院地図の見方
まずは国土地理院のホームページ「土地の成り立ちから災害リスクを知る」をクリック。“土地の成り立ち”とは、今の土地がどのようにできてきたかということです。
ここで大町町の昔の地形の特徴を調べます。今回の例、「佐賀県 大町町」と打ち込んで検索。
地理院地図の画面を拡大してみると、地図で白く塗られている川の周りに青いところがあります。これはかつて六角川が流れていた跡「旧河道」です。

「川はずっと同じところを流れているわけじゃない。この地域には曲がりくねった昔の川があることが、この地図を見ると勉強できます」(ヤモリン博士)
(参考)旧河道とは
「地図はいまも悪夢を知っている/耳慣れない“キューカドー”」(災害列島)
地図には、他にもいろんな色が付いています。その部分をクリックすると、小窓が開き、場所の特徴を教えてくれます。
薄い緑色は何を表しているのか?
クリックすると「氾濫平野」と書いています。川が氾濫して、あふれてできた平たい土地のことです。川が曲がりくねって流れているので、このあたりの土地は低く、河川の氾濫に注意が必要です。

ところどころにある黄色いところは「自然堤防」。洪水が土砂を運んでできた土地で、丘のように少し高くなって残っているものです。

「自然堤防はちょっと高くなっているため、水害で危ない、川があふれたときなどは、まず逃げるにはいいところです」(ヤモリン博士)

このように調べてみると、一つの地図からいろんなことがわかります。皆さんもぜひご自分の「わが町」の地図をチェックしてみてください。
こどもの視点で!小学生が防災アプリ開発(神奈川県逗子市)
神奈川県逗子市は、海と山に囲まれ、大勢の観光客が訪れる都市です。地震が起きた場合、津波や土砂崩れなどの災害が想定されています。

逗子市の小学生たちが作ったのは、防災アプリ『ずし防くん』!

地図をクリックすると、崖くずれや浸水箇所などの危険な場所や、避難場所などの情報を見ることができます。

例えば、アプリの地図から、避難場所に指定されている「逗子葉山高校」をクリックすると、「グラウンドが広いから多くの人が避難できる。給食室で料理ができる」と、情報が表示されます。

アプリは、2023年の9月1日の防災の日にリリースされました。作成するプロジェクトに参加したのは、市内5つの小学校から集まった4年生から6年生までの18人。子どもたちは、市のハザードマップを使って、地域をくまなく歩き、独自に取材。集めた情報をアプリの中に盛り込みました。

アプリのキャラクラー「ずし防くん」の声担当・島楓さん(逗子小学校4年)。
「意外と低いところとか知らない避難場所が多くて。アプリを作ってそういうのが考えられるようになりました」
このアプリを企画したのは、逗子市商工会の女性部の皆さんです。子どもたちの親として、ある願いがありました。
「市が提供するハザードマップは、子どもが読み取るのは難しいと感じていて、登下校のときなどに被災したときに、“みずから考えて行動できるように”という願いがあります」(逗子市商工会女性部 北川淡美さん)
小坪小学校5年の北川景悠さんと伊藤天陽さんは、アプリづくりに携わったことがきっかけで、帰宅途中などに町の情報を集め続けています。
この日は、アプリを一緒に作った地元の防災士の服部誠さんに誘われて、高台の避難場所までを歩きました。

駐車場にあるハザードマップを発見したふたり。服部さんのタブレットのマップと違うことを見つけました。確かめると、この駐車場のハザードマップは平成25年3月のものを参考にしていました。
「防災安全課にちょっと古いですよって言いに行こうか。ナイス視点!」(防災士・服部さん)

さらに、道路では、避難場所へ誘導する表示が消えていることにも気がつきました。

「大人が気づいていないことを、ふたりともすばらしい発想ですね」(防災士・服部さん)
ふたりは津波が来ることを想定して、海岸の近くから高台の避難場所まで実際に走って、タイムを測ってみました。
「3分49秒。(この地区は)津波がくるのは9分だっけ?逃げ切ったぞー!」

子どもたちの視点を生かした『ずし防くん』はアップデートを目指しています。
「アプリの出来栄え自体は、専門家の人たちに劣るけど、それでも市の役に立てることを示せるひとつの機会になったので、とてもいい出来栄えだったと思いました」(沼間小学校5年 出村哲平さん)
■防災のヒント:土地の特徴に応じた対策を用意する
「みんなが住んでいる町でも必ずハザードマップは大人の人たちが作っているので、まずそれをちゃんと勉強しましょう。その上で自分たちのオリジナルのマップをアプリで作ることにも挑戦してみてもよいかもしれません」(ヤモリン博士)
神奈川県逗子市の取り組みから学ぶ防災のヒントは「土地の特徴に応じた対策を用意する」こと。

「スポーツで試合するときに相手の弱点や強いところを調べようとするのと同じで、防災もそれぞれの土地の特徴に応じた対策をしましょう」(ヤモリン博士)
町の弱点を知る?ゲーム感覚で 防災オリエンテーリング(京都市)
京都の小学校が地域一体で取り組むゲーム感覚の防災オリエンテーリングを行っています。このイベントに防災キッズ団も…。

京都市立正親(せいしん)小学校。創立154年の歴史があります。3人を出迎えてくれたのは、校長の阿部正人さん。
「皆さんに本校の“ミッションX”に参加していただきます」(阿部校長)
“ミッションX”とは、児童が参加して年に一度行われる防災オリエンテーリング。ことしは67人が集まりました。
グループに分かれた子どもたちが、学校をスタートし、学区内11か所のポイントを巡って制限時間内に戻ってくるゲーム。ポイント地点にはそれぞれミッションがあります。

例えば、「警察官の手信号に従うミッション」、「消防士の指導のもと即席の担架を作るミッション」など、ひとつひとつクリアしてゴールを目指します。


さらに、黒ずくめの姿をした「ハンター」が登場!現れたら、予期せぬ災害リスクが迫っている設定で、立ち去るまで動けないルールになっています。

学区内には、京都ならではの古くから残る木造住宅が立ち並んでいます。そして、道幅4メートル以下の狭い路地が70以上もあり、その多くが袋小路になっています。

さらに、地域の高齢化が進んだことで空き家が増え、倒壊の危険があるなど避難の課題を抱えています。ミッションXの取り組みは、こうした現状を子どもたちに直に感じてほしいと4年前に始まりました。

「教室で勉強する方法もありますが、自分たちの住んでいる地域に出て、地域の方と触れ合って、防災のことを知ってほしい」(阿部校長)

いよいよミッションXスタート!キッズ団を始め、子どもたちが元気いっぱいに出発!

楽さんチーム、学校から少し離れたこちらのポイントに到着!
細い路地を進んだ先には、1軒の空き家。ここでミッション!クイズが出題されます。
Q.正親学区に空き家は何軒(戸)あるか?①6戸 ②60戸 ③600戸

正解は、②の60戸。
空き家は倒壊すると、避難の妨げになりかねないため、住民たちは行政と相談し、持ち主と話し合いながら耐震強化などの対策を進めています。

おーちゃんチームも空き家に関するクイズに挑戦!
Q.空き家は使われていないので普通の家より傷まない。〇か×か?

答えは…×が正解!(空き家はふつうの家より傷む) みごとクリアです!
こちらのミッションでは、細い路地を進んでいくときに、ハンターが登場!“予期せぬ危険”が迫っているサインです。
細い路地では地震の際、倒壊家屋などで道が塞がれることもあります。立ち止まって注意深く周りを見て、慎重に行動することを体験します。

さらに奥へ進んでいくと、行き止まりに避難扉を発見。ここを通過すればミッションクリア、覚えておけばいざという時に役立ちます。
女の子「ふだんは開かないけど、できるだけ速やかな避難ができるように扉がある」

一方、こちらは、お年寄りに避難を促すミッション!
大きな地震が起きました。家の前に座り込んでいるおばあちゃんを発見!安全な場所に避難してもらえるよう、声をかけましょう。避難を渋るおばあちゃんの気持ちを変えることができればクリアです。

男の子「避難所は、あの学校です」
おばあちゃん「私ね、歯の調子が悪いんですよ。みんな一緒のお食事でしょ、やわらかい物じゃないと食べられないんですよ」
男の子「ようかんとか、やわらかい物もあります」
おばあちゃん「それやったらいけそうですね!」

まーちゃんチームもやってきました。
おばあちゃん「私のとこね、猫を飼っているんですよ。ちょっと行かれないんです」
まーちゃん「キケンなので避難しましょう!」
男の子「まず自分が身を守ってから、そのあと猫を助けにいきましょう!自分もまきこまれちゃうかもしれませんよ」
おばあちゃん「じゃ、分かりました!」

このミッションで、“お年寄りにとっては避難することが大変なんだ”ということを学びました。
このミッションXには、保護者や地域の人たち50人以上が携わっています。ハンターも児童のお父さん。見守り役も兼ねています。
地域が一丸となって、子どもたちにわが町の危険を伝え、いざという時のために備えています。

「地域の“親睦と絆”。昔のようなほんわかした絆で、お互いを助け合うと若い子に教える責任だと思っています」(正親学区防災まちづくり委員会長 尾﨑富美雄さん)
力を合わせてミッションを乗り越えた子どもたち。たくさんの町の発見がありました!
「避難経路とかめちゃくちゃ細かいところにあった。知っている人が多い方がみんなで避難できる」
「京都って小さな道がいろいろと入り組んでいるからちゃんと理解していかないと」

■防災のヒント:自分の安全を守ろう=みんなで助かろう
京都正親小学校の取り組みから学ぶ防災のヒントは「自分の安全を守ろう=みんなで助かろう」。
「災害の時は他の人のことまで手が回らないかもしれません。だからこそ、ふだんから、町の大人たちも一緒になって協力して、みんなで助かろうという気持ちを盛り上げていく、雰囲気を作っていくことが大事」(ヤモリン博士)

最後に、ヤモリン博士こと矢守克也教授から全国の皆さんへのメッセージです。
「全国の子どもたちにも、今日のいろんな活動のいいところを、どんどん真似して取り組んでほしいなと思います。同時に、子どもたちと一緒に大人も頑張ってほしい」

この記事は、明日をまもるナビ「チャレンジ!BOSAIアクション 第六弾」(2023年11月23日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しました。