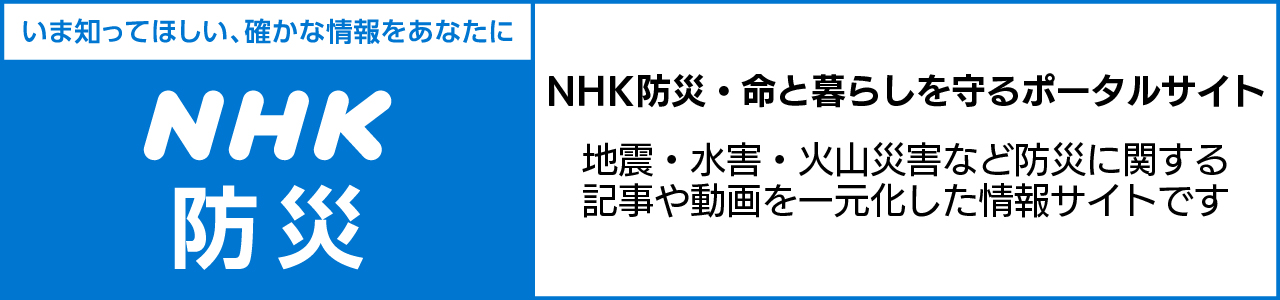“地域防災の要”とも言われる「消防団」。能登半島地震の被災地でも寸断した道路の応急対応や夜間のパトロール、避難所の運営支援などの活動にあたりました。しかし全国では消防団員の不足が深刻に。機能の低下が懸念されています。地域になくてはならない消防団、その未来を考えます。
「消防団」とは?
「消防団」は、仕事を持つ市民などがさまざまな災害の初動対応などに当たる組織です。

“消防団”と、消防署にいる“消防職員”は何が違うのでしょうか。
消防本部に所属する専業の消防職員は、常勤の地方公務員です。
一方、消防団員は、非常勤の特別職地方公務員という立場で、地域密着型の組織です。

今年1月の能登半島地震の被災地でも、消防団の皆さんは寸断した道路の応急対応や夜間のパトロール、避難所の運営の支援など、さまざまな活動をしています。

輪島市の消防団では、道路寸断の中、消防車に乗ってけが人の搬送、避難誘導などを行いました。

いざというときに頼りになる消防団ですが、全国の消防団員の数は年々減少しています。2023年度には76万人あまりになり、必要と定められた定数の88万人からは12万人以上、およそ14%が不足しているのです。

消防行政が専門で消防団の実情を調査・研究している関西大学社会安全学部教授の永田尚三さんは、次のように指摘しています。
「消防職員は行政の職員なので、その人数には限界がある。能登半島地震のような大きな災害が起きた時に、マンパワーを持った消防団の存在は必要になる」(永田さん)

大切なのに“団員不足”
地域防災に極めて重要な消防団員。
人口およそ11万人の栃木県佐野市の「佐野市消防団」は、31の分団があり、およそ600人が活動しています。

しかしその数は、佐野市では定数(742人)よりおよそ150人不足。募集を強化しても団員はなかなか増えません。
そこで今検討しているのが消防団の統廃合です。
各分団で団員が減っている今、いざというとき必要な人数が集まらず、出動まで時間がかかりがちです。

そこで、例えば隣どうしの団をいくつか統合。地区ごとにある消防団の拠点も、1か所に集約。担当する範囲を広げる代わりに、1つの団に必要な人数を確保できる仕組みです。

しかし、住民アンケートで、統廃合によって地元から消防団の拠点がなくなる可能性について尋ねたところ、「不安」や「反対」という回答は7割を超えました。

佐野市内の山間部にある消防団の拠点も統廃合が検討されています。
地元の町会長・須藤信夫さんは、この拠点がなくなることを不安に思っています。地区を通る幹線道路は少なく、地震などで寸断し孤立すれば、外から消防団に来てもらうことも難しいからです。

こうした住民の不安を受け止めながら、市は消防団の存続のあり方を探ろうとしています。
佐野市消防本部・消防団係長 根岸康貴さんは、「消防団は地域防災の要。ありとあらゆる施策を推進して活性化を進めていく必要がある」と話しています。
関西大学の永田さんは「全国で同じ状況が生じている」と指摘します。
市町村では定員の確保が毎年大変で、分団の統廃合が相次いでいます。また、消防団員の定年制を廃止して、人員確保するということもあるといいます。
消防団 誰がなれる?報酬は?どんな仕事?
消防団は18歳以上の健康な人であれば、誰でも入団資格があります。
さらに、消防団で働けば市町村から報酬がもらえます。
各市町村によって異なりますが、国が定めた標準額で年3万6500円、さらに出動すれば、1日8000円の出動手当がプラスされます。

消防団の仕事には、火災の消火のほかに、災害対応、機器の保守、訓練、子どもへの指導など多様な活動があります。

【参考】
消防団ホームページ(総務省消防庁)
消防団の制度、入団方法や活動内容を紹介しています。
※NHKサイトを離れます
消防団のやりがいとは?
消防団員の方のモチベーションとは何なのか。「消防団が生きがいだ」という人たちを通して探ってみました。

■東京都奥多摩町の森田さん…地元への愛と熱意・子どもたちの尊敬
東京都奥多摩町は、消防署は1か所しかないため、住民による消防団への期待が高い地域です。
この町に消防団一筋の男性がいると聞き、町役場を訪ねました。出会えたのは交通防災係の森田宏樹さんです。
一市民として24年間消防団に参加。今は役場で町の消防団の事務局を担当。まさに「ミスター消防団」です。

「自分の居場所かもしれないです。私を10代、20代のころから育ててくれた組織が消防団です」(森田さん)
奥多摩町に代々続く家系の森田さんは、自身も地元の生まれ育ちです。
祖父も父も消防団員。森田さんにとって消防団は幼い頃から身近な存在でした。家には、団員たちが集まり、食卓を囲みました。みんな森田さんをかわいがってくれました。

「地域に当たり前にある組織なので、自分も将来、この組織に入ると考えていました」(森田さん)
18歳で入団し打ち込んだのが、消火技術などを分団ごとに競う操法(そうほう)大会です。
野球部出身で足の速い森田さんはホースを持って走る係。「あの分団には負けたくない」と競争心に火がつき、部活の感覚で日夜練習に没頭しました。

訓練に励んだ森田さんの熱意は、実際の火災現場でも生かされました。
火災の消火は、水源から現場までホースを引き、ポンプで水をくみ上げて行います。森田さんは、ときには急斜面の上や、数キロ離れた場所にまでホースを運搬しました。

森田さんは、家では4人の子どもを持つ父親。子どもたちからの尊敬のまなざしをうけて、さらにやる気が高まっています。
子どもたちも消防団の訓練をまねするようになりました。

「敬礼!右側後方水槽、手びろめによる二重巻ホース一線延長!」(子どもたち)
父の姿を見て成長する子どもたち。森田さんは、町もこの子たちも守りたいといいます。
■焼津市の石川さん…日常生活にも役立つ・知的好奇心
一方、静岡県焼津市の消防団には、全国でも先進的な取り組みをしている人がいます。
ドローンを操作する石川幸子さんは、縁もゆかりもなかった消防団に飛び込み、14年間、活動してきました。消防団では、団員募集などの広報活動をはじめ、高齢者宅への防火訪問など、多くの役目を果たしています。

ふだんは高齢者施設で働く石川さん。やりがいのひとつは消防団で学んだことが日常生活に役立つことだといいます。

意識を失った施設の利用者に応急救命処置を実施。また、自宅でも、子どもが出血したときに適切な止血を行うことができました。

「活動の中で応急救命普及員の資格を取らせていただいている。学べる機会があるところはすごく魅力的だった」(石川さん)

さらに2022年に入隊したのが、新たに作られたドローン隊。元々興味のあったドローンの操作や法令を学び、パイロットの資格まで得られました。
「知的好奇心も満たせる」、それがもうひとつのやりがいです。

そんな石川さんに2年前うれしいニュースが。大学生の長女、舞さんが、なんと消防団に入団したのです。地域貢献に関心があると聞き、石川さんが勧誘しました。
「大学生しながらバイトしながらでもできるかなと思って入りました。ぶっちゃけ就職活動に使えるかなと思って」(長女の舞さん)
スカウトした娘と同じ活動をする。やりがいがまたひとつ増えました。

■奥多摩町の森田さんもスカウトで新入団員を確保
奥多摩町の森田さんも、大好きな消防団の団員減少に胸を痛めて、去年からスカウトに力を入れ始めました。町内に広く呼びかけましたが、効果は今ひとつ。

そこで「この人なら」という人に狙いを定めて声をかけました。
そのひとりが保育士の井上七星さんです。実は井上さんのお父さんは消防団長。その娘なら入団してくれると森田さんは確信し説得。見事OKをもらえました。
「災害が保育園であったときは、率先して動けるようにできたらいいなと思います」(井上さん)

森田さんたちの声かけによって、2023年、実に女性7人、男性10人が入団。やりがいが伝わったようです。

“ここがイヤだよ 消防団” なぜ敬遠される?
やりがいもある消防団ですが、なぜ敬遠されるのか。SNSでの投稿から探ってみました。

① 目的不明な訓練
「操法訓練は基礎技術や安全管理が身につきます。一方、その練度を競い合う『操法大会』では、 “所作の美しさ”が評価基準になるなど、競技化しているとの指摘もあります」(永田さん)
② 飲み会への強制参加
「強制参加はできません。飲み会などは価値観が変わってきて、むしろ自分の時間を使いたいという人も増えてきています」(永田さん)
③ 報酬の流用・着服
「例えば、団員の出動手当などの報酬を消防団が管理して、団全体の懇親目的に使ったり、操法訓練などで使う手袋や靴などの消耗品の購入費用にあてたりしていたことがありました。
現在では、報酬を団員個人に直接振り込むように変わってきています」(永田さん)
特定の活動のみに参加「機能別団員・分団」
減り続ける消防団員をどうしたら増やせるのか。その対策の鍵として、現在、国では「機能別団員・分団」という取り組みを進めています。
消防団の主な仕事をフルコースでこなす一般団員ではなく、一部の仕事だけを担う団員や分団を設ける制度です。2005年に導入されてから、さまざまな種類が誕生していて、2023年4月時点でおよそ3万4000人が登録しています。


どんな効果があるのか。機能別団員の導入に力を入れている京都市の消防団を取材しました。
京都市消防団で導入している機能別分団は主に5つ。「ジュニア消防団指導班」のほか、防災についての啓発などを行う「予防広報班」。応急手当ての講習を開く「応急救護班」などです。

「ジュニア消防団」は、全国に約4300ある組織で、さまざまな訓練や学習を通して防災の知識を身につけます。
「ジュニア消防団指導班」とは、その「ジュニア消防団」を引率する大人たちで、名前のとおり、子どもたちの指導だけを行う分団です。

京都市東山区の消防団にはジュニア指導班が7人。月に一度、消防施設の見学や、防災グッズの制作などをサポートします。
“機能別”のメリット① 負担なく入れる
一般の団員と違い、急な呼び出しもないため、負担も少ないそうです。
看護師として働いている女性は、「土曜日や夜勤もあるが、1年先の行動計画を先にもらうので勤務表も作りやすい」といいます。
“機能別”のメリット② 一般の団員の増加も期待
本来、いくつもの任務を抱える消防団員。そこに特定の役目だけを担う機能別団員が増えたことで一般の団員の負担も軽減。そのため、一般の団員の増加にもつながると期待されています。

「救命指導を実際にやる応急救護班は、今まで一般の分団の方が来て指導していたので、一般の団員の負担軽減につながっています」(京都市東山消防署で消防団担当の渡辺美紀副署長)
“機能別”のメリット③ 一般の団員にチェンジ
機能別分団制度を設けて15年たつ京都市では、新たな効果も現れました。
消防ポンプの説明を受けている3人の女性は、もともと中京区のジュニア消防団指導班のメンバーでした。その活動を通して消防団へのやる気が高まり、消火も行う一般の団員に転換したのです。

中には防災のリーダーを務められる資格を取ろうとする人も。米田昭子さんは、ジュニア消防団指導班に参加したことで防災活動が地域の人に喜ばれると実感。専門的に学びたいと考え、防災士の資格を取ろうと勉強しています。
“機能別”のメリット④ エキスパートを確保
「機甲班」と呼ばれる分団は、大災害の時に必要となる障害物や瓦礫(がれき)の撤去に使われる重機の数々を操縦できるエキスパートを確保する仕組みです。
日頃から重機を使う建設業者や造園業社が登録。いざという時に必要な重機を出してもらいます。

およそ130台のクレーンを所有する建設会社もそのひとつ。7人が機甲班に登録し、要請があれば重機にマグネットシートを貼り、消防団の活動として現場に向かいます。

分団員として登録する竹内さんが運転するこのクレーンは、被災地に駆けつけ、25トンものがれきや障害物を撤去します。
機甲班には、あわせて42の事業所・116人が登録。京都市内一円に駆けつけることになっています。

関西大学・永田さんも、機能別団員・分団に関して「消防団に入る人たちの裾野が広がるメリットは間違いなくある」と取り組みを評価。
一方で、「実際の災害時に、機能別団員がどの程度機能するか。今後、訓練や想定をしっかりしていく必要がある」と指摘しています。
消防団 機能を維持していくためのカギ
これからの消防団がその機能を維持していくために必要なことは何でしょうか。
団員数を増やす試みと同時に、永田さんは、「少ない団員でも消防団の活動を維持していける体制整備」が必要だといいます。

そのひとつが「活動の効率化」です。
そのためのツールとして「ファイヤーチーフ」というアプリが開発されています。火災が起こった場合、携帯電話で団員が出動できるかどうかを瞬時に確認できるシステムです。

「災害が起きると、分団のリーダーが一人一人に連絡をとらなくてはならず、ものすごく時間も手間もかかる。このシステムだと何分後に何人出動できるといったようなことが瞬時にわかり、少ない団員でも災害等に対応でき、手間を省くという視点からも、非常に有効なシステムではないか」(永田さん)
もうひとつは「新たな防災文化」。
永田さんが参考例としてあげたのはドイツの「青少年消防団」です。
消防の訓練と同時に、大人の消防団員が子どもたちに勉強などを教えてくれたりする仕組みです。子どものころから消防団に行くのが当たり前になって、大人になってもそのまま続けてくれるケースが結構あるそうです。

ドイツは子どもの消防団に力を入れたことで、人口は日本より少ないおよそ8000万人でありながら、消防団員は100万人を超えています。
「日本に合う形にアレンジする必要はありますが、消防団のイメージを変えるよい方法になると思います」(永田さん)
■能登半島地震からも見えた消防団の重要さ
今回の能登半島地震の際にも永田さんは、消防団の重要さを改めて強調します。
「行方不明者のリストを作る時に、消防団の持つ情報が行政の情報よりも役に立った。地域密着の消防団だからこそできる仕事がある。社会で求められる役割、期待をうまく果たせる組織にしていく必要がこれからもあります」

この記事は、明日をまもるナビ「どう守る?あなたの町の消防団」(2024年2月18日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。