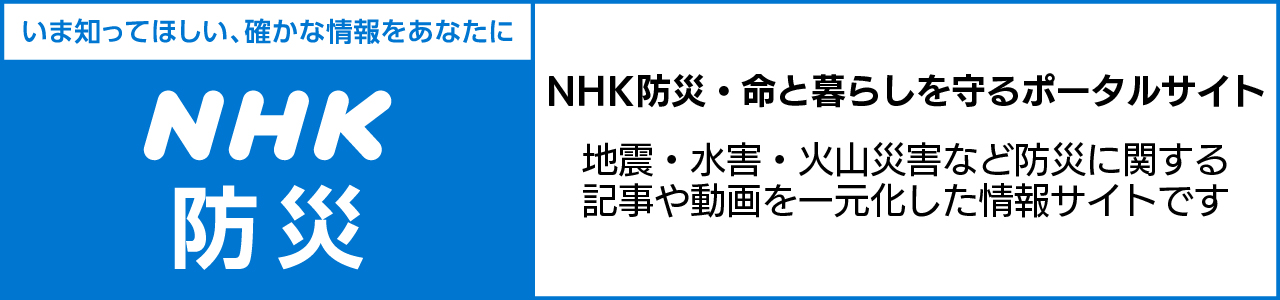地震や津波、台風に洪水。日本ははるか昔から多くの災害に見舞われてきました。しかし、先人たちはただ黙って受け入れてきたわけではありません。ある者は自然を巧みに操り、ある者は巨大な防潮堤を築くなど、現代に見直されるような対策を行ってきました。歴史学者の磯田道史さんとともに、氾濫を繰り返す川と闘った戦国大名・武田信玄の治水術を探り、その知恵を学びます。
「日本の川は音がする!」急こう配 洪水時に水量が急増
“日本の川は音がする”。これは日本の川の特徴を端的に示す言葉です。

世界の主要河川の源流から河口までの距離と標高を表したグラフです。角度が緩やかなほど穏やかな流れを表していて、急な角度は流れが激しいことを示しています。
同じ標高差でも、日本の川は短い距離を一気に流れ落ちていて、流れが速いということがグラフから分かります。
「明治時代に来日した外国人の土木技師が、日本の川を視察して『これは川ではない、滝だ』と言ったそうです。ヨーロッパ人の感覚からすると、日本の川は滝であり、そのため“音がする”」(国際日本文化研究センター教授・磯田道史さん)
洪水時と平常時の流れる水量を比較しても、ミシシッピ川がおよそ3倍、テムズ川がおよそ8倍に対して、日本の利根川はおよそ100倍と大きく違います。

そもそも日本の年間降水量は世界平均のおよそ2倍あり、さらに梅雨や台風の季節に集中して降ります。そのため日本の河川は、洪水になると一気に水の量が増すのです。
歴史学者の磯田さんは、こんな日本の川の特徴が日本の歴史を形づくってきたと捉えています。
「日本の川はいわば“瞬間湯沸かし器”。ふだんは穏やかでも、いったん大雨が降ると表情が一変し、太古から氾濫を繰り返してきた。これをコントロールするために先人たちが取り組んできたのが治水であり、その伝統を私たちの歴史は繰り返して来た」(磯田さん)

自然を巧みに操る 信玄流・治水術
“戦国最強”とうたわれ、数々のライバルを打ち負かした猛将・武田信玄。
信玄の領国・甲斐は、四方を山で囲まれ、急流河川が幾重にも流れていた日本屈指の洪水多発地帯でした。
領国の安定のため、信玄が取り組んだのが治水。
「信玄堤」(しんげんづつみ)と呼ばれる堤防を甲府盆地北部に築いたのです。

「信玄堤」は、南アルプスから流れ来る急流河川から甲府盆地を守るために造られた、およそ3キロに及ぶ堤防です。

釜無川(かまなしがわ)と御勅使川(みだいがわ)という2つの川の流れを受け止める場所に位置しています。

信玄の時代、この2つの川は流れが定まらず、洪水による氾濫を繰り返していたのです。

江戸時代に書かれた「甲斐国志」という資料には、「信玄堤」の他にもさまざまな治水施設が甲府盆地に存在したと記されています。

その一つが「石積出」(いしつみだし)。高さ7メートル、幅17メートル、長さ83メートルにも及ぶ城壁のような巨大な石の塊です。当時、洪水を引き起こしていた御勅使川の流れをまとめるために築いたと言われています。

そして「石積出」によって向きを変えられた川は、「高岩」(たかいわ)と呼ばれる釜無川沿いの断崖に激突。ここで一旦勢いを弱めた川を、下流の信玄堤が受け止め、氾濫を防ごうとしたのです。

信玄堤が途切れる釜無川の下流域には「霞堤」(かすみてい)という隙間の空いた堤防が築かれました。今もそのあとを見ることができます。

洪水時には隙間からゆっくりと水があふれ出すことで、水の勢いを逃がし、堤防の決壊を防ぎました。そして、洪水が収まれば自然と水が川に戻っていく仕組みです。

他にも武田信玄が考案したと言われる治水術があります。
「聖牛」(せいぎゅう)という、材木を組み合わせた三角すいの建造物です。堤防に設置して、堤防に打ちつける水の勢いを弱める効果があり、牛の角のように見えるために、このような名前がついているとのことです。

自然を巧みに操る、信玄流・治水術。
その考え方で重要な点を磯田さんは次のように分析します。
「そもそも人間は自然に勝てない。氾濫を防ぐために自然と自然を戦わせて、逆らわずに巧みにいなしながら、水を統御していく。これは戦争の防御陣地を作るのに似ています。この治水工事をやるチームワークの強さが、他の国へ攻め出していくときの、信玄の強さにもつながっています」
巧みな治水で領国をまとめ領民を豊かにした武田信玄は、さらに堤防を守らせるために、あることを利用しました。それは「おみゆきさん」という毎年4月に行われている水防祈願の祭りです。大勢の領民が、堤を踏み固めて強固にし、保守するという意味合いもありました。

さらに、信玄は河川の流域に住む農民たちの力も利用。
「洪水が起きたときに税を安くしたり免除をしたりしながら、公の大名の力と住民の力を合わせて防災・救助・避難活動を行ったと言われています」(磯田さん)
戦国大名の治水思想は現代にも
戦国大名が行った自然を利用した治水の思想は、現代でも効果を発揮しています。
2019年10月、台風19号で横浜を流れる鶴見川があふれて、「横浜国際総合競技場」周辺が浸水しました。

実はこの周辺では、競技場の周辺を広大な遊水地にすることで、下流域を鶴見川の大氾濫から守っています。

さらに競技場の下が高床式になっていて、下の駐車場にも水が入る仕組みです。

台風19号では、浸水の翌日にポンプで排水を行い、予定されていたラグビーワールドカップの試合も行われ、当時大きな話題になりました。
この記事は、明日をまもるナビ「歴史が伝える 災害と闘った日本人の知恵」(2024年2月11日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。