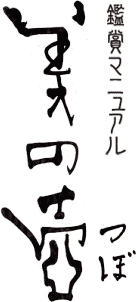file253 「カントリー・アンティーク」
 |
かつて、欧米の田舎で使われていた家具や道具。通称、カントリー・アンティークと呼ばれます。 |

|
そんなカントリー・アンティークを都会の暮らしに取り入れるスタイル。 |
 |
西洋の人々には、古くから田舎への憧れがありました。 |
 |
特に産業革命以降、ロンドンやパリの人々は、週末ごとに都会を抜け出して、田舎暮らしを楽しみました。 |

|
同時に、名もない人の手で生み出された品々を愛(め)でる美意識が生まれます。 |
 |
日本にカントリー・アンティークが紹介されたのは、1980年代。 |
壱のツボ たくましい手が生んだささやかな飾りを愛でる
 |
元雑貨店オーナーの天沼寿子さん。日本に初めてカントリースタイルを紹介した立役者です。 |
 |
カントリー・アンティークの家具の多くは、素人や名も無い職人が作ったものです。 |

|
扉のない食器棚は入口の脇に置かれていました。畑から戻ってすぐにお茶を準備するためです。 |
 |
そんな実用的な家具にもシンプルな曲線模様の飾りを入れるのを忘れていません。 |

|
天沼さんが特別大事にしているという家具。19世紀に作られたスツール。屋外でお茶を飲むときなどに使われました。 |
弐のツボ 過去の使い手に思いをはせる
 |
埼玉県に住む人形作家、毛塚千代さん。大好きなカントリー・アンティークに囲まれた暮らしです。 |
 |
ホーローは鉄などの金属にガラスを焼き付けて作ります。そのため表面が欠けやすくそこから錆(さ)びてしまいます。 |
 |
毛塚 「傷も味のうちで、 つるつるより少し使った形跡があった方が、より一層いとおしい。どこのお母さんがどうやって使っていたんだろうとか思うとなんかずっと楽しくなる。」 ふたつ目のツボ、 |
 |
毛塚さんの、アンティークとのつきあいには哲学があります。 |
 |
毛塚さんが生まれ育ったのは地方の農家。西洋の文化にはあまり馴染(なじ)みがありませんでした。しかし、大人になって出会ったカントリー・アンティークは、意外なほど親しみやすいものでした。 毛塚 「こういう使い込まれたような物って温かいじゃないですか。同じ匂いというか空気感というか、昔の子どもの頃に育った家にも流れていたのと同じような気がする。西洋と日本の違いなんだけど、だから好きなんだと思う。」 |
 |
素朴な道具を使うことで遠い国や時代の人々とつながる喜び。カントリー・アンティークのもう一つの楽しみ方です。 |
参のツボ 古材で作る世界で一つのカントリー
 |
日本の家が自分だけのカントリーの世界に生まれ変わりました。 3つ目のツボ、 |
 |
カントリー・アンティーク愛好家の、究極の夢をかなえた住まいです。 |
 |
インテリアに関する著作で知られる青柳啓子さん。古材使いの達人です。 |
 |
古材の一つ一つは青柳さんが各地の店に足を運んで探しました。そうした古材に、自分で手を加えることもあります。 |
 |
台は古材に自分で漆喰(しっくい)を塗りさらに古びた感じを出しました。大理石のシンクはギリシャのもの。 青柳 「本当に憧れているから、そういう空間にするにはどうしたらいいかということを考えて一つ一つこだわって探して作り上げましたね。私のイメージするプロヴァンスですね。」 |
 |
現代の日本にいるという現実を超える住まい。カギは、住む人の想像力なのです。 |
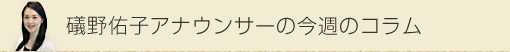
ぬくもりや、温かさ…。
名もない人の手で作られた素朴な家具が、本当に愛おしく感じました。
少しくらいゆがんでいてもそれが味わいになり、個性になるんですね。
優しさやゆとりを大切にする暮らし、すてきだなぁ♪
それにしても、出会いって不思議なものですね!
何十年も前に遠い国で使われていた家具や古材が、今こうして自分の目の前にある…。大切にしてくれる人のもとへ、物もやってくるのかなと考えてしまいました。人と人、人と物。どんな出会いも大事にしたいなと思う今日この頃です。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 | 使われた場所 (番組開始後) |
|---|---|---|
| Moanin' | Art Blakey & The Jazz Messengers | 0分2秒 |
| The Middle of Love | Blossom Dearie | 2分24秒 |
| Wandering | Oscar Peterson | 3分48秒 |
| Mother Nature's Son | Joel Frahm & Brad Mehldau | 6分58秒 |
| Humoresque | Art Tatum | 9分56秒 |
| That's Old Feeling | Paul Desmond | 11分52秒 |
| I'll Take Romance | Bud Shank with Len Mercer Strings | 14分4秒 |
| A Nice Day | Chico Hamilton Quintet | 16分11秒 |
| St.Thomas | Jim Hall & Ron Carter | 17分20秒 |
| Li'l Darlin' | Turtle Island String Quartet | 18分25秒 |
| Candy | Lee Morgan | 21分48秒 |
| Claire De Lune | Phil Woods & Michel Legrand | 24分13秒 |
| Shoot The Moon | Norah Jones | 26分6秒 |