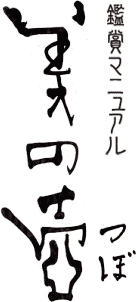file247 「沖縄の民家」
壱のツボ 時が生み出す無限の赤を味わえ
 |
金城さんは、さまざまな色を赤瓦に使います。 一つ目のツボ、 |

|
実はこの赤、沖縄の土に由来します。 |
 |
一方、こちらは、赤瓦が白いもので囲われています。 |
 |
この漆喰もまた、雨や日差しで風化。白から灰色へと変化します。 |
 |
さらに赤瓦の屋根をより魅力的に見せるものがあります。 |
弐のツボ 雨端柱が魅せる極上の空間
 |
沖縄の民家は中国と日本、そして琉球の文化が混じった独特の形をしています。 |
 |
最大の特徴は玄関がないこと。広く取った開口部から自由に出入りします。 |
 |
280年前に建てられた「中村家」。 |
 |
開口部には部屋を雨や日差しから守るため、長い軒があります。この軒下の空間を、「雨端(アマハジ)」といいます。 |
 |
雨端柱が作り出す、もう一つのすてきな美があります。 |
 |
そして山城さんご自慢の雨端柱。 山城 「これは、うちのおじいさんが明治の代にうちの実家に植えたチャーギですね。今、県産のチャーギを探すのは大変です。第二次世界大戦があったからだいたいそれで古いチャーギはなくなっちゃったわけですから。今もっと大事にしないといけないね。」 |
参のツボ 先人が作り上げた島の景色をめでる
 |
竹富島。美しい白い道が印象的な島です。 |
 |
さらに石積みには、ある想いが込められているといいます。 上勢頭 「竹富のキーワードは<うつぐみ=助け合い>です。この石垣自体も大きい石、小さい石、それぞれの立場で<うつぐみ>しあっている、助けあっているってことでしょうね。」 台風の多い島で村の人が協力していきてきました。石垣には知恵と島の精神が宿っています。 |
 |
もう一つ独特の景観を持つ島を紹介しましょう。 |
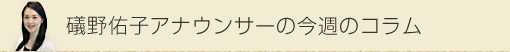
沖縄~♪心はもうすっかり沖縄に飛んでいます(笑)島のゆったりとした時間と、風が心地よく流れていく様子。良いですね~。民家も実用的であり、そして美しい!土地が育む美、というものを改めて教えてもらいました。
沖縄の本島には行ったことがあるのですが、離島は未経験です。
赤瓦と白い道、黒い壁をこの目で見た~い!
あ、シーサーも忘れずに。あんなに個性的で可愛(かわい)いものとは知りませんでした。魔物だけど、意外とゆるキャラ?!
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 | 使われた場所 (番組開始後) |
|---|---|---|
| Moanin' | Art Blakey & The Jazz Messengers | 0分2秒 |
| てぃんさぐぬ花 | 吉川 忠英 | 1分12秒 |
| Per Te | Chris Botti | 2分47秒 |
| Tabarka | Keith Jarrett | 4分40秒 |
| Maiden Voyage | Bobby Hutcherson | 5分38秒 |
| Creole Blues | Marcus Roberts | 7分51秒 |
| Us Three | Horace Parlan | 8分55秒 |
| I Remember Clifford | Lee Morgan | 11分2秒 |
| Cinema Paradiso | Charlie Haden / Pat Metheny | 12分23秒 |
| Stolen Moments | Turtle Island String Quartet | 13分54秒 |
| You Leave Me Breathless | Milt Jackson | 16分21秒 |
| Sea Glass | Joey Calderazzo | 18分44秒 |
| Take The A Train | Herb Ohta | 21分20秒 |
| Summer Time | Jim Hall & Pat Metheny | 23分41秒 |
| For Heaven's Sake | Makoto Ozone & Gary Burton | 25分5秒 |
| Over The Rainbow | Chris Botti | 25分55秒 |
| ハイサイおじさん | 吉川 忠英 | 28分25秒 |