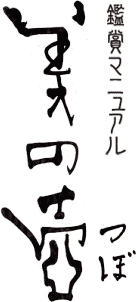file238 「サキュレント 魅惑の多肉植物」
壱のツボ 環境が生んだ不思議な造形
 |
13年前、フラワーアレンジメントの世界で多肉植物を知った松山美紗さん。それ以来、多肉植物、一筋。 |

|
こちらは『乙女心』。 |
 |
『アドロミスクス』。なんだか爬虫(はちゅう)類のように見えませんか? 松山 「良く見るとすごくグロテスクなんですけど、何でこういう風な模様がついたのかなって思うとこれも何かちょっとおもしろく愛おしくなるかなって思いますね。」 |

|
原産地に近い環境で作ると、多肉植物はより美しく育つといいます。 |
 |
萩原さんの温室。黒いネットがかけてあります。これがポイント。 萩原 「この黒いのが遮光ネットです。これは50パーセントの遮光率です。遮光しないで栽培してますと、萎縮してしまって、成長しなくなってしまう。いろいろ経験しながら試行錯誤でやってました。」 |
 |
萩原さんが手塩にかけて育てたハオルシア。こちらはオブツーサという種類。まるで水晶のような窓をもっています。 |
弐のツボ 無限の色を育てる

|
小雪舞う3月。長野県、小諸市。 |
 |
細やかな温度管理の元、たっぷり紫外線を浴びせ育てると、秋から春にかけてこんな楽しみが待っています。 |

|
姫黄金花月。通称「金のなる木」。こちらも葉がみごとに色づいています。 |
 |
5カ月前に発芽した幼いリトープス。一度に20万もの種を播きました。 島田 「これだけたくさん播(ま)いてなかなかでないのですよね、変わった色っていうのは。普通に装っていますけど、飛び跳ねたいぐらいの気持ちぐらいの気持ちですよね、本当は。」 この一粒を4年かけて繁殖可能な成体に育てます。 |
 |
こちらは、黄緑の個体から生まれた2世代目。偶然みつかる黄緑とその兄弟に赤茶色を交配すると10パーセントの割合で黄緑が出現するといいます。 |
 |
こちらは2年前、赤茶色の親から偶然、産まれた紫の子ども。この紫も長い時間をかけて交配を重ね、美しい紫に育てていきます。 |
参のツボ 不可能を可能にする『生きた絵の具
 |
ハンバーグを側面につけた巣箱。 柳生「多肉植物の最大の魅力は、不可能を可能にしてくれることです。多肉植物は、まず絵の具のようにたくさんの色があります。白が欲しいなって思った時に、白があるんです。で、わずかな土でも育つというすごく強じんな、強い性質もあり、その二つが重なると、リースが可能だったり、何年も何年も生き続けたり、それがむしろ機嫌がよかったりするからすごいことですよね。多肉植物って。」 |
 |
こんな楽しい遊びも。丸太をくりぬいた中に土を入れ挿しています。 「不可能を可能にする『生きた絵の具』」 |
|
園芸研究家の奥峰子さん。ガーデニングの本場イギリスで学び、多肉植物を使った園芸を得意とします。 奥 「タペストリーガーデンとかあるいはカーペットベェディングっていう言い方をするのですけれども、ペルシャ絨毯(じゅうたん)のように、複雑な模様の絨毯のように多肉植物を使って地面に模様を描いていっているのですね。」 イギリスでは、19世紀から、キャンバスに絵を描くような多肉植物の寄せ植えが発展しました。 |
 |
ささやかなスペースも活用できます。 |
 |
誕生日や特別な記念日などに、部屋の中を華やかに飾ることもできます。 |
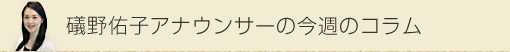
「多肉ライフ」、ですか。
今回初めて知った言葉なのですが、面白い言葉の響きですよね~。
初め、お肉をたくさん食べる生活のことかと思ってしまいましたが・・。
最近インテリアショップやカフェで本当によく見かけるようになりましたね。
お花とは違って一見地味ですが、何ともいえない独特の魅力があります。
形自体が不思議でじーっと見ていても飽きませんし、
たたずまいが何とも魅力でほっとするといいますか。
そしてやはり、ぷにゅぷにゅした感触。
ディレクターが買った物を実際に触らせてもらったのですが、
一度触ると、指が離せない~!指先から癒される~。
はるばる遠い異国からやって来て、今ここで私を癒してくれていると思うと
さらに愛おしくなります。
今回驚いたのは、色のバリエーション!
微妙な中間色から鮮やかなグリーン、ずらりと色とりどりに並ぶ様子は
まるでカップケーキのように美しく見えました。すごい技術ですね!
植物はお手入れに気を使いますが、水やりも少なくて世話もラク、
というのが私にとっては一番の魅力かもしれません。
ささやかながら、多肉ライフ始めてみようかなと思っているところです。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 | 使われた場所 (番組開始後) |
|---|---|---|
| Moanin' | Art Blakey & The Jazz Messengers | 0分2秒 |
| Tout Doucement | Blossom Dearlie | 1分32秒 |
| Jubilation | Bud Shank | 3分5秒 |
| Forgive Me If I'm Late | Sadao Watanabe | 4分13秒 |
| Love For Sale | Jacky Terrasson | 6分20秒 |
| The Drum Thing | John Coltrane | 7分57秒 |
| 即興の花と水(ニ) | 菊地成孔 /南博 | 10分25秒 |
| Improvisation On “Bolero” | Larry Coryell | 11分30秒 |
| Claire De Lune | Phil Woods & Michael Legrand | 13分30秒 |
| My Song | Keith Jarrett | 15分13秒 |
| The French Fiddler | Oscar Perterson | 17分58秒 |
| In The Wee Small Hours Of The Morning | Wynton Marsalis | 19分47秒 |
| Have You met Miss Jones? | Paul Smith | 21分57秒 |
| Anythibg Goes | Stephan Grappelli & Yo-Yo Ma | 24分12秒 |
| Dear Prudence | Brad Meldah | 25分22秒 |
| Stardust | Pied Pipers With Frank Sinatra | 26分38秒 |