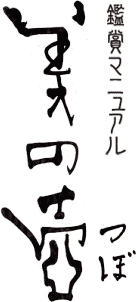File226 「かごバッグ」

|
街で、草木や竹を編んだバッグを持つ女性を見かけませんか?ファッションの世界で、これを「かごバッグ」と言います。古くから多くの女性に愛され続けてきたアイテムです。 |

|
スタイリストの椎名直子さん。かごバッグにほれ込み、ほかのバッグはほとんど使わないといいます。 椎名 「宝物ですが、どちらかというと夫婦や友達みたいな感じです。棚の上に置いておくというよりは、ぞんざいな扱いをしていても信じ合ってるような。」 今、注目されているのが日本製のかごバッグ。そこには、身近にある材料を暮らしにいかしてきた、人々の知恵や工夫が隠されています。 |
壱のツボ 「手」が生み出す豊かな表情
 |
同じ素材を用いたバッグでも、よく見るとさまざまな網み目があります。定番の「網代(あじろ)編み」から、花ビラが重なり合うような「花結び編み」、立体的に編まれた「亀甲編み」など、編み方を変えることで全く異なる表情が生み出されます。 |
 |
日本製のかごバッグ専門店の店主、籾山瑞枝(もみやま・みずえ)さん。 籾山 「人の手によって紡ぎ出される表情の豊かさや、楽しさが編み目の魅力じゃないかと思います。」 ひとつ目のツボ、 |

|
古くからかごバッグが作られていた青森県・弘前市。 葛西 「私が気をつけているのは皮の肌と切り幅ですね。いかに肌がよくても切り幅が一定でないと、きれいな、まっすぐな編み目はそろいません」 |
 |
使用する山ブドウの樹皮は、太さも厚さも均一ではありません。さらに、ねじれていたり反っていたりとさまざまな癖があります。まずはこれを丹念に加工し、編みやすく美しいものにしていきます。 |
 |
はじめに樹皮を一定の幅にカット。それを水でぬらし、専用の道具でこすると、繊維が均等になり癖が減るといいます。 |
 |
さらに、皮の厚い部分を手で探り、均等な厚みに削っていきます。 |
 |
編みの作業のコツは、少し食い込ませて編んでいくこと。水を含ませ編みやすくした山ブドウの皮。重ねて編まないと、乾いた時隙間ができ、美しい編み目にならないのです。 |

|
もうひとつのコツは、なめしても消えない癖を、引っ張って矯正しながら編んでいくこと。手で触れて確かめながら微妙な力加減で進める作業です。 |
 |
ぎゅっと詰まった美しい編み目。それは野生の力との地道な戦いを経て生み出されるものなのです。 |

|
青森のかごバッグは、職人たちだけでなく、農家の人たちもその担い手でした。かつて津軽の人たちは、冬の農閑期、暮らしに使うかごを作り、時にそれを売って生計の足しにもしていました。 |
 |
りんご農家の西沢つえさん。りんごの収穫が終わる12月から4月までの間、かご作りをします。 西沢 「お父さんもおじいちゃんも出稼ぎに行っていたころは、雪片づけやら子どもの世話やら大変だったけど、好きなかご作りでこの作業場に来れば、ほっとしました」 美しい編み目には、家を守りながらかごを作り続けた、女性たちの手仕事のぬくもりが込められています。 |
弐のツボ ありのままを愛(め)でよ
 |
次は、カゴの材料に注目します。かご作家の真木雅子さんは、さまざまな材料を使い、表情の異なるバッグを制作してきました。 真木 「アケビは御殿場や信州、東北など寒い所のものが赤くてとてもきれいです。ツヅラフジは四国や九州にあり、少し青みがかっています。」 |
 |
クルミの木の皮を巧みに使ったバッグです。 真木 「クルミは表と裏で色がかなり違うので、使い分けることによって非常にきれいな市松が浮かび上がってきます。」 かごバッグにはそれぞれの素材の個性が存分に生かされているのです。 ふたつ目のツボ |
 |
秋田県・横手は、かごバッグの材料として人気の高いアケビの産地です。秋はアケビの収穫時期。良質なつるがあるのは、適度に光の差す低木の雑木林だといいます。 |
 |
バッグに使うのは、根元から出ている若いつるです。春に芽を出し、秋まで伸びたもので、適度な弾力をもち自由な造形が可能です。しなやかなアケビのつるですが、それでも無理に曲げるとヒビが入り台無しになります。 |
 |
かご職人の中川原信一さん。つるを痛めない絶妙な力加減と手さばきは、半世紀かけて体で覚えたものです。 中川原 「気障(きざ)っぽく言えば、材料と会話しながら作るって言うかな。丁寧に丁寧に一生懸命作ることだけを心がけています。」 |
参のツボ 使うほど深まる色艶(いろつや)
 |
モデルの桐島かれんさん。山ブドウのかごバッグを愛用して10年になります。 桐島 「とにかく使い込めば使い込むほど、つるがどんどんやわらかくなってきます。そして手脂によって艶(つや)が出てくる。かごバッグには育てる楽しみがあるんです。」 |
 |
新品のバッグは、樹皮の堅い感じが残っています。 |
 |
30年使い続けられたものは、桐島さんのバッグよりさらにあめ色が濃く、黒に近くなっています。 3つ目のツボ、 |
 |
一つのかごバッグを23年間愛用している中田正子さん。 |
 |
中田 「主人が故人となった今では、そばにおいておくだけで頼りになる想いがございます。」 かごバッグは時に人生を共に歩く味わい深いパートナーにもなってくれるのです。 |
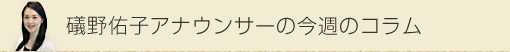
1つのかごバッグを何十年も使い続け、艶や色味が変わっていき、手の脂で深い味わいが生まれる。まさに、一生物ですよね~。
欲しくても、何か月も待たなければ手に入らないものもあるそうです!
自然の営みの中で生まれる、100パーセント天然の素材ですから、人間の欲求通りにいかないのは、当たり前ですよね。
そう考えるとかごバッグって、“自然からの恵み”を私達が使わせてもらっているんだなあとしみじみ感じます。
職人さんの、「弦に負担がかからないように丸く編んでいる」という言葉が印象に残りました。
女性が持つものと思われがちですが、実は男性が持っても良いそうですよ。
さらりとかごバッグを持っている男性、渋くてカッコ良いかも!!
番組中の草刈さんも、お似合いでしたよね♪
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 | 使われた場所 (番組開始後) |
|---|---|---|
| Moanin' | Art Blakey & The Jazz Messengers | 0分2秒 |
| The Song Is You | Bob Thompson | 1分26秒 |
| Waltz For Debby | Cannonball Adderley & Bill Evans | 2分44秒 |
| But Not For Me | The Modern Jazz Quartet | 4分34秒 |
| Say It | John Coltrane | 6分16秒 |
| Evidence | Thelonious Monk | 8分8秒 |
| Stars Fell On Alabama | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 10分58秒 |
| It Could Happen To Me | Horace Parlan | 14分40秒 |
| Love For Sale | Miles Davis | 15分48秒 |
| Last Train Home | Pat Metheny | 18分20秒 |
| The Nearness Of You | Norah Jones | 20分25秒 |
| Four | Phineas Newborn Jr. | 22分30秒 |
| What's New | Bill Evans & Jeremy Steig | 23分16秒 |
| Green Sleeves | Paul Desmond | 24分53秒 |
| I'll Never Smile Again | Pied Pipers With Frank Sinatra | 26分43秒 |
| Marciac Fun | Wynton Marsalis | 28分23秒 |