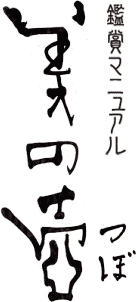file212 「京焼」
壱のツボ ぶつかり合う色の競演に酔う
 |
まずは色彩に注目。 |

|
仁清の傑作、色絵芥子文茶壷(いろえけしもんちゃつぼ)。 |
 |
陶芸家・山岡善昇さんです。 |
弐のツボ 薄さに込めた、心意気

|
腕自慢の職人が作ったおちょこは、実際どれくらいの薄さなのか?超音波で測定してみると、わずか1.3ミリ。更に違う箇所を測ってみても、全く同じ1.3ミリ。驚きの精度です。薄さを生み出す超絶技巧。ここにも京焼ならではの美学があるのです。 京焼鑑賞 二のツボ、 |
 |
京焼の「薄さ」の魅力を引き出すのが、「絵付け」です。 |
 |
透き通るほど薄い盃(さかずき)に、極細の線で描かれた桜がはかない美しさを感じさせます。 |
 |
光にかざすと、裏側の模様が透けて見える仕掛け。霞(かすみ)がかかったようなおぼろげな風景が、浮かび上がります。京の雅が形になった、繊細極まりないたたずまいです。 |
参のツボ 伊達(だて)道具で風流を楽しむ
 |
ユニークなデザインに、京都ならではの美意識が込められています。 |
 |
東京世田谷の美術館にこうした伊達道具、初期の名品がありました。作者は京焼の美学を確立したあの野々村仁清(ののむらにんせい)。 |
 |
さて、この伊達道具、何に使うかわかりますか? |
 |
正解は、ウサギのフタを取ると、こちらも香炉。 |
 |
更にこんな驚かせ方もありました。 |
 |
こちらは江戸時代中期に作られた焼物、ある楽器を模しています。 |
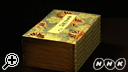 |
こちらも商人たちの心意気を感じさせる伊達道具。 |
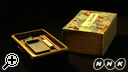 |
さて中身はというとすずり箱。商人たちが常に傍らに置いた商売道具です。江戸時代、公家に代わり京の文化の担い手となった商人たち。 王朝の雅をも自らの世界に取り込んだという、自負と余裕を感じさせます。 |
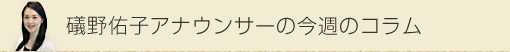
京焼が各地の焼き物の良いところを取り入れ、京都という土地の「誂え(あつらえ)」の文化が生み出したものだということに深く納得しました。さまざまな技術を取り入れる柔軟さを持ち、新しい色や、薄さに挑戦する職人たち。注文主を満足させて、さらに驚かせようという心意気が伝わってきます。
法螺貝(ほら貝)の形をしたものや、本の形を模したもの、驚きですよね!
それから最後に登場した、現代の京焼。花を生けて部屋に飾ったら素敵だろうな~。オブジェとしても使えるということで、使う人自身が自由に発想できることが、現代の生活スタイルになじむのでしょうね。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| Milou | Stephane Grappelli |
| Nica's Dream | Kenny Burrell |
| Oh Lady Be Good | Turtle Island String Quartet |
| Billy Boy | Miles Davis |
| A Night In Tunisia | Art Blakey And The Jazz Messengers |
| Brick Busters | 山下洋輔 |
| Waltz For Debby | Kronos Quartet |
| St.Thomas | Jim Hall & Ron Carter |
| Milestones | Walter Bishop Jr. |
| Waltz For Debby | John McLaughlin |
| Thelonious | Wynton Marsalis |
| Loose Duck | Wynton Marsalis |
| 孤軍 | 秋吉 敏子 |
| Waltz For Debby | Cannonball Adderley |
| Tiger Rag | Stephane Grappelli |